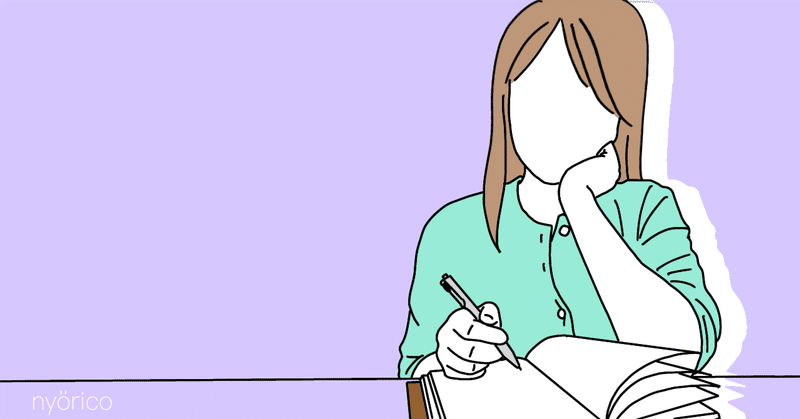
「ハッピィ・バースデイ」第4話(全10話)
夜。暗くなってからの教室に、私はいつも時代の流れを感じる。私が学生の頃、教室も塾も、夕方までしかいなかった。高校のときだって、文化祭の前日以外は、こんな時間は家にいた。まして小学生のときなんて、夜の七時以降に外に出るなんて! いくら勉強のためとはいえ、親と一緒のときでなければ考えられないことだった。昼間はランドセルを背負っている子どもたちが、家に帰って夜のお弁当を持って、アルバイトをはしごしたような疲れた顔でやってきて、静かに問題を解いている姿を見ると、聡志が「受験塾がわからない」というのも理解できる。
最後のコマは復習テスト。ホワイトボードに赤ペンで「国語 九時三十分まで」と書き、机間巡視をする。今日の中学入試の問題は、私も巻末の解法を読まないとわからなかった。一周だけゆっくり歩き、教卓のいすに座り、生徒の顔を見る。悩みながら、眠い目をこすり文章を読んでいる。小学生の私は、彼らと同じようにここに座る事ができるのだろうかと考える。まして、今の私ですら、彼らのように、我慢して座って問題を解くことができるのかな……。
最近の私の問題は、「いつまで聡志とこの関係を続けるか」だ。別れたはずなのに、お酒飲んだり、家に泊まったり。一緒にいるのは嫌ではない。ただ、ずっといるとどうしても見たくないところばかりが目に付くようになってしまった。いつからだろう。
初めて聡志とワインを飲みに行ったとき、いつまでも会話が途切れる事はなかった。ワインのお店で店員さんの似合う髪形についてこっそりと話し、次のお店では好きな居酒屋メニューの話から、昨日食べた朝ご飯、その前食べた朝ご飯と、記憶ゲームで盛り上がった。箸が転がっても、記憶が飛んでいても、おかしい時間だった。そのまま私を改札まで見送ってくれて、でもそこでも今度は次に行きたいデートの場所の話で盛り上がって。終電近くまで立ち話をして、
「今度は聡志くんの部屋に行きたい」
って言ったんだよね。そしたら、強ばった笑顔と大きな声で(きっと、しっぽを振りながら)、
「じゃあ、今から」
ってね。あれから一年間、ほぼべったりな時間を聡志と過ごして、気がつくと「少しでも一緒にいたい」から「少しだけ一緒にいたい」に変わってしまった。
ふと現実に戻ると、必死に目の前の問題を解いている小学生。偉いね、みんな。それに比べて私は……。ガタリ。意味もなくイスから立ち上がってしまった。物音に反応して一斉にこっちを向く生徒たち。やば。何か言わなきゃ。えーっと……。
「わからない問題があったら、じっくり時間をかけて解いてみてね」
思わず自虐的に言ってみる。「邪魔するな」と言わんばかりの視線を送る生徒たちに怯えるように、静かにまたイスに座る。あのね、先生はわからない問題は、めんどくさいから、ほうっています! いつかチャイムがなって、終了っ! て言われるのを待つほうが楽なんだよね。私は生徒の顔を見ながら、心の中でつぶやいた。
時計が九時三十分を指した。プリントが後ろの席からすごい速さで回収される。
「はい。今日はここまで。気をつけて帰ってね」
私が言ったから帰り支度が始まったのか、帰り支度が始まったから私が言ったのかわからないが、生徒たちはカバンに荷物を詰め始めた。生徒同士でじゃれあったり、憎まれ口をたたいたりしながら。私は手を後ろで組んで受付まで見送りながら、この様子を眺める。このときばかりは、彼らも小学生の顔だ。殻が破れて子どもに戻り、母親のもとへと帰っていく。自然界らしいこの時間帯が、私は好きだ。
病院の待合室のようにベンチが並ぶ受付まで迎えにきている母親のもとへ走っていく子どもを見ていて、ふと思う。私は今日、どこへ帰るんだろ。明日は三十歳の誕生日なのに……。ん? 誕生日……? あ、しまった! 遠藤さんにプレゼント! 明日彼女は休みの日なので、今日のうちに渡さないと。今まで歩いてきた教室からの廊下をダッシュで戻り、机の横にかけたカバンに入っているプレゼントをつかむ。危ない危ない。忘れるところだった。そして再びダッシュで戻る。まだ誰も帰っていない。
「遠藤さん!」
疲れて猫背になって歩く遠藤さんを、受付の横で、息を切らしながら呼び止める。
「……はい?」
疲れているからなのか、ワンテンポ遅れて返事がくる。私は、教室にいる生徒にも、ボーっとしている遠藤さんにも聞こえる大きな声で、
「みなさん、明日は遠藤さんのお誕生日です!」
と叫び、プレゼントを渡した。帰り支度をやめて受付まで来て、拍手をする子どもたち。自分がされて嬉しい事は、相手も嬉しい。国語の模範解答だ。
「うわあ! みんな、どうもありがとう!」
遠藤さんも、私の「忘れていた演出」が思わぬサプライズとなり、喜んだ。握手を求めながら、
「夏美先生! ありがとうございます!」
と私の目を見つめ、お礼を言った。この子、背が高くなったな。小柄の私と同じくらいの目線になってる。私はどんどんみんなを見上げていくよ。こうしてお互い歳をとっていくんだね。遠藤さんはプレゼントが電子手帳だとわかると、
「うわあ! これ欲しかったんだ! 夏美先生、何で知ってたんですか?!」
嘘かホントかわからないことを言いながら、その場で何度も飛び跳ねた。一緒に受付で見送っている教室長も満足そうに、ジャンプに合わせて顔を上下に動かした。
「実は私、お母さんと誕生日一緒なの。だから明日は最高の一日です!」
え? お母さんも? 一瞬、お母さんの年齢を聞きたい気持ちに襲われたが、ぐっと我慢する。
「半分にならないの?」
「え?」
算数の入試問題集に載りそうな質問を、一人の男子生徒がした。
「お祝い、お母さんもでしょ?」
「そうだよ」
「だったら普通、半分でしょ?」
「だから、二倍だよ」
「ふーん……そうかな……」
「そうだよ……」
私も他の生徒と同じく、鶏のように首を動かしながら、二人の会話を聞いていた。そして、それぞれが不完全燃焼なままで、今日の授業は終わった。
第5話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
