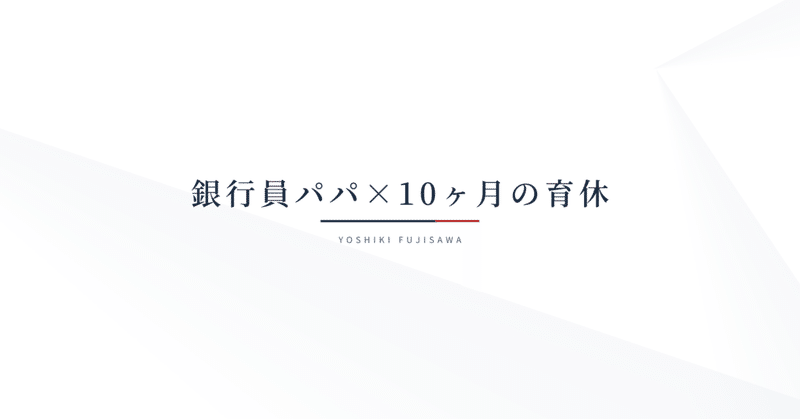
10ヶ月の男性育休中、どう過ごした?
10ヶ月の育休(生後1ヶ月〜11ヶ月)を取り終えた銀行員パパが育休中の育児について記録します。
前回は育児全般について記載しましたが、今回は育休中の過ごし方・役割分担等について書きます。
担当入替え制
我が家では育休期間中、主に以下のルールで過ごしていました。
①育児メイン、②家事メインの担当入替え制
1週間単位で担当を入替える
リフレッシュのためお互いの一人時間を可能な範囲で作る(その間は片方がワンオペ)
この方式で10ヶ月過ごして思ったことは、以下の通りです。
メリット
それぞれ経験した失敗や成功を互いに共有して次に活かせる
育児・家事で「やったことがないから不安。わからない」が無い(はず)
👶の機嫌に関係なく担当として責任を持って接するため、👶もワンオペを受け入れてくれる(気がする)
デメリット(や苦心したこと)
担当の切り替え日は👶の寝付きが良くない日が多い
2人ともキツくなった時、お互い経験してるからこそ議論(言い合い)が白熱する(メリットでもありデメリットでもある)
(パパのみ)家事メイン担当の時、謎のプロ意識が働き家事に時間がかかって👶と過ごす時間が少なくなるという本末転倒な事態が起きた
育児も家事もやることは多い・・・
では実際どのような仕事があったのか、以下に一覧化してみました。イメージしやすいよう、少し細かくしました。
①育児メイン担当のやること
オムツ替え(おしっこ)
新しいオムツを用意
服・オムツを脱がす
素早く新しいオムツを履かせ、服を着せる
古いオムツを丸めゴミ箱に入れる
オムツ替え(💩)
新しいオムツ・オムツ用のゴミ袋・お尻拭き・気を引くモノを用意
服・オムツを脱がし、気を引くモノを渡して寝返りを防ぐ
お尻の💩を綺麗に拭き取る
素早く新しいオムツを履かせ、服を着せる
古いオムツをゴミ袋に入れ臭いを塞ぎゴミ箱に入れる
ミルク調乳〜授乳
月齢毎の適量を基準に👶に合った量の粉ミルクを哺乳瓶に入れる
熱湯(約80℃)で殺菌してミルクを作り、👶が飲む温度(40℃前後)に整える
👶のペースでミルクをあげる
吐き戻しを防ぐため縦抱きor太ももに👶を座らせゲップを出させる
ミルクを飲んだ時間・量を記録して次のミルクに備える
寝かしつけ・夜間対応
月齢毎の活動時間に合わせ、眉が赤くなる・頭をこすりつけてくる等の兆候をみて寝かしつける
入眠後の10分程は眠りが浅いためベビーカメラで注意深く見守る
特に夜間は、うつ伏せ寝による窒息に注意しつつ、睡眠が浅くなって起きそうになった時はおしゃぶり・トントン、場合によって抱っこや授乳等をしてなるべく完全には目が覚めないようにする
沐浴・入浴
体を洗う。首・手足・肉の間等の汚れが溜まりやすい箇所を念入りに
2~3分の入浴で体を温める。全体で15分くらいで終えるようなるべく手際よく進める
👶が起きてる間の諸々
遊び:寝んね期はメリーやうちわを使って興味を引く。うつ伏せ期はおもちゃを使ってハイハイを誘う。ハイハイ期は部屋の危険を排除して一緒に楽しむ。立っちを始めたらゴッツンを防止しながら一緒に楽しむ
絵本:複数回読む。抑揚をつけるなどパターンを変えて興味を引く
音楽:「くもんのうた200えほん」を流し、歌詞を覚えて歌いかける
散歩等:お出かけセットを準備し、抱っこ紐とベビーカーを駆使する
爪切り:爪は1週間程で伸びるので、暴れない時間帯に爪を切る
②家事メイン担当のやること
最初は家事メイン担当はキッチリと分けて家事のみを担当していたのですが、育児メイン担当の負担が大きく疲弊したので、家事メイン担当も柔軟に育児の一部をやるようにしました。
👶起床〜朝寝のお世話
体温測定
着替え
遊び
授乳→寝かしつけ
👶入浴後のお世話
体を拭く
保湿
着替え
鼻水吸引
👶夜間対応を交代(週1回程)
👶離乳食
メニュー決め、買い出し
初めて食べるチャレンジ食材があればアレルギー有無や調理法を確認
月齢と進捗に合わせた調理、食べさせ、片付け
料理・洗濯・掃除・片付け・消毒(哺乳瓶・おもちゃ)・ゴミ捨てetc
③2人でやること
消耗品(ミルク・オムツ・お尻拭き)等の在庫管理・購入
予防接種・健診(※)1歳まで
B型肝炎(2回)、ヒブ(3回)、肺炎球菌(3回)、四種混合(3回)、ロタウイルス(1~2回)の接種スケジュールを管理。小児科予約、接種券を記入の上、接種対応
生後1ヶ月、3~4ヶ月、6~7ヶ月、9~10ヶ月等の健診用紙を記入の上、健診対応
発達段階に合わせた環境作り
遊び場はプレイマット等を敷き怪我・騒音を防止。家電・家具等の危険なものを極力取り除き、絵本やおもちゃの保管スペースを作る
絵本やおもちゃはサブスクを活用して発達段階に合ったものを用意
寝室には遮光カーテンを付け、ホワイトノイズを流し、室温を大人が肌寒い程度に調整、湿度を40~60%に調整
👶に合わせて過ごす日々
育休中は特に、👶のリズムに合わせて生活していました。
👶のリズムを知るため、「ぴよログ」アプリを使って、主に以下を記録して活用しています。
寝た・起きた
(睡眠リズムと睡眠量の記録・可視化)授乳・離乳食
(食事リズムや授乳量の記録・可視化)おしっこ・💩
(排泄リズムの記録・可視化)身長、体重、頭囲
(成長の記録・成長曲線による可視化)
睡眠不足になるほど記憶がなくなるので、ぴよログのおかげで👶の成長を正確に記録でき、後日振り返ることができています。無料で1日1枚の写真を付けて日記を残す機能もあるので、育児記録もできる範囲で蓄積できています。
以下、生後2ヶ月〜11ヶ月の記録を1週間毎に並べてみました。


表の推移からざっくり読み取れるのは以下のことです。
1日のトータル睡眠時間と日中の睡眠回数が減っている
→体力が増え活動時間が増えたため1日のおしっこ取替えの回数が減っている
→排泄機能が発達したため1日のミルクの回数が減っている
→1回当たりに飲む量が増えたため
これらは一般的にベビーの成長に伴って現れる変化だと思います。関連して、我が家が苦しんでいた(る)育児は大きく以下の2つです。
①頻回ちょびミルク(解消済)
②離乳食をあまり食べない(今も)
①頻回ちょびミルク…1日中ミルク…
👶は生後6ヶ月の頃まで頻回ちょびミルクでした。
当時は1時間毎に60mlずつあげていた(10mlしか飲まない時もありました)ので、1日中ミルクをあげている感覚でした。👶もずっと不機嫌でした。
6-7ヶ月の健診で医師に相談し、「泣いても耐えて時間をおいてミルクをあげてみましょう」とアドバイスをもらいました。👶のギャン泣き(むせて吐きそうになるほどの大泣き)に耐え、ミルクの間隔をあけると、少しずつ纏めて飲めるようになりました。最近は休憩しながらも1回あたり180〜240ml飲むことも増え、お互い授乳が楽になりました。
②離乳食が全然進まない…
今度は離乳食を食べないのが悩みです。特に生後10ヶ月を過ぎる頃までは、数口で拒否&癇癪を起こして完食することは1回も無かったので、頑張って作った時は落ち込んでました…。
離乳食の参考書には、幼児食までのステップとして以下の4つの段階が記載されています。
「ゴックン期」(目安:生後5〜6ヵ月)
「モグモグ期」(目安:生後7〜8ヵ月)
「カミカミ期」(目安:生後9〜11ヵ月)
「パクパク期」(目安:生後12〜18ヵ月)
目安の月齢に固執するあまり、なかなか形状と量がステップアップせず、体重も増えないことに焦りを覚えていました。
👶の発達状況に合わせて進めるしかないと思うようになったものの、なかなか進まないのは心配になります。
離乳食のステップアップにも影響する乳歯の生え具合について、現在生後11ヶ月の👶は下前歯2本が半分くらい出ていて、上歯1本が少し見えている程度です。これは他のベビーと比べて早くない様で、最近の歯科検診で『歯が生えてないからまだ食べなくても仕方ないよ。これだけ背も高くて大きかったら大丈夫。歯が生えたら食べられるようになるよ。』と言ってもらえた様で、少し安心しています。少しずつ完食できることも出てきて、👶の成長に感動しています。
何かと上手くいかない日々もありますが、生後8ヶ月頃に👶が10日間ほど鼻風邪で体調を崩していたことを思うと、元気に過ごしてくれていることが何よりと考えるようになり、精神的に少し楽になりました。
次回以降、育休中のお金や育休後の現在について纏めたいと思います!
