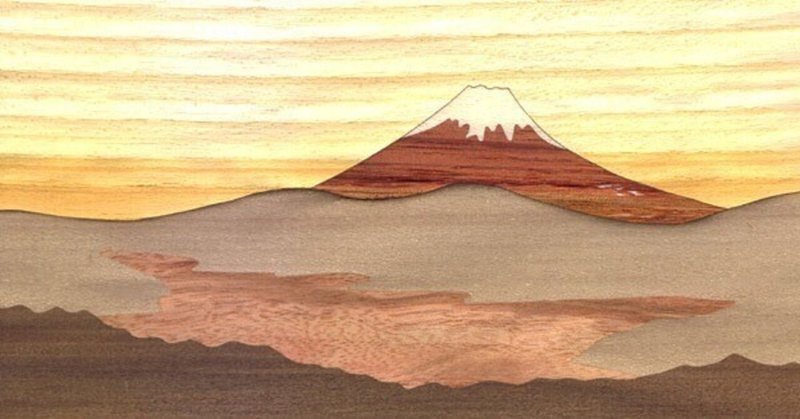
木材のアップサイクル:資生堂とヤマハの取り組みから学ぶ
「日本パッケージデザイン大賞2023」に資生堂「BAUM」が選ばれました
化粧品の容器に木材をアップサイクル利用
BAUMは資生堂のスキンケアブランドです
コンセプトを「樹木との共生」とし、
高級木製家具で有名な「カリモク」の製造過程で出る端材を ボトルの部品や容器のフタに使っています
木材のアップサイクルだけにとどまらず、
バイオPETやリサイクルガラスなど環境負荷を考慮した素材を活用したり、店舗での植物の育成し、その稚木などの植樹活動などもしています
今回の大賞は、製品パッケージの審美性に加え、
「樹木との共生」というブランドの取り組み全体における社会性の高さが評価されたそうです
BAUMに使用する木製パーツには、家具製造の過程で出る端材を再利用しています。その取り組みは、[カリモク家具]とのコラボレーションにより実現しました。できるだけ自然環境に負荷をかけないよう木という材料にこだわり、森林資源の有効活用を推進する木製家具メーカーです。東北や北海道地方で採取されるオーク材を無駄なく活かし、アップサイクルすることで蘇る素材には、言い尽くせない魅力があります。継ぎ目や天然木ならではの節や色むら。すべてが世界にひとつの個性であり、貴重な味わいなのです。
自然環境への配慮として、BAUMのパッケージに使用する一部プラスチック容器にはバイオPETを、ガラス容器にはリサイクルガラスを採用。そして外箱には適正管理された森林木材による製品であることが証明されたFSC森林認証紙を使用しています。
樹木は循環する資源の象徴。その樹木の恵みをきちんといただき、より良く巡らせるひとつの行動として、BAUMは植樹活動を行っていきます。パッケージの木枠で用いるオーク(ナラ)の木の苗木をBAUMカウンターで大切に育て、樹木の故郷の一つである岩手県の「BAUMオークの森」に植樹し、保全。育ったら採取し、再びBAUMに活用する循環をめざしていきます。
そういえば、楽器メーカーのヤマハも面白い取り組みをしています
ヤマハが作った「寄せ集め木材」のギター
ヤマハでは、ピアノをはじめ木製の楽器の製造のために、希少樹種も含め様々な木材を使用していますが、製造の過程で端材も結構発生するそうですそういった資源の有効利用と、今後の知見を蓄積するために、ファゴットやマリンバ、リコーダーやピアノの製造で出た端材でギターを作ってみたそうです
出来上がったギターは、さすがヤマハ!と思わせる完成度で、マジ物欲をそそりますが、残念ながら発売の予定はないそうです

『ヤマハが試しにつくった「エレキ」が面白い “牛肉の部位”に見えてきた』より

ヤマハでは楽器を作るために多くの木材を調達して使用しますが、中には、残念ながら楽器に使えなかった材料や端材が発生します。ヤマハではこれらを「未利用材」と呼んで、それらを資源として有効活用する取り組みを進めています。多種多様な楽器に用いられる木材には、これまでギターにはあまり用いられなかった木材も含まれますが、それらの魅力を再度見直し、ギター材料として蘇らせることで、ギターの新しい価値を探索しています。その際にも、材料のリサイクルの為に品質を妥協するのではなく、それぞれの材料が持つ価値を活かしたアップサイクルを目指します。
2023年5月29日まで、ヤマハ銀座店に現物が展示されているそうです
木のアップサイクルが、時計の針を巻き戻してくれることに期待
高度成長期、それまで木材で作られていた様々なものが、プラスチックに置き換えられていきました
人口増加に伴う大量生産、大量消費という時代背景のもと、
軽くて壊れにくい、湿気の多い気候風土でもカビが発生しない、
なにより均一で大量生産が可能で、価格も安いという機能的な側面と、
今の若い人には想像できないと思いますが、当時の感覚では「プラスチックの方が近代的でおしゃれ」という情緒的側面が相まって
あらゆるものがプラスチック製になり、
その結果、木工製品や漆の作り手が減り、家内制的な林業も衰退、多くの里山崩壊の一因になりました
今、時代は主客転倒し、「脱プラ」の追い風もあり、吸湿性や断熱性など機能性が見直され、「木の方がおしゃれ」「ぬくもりを感じる」「地球にやさしい」といった情緒的価値が主流になってきています
「木をプラスチックに」から、時計の針を巻き戻すように「プラスチックを木へ」…その積み重ねが、林業や里山の復活につながっていけばと思っています
「木賃」ではなく、「キチンと儲かる」木製品を
木のアップサイクルを持続的なものとして、里山再生につなげるためには、
「キチンと儲かる(正当な 安売りしない)価格付け」が大前提だと思います
今はあまり使いませんが、「安宿」という意味の「木賃宿」は、自炊の薪程度の宿賃というのが語源だそうです
木賃+手間賃レベルでは持続的な収入は得られません
そこに情緒的な価値やストーリーを吹き込み、「高いけど欲しい」と思える木製品を生み出すことが大切だと思います
今回の二つの企業の試みに、私が注目したのは、
木の利用が機能的な価値のアプローチではないこと
そして、化粧品や趣味の分野であることでした
BAUMは、クレンジングなどが 4000円台、ローションやミルクなどが 7~8000円台のどちらかといえば高価格帯のスキンケアですし、
ヤマハのギターは市販予定はないものの、仮に販売したら結構いい値付けでも売れるのではと思っています
消費者の環境に対する意識が高まり、
価格の高い安いではなく、エシカル消費などに代表される
製品の素材や生産過程、環境への配慮などを日常生活における購買の判断軸とする動きが広がっており、
企業側でもSDGsへの取り組みやCO2排出量の測定など環境保全への取り組みが求められる
こうした潮流の中で、里山や林業がきちんと儲かる 木のアップサイクルの試みに注目しています。
ページトップの画像は、「寄木細工専門店 箱根丸山物産」様の「寄木細工に使用する実物の模様」ダウンロードページから拝借させていただきましたhttps://www.hakonemaruyama.co.jp/yosegi-free-wallpaper.htm
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
