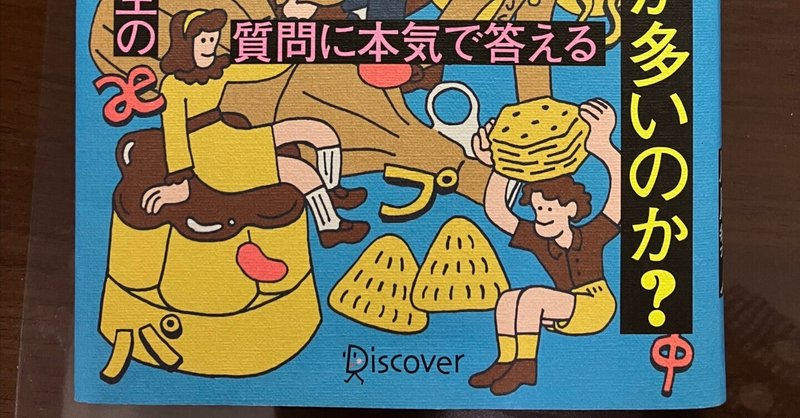
科学的・合理的な説明を使う中での非科学との向き合い方
川原繁人さんにご著書『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか? 言語学者、小学生の質問に本気で答える』をご恵贈いただきました。コロナ禍からさらにブーストがかかったように出版されていますね。まずは目次を。
はじめまして、言語学者です
朝礼:ことばはおもしろい
1時間目:濁点「゛」のなぞ
2時間目:「ぱぴぷぺぽ」にまつわるエトセトラ
3時間目:子どもの言い間違いを愛でる
昼休み:「わかった?」って聞いちゃダメ
4時間目:プリキュアに似合う音
5時間目:ポケモンの進化は名前でわかる
6時間目:原始人のしゃべり方
7時間目:世界と日本の多様なことば
放課後:まだまだ質問に答える
スペシャル対談:橋爪大三郎×川原繁人 ~社会学者と言語学者が考える「学び」とは~
私も小学生向けに言語学のテーマで自由研究をしようという本を出したことがあり,関心を持っている話題でした。
本書の特徴
概要
川原さんはこれまで音声学の啓蒙書,教科書から自身の研究テーマや言語関係の話題に関するエッセイまで広い射程範囲のものが出ています。今回の本は大きく3つのパートから成っています。
小学校(和光小学校)で4,5年生の希望者に行った授業(事前にもらった質問に答える形)
課ごとの追加解説
まとめと復習として社会学者橋爪大三郎との対談
扱うトピックの半分くらいは過去の著書で大なり小なり扱われているものです。ただそれらのトピックを小学生相手に料理し紹介するにあたり,どう情報をそぎ落としていくのかという点で情報の取捨選択の実演が見えます。なお,過去の著作で扱われているとは書きましたが,例えば/p/の音象徴とプリキュアの名前の関係のように過去の著作と解釈の変わったものもあります。
授業は(ほぼ?)そのまま収録。補足を活用
授業の部分は書き起こしと後から川原さんが付けた補足,さらに上級編としてレベルアップ解説の3つからなっています。授業部分の書き起こしは授業でついやってしまったミスも次のようにそのまま収録してあり,「そうそう!」となったりします。
まとめるとね,のどの奥には声帯が2枚あって,声を出す時に震えて音を出してくれています。でも,「け」って言う時には声帯が開いていて震えてないの。
じゃあ,「えげ」の時はどうなっているのかを見てみようね。
「母音」の部分……あ,「母音」って言っちゃダメだ。みんなには伝わらないものね。最初の「え」の部分は,前と同じように声帯は震えているね。そして「げ」に入ります。さっきの「け」の時と何が違うかな?
*補足*
思わず「母音」という専門用語を使ってしまっています。小学生相手に専門用語を使わずにどこまで伝えられるか,常に意識はしていたつもりですが,ぽろっと出てしまったのですね。ここでは自分で気がついて言い直しました。
他にも,補足はうまく活用されているところがあります。例えば,小さい頃「どなべ」を「どばべ」と言ってたという子に,その理由を説明するくだりでは次のようにより具体的な解説をしています。
みとが「どばべ」って言ってた時,「私,最後の『べ」の音で唇を閉じよう」って思ってたんじゃないかな。そうしたら,ちょっと早めに前の音でも唇を閉じちゃって,「な」のところで「ば」の音が出ちゃったんだね。
*補足*
この説明は実は不完全です。「どなべ」の「べ」の唇を閉じる動作だけが,「な」にコピーされたのであれば,「どまべ」になるはずです。
ですから,もう少し正確に言うと,「どなべ[donabe]」の「べ」の子音部分である[b]が,前の子音にコピーされて「どばべ[dobabe]」になったのです。ローマ字を習っていない生徒もいるので,授業では簡略化して説明しました。
身近な素材や視覚教材を活用
授業サポートページを見ても分かるように,これまでの著作でも登場した声帯のビデオや発音時のMRI映像などが活用されています。
この他『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』など特にいま子供たちに(大人も多いって?まあまあ)人気のマンガ,アニメからの実例や,おなじみポケモンを題材にした音象徴の話題などを扱っています。
非科学との向き合い方
授業の後半で扱われている質問のひとつに「野菜の名前はどう決まったか?」というものがあります。つまり,ものの名前の決まり方に関する質問です。例えば多くの言語学の授業だと,言語の恣意性,つまり名前と対象には有機的な繋がりがない(だからこそ同じ犬という動物を日本語ではinuと呼び英語ではdogと呼ぶ)として問題としません。
川原さんもこの問題には答がないとしていますが,同時にメッセージとして(旧約)聖書の「創世記」を取りあげ,聖書にあるということは,人間がずっと考えてきたことで,それを疑問に思ったことがすごい,そういうのを大事にしてほしいということを伝えています。なお,この後のレベルアップ解説では恣意性と音象徴と言語獲得の話題を取りあげて説明しているので詳しいことを知りたい方はそちらもどうぞ。
また,聖書はこの後も「世界の言語がなぜ同じじゃないのか?」という質問で登場します。勘の鋭い人だと「バベルの塔」が出てくることは予想が付くと思います。これも「正しくはない」説明ではありますが,「なぜ言葉が違うのか」も人間がずっと考えてきた問題で,これからも考えるべきテーマだと話しています。ちなみにこの話題(言語変化)も川原さんなりの説明がこの後に出てきます。
宗教的なものは非科学的としてまったく視野に入れないことが多いのは確かで,私もキリスト教系の大学に勤めていますが,礼拝などには時折参加するものの,それと自分の研究は別のように考えており,反省するところです。
おわりに
本書は言語学,特に音声についてかなり幅広い話題を気軽につまみ食いするのにちょうどよい内容・構成となっています。また,最後の対談は授業全体のふり返りとして機能しているほか,ここ数年川原さんが言語研究者が研究コミュニティに閉じているのではないか,もっと広く社会に目を向けるべきではないかということを強く危惧しており,そのことも取りあげられているように読みました。お世辞抜きに川原さんのこれからの活躍を約束させてくれる本になっていると思います。
ちょっと前の部分との繋がりが悪いので補足,補遺的に,最後に対談の一部にちょっと気になる記述があるのでそこだけ簡単に触れておきます。対談の中で手話の研究が盛んになっていることが触れられていました。
橋爪 手話と音声言語の自動翻訳機があれば,障害を持っている人にはすばらしいツールになるな。
この話題は私もまだ語るのに十分な資格がないと思いますが2つだけ。
第一に,「障害を持っている人」というのは,いわゆる聴覚障害とされる方の多様性,特にろう者は障害者という病理的な見方ではなく,マイノリティであるという見方があります。ひとまずオンラインで手軽に読めそうなものを。
第二に,(精度の高い)自動翻訳機は「障害を持っている人には」というより,聴者にとっても手話が理解できるのだからすばらしいツールになるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
