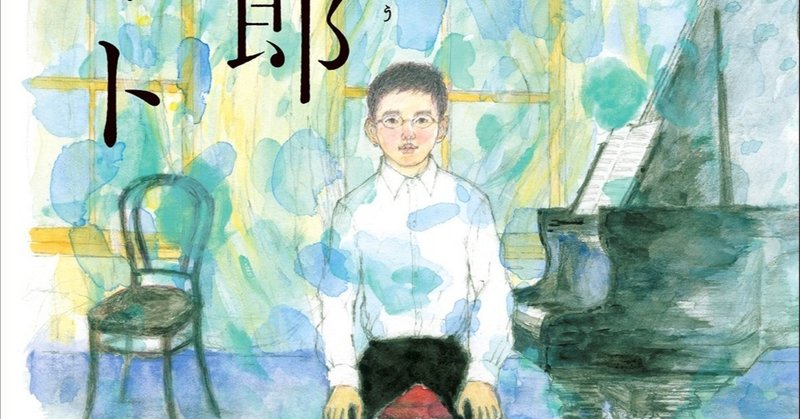
読書感想文と谷津の七転八倒③
【PR】
前回の続きなんだぜ。
小学校からしばらく、わたしは読書感想から離れています。
なんでかというと、単純に部活動などで忙しかったからです。思えば、中学高校時代は一生を通じて最も本を読んでいない時期で、多感なあの時期にたくさん本を読んでおけばよかったなあと後悔しています。まあ実はこの時期、嫌な経験があってなおのこと読書感想文から離れていましたし、あまり本を読んでいませんでした(端的に言うと、高校時代に出会った国語教師と全くそりが合わず、その教師が毎回のように800文字の読書感想を課してくるおかげで本当に読書が嫌いになりかけていたのです。もうその教師は教職を退いているはずですし、今更筆誅を加えても空しいだけなのでこのくらいにしておきます)。
本を読むという行ないは、著者の用意した正解を読むこと――。もし正解があるなら、わたしが読む必要なくね? だって、正解があるなら、誰かにその正解を聞けばいいんだから。
そんな思いに囚われていたのですね。
ところが、大学に入った時、そんなわたしの考えは覆されます。
先に大学生になっていた、国文学を専攻していた姉が、こんなことをわたしに言ってきたのです。
「ねえねえ、ロラン=バルトのテクスト論って知ってる?」
当然知るわけがありません。
姉が言うには、テキスト論というのは文学研究におけるアプローチ法の一つで、”著者”の存在を過度に意識せず、目の前にある本に存在する構造や”感動のメカニズム”のありかを探る、というスタイルで、ロラン=バルトという人が主唱したものだ、と。
その後、わたしなりに調べてみると、ロラン=バルトはこんなことを言っていました。
「作者の死」と。
これには注釈が必要ですね。この言葉は、小説の中身を規定する存在である「作者」というものはもう意識しなくてもいいのだ、「作者の言いたいこと」を探るのではなくて、「目の前の文章から浮かび上がるものは何なのかを探る」ことが本を読む行ないなのだ、ということなのです。
ロラン=バルトのテキスト論を知ってからなんです。わたしがまた本を読みだすようになったのは。
本を読むという行ないに正解はない。
ただそこには己の正解があって答えがある。
そのことに、自由を感じたんですね。
そしてそれから、わたしの読書感想はどうなっていったかというと……次回に続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
