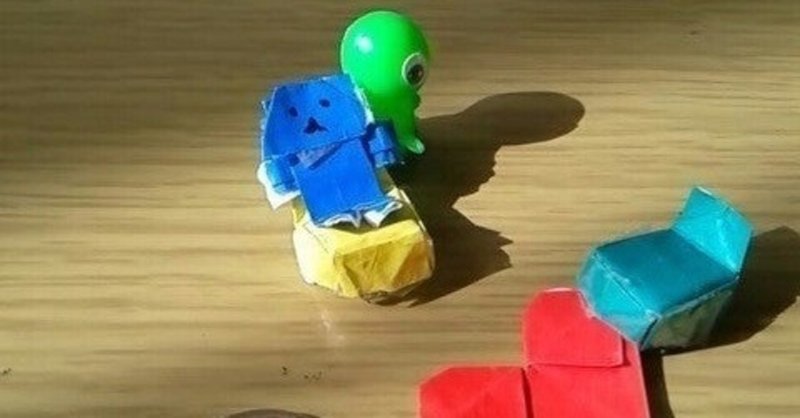
資源を通じたナショナリズムが台頭?
この流れもグローバリゼーションからナショナリズムへの変化の一部なのか、それとも一種の対中政策なのか?資源が少ない日本は、常に想定しておかないといけない課題の一つだろう。
上記記事の通り、パプア政府はカナダのバリックゴールド社と中国の紫金鉱業集団が95%のプロジェクト権益を所有する、ポルゲラ鉱山の採掘権(2019年8月に期限切れ)の更新申請を認めず、また同国裁判所も鉱山の支配権が同国政府に戻ったと発表。加えて2020年8月25日、ポルゲラ鉱山の20年間の採掘権を国営企業・クムル・ミネラルズ(KMHL)に供与した、と政府が発表した。
中国の金採掘大手の紫金鉱業集団が同社最大の金鉱権益を失うリスクが高まったことを意味する。紫金鉱業は2015年、ポルゲラ鉱山の採掘権を持つBNLの株式の50%を2億9800万ドル(約316億円)で買収。2019年には紫金鉱業の金生産量の21.6%に当たる8.83トンがポルゲラ鉱山から配分され、5億2600万元(約82億円)相当の純利益をもたらした
一般的に鉱山から出たキャッシュフローの一部は、同国政府の税収になり、経済的なメリットのみ考えれば、国営化が必ずしもベストでない選択肢、というのは比較的理解されやすいかと思います。しかし同国政府が事実上の強制剥奪を行ったのは、それ以上の意味があるのでしょう。
似たような流れとして、インドネシア政府はニッケル鉱の全面輸出禁止を、2020年1月から開始した。要するに、掘り出した鉱石だけを輸出しても市場価格通りで、付加価値はあまりなく、精錬所のある国で大きな価値に代わる(特にニッケルは、鉄鋼のメッキ材なので、製鉄所が多いところが消費地となる)わけなので、インドネシア国内で付加価値を高めてから輸出してね、お金をちゃんと落としてね、という意味です。
インドネシア政府の動きがあったからどうか分からないが、2020年になって、日本の住友金属鉱山もインドネシアでのニッケル鉱山の権益持分を下げていたり、するそうです。
天然ガスの世界でも、資源ナショナリズム、というか、資源輸出国が途中で条件設定を変更し、国営企業を介入や比率を上げるなど、どのように輸出国に多くの資金(税金等)がちゃんと落ちて、雇用も生まれるか、という『国益優先』というスローガンのもと、政治的な側面を強く促されるわけである。
日本の商社が関わった、そのような案件の一つはロシアのサハリン2LNGプロジェクトであろう。またタイやインドネシアでも似たようなケースが見られるようである。加えてコロナ禍において、経済が落ち込み、資源輸出国の税収確保のためにも、もっと『資源ナショナリズム』の考えがはびこり始めても、不思議でないような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
