
楽譜のお勉強【84】マリオ・ダヴィドフスキー『シンクロニズムズ 第9番』
マリオ・ダヴィドフスキー(Mario Davidovsky, 1934-2019)はアルゼンチンに生まれ、アメリカ合衆国に帰化したアメリカの作曲家です。今回読む『シンクロニズムズ 第9番』(»Synchronisms No. 9« for violin and tape, 1988)を含む『シンクロニズムズ』のシリーズは、彼の代表作であるとともに、アメリカ発の楽器と電子音響のための音楽の中でも重要な作品群に数えられます。コープランドやバビットに学んだダヴィドフスキーの音楽は、アメリカの大学シーンを中心に長年流行したアカデミックな現代音楽のサウンドが特徴的で、アメリカ現代音楽の一面を強く体現していると言えるでしょう。
『シンクロニズムズ』のシリーズは全部で1962年から2006年にかけて、ダヴィドフスキーのほぼ全創作時期に渡って12曲が作曲されました。第1番から第12番までの編成は次のとおりです。1) フルートと電子音(1962)、2) フルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、テープ(1964)、3) チェロと電子音(1964)、4) 合唱とテープ(1966)、5) 打楽器アンサンブルとテープ(1969)、6) ピアノと電子音(1970)、7) 管弦楽とテープ(1974)、8) 木管五重奏とテープ(1974)、9) ヴァイオリンとテープ(1988)、10) ギターとテープ(1992)、11) コントラバスとテープ(2005)、12) クラリネットとテープ(2006)。大小さまざまな編成と電子音が繰り広げる音響が魅力です。タイトルの「synchronism」という語は「同期」と訳されます。実際に電子音と楽器の音がさまざまに同期を試み、一つの音響体を作り出していくことが作品の主眼になっています。
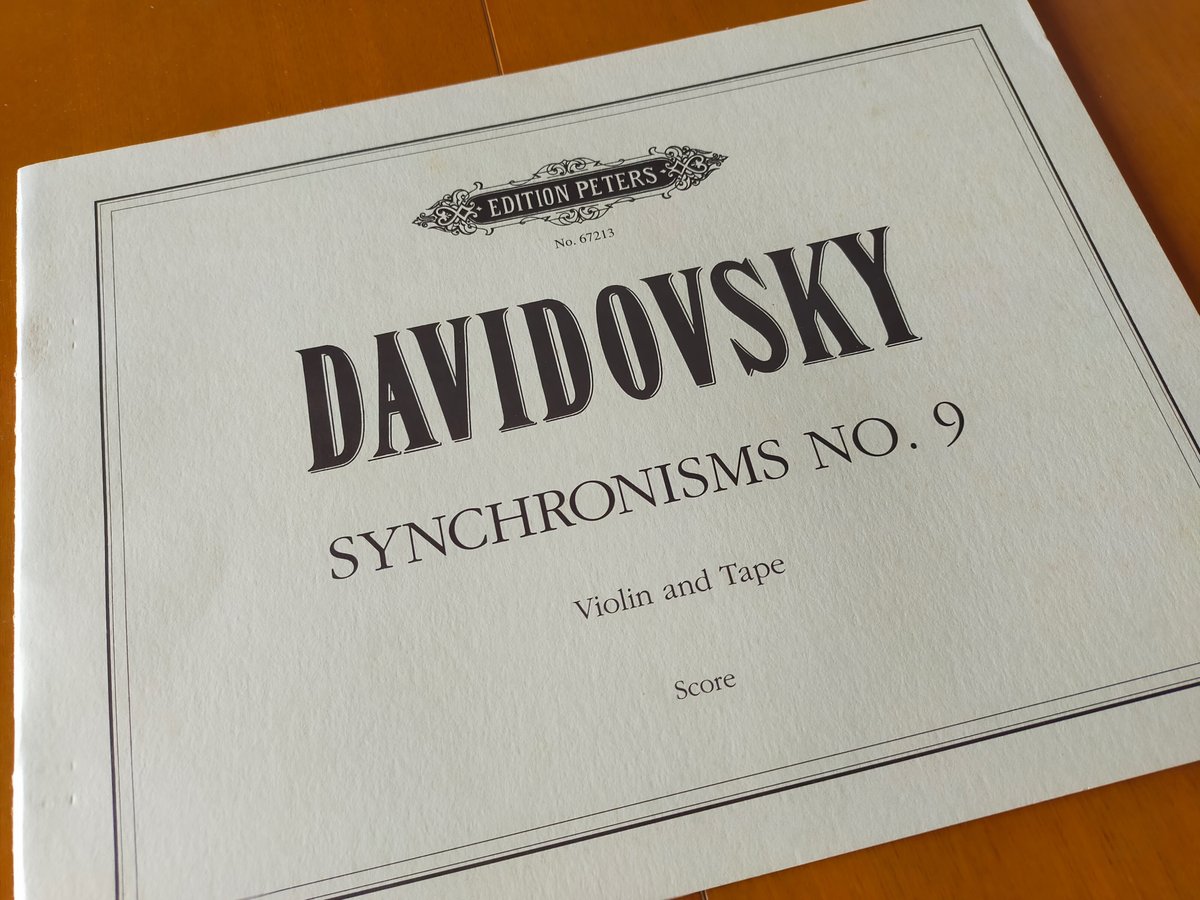
ヴァイオリンとテープのために書かれた第9番は、多くの箇所でテープ音とのユニゾンによる同期を求められるため、演奏家は神経を尖らせます。ユニゾン箇所では、テープの音色もヴァイオリンとよく融和するように作られており、そこから少し逸脱する音の身振りが上品な音響空間を作りだす仕掛けです。曲の冒頭はほとんど調性音楽かと思うような完全4度上行モチーフで開始しますが、緩やかに音型が下行していく中で調性感はすぐに消失します。協和音程や反復音型を多く用いているのに、セリエリズムの影響を強く受けたアメリカ・アカデミズムの響きがするのは少し不思議な感じがします。これはやはりバビットやカーターと同様に、要所要所に脈絡を感じない短9度の響きを入れたりしていること、極端な跳躍音型が突飛に現れることなどが関係していると思います。
アメリカ・アカデミズムの現代音楽の響きの魅力はその透徹とした抽象性だと感じています。そういう感性で楽譜を読みながら音を聞いていると、何箇所か強い違和感を感じる箇所があります。例えば42小節目では、4本の弦をアルペジオで上下行する分散和音音型が現れますが、これは極めてロマン派的な音楽と結びつきやすいジェスチャーです。音は少しは吟味されて調性感の緩和は目指されいるように見えますが、全く調性を感じない音列ということもありません(和音進行C#D#A#E→AFABb→GFAB、低音から高音の順に記述)。この音型にはびっくりしましたが、その後の展開を見てみると、ちょっと布石のような感じもあります。この後、もっと抽象的で自由な形で上行音型と下行音型が大きくテンポを揺らしながら電子音と掛け合うセクションが長く続きます。上行と下行の運動性を素早く提示することで後続セクションの方向性を示したとも解釈できるかもしれません。
後半では電子音響が複雑さを増していきます。そうは言っても、現代の電子音楽のようなものすごく複雑なノイズとは比べるべくもないのですが、これはヴァイオリンとの関係への配慮だと思います。基本的にテープ・パートは3段の五線譜で音高が書かれていますが、後半では音高を正確に示すことのできない記譜が増えていきます。その音色の多様さに呼応するように、ヴァイオリン・パートにもピツィカートが多用されていき、また弓の使い方も細かく指示されていくようになります。最後はフォルテ4つの激しい強奏で終わりますが、なんだか唐突で脈絡のない終わり方のような気もしました。
この作品全体を通して一番魅力的と感じたのはやはりユニゾンの扱い方とユニゾンから外れる音の身振りの面白さでしょうか。アメリカ・アカデミズムの現代音楽の作曲には、あまり惰性を感じる箇所がありません。一瞬一瞬をしっかり考えて作曲してあることが多いので、パターンとして読めるものがほとんどないのです。その抽象性は数多くのファンを獲得するのには向いていなかったのかもしれませんが、作曲に向き合う姿勢を感じる上では大変刺激を受けます。難しい作曲に取り組むとき、カーターやバビット、ウォリネン、ダヴィドフスキーといった作曲家に思いを馳せることがしばしばあります。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
