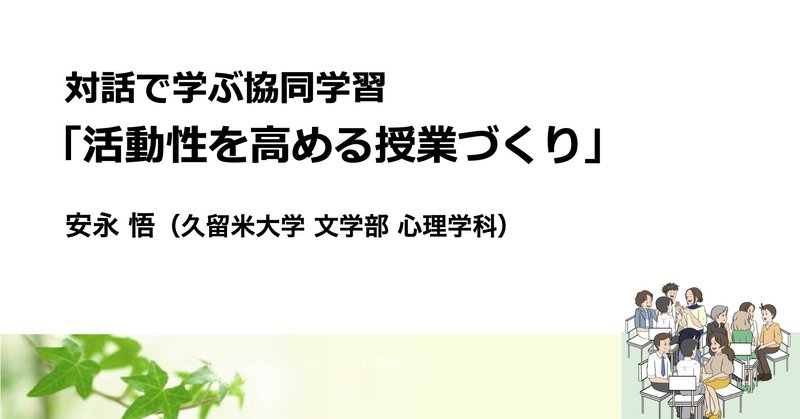
第3回 仲間づくり (その2) 安心して学びを深め合える仲間づくりのために
事前に登録していただいている読者からコメントが届きました。その全文を以下に掲載します。わたしからの返信は次回になります。
*
第3回(その2)は相模原看護専門学校が担当します。今回の担当は岡田佐枝子です。臨床で10年あまり、看護教員として働いて20年以上になります。臨床の場ではさまざまな診療科を経験しました。そこでの失敗も含めた色々な体験は、教員として学生に話をする際にとても役立っています。
基礎看護学を主に担当し、共通基本技術のコミュニケーション、看護過程、日常生活援助技術の食事、排泄、移動、診療援助技術などに携わっています。なかでも、担当してもっとも刺激を感じるのは基礎看護学実習です。長年看護師として働いていると、当然のことと捉えてしまっていることについて、学生から質問を受けることがあります。改めて聞かれると、自分も理由を知らないことがあり、新たな視点にハッとさせられます。常に疑問をもち、学び続けることができるよう努めています。
第2回までの内容を拝見し、学生の協同学習について、自分が何となく気にしてはいたものの積極的に答えを探していなかったことについて、そう考えればいいのかと膝を打つような思いをしました。
今回のテーマの「仲間づくり」について、本校の2人で話し合いました。自分の行っている授業の内容や意識しているかかわりについて、安永先生にアドバイスを頂けると有難いです。
◯仲間づくりの継続性について
私が仲間づくりとして心がけていたことで思い出すエピソードは、一年生の4月から始まるコミュニケーションの講義での導入です。
専門学校では、高校卒業直後の18歳から50歳台まで、さまざまな年齢の、異なる経験を持った学生が集まります。そこで、新入生の緊張を和らげ、クラスの人間関係をつくるためアイスブレイクを行いました。誕生日順に並んでもらっての伝言ゲームや、じゃんけんでの勝ち抜きゲームなどを行なうことで、少しずつ仲間との関係性を築けるように意識しました。
また、お互いの外観からどんな人だと思うか考えフィードバックしたり、ことばで図形を伝えるゲームを行ったりしていました。このゲームでは、外観だけではわからない相手との言語的・非言語的コミュニケーションの大切さを学んでほしいと考えました。時間は最初に学生に伝え、時計やストップウォッチを使用して、時間厳守で取り組みました。
毎回相手を変えてゲームを行い、できるだけ多くのクラスメイトと話せるようにしたことで、話したことのない相手と会話のきっかけになり良かった、という声はありましたが、それで終わりになっていました。その場その場での仲間づくりで良いのか、何かその後の関係づくりとして継続させる工夫があるのではないかと考えています。
◯協同学習で学びを深める
看護は実践の科学と言われます。実施する看護援助の根拠を、自分の体験を通して明確にしていくことは、大きな意味があると感じています。
看護形態機能学の講義では、看護教員が解剖生理学の一部を講義し、生理機能の演習とその変動の意味の分析をグループで行っています。「息をする」の演習では、安静時と5分間運動後の呼吸数測定や、臥位と座位、腹帯をまいた状態での肺機能検査など、生理機能の測定を実施し、得られたデータの意味付けをグループで検討します。なぜ体位が変わると、肺活量が変わるのか、呼吸が苦しい患者さんへの援助はどうすれば効果的なのかを考える根拠になるためです。
学生はこの演習を通して、改めて「ひと」の身体の仕組みと働きを、体験とテキストの読み込みから、関連づけて考えていました。自分たちの身体を使うことで、何故呼吸困難の際に、仰臥位よりも座位が楽なのか、重力に影響を受ける横隔膜と腹部内臓の移動のイメージ化ができてくると、ストンと落ちる感じがわかりました。
また自分が納得した内容を、テキストを広げたり図を描いたりしてグループメンバーに伝える姿も見られました。
しかし、この形態機能学の演習で残念に感じたのは、個々の学生の事前提出された課題は良くできていたのに、グループでまとめた内容は、完成度が下がってしまった時です。学生は効率を優先するのか、グループメンバーで課題を分担してしまうこともあり、授業中に再度話し合いで内容を深めるよう説明したこともありました。一方で話し合いはしていてもなかなか内容が深まらず、何とかまとめたものの十分な検討ができなかったこともあります。
このような話し合いの場で学生同士が安心して意見交換するためには、教員のファシリテーターとしての関わりや環境づくりが重要です。正解、不正解だけではなく、お互いにどんな意見も否定しないで一旦受け入れることを始めに伝え、教員も含めて実行する必要があります。その安心感がないと、学生は間違うことを恐れ、自分の意見を言わず、他の学生や教員の顔色ばかりうかがうようになると考えます。自分は、学びの過程にある学生に、この安心感をもってもらえているだろうか、威圧的になっていないだろうかと、改めて振り返っています。
第2回(その5)で言われたように、学生を信じて任せることと教員としてのファシリテーションの難しさを痛感します。適切な介入のタイミングと方法について良い方法があれば、と悩んでいます。
◯協同学習の評価のあり方
このようなグループワークでよく出る問題は、取り組み状況の差です。事前に課題を提出してもらい、授業当日に話し合いができるようにと計画しても、課題を十分にやってこない学生がいます。
グループメンバーからも、「自分はがんばってやってきたのに、その内容を『どう書くの?』と聞かれて写されるばかりで、嫌な気持ちになる」などの批判的な意見が出され、グループの雰囲気も悪くなりがちです。他の学生に伝えることで、自分の学びにもなるとは思いますが、学生の不公平感はぬぐえません。課題の取り組みが十分でない学生は、何らかの理由で時間がなかったり、課題への動機付けが不十分だったり、課題内容の理解ができていなかったのだと感じています。
そのため課題を提出しない学生へは、個別指導を行なったり、事前課題を出さないことで減点したりしていますが、点数をとるための提出になるようで、これもいかがなものかとも思っています。
また評価はレポートで行いますが、評価の視点を提示し、自己評価も書いてもらっています。実施はしなかったのですが、グループ間でメンバーの相互評価を行うというのは、どうでしょうか? 他者からの視線や誉めことばがあればがんばれるというのは、外発的動機付けであり、内発的動機付けにならないのではないかと悩むところです。自分たちが成長するための学びであるはずなのにと感じ、評価のあり方についてももやもやした感じがぬぐえません。
お互いに学びを深めるための事前準備を整え、学びを深め合えるには、どのような方法が効果的なのか、ご教示いただければありがたいです。
これまでのやりとりの往復で、教員が学ばせたい内容や伝えたい内容を押し付けるのではなく、学生が必要な学習内容を自ら学びとるように関わることが望ましいと再認識しました。
しかし、学習内容の保証と言う点では、教員としてやはり不安もあります。看護師としての自分たちがより適切だと考える内容や方法は、根拠と共に学生に伝えることが良いとも言われていました。
学生には、学び方を学び、看護師として自ら成長し続けられる人になってほしい、根拠ある学びを自ら得てほしいと考えます。そのための仕掛けづくりとして、教員自身が成長し続けることが必要だと感じています。そのような教員同士の共通認識をどう作っていくかが課題です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
