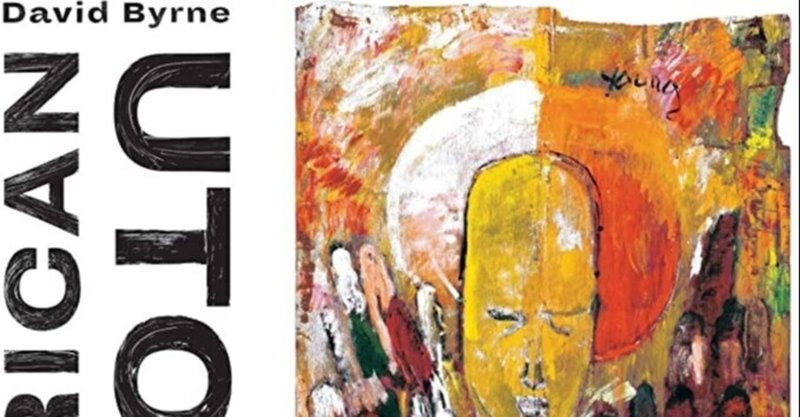
David Byrne / American Utopia
David Byrne、ディヴィッド・バーン。元Talking Headsのボーカル兼ギターにして、ポストロック/ニューウェーブのアイコンの一人です。ロックにワールドビートを持ち込み、ロックのリズムを多様化したパイオニアの一人。彼が2018年のアルバム「American Utopia」を基にしたブロードウェイミュージカルをスパイク・リー監督と組んで映画化したのが本作。現在放映中です。
アフロビート、アフリカ音楽やラテン音楽を取り入れたリズムの坩堝。バンドメンバーにはブラジルから来たメンバーも来て国際色豊か。バーン本人もスコットランドからの移民です。最初は人間の脳の構造を説き、コミュニケーションの話、自叙伝的な話も織り交ぜながら、移民国家アメリカの直面する人種差別の問題、BLMの問題に切り込んでいきます。それを支えるのが世界中のリズムをミクスチャーした力強い音楽と多国籍なバンド。「他人とのつながりの中で、協調することで生きて行く」。作り上げられた強靭な音楽に支えられ、一貫したメッセージを感じます。
ディヴィッドバーンも撮影時67歳。さすがに衰えも感じるものの、音楽が始まると魔力を帯びていく。発せられるメッセージが力強く響いてくる。音楽の力は演奏者をエンパワーメントすることだと思います。それは口ずさむだけであっても。メッセージを歌にすることで心を動かすことがあるし、完成された音楽はステージの上で魔法を産む。演者しかいないシンプルなステージゆえに音楽の力と、そこに込められたメッセージが純粋に伝わってきます。こういう作品を見ると音楽の力、ロックの力を改めて感じますね。一流のプロフェッショナル達が全力を出し切って作り上げた結晶。
しかし、この映画、単館公演かと思ったら全国配給なんですね。こうした作品が全国で見られるのは素晴らしいことだと思います。お近くの方は是非。
バーンは昔からこうした「演劇とライブの融合」に積極的なアーティストで、1983年12月、ハリウッドのパンテージ・シアターで撮影された傑作ライブビデオ「Stop Making Sense(1984)」を残しています。そちらも印象に残る素晴らしいライブビデオでした。
この映画(というかブロードウェイ版)のサントラも出ているのですが、サントラを聴きながらレビューするとそのまま映画のネタバレになりそうなので、今日はアルバム「American Utopia(2018)」を聴いてみます。
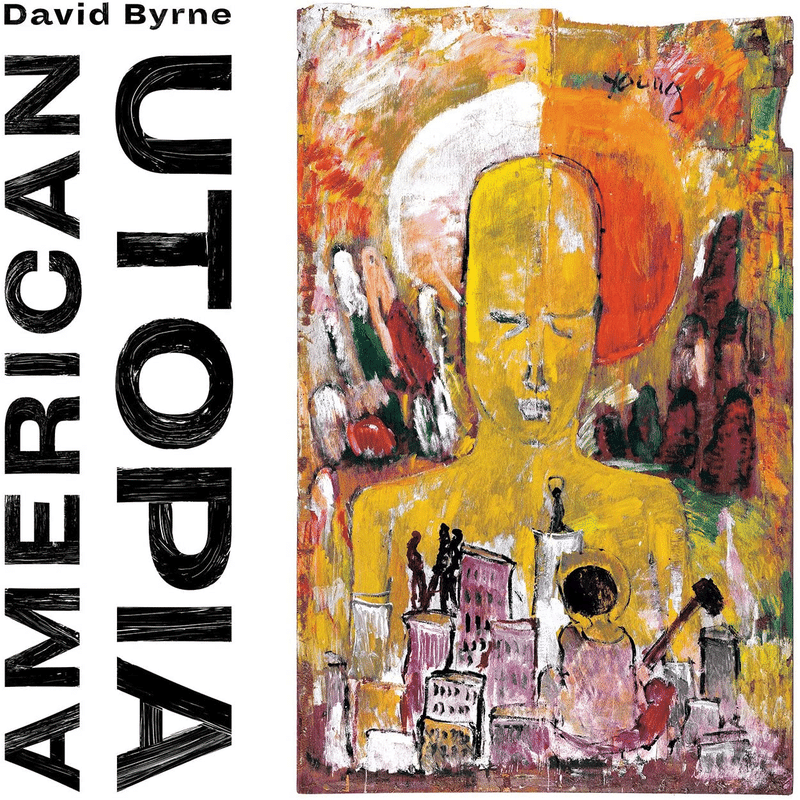
活動地域:US、UK
リリース:2018年3月9日
ジャンル:Rock、new wave、art pop、worldbeat、electronic
活動年:1971-現在
レコーディングメンバー:Wiki参照

総合評価 ★★★★☆
味わい深いいいアルバム。2018年のロックアルバム。新しい領域を切り拓くというより、掘り下げる。自身のスタイルや作家性を掘り下げ、豊かな音世界を生み出している。スタイルの確立した音楽家が自分の領域をさらに深く掘り下げた傑作。大人による大人のためのロックミュージック。サブカルチャー、カウンターカルチャーではなくハイカルチャーの風格がある。
++++
1.I Dance Like This 3:34 ★★★★☆
ピアノメイン、かすかにアコギの音か、いやペダルノイズか。ちょっとしたノイズから他の音が入ってくる。バラード調で始まるが、コーラスではビートが強調される。シンプルだがトライバル感があるビート。音像はアコースティックな印象が強い。異質な二つの世界が混在する、行き来するような曲。
2.Gasoline And Dirty Sheets 3:20 ★★★★
それほどフックが強いわけではないがボーカルとメロディに説得力がある。ビートがいきいきとしているからだろう。ある時点からロックの中心がオルタナティブに移ったと思うが、そこで重要なのはギターよりベース音になった気がしている。ギターで言えば5弦6弦の低音部分と言うか。リズム、ビート、リフの方が重要。この曲もボーカルに絡み合う楽器で一番よく聞こえるのはベース、そしてリズム。
3.Every Day Is A Miracle 4:46 ★★★★
不安定なコード進行のヴァースからシンプルで安定したコーラスへ、対比によって開放感が出る。水が跳ねるようなリズム。ポストパンク的な言葉の羅列がヴァースのつかみどころの無さを強調する。それらの断片が「毎日が奇跡」というコーラスに吸収されていく。日々の混乱、世界の混沌を日々への感謝に着地させるように。人生賛歌でもあるが、説明を除外した見方によってはかなりシニカルでパンクな曲でもある。
4.Dog's Mind 2:30 ★★★
”US”のころのピーターガブリエルみたいな曲。考えてみるとピーターガブリエルやポールサイモンがトライバルビート、ワールドビートを取り入れたのはトーキングヘッズやThe Pop Groupあたりが震源地なのだろうか。時系列的を追ってみないと分からないが、そんな気がするな。インタールード的な曲。メタル界にトライバルビートを持ち込んだセパルトゥラのルーツもその頃かな。
5.This Is That 4:31 ★★★★☆
インダストリアルな質感、さまざまなノイズ音、エフェクト音が出てくるがこのあたりは生音で出しているのだろうか。どこか息遣い、演奏者の生身感を感じられる。ジャングルのような、さまざまなものが蠢く音とも言えるが、一つ一つの音は都会的。雑踏と野生を感じる音。リズムがしなやかだからだろう。都会に紛れ込んだ野生と言うべきか。考えてみたら私たち人間も野生の生物なのだけれど。野生の部分が都会で窮屈になるのかもしれない。暴走するのではなく、悠然としたしなやかなたたずまいで曲は進む。
6.It's Not Dark Up Here 4:11 ★★★★
引っかかりがある、反復するリフ。トライバルビート。Stop Making Senceのような、昔のトーキングヘッズを思い出させるがだいぶビートは穏やかになっている。スロウにじっくり攻めてくる。この曲もピーガブ(ピーターガブリエル)感が強いな。もともとそんなに共通項は感じなかったのだけれど。映画でも披露されたが4,6はピーガブ感があった。ベースの音にトニー・レヴィン感があり、歌メロにピーガブ感がある。案外歌い方が似ている(きた)のかもしれない。
7.Bullet 3:10 ★★★☆
アコースティックで開放感がある、輪になってスロウなダンスを踊るような。明るい曲調。歌詞は撃たれた男の歌。「弾丸が彼の肌を引き裂いた」。牧歌的な音像で物騒なシーンを細かく描写していく。
8.Doing The Right Thing 3:39 ★★★★☆
「正しいことをする」「私は常に正しいことをする」。キャンセルカルチャーにさらされた有名人のストレスだろうか、あるいはSNSの相互監視か。自粛警察か。ジョージオーウェルの1984では「ビッグブラザー」、中央集権の巨大機会による監視社会が描かれたが村上春樹は1Q84で「スモールピープル」小さな人々に監視される。相互監視。曲調が疾走感を増していく。空間を浮くような、浮遊感と高揚感のある曲調。あるいはそこまでシニカルではなく「正しいことをしろ(人種差別をやめろ)」という歌か。
9.Everybody's Coming To My House 3:30 ★★★★★
ジャジーなオープニング、からのポストパンク感が強い歌い方。そうそう、デヴィッドバーンはもともとこんな歌い方だった。だからピーガブとは違ったんだよな。やや性急なリズム。飛び跳ねる電子音。飛び跳ねる言葉。電子化された祝祭。リバーブが適度にかかったリズムはなぜかコンクリートのビル群を想起させる。工事現場なのか雑踏なのか。コンクリートの壁に反響する感覚が素材を思い浮かべさせるのか。潜っていく、入り込んでいく感覚がある曲。
10.Here 4:14 ★★★☆
たたずむような曲。悠然としたリズム。大草原、あるいは雑踏の中で自分のペースを守るように。「Here Is The Alien」という歌詞が耳に残る。Stingの「Englishman In New York」的なテーマだろうか。皆とこかで異邦人の感覚を持っている。日常の中でどれだけ異邦人として扱われるか、「自分の居場所」と思えるところがどれだけあるか。日常の中で疎外感を感じる比率の差がマイノリティとマジョリティなのだろうか。考えが広がりながら終曲。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
