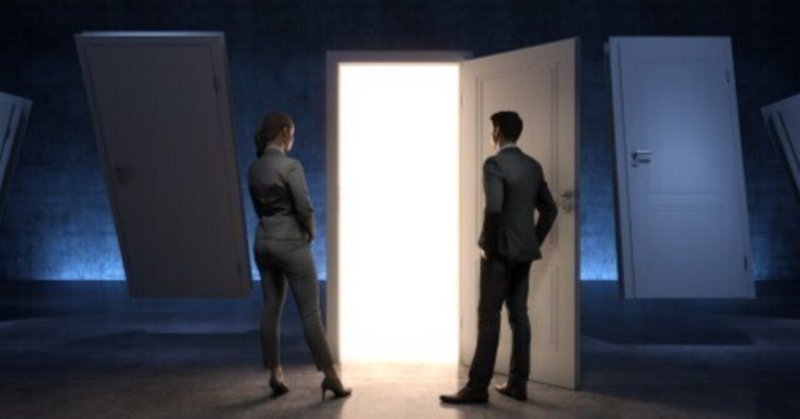
プロダクトマネージャー(PdM)になるために_#11_企業成長に合わせた変化の導入テクニック
IT業界で引く手あまたのPdMについて学習しています。
前回の【#10_MECEな検証を実現するテスト方法一覧】では以下10個の製品発見を成功させるテクニックの内、⑤~➈を一気に学習しました。
#10はアイディエーションで顧客と一緒に考えるマインドを作り、一緒に問題を見つける過程の中で共感を創るツールであるプロトタイプを使って「何をどのように検証するか」を詳細に把握しました。
内容はすべて覚えるものではなく、必要な時に確認する参考書のような位置づけになります。
今回はいよいよ最後の⑩とスケールアッププロセスについて学習していきます。
文字数:約4,400
成功する製品を発見する10のテクニック
<① フレーミングテクニック>
<② プランニングテクニック>
<③ アイディエーションテクニック>
<④ プロトタイピングテクニック>
<⑤ テストテクニック>
<⑥ 実現可能性テスト>
<⑦ ユーザビリティテスト>
<⑧ 価値のテスト>
<⑨ 事業実現性テスト>
<⑩ トランスフォーメーションのテクニック>
参考図書
④ 成功するためのプロセス~製品の発見のテクニックPart.4~
概要 ⑩トランスフォーメーションのテクニック
・開発チームは会社に新しいテクニックを取り入れ、仕事のやり方を変えるのは「言うは易く行うは難し」
・組織がこれらの変化を成し遂げるのに役立つテクニックを紹介していく
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P312
■Chapter58 ディスカバリースプリントのテクニック
・ディスカバリースプリントは一週間のタイムフレームで、開発チームが直面している重要な問題やリスクに取り組めれるようにデザインされている
・週5日間を次のように設計する
1日目:問題空間をマッピングして問題を構成し、解決すべき問題とターゲット顧客を選ぶ
2日目:ソリューションに対するいくつかの異なるアプローチを追求する(ソリューション案を出す)
3日目:さまざまなソリューションの候補を絞り込み具体化する
4日目:高忠実度のユーザープロトタイプを作る
5日目:実際の顧客に使ってもらい反応を見る
・開発チームがアジャイルに移行するとき多くの会社はアジャイルコーチと契約するか社員を雇う
・ただ注意すべきはアジャイルコーチはエンジニアリングとリリースの側面は理解していても製品発見の側面は理解していない
・アジャイルコーチは問題が多かったため、元PdMや元デザイナーのディスカバリーコーチの需要が高まった
・ディスカバリーコーチはエンジニアの仕事を共同作業に組込む方法を知っており、エンジニアの時間を配慮しながらも、エンジニアイノベーションの中で果たす役割を理解している
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P313〜317
■Chapter59 パイロットチームのテクニック
・組織内に、「変化にすぐ飛びつく人」「ほかの人が使ってうまく行くか確かめたい人」「納得するまである程度の時間がかかる人」「変化が嫌いで強制されなければ変わらない人」がいる
・一気に変化しようとするとラガード(変化を嫌う人)は抵抗し妨害さえするかもしれない
・ここで有効になるのがパイロットチームで、広範囲に展開する前に組織の一部で変化を実施する
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P318〜319
■Chapter60 組織をロードマップから切り離す
・多くの開発チームが開発ロードマップをやめたがっているのに組織は保守的で、時代遅れの四半期ごとの開発ロードマップにとらわれていることが多い
・こうした組織の硬直性に対して
1、既存ロードマップを半年から1年続ける計画を立てる
2、開発ロードマップの項目に言及するたびにその機能が貢献すると考え、実際のビジネスのアウトカムを思い出させる
・新しい機能が目標に達しない場合は、学習したことを具体的に指摘するとともに、望ましい結果を得る方法としてほかのアイデアを持っていることを説明する
・目標は組織が注目するポイントを時間をかけて、「特定の機能を特定の期日に開始するマインド」から「ビジネスの成果にこだわるマインド」に移すこと
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P320〜321
概要 スケールアップにおけるプロセス
・企業が成長するにつれてリスクを嫌うのはよく分かる
・企業が獲得したものを守ろうとする1つの方法はエラーやリスクを減らす名目で物事のやり方を標準化しプロセスを決めること
・ここからのテクニックは、成長とスケールアップを続けても持続的イノベーションを行う能力を維持することを目的とする
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P322~323
■Chapter61 ステークホルダーを管理する
・多くのPdMにとってステークホルダーの管理は最も嫌いな分野
・まずここでは誰がステークホルダーかを明確にし、PdMがステークホルダーに負う責任がなにかを考える
<ステークホルダーの定義>
・スタートアップは規模が小さいのでステークホルダーがほとんどいない
・ステークホルダーかどうかを判断する一つに「拒否権を持っているか」(=開発チームが仕事をスタートするのを妨げられるかどうか)がある
・ステークホルダーの一覧
+経営陣(CEO、マーケティング、販売、技術の各部門のリーダー)
+ビジネスパートナー(製品開発やビジネスで提携)
+財務部門(製品か財務上企業モデルに適合していることを確認する権限)
+法務部門(製品が正当化できることを確認する権限)
+コンプライアンス部門(製品が規範やポリシーを遵守していることを確認する権限)
+事業開発部門(製品が既存の契約や関係に違反しないことを確認する権限)
<PdMの責任>
・PdMはさまざまなステークホルダーの考えや制約を理解し、理解したことを開発チームに伝える責任がある
・各ステークホルダーの制約や懸念を理解するだけでは足りず、PdMはすべてのステークホルダーに問題を理解していると納得してもらう必要がある
・この責任を果たせなければ、ステークホルダーは不信感を募らせPdMをコントロールしようとする
<良いことが悪いことに変わる>
・組織をスケールアップするとき、スタッフの質を維持しながら成長を管理することは難しい
・アンチパターンとして非常に業績が良く、積極的に成長しているのに意図せず良い行動を悪い行動に置き換えてしまうことがある
・アンチパターンのシナリオは、後期のスタートアップあるいは成長期の企業において、これから雇おうとする人はすでに成長を止め、イノベーションの能力を失ってから時間が経ち、ブランドが確立された大企業出身者であり、すぐに辞めてしまう
・仮にGAFAに代表されるような強い企業経験者であっても以前のやり方をそのまま適用としてしまう
・問題は大企業出身者だからではなく、製品開発に弱い企業出身ということ
・このような変化のタイミングでの経験者採用時に発生しがちな問題を避ける方法は
1、非常に強い製品開発文化を持つこと
2、会社の文化や仕事のやり方を面接や新人研修のプロセスで明確にする
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P324〜332
■Chapter62 製品開発での学習を共有する
・スタートアップ期は製品開発チーム=会社のようなものなので学習したことは自然と共有される
・企業がスケールアップしてくると学習したことの共有が難しくなる
・テクニックとしては、週次あるいは隔週で全員参加型の会議を開き、開発リーダーが30分程度で製品発見で学習したことを発表する
・細かい話ではなく、何がうまくいき、何がうまくいかなかったか、次に何に取り組むかなど
・このテクニックを実施することと合わせて目標に取り組むために行う
<学習したことの共有を通して得られること>
1、物事が思うように進んでいないとき共有することで、参加者の中に結果を説明の考えを思いつく人がいることもある
2、ほかの開発チームが何を学習しているかを知ることができる
3、大きな学習に狙いを絞り、実際の顧客が居ないビジネスに影響しない小さな実験にこだわらないようにする
4、迅速な実験を継続的に行い、その結果から学習する必要性を組織が理解し文化となる
5、透明性や寛容さを持つことができ、ビジネスに貢献する形で顧客の問題を解決するために存在することを理解できる
熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
ISBN 978-4-8207-2750-7 C2034
P333〜334
<④ 成功するためのプロセス~製品の発見のテクニックPart.4~の所感>
このセクションは相当難しいです。
私が10年大企業にいた経験も合わせてですが、やはり成功体験を大事にするのは人間の性です。
そして大企業の場合は、成功体験がある人が出世し権限を持つことになりますので新しいことにチャレンジし、成功体験を壊すことに躊躇します。
イノベーションのジレンマの一部です。
もう一つ成長期、エンタープライズ期における企業の差別化要素は
「オーナー企業かいなか」
です。
オーナー企業の場合は変化に抗うことはできず、受け入れざるを得ません。そしてその決断はオーナーの力量にかかります。
つまり企業自体がサステイナブルではなくなります。
一方でオーナー企業でない場合は文化を継承し誰でも引っ張っていくことができる仕組みもあるのでサステイナブルではあります。
ただ、より成功体験がモノを言うようになり、結局硬直化します。
前職で一緒に働き、今は大手総合商社に転職した知人に聞いた話ですが、その会社では、新しいプロジェクトにまず甘噛みしてくる連中が多いとのことです。(まるで甘いものに群がる蟻のように)
そのプロジェクトが成功すれば「俺は最初にアドバイスしていた!」
失敗すれば「失敗すると思ってったよ…」
という光景が日常茶飯事ということです。
継承されている文化も定期的に見直した方が良いと思いました。
変化を企業に導入するのは、まさに本書の冒頭にあった「言うは易し」です。
うまく所感でまとまっておらず、ただの経験談になりましたが、このテーマの答えはビジネスに関与する限り付きまとうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
