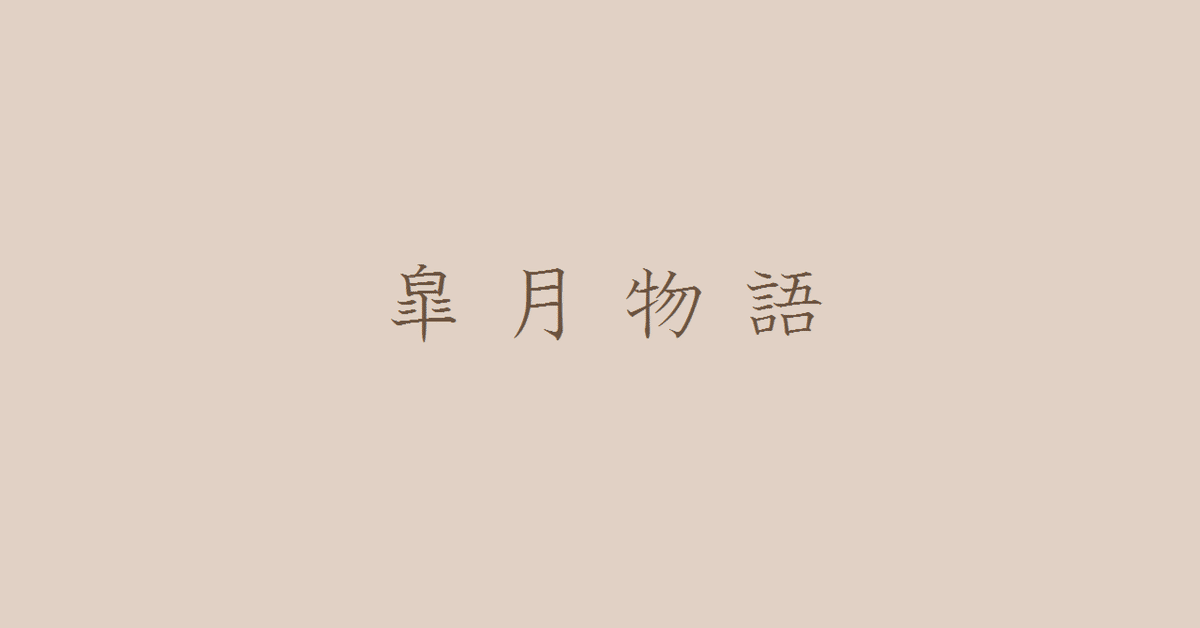
修学旅行、清水坂から産寧坂、二寧坂、高台寺公園まで(皐月物語 134)
藤城皐月たち6人は修学旅行の最初の訪問先、清水寺の参拝を終えて仁王門を離れようとしていた。出立の時間は10分遅れていた。
「いよいよお楽しみの買い物の時間だね」
「可愛い小物が欲しいな」
修学旅行前の授業の合間に、栗林真理と二橋絵梨花は清水での買い物に備え、寺社の歴史をそっちのけで土産物屋の情報収集をしていた。
皐月たちの班は旅行前の打ち合わせで、自分用のお土産を買う場所を清水にしようと決めていた。清水では小さな物や、ここでしか買えない物を買うのが合理的だと、班行動の方針にした。
清水坂には八ツ橋や漬物など定番の土産物屋が揃っている。だが、慌ててここでたくさんお土産を買ってしまうと、かさばる荷物を持ちながら他の訪問先をまわらなければならなくなる。家族へのお土産はこの日の最後に京都駅で買う予定だ。
「すごい人! 地元の豊川じゃ考えられない」
続々と詰めかける参拝客に吉口千由紀がドン引きしていた。皐月と神谷秀真も人の多さにげんなりしていたが、真理や絵梨花、岩原比呂志は平然としていた。真理は名古屋の塾に通っていて、絵梨花は名古屋に住んでいた。きっと人の多さに慣れているのだろう。比呂志は鉄道イベントの混雑を経験している。
「女子は買い物したいみたいだけど、僕たちはどうする? 岩原君は何か買う予定ある?」
「僕は京都駅で家族にお土産を買って、あとは出町柳駅で叡山電車のグッズを買おうと思ってる。神谷君は?」
「僕も家族へのお土産と、あとは八坂神社と伏見神寶神社でお守りを買ったりするくらいかな」
「じゃあ、ここではあまりお金を使えないね。藤城氏に言われて多めにお金を持ってきたけど、グッズなんて買おうと思ったら、お金なんかいくらあっても足りなくなる」
道は違えどオタク同士、お小遣いの使い道がはっきりしていて、比呂志と秀真は気が合うようだ。
「清水寺は僕たちにあまり関係ないところだね。せっかくだから食べ歩きでもしようか。皐月は?」
「俺はお世話になった芸妓に陶器を買いたいし、他にもお土産を渡したい人が何人かいる。食べ歩きするお金はないかも……。吉口さんは?」
「私は陶器が欲しいかな。可愛い小物も見てみたい。でもせっかくだから、美味しい物も食べてみたい」
「吉口さん、それって全部じゃん!」
皐月たちの班のメンバーは行きたい店がそれぞれ違うのかもしれない。全員で一斉に行動すると時間がかかるだろう。この時の皐月は予定の遅れを気にしていた。他のみんなは少し興奮していて、特に千由紀が舞い上がっているように見えた。皐月は時間とお金が心配で、とてもショッピングや食べ歩きを楽しめる心境ではなかった。
「それぞれに行きたいところへ行って、どこかで待ち合わせにしない?」
皐月は行き先を分散すれば時間を短縮できると考えた。それだけでなく、誰にも干渉されず一人で土産物を選びたかった。ガールフレンドの入屋千智と、住込みの女子高生の及川祐希へ渡すお土産を買うところを真理には見られたくなかった。
「じゃあ、どこで待ち合わせる?」
能天気な真理は皐月の真意に気付かなかったようだ。
「宝徳寺の前なんてどう? さっき通ったあさひ坂から出てすぐのところにあったお寺。あそこなら近くていいんじゃない?」
皐月がみんながわかりやすい、初見でない場所を候補地に挙げると、絵梨花に反対された。
「来迎院なんてどう? 産寧坂に入る曲がり角にあるお寺。そこなら分かりやすいし、遠くないでしょ。待ち合わせ場所があまり近いとお店の選択肢が狭まるから、少し離れたところがいいな」
絵梨花の言う通り、買い物できるエリアが狭くなると、買い物をする店を限定するのと同じになる。皐月も時間に余裕があれば清水全体から店を選びたいと思っていた。
「この辺りでいい店がなかったら、産寧坂や二寧坂で買えばいいよ。スケジュールを守ることよりも、お土産を買うことの方が大事だから」
班長の千由紀は時間の遅れでまわれる場所を減らさなければならなくなるという、最悪の事態を想定し始めたのかもしれない。もしもの時は訪問先を削ることになると、事前の打ち合わせで決めてある。
皐月たちは遡上する鮭のような参詣者に逆らって清水坂を下り始めた。これから皐月たち6人は清水坂、産寧坂、二寧坂を通り、祇園に向かう。
皐月は歩き始めてすぐに、仁王門のすぐ近くの土産物屋「もみぢや」に心魅かれてしまった。真っ先に店頭の八ツ橋のディスプレイに目が行った。
この陳列棚は甲板に緋毛氈が敷かれ、背板に簾がかかっている。商品を詰めて置かない余裕を持った陳列が混雑している参道の中で際立って見えた。
「御殿八ッ橋」を手に取ってみると、なんと無添加だった。原材料に桂皮と芥子の実が使われている。味付けの強い、固い八ツ橋なのだろう。こういう美味しそうで、健康にもよさそうなものがお土産にいいのかなと思っていたら、比呂志たちは先に進んでいた。
皐月はみんなと別行動をするつもりでいたが、一人置いて行かれるのは寂しいので、みんなを追いかけた。5人は少し先にある店の軒先でお茶を飲んでいた。
「あれっ? みんな同じとこにいんじゃん」
みんながいたのは瓦屋根の庇に提灯が並んでいる「本家西尾八ッ橋」だった。
「店内でお茶を飲みながら御試食下さい」
店の人にお茶を手渡された。試飲はたいてい紙コップなのに、ここでは茶碗に入れたお茶を出す。店先には丸盆に七客の湯呑茶碗が載せられ、それが何段にも積み重ねられて試飲客を待っていた。皐月は遠慮なくお茶を頂くことにした。
比呂志と秀真は店の中に入り、早速八ツ橋の試食をしていた。女子3人も小物を見ると言いながら、この店の八ツ橋が気になるようだ。
「八ツ橋を6枚食べたら二ツ橋になるね」
「それ絶対に言われると思った」
皐月の下らない冗談に二橋絵梨花が笑ってくれた。皐月は修学旅行に来る前から、絵梨花の名字の二橋を見るたびに八ツ橋を連想していた。
「お土産はともかく、自分のおやつ用に八ツ橋を買っちゃおうかな」
食べることが大好きな真理も店の中に入った。真理に続いて絵梨花や千由紀も店に入ったので、皐月も女子について行った。
「本家西尾八ッ橋」は京都で一番古い八ッ橋屋だという。店の中に入ると高い天井から赤と黒の字で「八ッ橋」と書かれた白い提灯がぶら下がっていた。格子で覆われた天井やカウンターの上の障子、紅白の提灯の放つ淡い明かりが和の雰囲気を出していて旅情を誘った。
カウンターの前に試食用の八ツ橋が置かれていた。あらゆる種類の八ツ橋が試食できるようだ。いくら試食の好きな皐月でも、その全てを食べるのは無理だと思った。
カウンターにいる女性の店員たちはオレンジ色のエプロンと三角巾が良く似合い、とても素敵だった。彼女らを前にして、ええ格好しいの皐月は試食に手を出すのを躊躇した。彼女らが他の客の相手をしている隙に「あん生八ッ橋 チョコレート」を食べた。皐月の知っている八ツ橋とは違い、これはこれでとても美味しかった。
「これ、美味いな。5個入りか……おやつの量にピッタリじゃん。どうしようかな……」
「それくらい買えばいいでしょ?」
いつの間にか真理が隣にいて、皐月の独り言の相手をしていた。
「そうなんだけどさ……お土産代を残しておかないとヤバいかなって」
「あんたはいろんな女にお土産を買わなきゃいけないからね。こんなとこにいないで、さっさと他の店に行ったら?」
「なんだよ。そんな言い方すんなよ……」
「このチョコの八ツ橋が欲しいんでしょ? 私が買うから、後で分けてあげるよ。あんたはさっさと買い物を済ませてきなさい」
「わかったよ」
皐月は追い出されるように「本家西尾八ッ橋」を出た。途中、千由紀と絵梨花が緋毛氈の敷かれた床几に腰を掛け、千由紀が抹茶、絵梨花が真っ黒なソフトクリームを食べていた。
「藤城さん、どうしたの?」
ソフトクリームを手にしながら絵梨花が真理に話しかけに来た。
「女に買うお土産を見てくるってさ」
「ふ~ん。それで真理ちゃんはヤキモチ焼いてるんだ」
「焼いてないよ!」
「そう?」
怒る真理を見て絵梨花がクスクスと笑った。
「私はちょっとヤキモチ焼いちゃうかな」
「なんで絵梨花がヤキモチ焼くの?」
「だって藤城さん、思いつめた顔してたよ。私もあんな風に想われてみたいな」
「あんなの無計画にお金を使って焦ってるだけでしょ」
絵梨花が笑いながら真理の質問をはぐらかした。真理が哀しそうな顔をしているのを千由紀はそばで黙って見ていた。
「本家西尾八ッ橋」を出た皐月はすぐ近くにある「朝日堂」に入った。「朝日堂」は京焼・清水焼の専門店だ。皐月は好きな女性たちには陶器を買おうと決めていた。
皐月には時間とお金がなかった。スケジュールの遅れが気になっていたし、手持ちのお金が思ったよりも足りていないこともわかっていた。
お金は規則を無視して余分に持って来た。予算の7000円では絶対に足りなくなると思い、2万円と小銭用に500円玉を10枚持って来た。これがコツコツ食費を削って捻出した、皐月の全財産だった。
買うものを素早く決めようと思った。最優先で芸妓の満への盃を買わなければならない。満の部屋に行った時、お酒が好きそうなことがわかった。狭い部屋だったので、邪魔にならないものを贈りたいと思った。
祐希にはいつも使う茶碗がいいと思った。引っ越しの時に祐希が持って来た茶碗があまりいいものに見えなかったからだ。もしかしたら百均で買ったものかもしれない。祐希には可愛い茶碗を使ってもらいたいと思った。
祐希の母の頼子にも何かを買わなければならない。皐月の母の小百合と二人でよくお酒を飲んでいるので、酒器がいいと思った。
千智には何を買ったらいいのかよくわからない。家の事情もあるので、迂闊なものは買えない。邪魔にならなくて、可愛い物で何かを見つけたい。千智へのお土産はこの店にこだわる必要がないと思った。
「朝日堂」は小学生には入るのに勇気のいる店だが、皐月は思い切って堂々と店の中に入った。ゆったりと店内を見ながらも集中力を高め、直感を働かせて買うべき品を探した。明らかにレベルの釣り合わないエリアには行かないで、買えそうなものが揃えてあるところだけを隈なく見た。
ラフな格好をした西洋人や、賑やかで楽しそうな中国人に紛れていると皐月は気持ちが楽になった。買いたいものは全て決まったので、笑顔の素敵な女性の店員に声を掛け、4点の陶器を精算してもらった。
満には青みがかった流天目の盃を選んだ。賑やかで華やかな満には家で落ち着いて日本酒を楽しんでもらいたいと思った。小さなものだが、小学生にしては頑張り過ぎた価格だった。
祐希には桜の絵が可愛い、白とピンクの飯碗を選んだ。黒陶土にパステルカラーの釉薬が掛けられていて、触ってみると立体感があった。白と黄色の飯碗もあったので、二つ買えばペアになったが、お金が足りなくなるので自分のものは諦めた。
頼子と小百合には葡萄の描かれた酒器にした。徳利と碗が二つセットになっているものだ。この店の酒器の中では安いものになってしまったが、白い肌に藍色の単色で絵付けされた美しいものだ。母と頼子にはこの碗で酒を飲んでもらいたいと思った。
千智に買う物も見つかった。千智には紅葉を象った箸置にした。紅の交趾は透明感があり、葉脈が金彩で絵付けされていた。小さくて、可愛らしくて美しかったので、皐月は自分のものも買った。千智にはあまり高いものを買えなかったが、自分と同じものをペアで持つことになるので、きっと喜んでもらえるだろうと思った。
これで皐月の修学旅行の小遣いはほとんどなくなった。あとは入館料に備えて用意していた500円玉が数枚残っているだけだ。京都駅では manaca の使えるポルタで買い物をすれば何とかなる。まだまだ余裕があると強がることにした。
買い物を終えた皐月は清水坂を下り、産寧坂との辻にある来迎院で真理たち5人を待った。
来迎院は清水寺の境外塔頭で、聖徳太子の開基と言われている。飛鳥時代の創建だが、詳細はわかっていない。清水寺の開創が778年なので、来迎院は清水寺よりも150年以上古い歴史があることになる。
本尊は聖徳太子が自ら彫った16歳の時の太子像で、秘仏となっている。扁額には「経書堂」とあり、かつては聖徳太子の写経所跡だったらしい。
皐月は境内の桜の樹の下で行き交う人を眺めていた。目の前には聖護院八ッ橋の店があり、ここも観光客でにぎわっていた。京都には八ツ橋を売る店が多い。皐月は住んでいる所に銘菓があることを羨ましく思った。
「藤城?」
声の聞こえる方を見ると、そこには野上実果子たち6年3組の班の子がいた。皐月は実果子たち6人には自分たちの班と違い、何となく余所余所しさを感じた。3組は担任の北川先生の方針で好きな子同士で班を決めたという。実果子たちの班は余った子を集めた班なのだろう。
「おう」
「お前、なんで一人なんだよ? 捨てられたのか?」
「みんな、まだ買い物してるんだよ。ここで待ち合わせ。それよりお前、リップしてるんだ」
「宿に行くまでには落とすよ」
実果子は金髪から黒髪に戻し、白い肌が際立つようになった。コーラルオレンジのリップは実果子の顔色をさらに明るく見せていた。
「その色、すごくいいな。色っぽくてキスしたくなっちゃうじゃねーか」
「してやってもいいぞ」
「えっ? 人、いっぱいいるけど……」
「バ~カ。するわけねーだろ。エロいな、お前は」
実果子は照れを隠すように笑っていた。普段の実果子は機嫌が悪そうで見た目が怖いが、たまに笑うと可愛くなる。一重瞼のシャープな顔立ちは皐月の好みだ。
「藤城たちは次、どこに行くんだ?」
「祇園。野上は三十三間堂に行ってたのか?」
「そう」
「どうだった?」
「どうって……仏像のことはよくわからないけど、とにかく凄かった……」
「そうか。凄かったか」
修学旅行には全く興味がないと言っていた実果子がこんな反応をするとは思わなかった。楽しんでいたようで、皐月はホッとした。
「藤城たちも行くのか?」
「いや。予定には入っていない」
「うわっ、もったいね~。あれは見ておいた方がいいって」
「へぇ~。野上がそこまで言うなら、いつか見に行かなきゃな。今度、三十三間堂を案内してくれよ」
「ここまで来るのに金かかるじゃん。無理!」
実果子は他のメンバーに置いて行かれそうになったので、あわてて皐月の元を離れ、走って仲間を追いかけた。途中で実果子は真理たちとすれ違い、仲の良い千由紀と二言三言話して、手を振って別れていた。みんなが来迎院にやって来たのは皐月が予想していたほど遅くはなかった。
「悪いな、皐月。遅くなっちゃって」
「大丈夫。そんなに遅れていないから。それより、ちゃんと欲しい物買えた? 吉口さんは陶器が欲しいって言ってたよね?」
「買えたよ。紅葉が描かれたマグカップを買った。ちょっとここで出すのは面倒だから、見せられないけど」
「いいよ。それより先を急ごう」
「七味家本舗」の手前にある産寧坂の入口は人でごった返していた。進む順番が来るのを待ち、皐月たちはゆっくりと産寧坂に入った。
産寧坂の始まりは勾配のある石段だった。道沿いの来迎院は継ぎ目が苔生す古風な石垣の上に建てられていて、他の建物はそれに倣うかのように現代的な御影石の石垣の上に建てられている。
産寧坂の沿道の両側には土産物屋や料亭など、様々な店が軒を連ねている。和風のイメージで統一されているが、一軒一軒を見ると個性に富んでいる。
和風建築でも造りはそれぞれ違っていて、現代的な和モダンの店もあれば、江戸から明治にかけて建てられた厨子二階の虫籠窓が見られる町屋もある。白壁の家もあれば、焦香や鳥の子色、夏虫色などの伝統色の壁の家もある。艶っぽい赤壁の家や紅殻格子の家もあり、見ているだけで楽しくなる街並みだ。
「あっ!」
前を歩いていた男子中学生たちが転ぶのを見て、皐月は思わず声を出してしまった。産寧坂は三年坂ともいい、転ぶと三年以内に死ぬという都市伝説がある。中学生たちはわざと転んだのか、大笑いして喜んでいた。
「三年殺し、発動じゃね?」
「わざとならセーフでしょ?」
「いやいやいや。裁きは厳正なものだと思うよ」
皐月ら男子三人は中学生たちに呆れていた。オカルト好きの秀真や皐月はこの手の冗談が嫌いだ。
「ここに枝垂桜があったんだよね。倒れちゃったけど」
「産寧坂の画像を検索すると、ここに桜があった頃の美しい写真がたくさん出てくるよね」
絵梨花と千由紀が話しているのは「明保野亭」の桜のことだ。
「ここで長州藩士と坂本龍馬が倒幕の密議をしたんだよね。二橋さんは佐幕派? 倒幕派?」
「私は佐幕派かな。新撰組が好きだし。吉口さんは?」
「ん~、私は倒幕派。小説やドラマの影響だけど、坂本龍馬ってなんかいいなって思って。栗林さんは?」
「私はどっちも好きじゃない。心情的には佐幕派。ところで佐幕の『佐』って、なんで『佐』?」
女子たちが喋っているのをなんとなく聞いていた皐月も、佐幕の佐について以前から気になっていた。
「佐っていうのは『佐ける』っていう意味。補佐って言葉があるでしょ。あれは補って佐けるっていう、補助と同じ意味。補佐は人を助ける限定だけど」
漢字に強い千由紀の説明はわかりやすかった。漢検2級まで取った皐月でも知らない知識だった。
「ちょっとここに寄らせてね」
真理が「まるん」という和菓子のお土産を売っている店に入って行った。少し遅れて千由紀や絵梨花も店に入ったので、皐月たち男子は興正寺の霊山本廟の入口の所で待つことにした。
「秀真と岩原氏は行かなくてよかったの?」
「僕は鉄道のグッズ代を取っておきたいからね」
「僕は写真を撮りたい。この辺りってすごく風情があるよね。神社仏閣もいいけど、こういう京都らしい街並みもいいなって」
「僕も鉄道写真ばかり撮っているけど、風景写真も勉強したくなってきた。今まで美しい風景まで関心が向かなかったからな……」
秀真や比呂志は写真への興味が広がったようだ。撮影は秀真と比呂志に任せて、皐月も真理を追って「まるん」の中に入った。真理はクッキーを選んでいた。
「真理、クッキーなんて食べるのか?」
「自分用じゃない。検番に持って行こうかなって思って。皐月は検番にお土産買った?」
「買ってない。もう金がないからな……」
「どうすんの?」
「まあ、京子姐さんに謝るよ。お金がなくて買えなかったって。恥ずかしいけど……」
真理が手に取っていたのは「舞妓さんしょこら」という、簪を挿した舞妓の顔がプリントされている、京都らしいデザインのショコラクッキーだ。見た目がとても可愛い。
「これ、二人で買ったことにしてあげるから、一緒に検番に持って行こう」
「うん……先の話になるけど、お金半分出すから」
皐月にとって真理の提案はありがたかった。「舞妓さんしょこら」は税込で1300円くらいの、そんなに高くないクッキーだ。皐月はお金が払えないことだけでなく、人の情けに縋らなければならないことが悲しかった。
「まるん」を出て秀真や比呂志と合流し、先を急いだ。産寧坂を左へ曲がりながら下ると、左手に大塀造の屋敷が見えた。塀には「ゆどうふ奥丹」という行燈があり、少し進むと立派な門があった。その向かいには「阿古屋茶屋」というお茶漬けを出す店があり、その角を右に曲がると二寧坂だ。
皐月たちは一度、二寧坂を通り過ぎて産寧坂をさらに下った。少し進むと、右手の塀をはみ出した庭木の梢から相輪が見えた。前方に大勢の人が立ち止まって写真を撮っていた。下り坂の先に京都で最もフォトジェニックな法観寺の八坂塔が見えた。
「修学旅行の栞の表紙と同じ写真を撮ろう」
修学旅行実行委員会で栞の表紙に描かれた八坂の塔のイラストを見た時、皐月はここでみんなと写真を撮りたいと思った。表紙のデザインを担当した実行委員の黄木昭弘は八坂塔の写真を参考にしてイラストを描いた。昭弘の絵を見た瞬間、皐月の脳内に修学旅行のイメージが一気に広がった。
ここでも幸い、すぐ近くに写真を撮っている女性グループがいた。皐月が声を掛けると、快く撮影を引き受けてくれた。表紙と同じように人を配置したかったが、撮影をしている人があまりにも多くて、そんな勝手な真似は出来なかった。皐月は彼女にお礼を言い、お返しに彼女たち全員が写るような写真を撮った。
「引き返すか」
皐月たちは法観寺には寄らず、先を急いだ。来た道を戻り、「五木茶屋」と「阿古屋茶屋」の間の細い路地を左に曲がって、二寧坂に入った。
二寧坂も始まりは石段だった。「阿古屋茶屋」の竹垣より下ったところに「我楽苦多」というカフェがあった。その軒先に番傘が三張かけられていた。二階の窓にかかっている簾と相俟って、古い日本を感じさせるいい雰囲気だ。
その先の二寧坂の街並みは産寧坂よりも情緒に富んでいた。古都のレトロな世界観が保たれていて、とても落ち着いていた。どことなく高級感が漂い、皐月は自分たちのような修学旅行生には場違いな所だと思った。
「俺たち子供が気楽に立ち寄れる店なんてなさそうだな」
「何言ってんだ、皐月。スタバがあるじゃんか」
「スタバ? そういえばあったかな。で、どこ?」
「目の前」
「マジ?」
秀真に言われた方を見ると大塀造の日本家屋があった。二階に掛かっている白木の看板にはスターバックスのセイレーンが焼かれていて、暖簾にもロゴが描かれていた。
「そっか……。ここなら俺たちでも入れるか。でも、なんか人が多いな」
「メニューは他のスタバと同じなんだって。値段も同じ。雰囲気を楽しむ所だと思うけど、これだけ人が多いと落ち付けないだろうね」
秀真はここのスタバに興味がなさそうだ。秀真は人の多い場所が苦手なので、こういう場所からはそっと離れるようにすると言っていた。
「清水には落ち着いたレストランや五つ星ホテルがあるみたいだけど、めっちゃ高いみたいだね」
「この近くのホテルなんか、最低でも一泊20万円以上するんだよ」
千由紀も真理も修学旅行と関係ないことを調べていたみたいだ。
「そういうところは上級国民とか海外の金持ちが行くところなんだろうな……」
皐月が独り言を漏らすと、絵梨花が反応した。
「高級ホテルはさすがに無理かもだけど、高級レストランとか料亭なら、そういう店が似合う大人になればいいんじゃない?」
「なれるかな……そんな店、ビビって気が引けちゃうな。なんだか住む世界が違うような気がする」
「そんなことないよ。そういうところで働いている人は私たちと同じ庶民なんだから。それに二寧坂から一本、中の道に入れば普通の民家が立ち並んでいるんだよ。ここが特別な場所ってわけでもない。だから、そんなに卑屈にならなくたっていいよ」
「そうかな……」
「大人になったら、私がそういう店に連れてってあげるよ。それなら怖くないでしょ?」
自信に溢れる絵梨花の顔が皐月には眩しかった。どうして絵梨花はそんなに堂々としていられるのだろう。生まれ育った環境が違うのだろうか。絵梨花はバイオリンを習っていて、私立中学に進学する。そういうことなのか、と皐月は一人納得した。
二寧坂と維新の道が交わる手前に細い路地がある。そこが一念坂だ。坂といっても傾斜はないし、100mにも満たない小径だ。
ねねの道に進むなら、維新の道まで出ないで、手前の一念坂を通って行った方がいい。そうすれば京都霊山護国神社を避けることができる。皐月と秀真は修学旅行だから、なるべく葬に関わる場所は避けたいと思い、一念坂を通ることに決めた。
一念坂も二寧坂のような風情がある。石畳のこの道に沿った家の壁の色は焦香に統一されていた。玄関には格子戸、二階の窓には欄干がある家が多い。一念坂はしっとりとした日本的な雰囲気が味わえる。皐月はカフェ「Unir」の非の打ちどころのない、格好いい塀が好きになった。
一念坂を抜けると、久しぶりに開けた場所に出た。右手には高台寺の入口があるが、ここは車用なので、徒歩で高台寺を訪れるならねねの道から入った方が趣がある。
ねねの道は産寧坂や二寧坂に比べて広くなだらかな道だ。豊臣秀吉の妻の高台院、通称ねねが創建した高台寺と、ねねが亡くなるまで住んでいた圓徳院の間を通る道が名前の由来となっている。
ねねの道の始まるところに「えびす屋」の人力車乗り場があった。ここで人力車を頼めば屈強な青年が俥夫となって車を引き、観光名所を案内しながらまわってくれる。この時、ちょうど外国人の夫婦が乗った人力車が引かれて出て行くところだった。
「御手洗いがあるけど、寄ってく?」
高台寺の入口に高台寺公園のトイレがあった。車止めがされていて、御影石が敷かれているこの一角に和風瓦葺きの門のような建物がある。高台寺の入口の一つかと見紛いそうになるが、それがトイレだ。皐月はトイレを見つけた時は必ず女子に声を掛けようと心がけている。
「僕は寄ろうかな」
「私も」
比呂志と絵梨花と真理が御手洗いに寄り、皐月たち三人は少し先の開けたところで待つことにした。秀真は公園からねねの道の写真を撮っていた。皐月はねねの道がよく見える所まで寄り、桜の樹の間から道を見下ろした。
「高台から見るねねの道もいいね」
隣に来た千由紀に皐月が話しかけた。
「下の道にトラックとタクシーが停まっていたから、雰囲気を壊しているなって思ってた。でもここから見るねねの道は悪くない」
千由紀はせっかくの景色を、車が邪魔しているのに腹を立てていたようだ。ねねの道は道幅が広いので、タクシーや自家用車がよく通る。
皐月たちのすぐ先に、公園からねねの道に下りる階段がある。下りたその正面の細い道が石塀小路だ。石塀小路は料亭や旅館、スナックなどが建ち並ぶ、むせ返るような情緒のある小径だ。
「どうする? 石塀小路を抜けて、八坂神社に行く? その方が少し近くなるけど」
「私はねねの道がいい。石塀小路って夜の店が並んでいる道でしょ? 子供がうろつくような所じゃないよ」
千由紀の拒絶は強かった。皐月は少し驚いたが、意外ではなかった。それは千由紀の家がスナックだということを知っていたからだ。
「ああ……。そうかもしれないな」
皐月の住むところにも似たような小径がある。情緒では石塀小路と比べ物にならないが、豊川の小路も車が通れない狭い道に料亭やスナック、旅館が立ち並んでいる。
ネットでは風情があると評判の石塀小路だが、皐月もできれば避けて通りたいと思っていたところだ。これは近親憎悪ようなものかもしれないと思っている。
「ねえ、吉口さん。ちょっと相談があるんだけど……」
「どうしたの? 改まっちゃって」
「うん。この後、祇園に行く予定になっているでしょ。俺が行きたいって言ってたところ。それでね……祇園、行くのやめにしてもいいかな?」
「えっ?」
千由紀が驚いた顔をして皐月を見た。皐月はその視線の相手をせず、桜の枝の隙間から、遠く石塀小路を超えて祇園の方を見据えていた。
最後まで読んでくれてありがとう。この記事を気に入ってもらえたら嬉しい。
