
Photo by
sigikai
2022/9/27 安倍晋三元首相国葬 賛否分かれる中実施
2022/9/27 夜のニュース比較、文字起こし
国葬に関する文字起こしが中心になっております。
その他の件の文字起こしについては、後ほど。
国葬

安倍晋三元首相国葬 賛否分かれる中実施
小川アナ「国論を二分したという風に表現がされますけど、二分したとシンプルに言い切ることが出来ないような様々な角度、様々な温度感がありますよね。国葬表明からの2ヶ月半の間、この声をもっと束ねることが出来なかったのか?と改めて感じるようでもありますけれども、木村さんは街の声どんな感想をお持ちになりますか?」
木村草太氏(東京都立大学(憲法学)教授)「自由のない国では国葬に反対したり、興味を持たなかったりということは出来ませんので、賛成・反対・興味なしと自由に話せる、そういう国であって良かったなと感じました。」
小川アナ「星さんは今日の国葬を取材されましたけれども、どんな感想でしょうか?」
星浩氏(TBSスペシャルコメンテーター)「会場では型通りの挨拶が続いたんですけども、菅さんが挨拶した中で、菅さんが時々涙ぐんだりして、終わった後会場から自然と拍手が湧いたということがありまして、菅さんの率直な挨拶が弔意を表明したいと思ってる人の心に響いたということはあったと思いましたね。」
小川アナ「悼む思いというのが画面を通しても滲んでくるような菅さんのスピーチというのが、1つのハイライトにもなった今日の国葬。ポイントを簡単に。」
国山アナ「今回の国葬の問題点、お二人に指摘して頂きました。木村草太さんは岸田賞授与式。星さんは“聞く力”の正体がバレたという指摘です。まず木村さんの指摘から見ていきましょうか。木村さんは、岸田総理の8月10日の記者会見の発言に注目されています。故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式、と。この中でこの部分“国全体と“という文言。法的問題点があるという指摘ですね。」
小川アナ「木村さん、この問題点というのは、どういうことでしょうか?」
木村氏「国全体というのは素直に見ますと、国民全員という意味になりますけれども、しかし弔意・敬意を持つか?については思想・良心の自由、それを表明するかどうか?は表現の自由として憲法に記されております。ですから、国全体という言葉が国民全員という意味で今回の儀式の国民全員の弔意・敬意を勝手に、あるいは強制的に表明するような儀式だということになりますと、これは憲法の保証する自由の侵害ではないか?という批判を免れなくなる。そういう意味で、この文言は非常に重要な意味を持っておりました。」
国山アナ「その文言なんですけども、国全体。その後、削除されているんですね。9月8日の国会説明では、故人に対する敬意と弔意を表す儀式ということで、ご覧の通り国全体という文言、削除された、ということです。」
小川アナ「この文言、なぜ削除されたのか?なんですが、木村さんはその意図、どう読み解きますか?」
木村氏「国全体という言葉がなくなったのは、国民全員の弔意や敬意を無理やり、あるいは勝手に表明する儀式ではないんだと明確にして、国民の思想・良心の自由の侵害がないということを説明するためだと思われます。国葬が決まってから多くの法律家は、国葬で敬意や弔意を無理やり表明させることになったら、これは違憲は免れないだろうという指摘をしてきましたので、そうした指摘を踏まえたものということになるかと思います。しかし、こうなると今度は誰の敬意・弔意を示す儀式なのか?ということが全くわからなくなるという問題が出て来ることになりました。今回の国葬、故人の業績を称えるという意味があるのかもしれませんが、国葬に値する業績があるかどうか?その判断基準があらかじめあった訳ではなく、今回の国葬について専門家が業績を政治から独立して判断した、客観的に考えたということもなく、岸田総理が主観的な評価で国葬にするということが決められました。ですから、国葬の中身は国民とは関係のない岸田さんの主観的な評価に基づく岸田賞の授与式のような中身になってしまった、ということかと思います。」
小川アナ「岸田さんの主観がある種の基準となってしまった、と。国全体という文言を削ってしまうと、もう国葬なのか?国葬とは詰まるところ、どういうものなのか?定義は何なのか?ということにもなってきますよね。」
木村氏「国葬と言っても、それは中身によって様々でして、うな重に松竹梅があるように、同じ国葬という名前であっても中身は様々な訳ですね。国全体としてという文言を削ってしまった結果、これはもう国民を巻き込まない、そういう儀式なんだ。そういうことが明確になってしまった、あるいはなったということかと思います。」
小川アナ「星さん、これはどうご覧なりますか?」
星氏「国というのは、中学校で習いますけど、三権分立で行政と司法と立法とありまして、岸田さんが率いているのは行政、内閣なんですね。やっぱり一番国権の最高機関、国会、立法機関ですので、国会を今回軽視して国葬を決めてしまったという経緯があるので、どう見ても国とは言えない、せいぜい内閣主導で決めたということですので、途中から国会を通してなかったなあというんで、国を削除したという、そういう経緯だと思いますね。」
国山アナ「それで言うと、内閣葬でも良かった訳ですよね。」
星氏「それを相当強引に国葬にしたというところが、そもそもボタンの掛け違えということだと思いますね。」
安倍晋三元首相 国葬
有働アナ「安倍さんを静かに悼みたいと思った方にも、そして抗議デモをした方にも、わだかまりが残りました。それは結局のところ、なぜ国葬なのか?という議論や説明が十分に尽くされなかったからです。賛成する人、反対する人の間につくってしまったより深い溝。本当ならその溝を埋めて、より多くの人が納得出来る答えを導くのが政治のはずです。まずはそこが変わることを望んでいます。」
安倍晋三元首相「国葬」 世間はどう過ごした?
小木アナ「率直にどんなことを感じまたか?」
大越アナ「本当にたくさんの方に話を聞いたんですけれども、皆さん一様に口にされていたのは、安倍さんという政治家に対して評価が分かれていることをもちろん知ってます、と。ただ、長年国政を担う、重責を果たした政治家があのような悲劇的な事件によって命を落としたということの事実の重み。それを考えると、自然と追悼の気持ち、追悼の列に並ぶというのは自然な行為ではないのかな、と皆さんおっしゃっていて、それは国葬に反対だという方にもそういう方はいらっしゃいましたね。ただ一方で、国葬という形をとったことで、弔意の強制ではないか?といった批判があがって、国論が二分されてしまった。これもまた事実ですよね。ですから、国民の最大公約数の気持ち、意見というものをもっと吸い上げる、別のやり方というのがあったんではないか?ということもやはり感じました。その辺り、どう考えますか?」
藤川みな代氏(テレビ朝日 政治部長)「国葬という方法を取ることについての理解が広がらないまま今日を迎えてしまったということについては、やはり大きく2つ理由があると思うんですね。手続きの問題とタイミングの問題。手続きに関して言えば、やっぱり決定の前後、いかなるタイミングでも国会の関与ということを岸田総理が積極的に求めなかったということが1つ大きいと思いますね。例えば、事前に根回しを野党に対してするとか、あるいは正式に決定した直後でも議会の承認を得るとか、そういった国会の意思を確認するということが今回なされなかったということは1つ対立や批判が長引く原因を作ってしまったと思いますね。」
大越アナ「判断が拙速だったという批判は免れないのかなあと思いますし、安倍さんの死後80日というタイミングについてはどういう風に考えますか?」
藤川氏「安部元総理が亡くなったという衝撃ですとか悲しみを共有し続ける、多くの方が共有し続けるにはちょっと2ヶ月半というのは長いということもありますし、今度政権の評価ですね。安倍元総理という政治家への歴史的な評価というものが定まっていくには、あまりにも短い、ということですね。自民党の中からは、2ヶ月半というのが国葬への理解が深まっていく時間ではなくて、旧統一教会の問題が深掘りされていく時間になってしまった、と悔やむ声も出ていますね。」
大越アナ「先程、永田町全体をある種の空白と言うんでしょうか、菅さんは喪失感を感じたという、弔辞に感じたというお話をされていましたけれども、政治の世界のみならず日本社会全体に置き換えても、ちょっと似通ったことが言えるんじゃないかなあという風に思っていて、安倍さんという政治家に対する評価というのは本当に支持、不支持がはっきり分かれる傾向にあると思うんですけれども、いずれにしても安倍さんはある種の座標軸として存在感は発揮したと思うんですね。良し悪しの評価は別としても座標軸が失われてから、私達は新たな座標軸を見出せずにいるというか、その座標軸ということを打ち出し切れていない岸田総理大臣の存在もあるのではないか?ということを思うんですが、どうでしょうか?」
藤川氏「そうですね。安倍政権への賛否ですとか、安倍元総理との距離感によって、政治を判断していくという一つの時代が終わっていくという中で、私達一人一人有権者にとっても何を基準にして政治家を選ぶか?また、リーダーである人に何を求めるのか?ということが具体的に問われていくことになると思うんですね。その今お話にあった岸田総理の存在感ということに関して言えば、岸田総理が言っている聞く力ということを聞くだけではなくて、聞いた後に何を実現するのか?という実現する力ということが、これから更に問われていくことになると思いますね。」
大越アナ「例えば、どのような点があるのでしょうか?」
藤川氏「目の前の課題で言うと、やはり旧統一教会の問題。党の調査では今回対象になっていなかった安倍元総理ですとか、細田衆議院議長、こうした方を、どのようにこれから考えていくのか?調査をするのかどうか?ということ。また、自己申告という調査から第三者的な、例えば弁護士であるとか、第三者的な目を入れた調査というのを岸田総理が覚悟を決めて踏み込んで行けるのかどうか?ということ。そして、秋以降、非常に深刻さが増している物価高ですとか、エネルギー供給の問題。そういったことに具体策をきっちり対策を取っていけるのか?ということが問われますね。」
大越アナ「10月3日には臨時国会が開かれますが、岸田総理大臣、参議院選挙で決断と実行というフレーズを使っていました。まさにその真価が試される時に来ているのだと思います。」
安倍晋三元首相の国葬 経済ブレーン語る 不透明な日本経済の課題は
田中アナ「浜田宏一さんのお話もありましたが、今改めて振り返って見ますと、アベノミクスとは一体何だったんでしょう?」
滝田洋一氏(解説キャスター)「これが第二次安倍政権が成立する前、10年前に日本を襲っていた、いわゆる6重苦の図なんですよね。中でも一番大きかったのは、超円高の問題だったと思うんですが、それを是正するために金融緩和を行なって、実際に円高を是正したというのは最大のアベノミクスの成果だと思います。」
田中アナ「円高の是正。今は円安の副作用が大きな問題になっていますが、第二次安倍政権が発足した10年前、これは超円高だったんですね。」
滝田氏「10年前は1ドル80円の超円高で、その超円高の元で日本経済は沈没寸前だったんですよね。1つ例を挙げましょう。トヨタ自動車なんですが、2008年のリーマンショック以降、単体、単独決算では4年連続で営業赤字だったんです。その赤字の合計額1兆4000億円に上ってたんですよね。そうした背景にある超円高を是正して、企業の経営や雇用を回復軌道に乗せた。そこが注目したいポイントだと思います。」
田中アナ「今や日本企業は過去最高益となっていますが、儲けが出た分をなかなか投資ですとか、賃上げに回せてこなかった、と言われていますよね。」
滝田氏「そこにあります通り、法人税を引き下げたり、日本主導でTPPをまとめるといった経済の活性化策を打ち出してはいるんですけど、なかなか肝心の企業が動かなかったんですよね。でも、最近の円安について、物は考えようなんですが、競争力が回復するという条件にもなる。しかも、サプライチェーンの確保というのが、重要性を増してるという。ここにきてようやく日本国内への投資というのが見直され始めているという風に思います。」
田中アナ「そうですか。またこちらに労働市場問題というのもありますが、女性や高齢者が働き手となることを後押ししてきた労働政策というのもありましたね。」
滝田氏「日本が人口減少の局面にある中で、日本経済が収縮せずに、道を拡大するように向かったというのは大きいと思うんですよね。やっぱり女性や高齢者、先ほど浜田さんおっしゃっておられましたけど、新規参入が500万人あったおかげですよね。ただし、課題が残ってるんですよね。年収が100万円を超えた辺りで税や社会保障の負担がドーンと重くなるという問題がありまして、それが働く女性にとっての大きな壁になっているという指摘があるのは確かです。」
田中アナ「その大きな壁を取り払うのが岸田総理に残された課題とも言えそうですね。」
国際

アップル 新型「iPhone14」一部をインドで生産
長内厚氏(早稲田大学ビジネススクール教授)
・“脱中国依存” 安定供給のためのリスク回避へ
・高度な軍事技術でもある半導体めぐる経済安保
・生産の移転&市場の反発 難しい課題に直面
その他
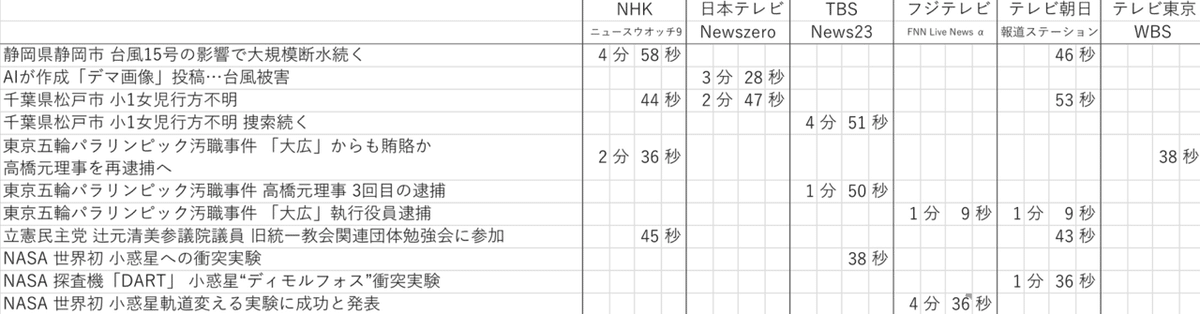

NASA 世界初 小惑星軌道変える実験に成功と発表
長内厚氏(早稲田大学ビジネススクール教授)
・進む宇宙観測の技術 小惑星衝突予測も
・宇宙へのアプローチ 受け身から積極的に
・“地球の危機” 人類共通の課題に各国協力を
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
