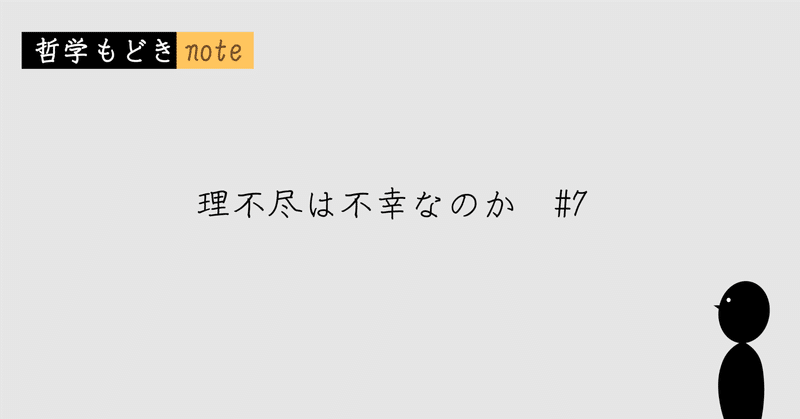
理不尽は不幸なのか #7
※この「哲学もどきnote」は、音声コンテンツ「哲学もどきラジオ」をテキストにしたものです。
ラジオで話した内容だけでなく、考えが進んだ部分や補足等も含まれます。
逆に、考えが進んでいなかったり、補足事項がないものは記事にしていないため、エピソード番号が飛び飛びになっています。ご了承ください。
太陽が眩しいから、人を殺した。
このあらすじで知られるカミュの『異邦人』。
不条理小説とも呼ばれています。
人間は筋の通らないことを一つの不幸な状態と考えることがあるようです。
今日は、なぜ筋が通らないことは不幸なのかを考えていきます。
理不尽・不条理な状況の整理
「理不尽は不幸なのか」というタイトルにも関わらず、冒頭部分で紹介した小説は不条理小説でした。
理不尽と不条理、辞書で調べてみるとこのように出てきます。
り-ふじん【理不尽】
①道理を尽くさないこと。
②道理に合わないこと。無理無体。
ふ-じょうり【不条理】
①道理に反すること。不合理なこと。背理。
②(absur de〈フランス〉)実存主義の用語で、人生に意義を見出す望みがないことをいい、絶望的な状況、限界状況を指す。特にフランスの作家カミュの不条理の哲学によって知られる。
簡単に言えばどちらも「筋が通らない」「理に反する」みたいな意味のようです。
(冒頭で紹介したものの今回は実存主義の不条理について深く考えたいわけではないので、不条理の②については触れません)
では「筋が通らない」「理に反する」というような状況で、かつ「不幸」であるような状況とは一体どんなものなのか。
まずはその状況・状態を詳細に見ていきます。
ストーリー理解ができない
「筋が通らない」状況を描くために少し参考にしたいのが千野帽子さんの『人はなぜ物語を求めるのか』という本です。
この本では人が「物語る動物」と表現され、人はストーリー形式で物事を把握したり、発信したりするということが書かれています。
この「ストーリー形式で物事を把握したり、発信する」という部分に注目して、「理不尽」と呼ばれる状態を見ていこうと思います。
たとえば、特定の人物が「他に好きな人ができたから不倫した」とします。
この因果関係、つまり「好きな人ができた」という理由・原因と「だから不倫をした」という結果を繋げるストーリーは不倫をした人物としてはストーリーとして理解することが可能ですが、された側が理解するのは難しい。
どういうことか。
この状態を理解しようとするとき、人間お得意の補完機能みたいのが働くようです。
たとえば、不倫した側の理解としてはこうなります。
「他に好きな人ができた。好きという感情は自然なものだし、それに抗うことはできない。だから不倫した」
もちろん「他に好きな人ができた」と「だから不倫した」の間に入る言葉は人それぞれ異なるかと思います。
ですが、このような仕方で不倫をした人物の中ではストーリーが出来上がり、把握されている。
では、不倫をされた側の人物としては「他に好きな人ができたから不倫した」という状況をどのように把握するでしょうか。
この場合、不倫をされた側は不倫をされたことを「不幸」と思っていることとします。
不倫されたことを「不幸」と思う場合に、不倫された側はどのようにこの状況を把握しているのか、ということです。
たとえば、このようになると思います。
「他に好きな人ができた。すでに結婚していて生涯自分だけを愛すると誓ったはず。だから、不倫した(という言い訳は許されない)」
不倫をした人物が把握し、発信しているストーリーを不倫された人物は受け入れられない。
同じストーリーで理解をすることができない。
「他に好きな人ができた」と「だから不倫した」の間を繋ぐ線がないということです。
その繋ぐ線こそが「道理」「筋」「理」として表現されているものです。
不倫をした人物と不倫をされた人物とで「道理」「筋」「理」が異なる。
だから、理解できない。
そして、それが不幸という体験になる。
自分の"理"を簡単に変えられない
自分自身が持っている、信じている理と自分自身が身を置いている状態・状況・環境との理が異なると不幸な状態になる。
これがここまでで整理した「理不尽だと不幸」な状態でした。
そう考えれば自分自身が持っている、信じている理を自分自身が身を置いている状態・状況・環境に合わせれば、つまりはズレをなくすことができれば不幸でなくなるのではないか。
けれど実際にはいろいろなところでこの「理不尽による不幸」が起こっているように思います。
人間は自分にとっての理を簡単に変える・換えることができず、それゆえに「理不尽」な状況が発生し、「不幸」になるのではないか。
ミシェル・フーコーという哲学者がとらえる権力を元に考えると、この「自分の理を変えられない・換えられない」ということがわかります。
私たちは私たちが生まれ、育った環境の中で社会に存在する規律・ルールなどを自分自身に内在化していきます。
お金を拾ってそのままポケットにしまってしまうことを「悪いこと」と自分自身で判断する場合には、この内在化された規律が働いているわけです。
そしてその規律は、その規律によって成り立っている社会に身を置いている限り、崩すことは難しい。
規律を内在化した私によってその規律は維持され続ける。
こういった状態にあるからこそ、自分とは異なる理に出会ったとき、その理を受け入れればもしかしたら幸せになるかもしれないとしても、自分の理を変える・換えることができず、不幸になってしまうのかもしれません。
いろいろな"理"
ここまで「理不尽は不幸である」状態がどのようなものか、どうしてその状態が発生するのかについて考えてきました。
キーワードとして"理"という言葉を多用しましたが、そもそもこの"理"にはどんなものがあるのかについても考えてみたいと思います。
"私"が行動するための"理"
先ほどの章で例に挙げた「他に好きな人ができたから不倫した」という状況の場合、不倫をした人物と不倫をされた人物とで"理"が違ったから、不幸になったのではないか、と整理しました。
私たちは個人として何か行為をする際に、何かを軸にして行為をしているような気がします。
マックス・ヴェーバーという社会学者は、人間が行為をするパターンは4つに分けられるのではないか、と考えました。
目的合理的行為:自分の目的のために合理的に判断をして行為する
価値合理的行為:倫理、美、宗教などの価値を軸に合理的に判断して行為する
感情的行為:感情や気分による行為
伝統的行為:内在化された規律・習慣による行為
ヴェーバーのこの整理から不倫した人物と不倫された人物の"理"、ここで言えば行動の軸・原理を考えてみると、このように整理できそうです。
不倫した人:感情的行為、伝統的行為
不倫された人:価値合理的行為、伝統的行為
不倫した人は「結婚しているけれどもこの人(自身の配偶者ではない人)と付き合いたい!好き!」という感情によって行為している。
もしもその人が男性というポジションだった場合、「男性は浮気・不倫をする生き物」という世の中に存在する考え方(伝統的な考え方としてとらえます)によって行為している。
不倫された人は「結婚をしたら他の人を好きになることは許されない」という倫理や伝統的な考え方を元に、不倫した人を糾弾する(という行為をする)。
同じ行為類型に分類できるものでも、その人が立っているポジションによって内在化している規律が異なり、それによってズレが生まれるということもありそうです。
理不尽な状況に陥ったとき「普通ならこうする」と言いたくなることがあると思いますが、人が実際に行為をするときには合理的に考える場合もあれば、そうでない場合もあり、そして合理的に考える場合でもどんな価値に依っているかによって行為が変わってしまう。
確かにそう考えると、理不尽な状況は多発しそうですね。
社会の"理"
ヴェーバーを元に「個人は何を軸に行為するか」を考えてきました。
これは「個人 対 個人」において理不尽な状況がなぜ発生してしまうのかを考えるのに役立ったと思います。
ですが、状況によっては「そもそもこの社会の"理"が自分の"理"と合わない」ということもあるように思います。
その場合の「理不尽による不幸」は、その社会に所属する限り永遠に続く不幸になってしまいます。
そんな絶望してしまいそうな理不尽な状況はどのようにして発生するのでしょうか?
社会学者のピエール・ブルデューという人がとらえる社会の考え方で整理するとわかってきます。
ブルデューは階級を軸に社会をとらえた人です。
たとえば学歴社会というものを見ていったときに、そこでは「努力していないから良い学歴が獲得できない」だとか、逆に「努力をしたから学歴が良い」というような言説が見られます。
ですが実際に学校教育についてみていくと、そもそもその教育方法自体が上層階級の人にとって「身につきやすい」ものになっている。
学校教育において良い成績をとり、良い学歴を積んでいける人は上層階級にいる人が多いという事実は、実際には「努力をしたから頭が良い」わけではないということを明らかにしている。
いろいろな社会が特定の集団にとって都合の良い"理"を適用した構造になっていて、けれどそれが「努力によって獲得できるもの」という言説が信じられることによって、その構造が隠されている。
これがブルデューが暴いた社会の構造でした。
そう考えると、特定の集団にとって都合の良い"理"が適用された社会の中に、もしもその特定の集団にいない人が所属をしているとすれば、「理不尽な不幸」が発生してしまうわけです。
しかもこの場合には社会の"理"が自分自身に内在化されていると、自分自身でも「努力していないから学歴が低いんだ」と思ってしまい、抜け出せない不幸に陥ってしまう可能性があります。
学歴社会というのは一つの例にすぎず、こういった「理不尽による不幸」は多く存在していて、そしてその不平等な構造が隠されてしまっているので、よりタチの悪い理不尽であるように思います。
『異邦人』を読んでも不幸にはならない?
ここまで「理不尽という不幸」について考えてきました。
「道理に合わない」ということだけを考えれば、不条理小説と呼ばれる「異邦人」も不幸な状況を呼び起こしそうです。
ですが、我々は『異邦人』に描かれる不条理さを読んでも「理不尽な状況による不幸」を感じることはなさそうです。
それは『異邦人』に描かれる不条理な状況が自分の環境に適用されるわけではないからです。
冒頭で紹介したように、『異邦人』は「太陽が眩しい」という理由で「人を殺す」というあらすじで知られています。
もしも殺された人の遺族であれば、その「道理に合わない」行為によって私は不幸になると思います。
なぜそんな理由(理、道理)で人を殺したのか、となるわけです。
でも『異邦人』を読んでも、私はその環境に身を置くことにはならない。
だから不幸にはならない。
つまり、「理不尽で不幸になる」という状況は、自分の"理"と異なる"理"を適用した行為や社会に出会い、自分の"理"ではなく、異なる"理"を暴力的に押し付けられるような状況なのではないか。
この自分の"理"を暴力的に押しつけてしまうという行為の仕方は、個人単位で考えるとフリードリヒ・ニーチェの「力への意志」という概念でも考えられそうです。
「力への意志」は、なんだか人というのは合理的に物事を考えて行為しているだけではない気がする、それは自分の力を示す、示したいという抗うことが難しい意志によるものなのではないか、という考えです。
不倫をした人が自分の力を示したいという意志を捨てさり、他者(配偶者)の理を受け入れることができれば、不倫に対する言い訳をせずに謝罪をするという行為に至る可能性もあります。
けれど、自分の力を示すために理を覆すことができない。
これも一つ、「理不尽は不幸である」という状況を生み出す要因のように思います。
今後の課題:なぜ"不幸"なのか
今回「理不尽は不幸なのか」というタイトルにも関わらず、「なぜ理不尽が不幸なのか」ということについてはあまり考えられませんでした。
「理不尽」という状況によって不幸になるのはなぜなのか、ということ自体は把握できたように思いますが、自分と異なる"理"を持っている人や環境にいるとなぜ不幸と感じるのか、ということについては、そもそも「不幸とは何なのか」ということについて考える必要がありそうです。
なので「理不尽は不幸なのか」というタイトルを読んで期待した内容にはなっていない部分もあると思いますが、これについては今後の課題として考えていきたいなぁと思っています。
ラジオの宣伝と次回予告
今回お話した内容を話しているラジオは、こちらになります。
次回は哲学もどきラジオ第8回「フェイクニュースはフェイクなのか?」を記事にする予定です。
更新は6/6です。お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
