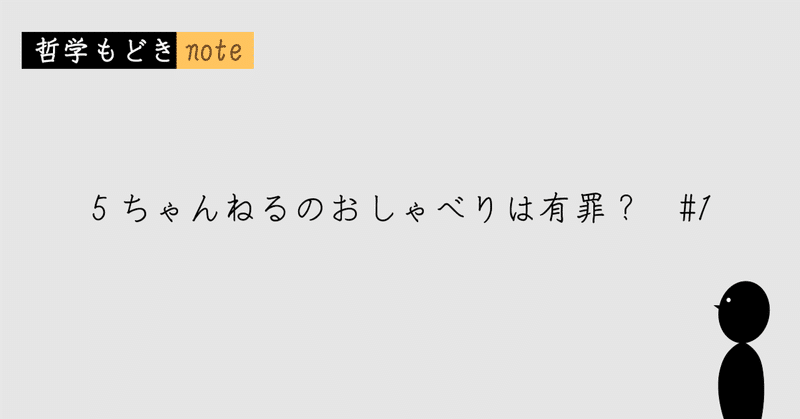
5ちゃんねるのおしゃべりは有罪? #1
あなたは今日、誰かと「おしゃべり」をしましたか?
今までにおしゃべりをしたことはありますか?
声を発したり、文字でやりとりしたり、手話で話したり、いろいろなおしゃべりの方法があると思います。
今までの人生でおしゃべりをしたことがないという方はあまりいないのではないかと思います。
おしゃべりは、「演説」や「発表」、「会議」というコミュニケーション方法より、なんだか軽い、気軽なコミュニケーションのような感じがあります。
ですが、この気軽なコミュニケーションには重たい罪があるように思うのです。
今回は「おしゃべりの罪」についてお話をしていきます。
哲学もどきnoteについて
お話に入る前に、簡単にこの「哲学もどきnote」の説明をさせてください。
私は2023年10月からSpotifyで「哲学もどきラジオ」という音声コンテンツを制作・配信しています。
「哲学もどきnote」で書いていく内容は「哲学もどきラジオ」でお話した内容を改めてテキストにしているものです。
ただ、イメージとしてはNHKの番組「100分de名著」のような形にしていく予定です。
「100分de名著」は、名著と言われる本を25分×4回で紹介していく番組なのですが、ひとつの名著を紹介するごとに、冊子が発売されます。
その冊子は番組の内容とそこまで逸れるわけではないのですが、番組のように会話をしながら進行していくわけではなく、番組で触れられていない部分にも触れていたりします。
この「哲学もどきnote」についても、「哲学もどきラジオ」でお話した内容と同じテーマを扱いながらもラジオを配信してから時間があいてから投稿するという事情もあり、少し考え方が変わっていたり、もう少しこんなことも話してみたかったというようなこともあったりするので、ラジオと全く同じ内容にはならないと思います。
なので、このnoteだけ読んでいただいても問題ないですし、ラジオを聴いたあとに読んだり、逆にこのnoteを読んだあとでラジオを聴いたりなど、お好きな形で消費していただければと思います(もちろん、消費の仕方について私が指定するような権利などないのですが)。
ただ、「哲学もどきラジオ」は毎週土曜に配信をしていますが、こちらのnoteは毎月6日の投稿となります(2024年1月時点での予定)。
ラジオを聴いてもすぐにnoteが読めるという形にはなっていないので、ご了承ください。
「おしゃべり」について考えようと思ったきっかけ:ヘーゲルが言ったらしいある言葉
「おしゃべり」について考えようと思ったきっかけは、弁証法でおなじみの哲学者ヘーゲルでした。
ヘーゲルが大学時代に歴史哲学の講義をした記録がまとめられた『歴史哲学講義』という本があるらしいのですが、そこにこんなことが書いてあるよーという話を聞いたのです。
「おしゃべりは罪がないけど、演説は罪がある!なぜなら歴史を動かすから!」
聞いたのです…と書いたのでお察しかもしれませんが、私はこの本を持っておりません。
ただ、「演説は罪だけど、おしゃべりは罪がない」というこの言葉を聞いたことで、「おしゃべり」について考えることになったため、紹介してみました。
ですが、おしゃべりについて考えるきっかけとなったのはこのヘーゲルの『歴史哲学講義』の又聞きだけではありません。
5ちゃんねるの差別言説
「おしゃべり」について考えるきっかけとなったもう一つは「5ちゃんねる」でした。
「5ちゃんねる」を知らない方もいるかと思いますので、簡単に説明をします。
「5ちゃんねる」はいわゆる「掲示板」と呼ばれるもので、何か話したいテーマのようなものがあったら、それを話すための部屋のようなものをつくります。
匿名の人たちが、その部屋にどんどんテキストベースの発言を投稿していく…というものです。
私はネットに疎く、2ちゃんねるも5ちゃんねるもあまり見たことがなかったのですが、あることをきっかけに5ちゃんねるをたくさん見なくてはいけなくなりました。
そこで驚いたのは、あまりにも差別言説が溢れている……ということでした。
「ハゲ」「デブ」「ブサイク」「大根足」「中卒」「高卒」「発達障害」「害児」
これらの「外見」「学歴」「障がい」に関する言葉は、自分の論の正当性を認めさせるための文脈で使われたり、またはテーマが芸能人に関するものであれば、その芸能人に対して使われたりしていました。
私は、SNS上でここまでの言葉で誰か人を中傷したりする人を見かけたことがあまりなかったため、驚きました。
対面での場においては、さらにこんな言葉たちにお目にかかることはありません。
正直、5ちゃんねるをはじめて見たときに、こう思いました。
「まだこんなことを言っている人たちがこの世に存在するんだ」
おしゃべりの機能
5ちゃんねるの場はまさに「おしゃべり」の場かと思います。
ですが、そもそも「おしゃべり」とはどんなものなのでしょうか?
なぜ人はおしゃべりができるのか? を考えてみると、おしゃべりの機能が見えてきます。
我々がおしゃべりできるのは同じ記号を共有しているからです。
たとえば、私は日本語話者です。
なので、日本語を話すことができる人と話すことができます。
では、日本語話者とであれば、誰とでもおしゃべりが出来るのか?と問われると、そんなことはありません。
同じ日本語をしゃべっていても共有できる文化、思想がなければおしゃべりをすることは難しいです。
たとえば、私はアイドルが好きですが、アイドルについておしゃべりをするときには、アイドルについて知っている人、もしくはその話題を受け入れてくれる人とでないとおしゃべりができません。
もう少し細かいことを言えば、「アイドル」という言葉があることによって、このおしゃべりがすごくスムーズに進行します。
「アイドル」の正しい定義はわかりませんが、たとえば「ステージで歌って踊るお仕事をしている人」みたいな意味があるとします。
もしも私がおしゃべりをしたいと思った相手が「アイドル」という言葉を「美味しい食べ物」と認識していたとしたら、私はアイドルのおしゃべりを
その人とすることができなさそうです。
「アイドル」という言葉で、私の思う「アイドル」の話ができるのは、私が「アイドル」という言葉を「ステージで歌って踊るお仕事をしている人」と認識していて、そして同じようにそう認識して「アイドル」という言葉を使う人がいて、そんな私や他の人たちが何度も何度も繰り返し「アイドル」という言葉を使ってきたから、「ステージで歌って踊るお仕事をしている人」を「アイドル」と呼んでおしゃべりをすることができるのです。
これは「なぜおしゃべりをすることができるのか」という問いの一つの答えでもあり、かつ、おしゃべりの機能でもあります。
つまり、おしゃべりがあることによって「言葉」が意味を保つことができるのです。
良い言葉も悪い言葉もおしゃべりの場によって、何度も繰り返されることによって、その言葉は死なずに使われ続ける、つまり再生産されることになるのです。
これが「おしゃべりの持つ罪性」に繋がってきます。
演説との違いから考える「おしゃべりの罪性」
せっかくヘーゲルの話をきっかけに「おしゃべり」について考えてみようと思ったので、演説とおしゃべりの違いから、「おしゃべりの罪性」について考えていきます。
正直に言っておくと、私は演説というものをしっかり聞いたことがありません。
なので、ここから話す「演説」については私のイメージであることをご了承ください。
私のイメージする演説を簡単に単語でまとめてしまうと、「権威」「伝播」「変化(改革)」です。
特におしゃべりと比較したとき、この3つが異なる点として挙げられるように思います。
権威
まず、「権威」について。
演説をする人を思い浮かべるときに、どんな人が思い浮かぶでしょうか?
私は完全に「政治家」です。
ただ、政治家でなくても演説をする人はいるのかもしれません。
たとえば社会活動に参加する方の中には、政治家というわけではないけれども何か主張したいことがあって、誰かの前に立ち演説をするということもあるかと思います。
また、広い範囲で考えれば、演説とはそもそも人前に立って話すことを言いますから、結婚式のスピーチも演説と捉えることができます。
政治家でなければ、権威性とか感じないんじゃないの?
と思われるかもしれませんが、実はそんなことはないと思っています。
人の前に立つこと、そして話すこと、話し終わること、これが出来た時点で、人々に人前に立つことを認められていると捉えることができるように思うのです。
(そうじゃない場合もあるかもなぁーと思いながら書いています。このあたりは今後もう少し考えてみますね)
その時点で、演説をするということそのものが権威性の表れのように思います。
人前で話すというこの演説の性質は、もう一つの「伝播」にも繋がってきます。
伝播
演説とはその形式上、1対1のコミュニケーションではありません。
基本的には1人が大勢に対して話すことで「演説」と認識されるかと思います。
何か主張したいことがあり、それがなるべく多くの人に伝えたいことであるとき、この演説という手段が有効であることはお分かりかと思います。
時間という制約を抱えて生きている以上、この演説という手法がなければ、多くの人に何かを伝えるということは難しいように思います。
変化(改革)
演説の意味を「人前で話すこと」として考えると、「変化」は演説に絶対的に当てはまる性質ではないように思います。
ただ、ヘーゲルが演説を罪として捉えたときにはこの性質がイメージされていたのではないかと思うのです。
ここからは完全に政治家をイメージして演説について語っていきます。
たとえば、政治家が演説をする際、その目的は「現状維持」ではないはずです。
何か現状に対して、不満や不安、変えなくてはという意思が存在するからこそ、「(現状はできていないことを)~します!」と公約するのです。
おしゃべりとの違い
演説とおしゃべりの違いの中で、特におしゃべりの罪性を浮き彫りにする特性は「変化(改革)」なのではないかと思います。
「おしゃべりの機能性」でお話をした通り、おしゃべりは言葉が繰り返され、反復され、再生産される場です。
演説の「変化」と比べたときに、この機能は「維持」と捉えることができると思います。
たとえ、どんなに演説が上手だったとしても、聴衆の心に響いたとしても、それが伝播されなければ、演説は失敗と言えるかもしれません。
聴衆の心に響いて、それが聴衆たちのおしゃべりの中で何度も何度も繰り返される。
そうして、演説をした人が望む状態へと近づいていく……。
そう考えると、演説だけでは歴史を変えることは難しそうです。
むしろ、演説とおしゃべりとのセットで歴史が変わっていく可能性もありそうですね。
さらに言えば、おしゃべりが演説を邪魔する可能性もあります。
演説のときに誰かのおしゃべりがうるさい!みたいな話ではありません。
たとえば、演説で「りんごはうまい」ということを伝えたとします(一体どんな演説なのでしょう…)。
おしゃべりの場では演説が行われる前から、「りんごはまずい」と言われ続けていたとします。
演説を聞いた何人かは心を打たれて、おしゃべりの場で「おい!りんごはうまいらしいぞ!」と言いますが、演説を聞いていない人たちによって「いやいや、りんごはまずいものだろう!」と反論され、「やっぱり、りんごはまずいよな」と納得してしまいます。
そうして、再びおしゃべりの場では「りんごがまずい」ということが繰り返されていきます。
今回はあまりにもわかりづらい「りんごがまずい」という言説でお話してみましたが、実際に想像すれば現実としてこのような光景が思い浮かぶのではないでしょうか?
なんだか演説よりも、おしゃべりの方が社会を回してそうな感じがしてきました。
おしゃべりは有罪! でも無罪?
5ちゃんねるで差別言説が今も存在し続けているのは、2ちゃんねるというネット文化から5ちゃんねるという文化に至るまで、それが繰り返されてきたからだ…と考えることができそうです。
もしも、5ちゃんねるとなるまでおしゃべりが繰り返されることがなければ、もしかしたら、もう少し差別言説は減っていたかもしれません……。
ですが、おしゃべりに歯止めをかける方法はあるのか、私にはわかりません。
なぜならおしゃべりはあまりにも気軽に始められるし、「空気を読む」日本文化では、良くないと思われるようなことを指摘するということも困難だったりするからです。
おしゃべりはこういった意味で有罪でもありますが、良いものでもあるように思います。
この世に存在する言葉には良い言葉もあるからです。
おしゃべりが言葉を繰り返し再生産する場であるとすれば、そこには希望も絶望もあるのではないか……と思います。
ラジオの宣伝と次回予告
今回のお話を音声でお届けしている「哲学もどきラジオ」のURLはこちらになります。
第2回の「なぜ人を殺してはいけないのか」という質問によって人の価値観がわかるなぁと思った話はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
