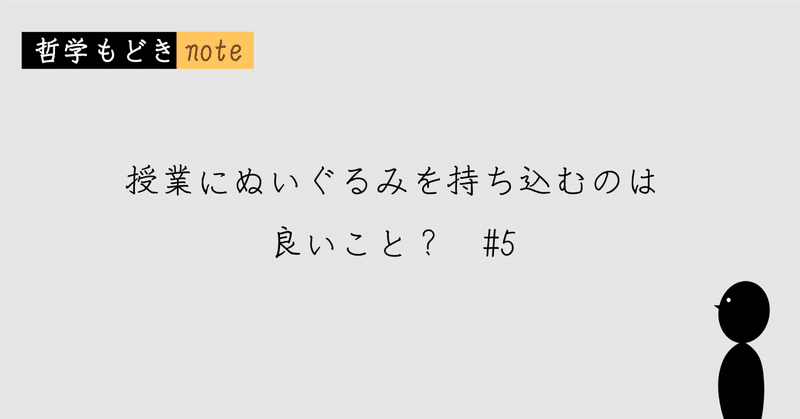
授業にぬいぐるみを持ち込むのは良いこと? #5
※この「哲学もどきnote」は、音声コンテンツ「哲学もどきラジオ」をテキストにしたものです。
ラジオで話した内容だけでなく、考えが進んだ部分や補足等も含まれます。
逆に、考えが進んでいなかったり、補足事項がないものは記事にしていないため、エピソード番号が飛び飛びになっています。ご了承ください。
『ナチスは「良いこと」もしたのか?』という本を読みました。
その本の中で定義されていた「良いこと」は
「オリジナルか」「目的が良いことか」「結果が良いものだったか」という3点でした。
皆さんにとって、「良いこと」とはどんなことでしょうか?
『ナチスは「良いこと」もしたのか?」の内容と「良いこと」
今回のテーマは「良いこと」、つまりは善悪、または道徳と呼ばれるようなものです。
このテーマについて考えるきっかけになったのは、2023年7月に発売されたこの本でした。
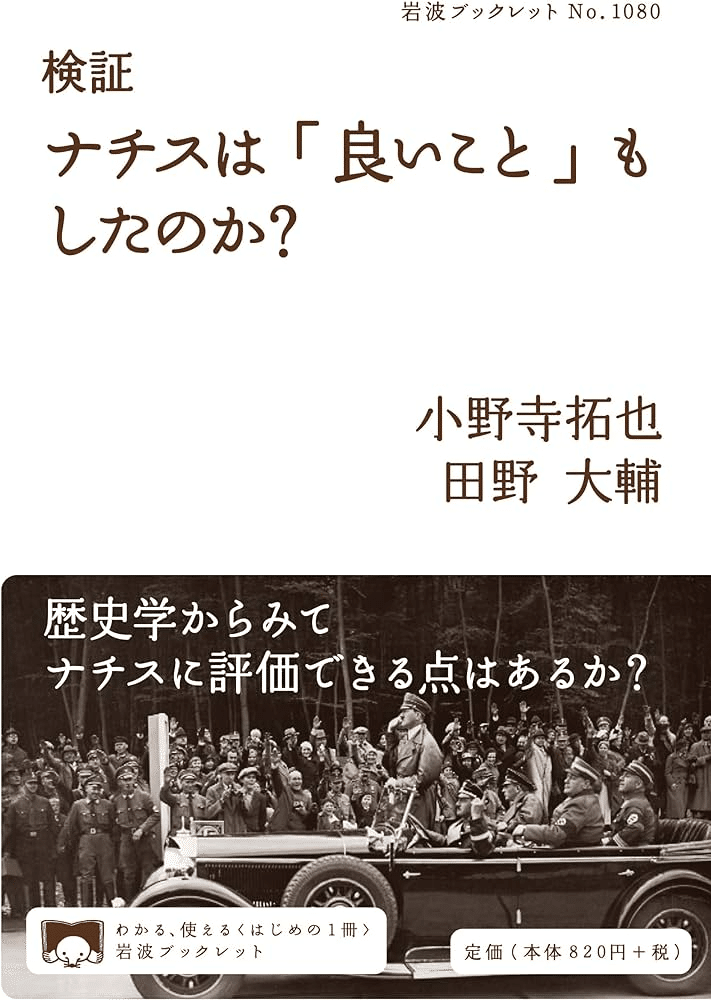
はじめに、この本の概略とこの本で定義されている「良いこと」について簡単に説明します。
まずは概略から。
この本を書いているのは歴史学者の二人です。
そのため、基本的に「歴史的な事実」を元に「ナチスは良いこともしたのか」という問いについて考えていくという内容になっています。
ですが、そもそもなぜ「ナチスは良いこともしたのか」という問いを考えようとしたのでしょうか?
私は知らなかったのですが、実はこの議論、定期的に繰り返されているそうなんです。
本書では、こんな例が挙げられていました。
2021年2月に、小論文を教える教える予備校講師のツイートがちょっとした騒ぎとなった出来事が挙げられる。そのツイートは、指導する女子校正が「ヒトラーのファンでナチスの政策を徹底的に肯定した内容」の小論文を提出したが、「文体が完璧」で添削に困った、というものだった。
※漢数字を算用数字に換えて表記しています。
これは日本の例ですが、ドイツの例も挙げられていました。
2007年に、あるニュースキャスターが家族政策やアウトバーンなどナチスの政策には良い面があったという趣旨の発言をして、世論を二分する騒動になったことがある。
※漢数字を算用数字に換えて表記しています。
このように、実際に今まで「ナチスは良いこともしたんじゃないか」という議論がされてきた。
その中でよく議論されてきた「ナチスがやったこと」について、歴史的事実を元に、本当にそれは「良いこと」だったのかを検証していくのが本書……というわけです。
もちろん「検証」と言うからには「良いこと」についても定義をしなくてはなりません。
本書では下記のように「良いこと」が定義されていました。
①その政策がナチスのオリジナルな政策だったのか(歴史的経緯)、②その政策がナチ体制においてどのような目的をもっていたのか(歴史的文脈)、③その政策が「肯定的」な結果を生んだのか(歴史的結果)
善悪の判断:授業にぬいぐるみを持ち込むことを悪と思っていた私
本書で定義されている「良いこと」を見て、自分にとって「良いこと」とはなんだろう……と考えました。
私は歴史学者ではないので、この本のアプローチに対して批判をできる立場ではありません。
あくまで、この本をきっかけに私なりに「良いこと」について考えた、のが今回の記事です。
まず思い浮かべたのが、大学時代のある経験でした。
大学生のとき、私は前の方の座席に座りがちな学生でした。
同じく前の方に座りがちなある同級生が、一番前、先生の目の前に座り、机の上に、ぬいぐるみを座らせたことがありました。
当時の私はその行為を見て「やめた方が良い」と伝えました。
ぬいぐるみを授業に持ち込み、さらに先生に見えるような状態にしておくことが、当時の私にとっては「悪いこと」だったからです。
ですが、不思議なことに今はこの行為を「悪いこと」とは思わないのです。
私自身、今ではぬいぐるみを連れ歩くことがあります。
喫茶店や飲食店でお気に入りのぬいぐるみをテーブルの上に出して、一緒に時間を楽しむ……という行為をします。
そう考えると、たった一人、私という人間の中でも「善悪」という判断は揺れるもの、固定されないものなのだということがわかります。
「良いこと」について
私のような一般人では「本当の良いこと」や「本当の道徳」などというものを捉えることはとても難しいことのように思います。
そもそも短い人生のなかでさえ私の「善悪」は変化しており、今後も変化してしまうかもしれません。
では、哲学者や社会学者であればどうでしょう?
ここからは『ナチスは「良いこと」もしたのか?』で「良いこと」とされていた3つの「良いこと」について、哲学者や社会学者の考えを借りて整理していってみようと思います。
「オリジナル」であることは「良い」
この「良い基準」を取り入れる際、本書では下記のように理由が述べられていました。
何かがナチスによる「発明、発見」であることと、それが「良いこと」であるかどうかはまったく別の問題のはずである。「オリジナル」であることは、「良い」という価値判断を一切保証しない。だがそれでも一般的には、「オリジナル」=「良いこと」と考えられていることが少なくない。
すごくリアリティのある書き方だなと思います。
論理的に「オリジナルであること」が「良いこと」と繋がりはしない。
けれども、実際に世の中を見渡してみれば「オリジナルであること」が「良いこと」とされていたりする。だから、その価値基準を採用しよう、ということです。
机上の空論や「良い」の理想形によって検証を行うよりも、現在の社会に実在する「良いこと」を採用しようという意図ですから、合理的な判断だと思います。
さらに、ある社会学者の視点から見ても、この「オリジナルであること」を「良いこと」とする価値基準はとても人間らしいものであるように思います。
その社会学者はマックス・ヴェーバーという方です。
ヴェーバーは人間が行為をするとき、どんなことを基準として行為をしているかということを4つに分類しました。
ヴェーバーはこの行為の4類型を提示することにより、「人間って合理的に行為してるばっかりじゃなく、全然合理的じゃない軸で行為してたりもするよねぇ」ということを明らかにしました。
この行為の4類型のひとつに「伝統的行為」というものがあります。
これは「昔/今まで/前から そうだったから」という理由に基づいての行為です。
たとえば、最近は問題視されるようになってきた「学校のルール」。
髪を染めてはいけません。
だとか
ピアスの穴を開けてはいけません。
だとか
スカートの丈は短くしちゃいけません。
それらの理由に納得がいかない!という人もいると思いますが、これらのルールが今でも残っている理由の一つは「今までそうだったから」なわけです(実際にはこれだけではありませんし、先生方はそうではない言い方で理由を述べるでしょうし、構造的に他の理由もあるだろうと思います)。
「オリジナルであれ」ば「良い」という考えも、本書で指摘されている通り、まったくもって合理的ではありません。
けれども「良いこと」とされている場が多くある。
なんだか「良いこと」というものが、どんどんふわふわしてきましたね。
「目的」が良ければ「良い」
ナチスのやったことは結果的に「悪かった」とされることが多い。
けれども、もしも「目的」自体は「良いもの」を目指していたのであれば、「良い」と判断できるのではないか。
ここで難しいなぁと思うのは、
そもそも「悪いことを目指して目的・目標を規定するという行為」はあり得るのかということです。
もちろん本書での検証では、その目的が「外から見たら」「客観的に見たら」「現時点から見たら」、「良いこと」なのかという試みです。
ここで一つの視点を取り入れることで、この「目的」が良ければ「良い」について考えてみます。
ハンナ・アーレントという方の視点です。
政治哲学者と呼ばれることもあるアーレントですが、アーレントはまさにこのナチスや全体主義、政治というものについて考えた人です。
本書では「目的」が良いものか、という検証がなされたのに対し、アーレントは「そもそも目的とか理想とか、みんなが向かっていけるユートピアみたいなものがあるという前提で政治をやるのってどうなのよ」的な思想を持ってらっしゃいます。
会社や学校、自治体、政府、いろいろな組織がそれぞれに「目的」を持って活動をしています。
ですが、それが「組織」である限り、そこには「いろいろな人」がいます。
その「いろいろな人」が単一の、一つの目的に向かっていくという状態ってなんだか不思議ですよね。
いろいろな人、複数の人がいるのであれば、その人たちが話し合って、こうしたい、ああしたい、としていくことが本来の人間の行為の仕方なんじゃないか? とアーレントは言うわけです。
本書では「目的が良いことか」というのが一つの視点としてあった。
けれども、アーレントの視点を取り入れると、
「そもそも複数の人たちが参加する場に、一つの目的や理想なんてものがあると思うことが『悪い』!」
となってしまいそうです。
「肯定的な結果」を生めば「良い」
ナチスの政策によって、結果として恩恵を受けている、という人もいることが、この「肯定的な結果」を生めば「良い」という価値基準を設定した理由のようです。
実際に恩恵を受けている人もいるのだろうなと思います。
ただこれもまた難しいのは、人によって「見えている現実が違う」ということです。
たとえば、高速道路が出来たときのことを考えてみます。
高速道路をよく使う人は「便利だ」と思うでしょうから、「肯定的な結果」としてとらえるでしょう。
ですが、近隣に住んでいる人にとっては「景色が変わってしまった」とか「夜も交通が多く、車の音がうるさい」とか、「否定的な結果」として見えるかもしれません。
これについては前回の記事で、ピエール・ブルデューを紹介している箇所でお話しています。
本日、配信された哲学もどきラジオでも似たようなお話をしているので、よろしければぜひ聞いてみてください。
「本当の道徳」とは何か
ここまで『ナチスは「良いこと」もしたのか?」を元に、「良いこと」ってなんだろーということについて考えてみました。
合理的ではない理由も「良いこと」とされる現実があったり、
みんなで一つの「良い目的」なんて持てないということがわかったり、
「結果」の見え方は人によって違うので一概に「良い」とは言えない、ということがわかったりしました。
そもそも「本当の善悪」だとか「本当の道徳」みたいなものってあるんでしょうか?
これについて、最後に二つの視点を紹介していきます。
自身の道徳は「内在化された規範」にすぎない
哲学者のミシェル・フーコーは「権力」というものをそれまでとは違う形で描き出した人です。
たとえば道端にお金が落ちていたときを想像してください。
周りには人影がなく、そもそも人通りの少ない場所。
お金は一万円としましょう。
このとき、いくつかの選択肢が考えられそうです。
交番に届ける
自分の懐におさめる
見なかったふりをする
この選択肢を考えているときに、もう「権力」が働いています。
交番に届けようが、自分の懐におさめようが、見なかったふりをしようが、誰にも見られていないのだから、何をしても誰にも何も言われない。
にも関わらず、「自分の中にある善悪の規準」によって、ここで何かを選択するわけです。
その「自分の中にある善悪の規準」は、今まで生きてきた社会の規範が自分に内在化したものです。
こんなふうに、人々の中に社会の規範のようなものが張り巡らされている。
この視点で考えれば、善悪は「個人によって違う」ということは言えなさそうです。
私の中にある善悪の規準は、私が生きている社会の中の善悪の規準であるはずだからです。
社会から離れたところに「本当の道徳」がある?
そう言ったものの、またブルデューの「人によって見えている現実が違う」というところに戻ってみると、自分が所属する社会によって善悪は違うわけだから、やっぱり「本当の道徳」「本当の善悪」なるものはないんじゃないか。
もしも「本当の道徳」があるとすれば、それは「社会から離れたところ」にあるんじゃないか?
これに対して「そうそう! 本当の道徳は社会から離れたところにあるんだよ!」と大きく頷く哲学者がいます。
フリードリヒ・ニーチェという方です。
孫引きになってしまいますが、ニーチェはこんなことを言っています。
私の道徳は、ひとりの人間から一般的な性格をしだいに奪い取って特殊化していき、ついには他の人間には理解しがたいものにしてしまうことである
もしも『ナチスは「良いこと」もしたのか?』の中で、こんな道徳を用いて検証をしようとすれば、それは一体何に向かっているのかわからなくなりそうです。
社会の中で言われている「ナチスは良いこともした!」という意見について、検証しようとしているわけですから。
けれども、合理的ではない「良いこと」が多くの人に受け入れられている現実があったり、見る視点によって、立っている場所によって、「良いこと」が違ったりする中で、一体我々は何が「良いもの」で何が「悪いもの」なのか。
それを突き詰めていくと、もしかしたらニーチェの言うように社会から外れていくしかないのかもしれない。
逆に、いろいろな人の善悪をそのままにどうにか何か良い方向に行こうとするのであれば、アーレントの言うように、複数の人がその人それぞれの「良いこと」を持ち寄って話し合う、という方法が良いのかもしれない。
そう考えると、授業にぬいぐるみを持ち込むことを悪いと思っていた私と、今ではそれを悪いと思っていない私、その流れも含めて自分はどんな善悪の規準を持っているのかを見つめることが、「良いこと」へと向かう一歩目なのかなぁと思います。
留意点
繰り返しますが、本記事は『ナチスは「良いこと」もしたのか?』の批判をしたいわけではありません。
そもそも「良いこと」の議論にページを割いてしまっては『ナチスは「良いこと」もしたのか?』の検証に入ることが難しいと思います。
そのため、本書における「良いこと」の定義だけに焦点を当てて批判することは的外れな批判だと思います。
なので本記事はあくまで、本書をきっかけに「良いこと」について考えた、と捉えていただければ幸いです。
ラジオの宣伝と次回予告
今回お話した内容を話しているラジオは、こちらになります。
次回は哲学もどきラジオ第7回「理不尽は不幸なのか」を記事にする予定です。
更新は5/6です。お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
