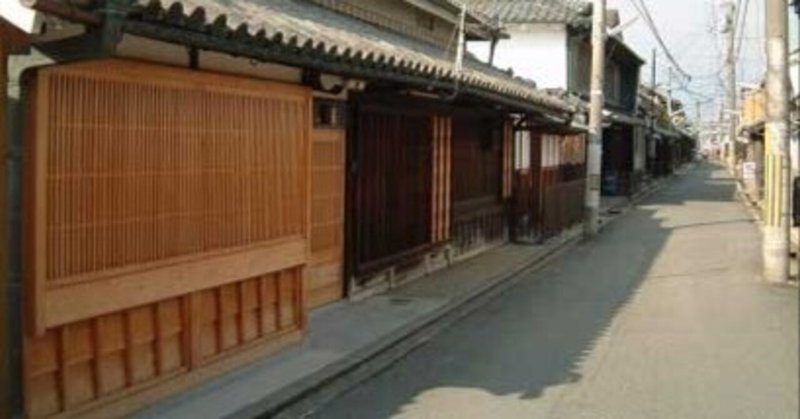
大和の古道について
奈良盆地には南北方向に3つの官道が敷設されており、西から下ツ道、中ツ道、上ツ道と呼ばれる。敷設時期は6世紀末〜7世紀初頭と考えられ、当初は奈良盆地と木津の港を結んでいたが、平城京造営時に下ツ道は取り込まれて朱雀大路になり、藤原京と平城京を結ぶ道になった。

この三道の敷設順序は諸説あるようだが、奈良盆地の条里に道幅分の余剰空間があり、下ツ道が条里の基準になっていたことがわかる。そこから敷設順序を推測すると下ツ道→上ツ道→中ツ道となろうか。なぜかというと、中ツ道は香久山の正面にぶち当たっていて、それを迂回させようとした痕跡は見つかっていない。山を道路敷設時の基準点とした例はいくつかあるようだが、この場合は山の真正面に道路が敷設されるのが却って不自然である。中ツ道は奈良と明日香を結ぶ道と考えられているが、香久山に邪魔されて明日香に到達しておらず、そこから下ツ道と上ツ道の中間に、機械的に敷設された道だと考えられる。この中ツ道が明日香に達していないことは、明日香の中ツ道延長ラインに位置するところで掘立柱建物が検出されていることからもわかる。
次に上ツ道である。私は、上ツ道の原型となる道(原・上ツ道)があったと考えている。その根拠は薄弱だが、古くは奈良盆地の中央部は湖(奈良湖)があるなど湿地帯で居住等に適さなかったこと、大和古墳群の古墳の一部に、現在残る上ツ道に主軸を並行させた古墳があることで、そこから上ツ道は原型となる道=原・上ツ道を再整備したものと考えたのである。もしかすると、この原・上ツ道を基準に下ツ道が敷設され、並行して上ツ道の整備が行われたのかもしれない。
大和の古道について、2つの仮説を立ててみた。いずれも根拠は薄弱だが、捨て去るには惜しいもので、できれば論文化したいと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
