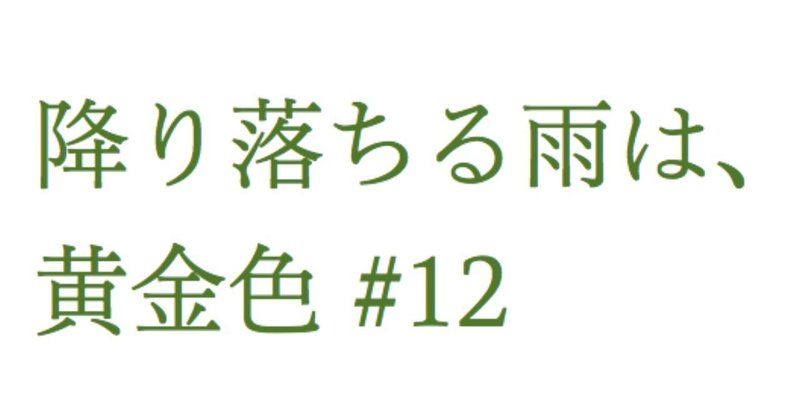
降り落ちる雨は、黄金色#12
佳代の居ない淋しさから、私は本の世界へ没頭していった。活字を目で追っている間は、嫌なことを忘れられた。想像力の翼を使えばここではない何処かへと行けた。
小説は私にとっての薬だ。崇高な作品のページの隙間からは、悲鳴が聞こえる。その声はとても心地がよく、マイノリティであることに悩む主人公が、足掻きながらも生きる姿にいつも勇気をもらっていた。私はいつも小説の中で希望を探している。
あれから、学校は病気で一週間ほど休んだ。私は死刑台にこれから昇る様な気持ちで、教室のドアを開けた。久しぶりに登校してみると、教室の空気がいつもと違う。軽い。何故かふわふ わとしている。そして謎の人だかりができて いる。その中心に居るのはスーパーリア充の鈴木奈津美だ。
彼女は選抜クラスの四組のくせに、他所のクラスまでよく遊びに来ている。私のいる三組は、就職も進学もできるクラスだ。
選抜クラスは上の大学を目指す競争社会の申し子のような生徒が多く、エリート意識が高い。そのため普通科の生徒からは、あまり評判がよくない。選抜科と普通科の間には見えない国境が存在している。
選抜科が一軍なら、普通科は二軍だ。二軍の中でもブサイクな者、友人のいないもの、勉強のできない者は三軍となる。同じ学年で格差が見える形でつけられる。廊下で選抜クラスの生徒とすれ違う度に劣等感を感じる。
奈津美は勉強ができる事を鼻にかけず、穏やかで誰とでも話せる。すらっと伸びた脚に、パッチリとした二重瞼。緻密な黒目がちな瞳。年上の大学生の彼氏。銀色の高そうなアクセサリを見せびらかす様に首に着けている。まさに女の子の憧れを具象化したようなモンスターだ。
彼女が教室にいると空間が明るくなる。教室では奈津美が原宿の路上で、 テレビ局のインタビューを受けた話で持ちきりだった。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
