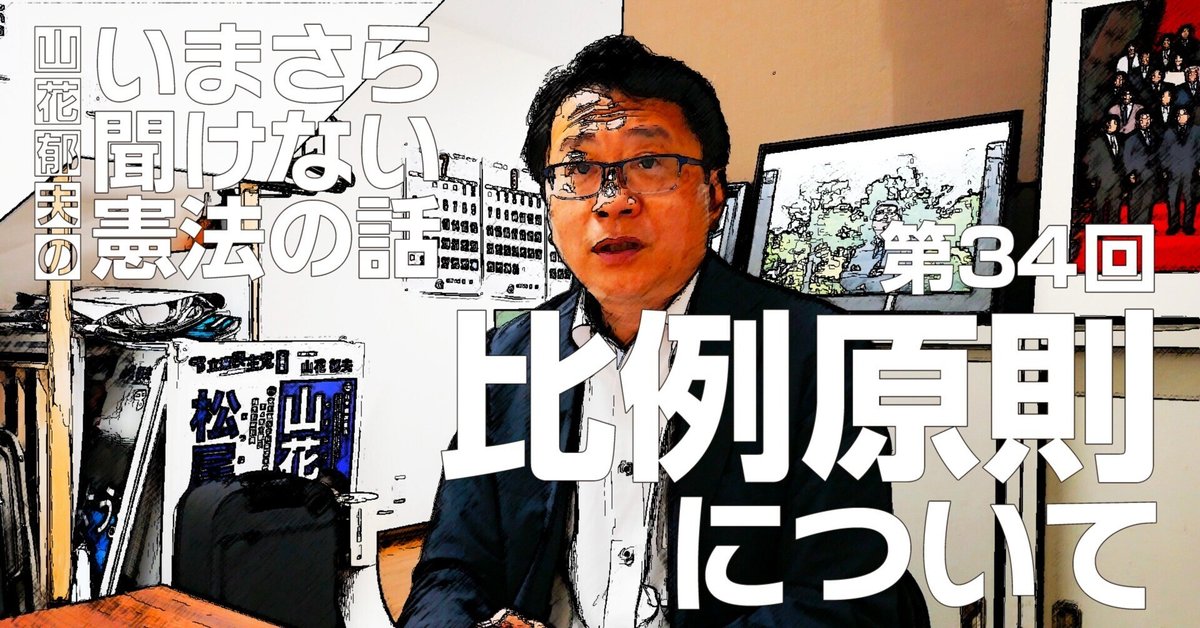
【第34回】比例原則について #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話
背景的権利
憲法に記述されている人権だけが大事だというつもりがないことは、ここまでお付き合いいただいた方にはご理解いただけるものと思います。そして、新たに主張される「人権」についても、単なる自由だったものがある日を境に突如として人権になるのではなく、主張され始めてから判例で取り上げられるまでの間、あるいは判例が積み重ねられている間は、いわは生成、発展のプロセスにあるものもあると評価できる場合もあると思います。
このことは、京都大学名誉教授の佐藤幸治先生が、憲法の保障する基本的人権にとっていわば背景的権利と称すべきもの(『憲法[第2版]』2020年・成文堂141頁)と分析されているのと同様ではないかと思われます。このような背景的権利と称すべきレベルに至っていれば、憲法で規定されている人権を制約し得るほどの対立利益になっていると考えられます。
それでは、背景的権利に至らない一般的自由であれば、憲法上の問題は生じない、つまり、いかようにも制限できると考えてよいでしょうか。いやいや、むやみに規制してよいわけではないのだ、という比例原則についてここで説明しておきたいと思います。
法の一般原則 比例原則
比例原則は、法の一般原理とか、一般原則と呼ばれるもので、憲法の人権論に固有のものではありません。当初、行政法の分野で警察比例の原則などのように用いられていた概念です。
目的に対して、自由や利益の制約の程度は比例的でなければならないというのか比例原則です。具体例でいうと、泥棒を捕まえるのに軍隊を使ってはいけないであるとか、スズメを撃つのに大砲を使ってはいけない、ということです。
憲法上の人権を制約する場合でなくても、この比例原則がありますから、行き過ぎた規制は、比例原則違反となることもあり得ます。
ここでは、憲法上の一般的自由に関連して比例原則を紹介しましたが、憲法上の人権についての違憲審査基準も、この比例原則を準則化したもの、ルールを具体化したものも少なくありません。制約の程度は比例的でなければならないといっても、必ずしも2の累乗のように数字で表現できるものではありませんから、たとえばLRAの原則のような形で、比例原則違反を表現しているのだ、と理解することができると思います。
わかりやすいことが正しいこととは限らないことについて
毎年、国会では多くの法律案について審議が行われ、新しい法律や既存の法律の改正が行われています。おおむね7割から8割は大きな対立なくして成立していくのですが、中には、与野党激突のような形で報じられるような政治的に注目を集める法案もあります。
今の日本で、法案の目的そのものが邪悪で、けしからんというものは、皆無とは言いませんが、そんなにめったにお目にかかることはないと思います。しかし、目的は理解できるとしても、その手段としてやりすぎではないのか、不適切ではないか、という争いはしばしばあります。法的に言えば比例原則違反ではないか、という争いです。
しかし、報道では、なかなか問題点の詳細まで丁寧に掘り下げることは難しいものですから、立法目的のところだけでなんとなく理解しているケースが間々あると思います。実は目的自体については与野党に争いは無いケースのほうが圧倒的に多数なのかもしれません。
「泥棒をしょっ引くと言っているんだから、じゃんじゃんやればいいではないか」、「犯罪には、ともかく重罰化」という主張はわかりやすいかもしれませんが、比例原則という観点からは、必ずしも正しい主張ではないことは、ここで強調しておきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
