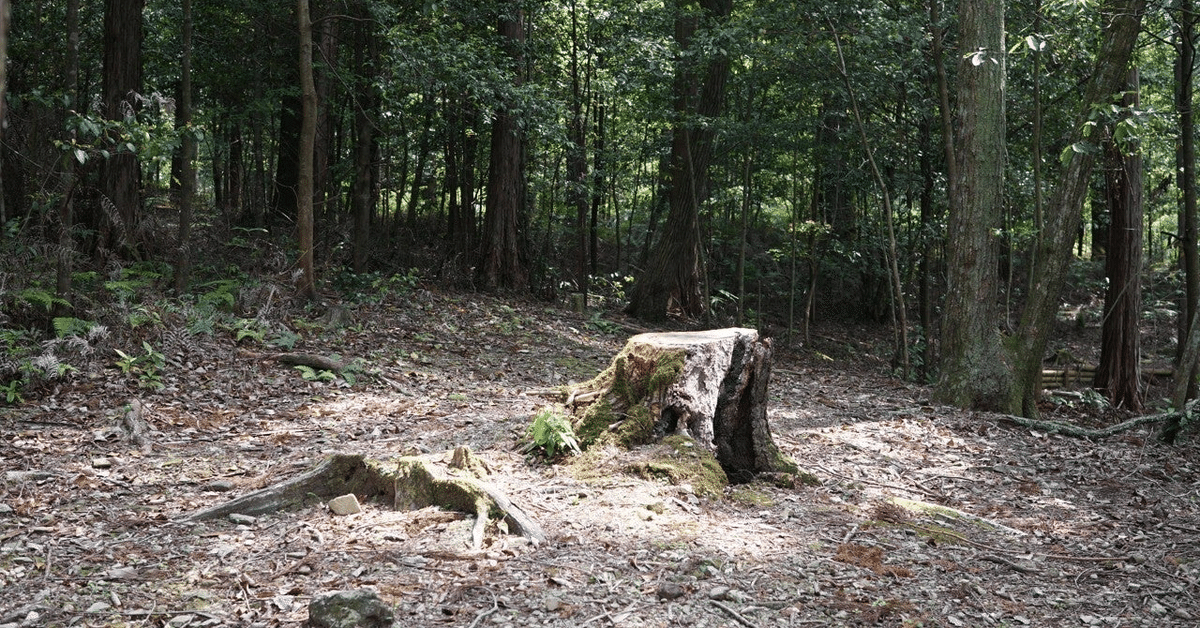
フォークナー 「アブサロム、アブサロム!」
はじめに
フォークナーの「アブサロム、アブサロム!」を読みました。感想を書こうと思います。
まず、作品全体を通読して感じたのは『オーソドックスな文学だな』という事です。話そのものは、トマス・サトペンという自らの野心に取り憑かれた人間が破滅していく物語で、主体の欲望に勝てなかった人間が社会的に破滅していくというのは、私の知っている範囲内で、『オーソドックスな文学作品』だと思います。
なので、全体を通読して、(良かったな)と素直に思いました。作品そのものも良かったし、自分の観点が間違っていなかった証明になっているとも感じ、その点でも(良かった)と思いました。
もっとも、この作品には明白な欠点があると思われますので、欠点の方を先に片付けてから、作品の本質について考えていきたいと思います。欠点は二つあります。
欠点一 語りの複雑さ
一つは、語りが複雑すぎる事です。また、語りが間接的過ぎて、トマス・サトペンという主人物の姿が作品終盤になるまで見えてこない事です。
通常、小説におけるキャラクターがその印象を読者に与えるのには二つの方法があります。一つはキャラクターの行為を描く事、もう一つはキャラクターが「」で喋る事です。
この場合、特に二つ目の「」で喋る事が重要と思われます。あるキャラクターが「」で話す事は、そのキャラクターの印象をほとんど決定づけると言っていいでしょう。シェイクスピアの作品におけるキャラクターのセリフの重要性は言うまでもないと思います。シェイクスピアにおいては、キャラクターの行為は、キャラクターのセリフを裏付けるものであるように私は感じます。それほどに、言葉で自分を表現するというのは、読者に強い印象を与えます。
この場合、()で内心を打ち明けるのも、私は「」で話すのと同じ事と捉えます。()で内心を打ち明けるとか、「」で会話するというのは、そのキャラクターの本質を読者に伝える重要な要素です。キャラクターの行為を描く事ももちろん重要ですが、それ以上に「」のセリフは、読者に、キャラクターに対する直接的な印象を与えます。
ですが、「アブサロム、アブサロム!」では語りの技巧が複雑化しており、あまりに間接的になっているので、トマス・サトペンのセリフは作品終盤までほとんど見られません。その為に、読者は、トマス・サトペンというキャラクターに対する印象が遠回りすぎて、いまいちこの人物が把握しきれません。トマス・サトペンがわからないという事は、この作品全体がわからないという事とイコールと言っていいでしょう。トマス・サトペンはそれほど重要な人物です。
作品の筋としては、トマス・サトペンの息子ヘンリーが腹違いの兄弟チャールズ・ボンを殺害するという事が重要となっています。解説すると、トマス・サトペンは、若い頃に、プランテーションの所有者の娘と結婚し、娘はチャールズ・ボンを産みます。しかし、娘が黒人との混血だと後から知らされ、サトペンは裏切られたと感じ、娘と離縁します。
その後、サトペンはエレンという娘と結婚して、二人の子供が産まれます。一人がヘンリーでもう一人がジュディスです。ヘンリーは男で、ジュディスは女です。ヘンリーは長じて、運命の偶然か、大学でチャールズ・ボンと仲良くなります。
ヘンリーは、妹のジュディスに近親相姦的な愛情を抱いています。また、親友のチャールズ・ボンに対しても親友として強い情愛を抱いています。ヘンリーはその感情を間接的に成就させる為に、チャールズ・ボンとジュディスを結婚させようとします。
ですが、二人が結婚すると、チャールズとジュディスは腹違いの兄妹なので、近親相姦となってしまいます。サトペンは近親相姦を防ぐ為、また、黒人の血を持った子孫を回避する為に、チャールズに黒人の血が混じっている事実をヘンリーに伝えます。ヘンリーは、チャールズに黒人の血が混じっている事、ジュディスの腹違いの兄である事に耐えられず、チャールズを殺してしまいます。
このエピソードは作品の中でも、特に重要な出来事として取り上げられています。このあらすじを見てもわかるように、ヘンリー、チャールズ、ジュディスという人物は全て、トマス・サトペンという人物が産んだ子供であり、また精神的にトマス・サトペンに支配されている人物です。チャールズ・ボンはサトペンを憎んでいますが、憎しみという形もまた、対象との一種の関係のあり方です。全ての発端はトマス・サトペンにあり、チャールズ、ヘンリー、ジュディスの三角関係はあくまでもトマス・サトペンの破滅を客体化する為に表された関係だと言えます。
ですので、あくまでもこの作品ではトマス・サトペンというキャラクターが大切です。ヘンリーはトマス・サトペンの傀儡であり、チャールズ・ボンはトマス・サトペンに対する憎しみによって行動しており、トマス・サトペンに固執しています。ジュディスは無気力で、ほとんど印象がないのですが、彼女はヘンリーの言いなりで、自分以外の強い他者に隷属するタイプの女性なのでしょう。これらの関係の中心にはトマス・サトペンがいます。
だからトマス・サトペンという主人物が読者に伝わるかどうかがこの作品の成否を決めると言ってもいいのですが、語りが間接的すぎて、複雑すぎて、わかりにくくなっています。私はこの語りは欠点だと捉えています。おそらく、フォークナー研究者や愛読者は『それこそがフォークナーの良いところだ』と言うと思いますが、私はそう感じませんでした。
描こうとしている事そのものはオーソドックスな文学作品なので、語りの構造を、例えば三人称にするとか、あるいは事件を知っている一人の人物が聞き手に事件の全貌を語る、というようにすればもっとわかりやすくなったと思います。また、わかりやすくなるだけでなく、トマス・サトペンの人物像を直接的に表す事になり、作品が伝えようとしているイメージはより鮮明になったと思います。これが、私が感じた欠点の第一です。
欠点二 比喩
欠点の第二は、比喩が大袈裟すぎる事です。トマス・サトペンの事は作中でしばしば「悪魔」と呼ばれるのですが、読んでいて、悪魔というほどの悪漢に私は感じませんでした。
また、その他にも聖書の言葉などを用いて、「悪魔」に類するような大袈裟な形容がよく使われるのですが、どう読んでもそこまでの巨大な話、巨大なキャラクターには私には見えませんでした。
これは、第一の欠点とも関連した事柄で、語りが間接的過ぎて、キャラクター像がはっきりしないままに、大きな比喩が使われるので、比喩だけが大きく突出して、キャラクターを置き去りにしているように見えました。
例えば、ドストエフスキー「悪霊」という作品の悪漢スタヴローギンというキャラクターは実によく描けています。スタヴローギンは、悪魔という形容が適切だと言ってもいいほどですが、別にそういう比喩を使わなくても、スタヴローギンの怪物性は十分伝わってきます。
スタヴローギンとトマス・サトペンを比べると、トマス・サトペンはより卑小なキャラクターです。田舎の、野心に取り憑かれた人物という感じで、都市で自己意識の豊富さに呻吟するスタヴローギンとはだいぶ違います。どちらがより「悪魔的」かと言われると、私は迷う事なくスタヴローギンを取ります。スタヴローギンは巨大な悪ですが、同時に善悪を越えようとする存在でもあります。
スタヴローギンの怪物性は、彼にまつわる様々なエピソードで十分に描けています。それと比べた時、トマス・サトペンの悪行は悪魔というには卑小なエピソードの集積に留まっています。このあたりも、キャラクターの実像とフォークナーとの語りの乖離があって、それが作品の欠点となっています。この大袈裟すぎる比喩が私の思う第二の欠点です。
悲劇の発端
欠点についてはこれで片付いたので、ここからは作品の本質について私なりに考えていこうと思います。
その前に、トマス・サトペンにまつわるもう一つのエピソードについて説明しておいた方がいいでしょう。それはサトペン自身が死ぬエピソードです。サトペンの破滅を表すのは、このエピソードと、上記のヘンリーのチャールズ殺害事件の二つ、この二つが特に大きいと思います。
サトペンが初老の年齢に差し掛かった頃の話です。上記の殺人事件の為に、息子の一人は殺され、もう一人は殺人犯になってしまいました。サトペンは、巨大な邸宅を持ち、自分の王国を作るのが夢でした。この夢が生まれたのはある事柄が原因ですが、それは後で説明します。この王国は、サトペンの息子が継がなければならない。サトペンはそう考えていました。ですが、今言ったように息子二人はもう跡取りとして期待できません。
そこでサトペンは自らの土地に住んでいたウォッシュ・ジョーンズの孫娘に目を付けます。娘はまだ15才ですが、彼女を誘惑したのか、言いくるめたのか、そのあたりはよくわかりませんが、彼女と関係を持ち、無理矢理に子供を生ませます。しかし生まれたのは娘だったので、サトペンは娘に侮辱的な言葉を浴びせかけます。
孫娘と関係し、子供を生ませ、更には侮辱したサトペンに、祖父のウォッシュ・ジョーンズは怒り狂い、サトペンを殺害します。ジョーンズはその後に孫娘も殺してしまいます。二人を殺したジョーンズは、民警団に殺されます。これで、サトペンの夢は破れます。これがサトペンの破滅の重要なエピソードの第二です。
このエピソードで強調しておきたいのは、サトペンを殺したウォッシュ・ジョーンズという人物も元々は、サトペンの言いなりだったという事です。ジョーンズがそういう独白をする場面があります。「わしはあんたの命令に背いた事がなかった」とかなんとか、そんな感じです。
これらのエピソードを概観してわかるのは、サトペンの破滅は全て、サトペンに精神的に支配されていた人間が引き起こしたという事です。ヘンリーやチャールズ・ボン、ウォッシュ・ジョーンズ、ジュディス、ジョーンズの孫娘。これらのキャラクターの背後にあるのはサトペンその人であり、またそのようなサトペンを突き動かしていたのはサトペンの王国設立の夢です。この複雑な作品の中心に台風の目のように位置するのはトマス・サトペンであり、またサトペンの野心です。それらが渦を巻いて全体を構成しており、それはやがてサトペン自身を破滅に導きます。
こうした事態は人間にとって普遍的な事とも言えます。わかりやすく言えば、人間が人工知能を生み出し、その人工知能によって人間が滅ぼされるというような事です。私が思い起こすのは西郷隆盛で、西郷隆盛は自らの精神的な末子と言っていい、弟子達に引きずられるように破滅していきました。自分の思想を完全にコピーした他の人間がいたとしても、それが「他者」である事によって、本人には思い寄らないドラマが引き起こされます。こうした事は過去、人間に普通に起こってきた事だと思います。
さて、それではその台風の中心になっているトマス・サトペンとはどういう人物だったのでしょうか。いや、トマス・サトペンというより、トマス・サトペンという個人を動かしていた彼の野心、夢というのはそもそもどういうものだったのでしょうか。ここに私はこの作品を読み解く鍵があるように思います。
サトペンが野心を持つようになったエピソードは作品の後半部に描かれています。サトペンがまだ子供の頃、用事を言いつけられて、ある金持ちの家に行きます。すると、用事を話す前に黒人の召使いが現れて、侮蔑的な言葉を投げつけられます。サトペンはショックを受けてすごすごと引き返し、その事について、繰り返し反芻して考えます。彼は、のっけから自分を汚いものでもあるかのように取り扱った召使いの態度にショックを受けたのです。サトペンの生涯に火をつけたエピソードとは、たったこれだけのものです。
このエピソードには何があるのでしょうか。私は、それは、この時にこの少年がこの世界の真実を知った、という事だと思います。真実というのは、現実というのは理想的な、滑らかなものではなく、不合理で、でこぼことしていて、そして何よりも「力」が支配しているという事です。
サトペンは、このエピソードに出会う前は「無垢」だったと作者は繰り返し注意しています。サトペンは用事を話す前から、黒人の召使いに見下され、人間扱いされませんでした。これは今にも通じる問題と言っていいでしょう。例えば、我々の社会においても「社員には挨拶するけど、バイトには挨拶しない」とった人はたしかに存在します。彼にとっては対象の「人間」は問題ではなく、人間が作り出した権威が問題なのです。こうした人は人類が文明化して以来ずっといたでしょうし、これからも居続けるでしょう。
無垢な少年のサトペンは、黒人の召使いに出会うまでは、少なくとも自分は一人の人間であり、たとえどのような地位であろうと、立場であろうと、一人の人間として扱われると無意識的に期待していました。もちろん、彼には「どのような地位であろうと」というような社会的観念があったわけではないですが、少なくとも、彼は一人の人間として、他の人間と普通に関われると期待していたのです。
それが、そういう甘い観念が通用しない世界があると彼は知ったのです。黒人の召使いにそのような態度を取らせたのはその主人の地位であり、更にその主人の存在を許しているこの世界そのものーーそれが一つの巨大な現実としてサトペンの眼に降り掛かってきたのでしょう。
ここからサトペンの野心が始まりました。彼の黒人嫌悪もそこに端を発しているのでしょう。彼は、いわば怪物に打ち勝とうとして自身が怪物になってしまった人間に例えられます。彼は、彼を押し潰した現実に打ち勝とうとして、自らもその現実になってしまい、そうしてその自重によって自身も滅びてしまいました。彼は、彼を軽蔑した金持ちよりももっと大きな自分だけの世界を作ろうとし、その世界を維持する為に強引に子供を作り、その強引さ故に殺される事になりました。
だから、サトペンの野心の発端は、アメリカの南部に限定されるものではないと私は思います。そうではなく、現代の我々にも通底するテーマではないかと思います。それはこの世界が、現実には力で支配されており、力がものを言う世界だという事です。そしてその事に徹底的に気づく瞬間というのがある種の個人にはあるのだと思います。例えば、学者の丸山真男は、左翼学生と見られて警察の取り調べを受けた時、随分ひどい扱いを受けたそうですが(殴られたりしたのでしょう)、取り調べを受けて外に出た時、警察の建物の裏でバナナの叩き売りをしているのに衝撃を受けたそうです。
さっきまでは理不尽な血と暴力が支配していたにも関わらず、そこから一歩外に出ると、平和で日常的な「バナナの叩き売り」が展開されている。この光景のコントラストに丸山は衝撃を受けたそうです。丸山真男はその時、彼なりに世界の相貌を発見したのでしょう。彼は、この世界がそんな風に異なった風景を平気で同居させるような、矛盾に満ちたものだと知ったのでしょう。
こうした精神的な衝撃が、丸山を単なる東大の優等生学者という立場から抜け出させ、一個の思想家に作り上げていったと私は思います。そうした経験を通じて人は何かに気づくのだと思います。
オーソドックスな文学作品
トマス・サトペンの物語はそのようなものです。彼の精神的動機は、黒人の召使いに軽蔑的に扱われたという少年時のたった一つのエピソードでした。そんなエピソードは何でもないと人は言うかもしれませんが、人は、大抵他人にはくだらないと思われるような事柄に固執して生きるものです。また文学はそういうものを描くのだと思います。
そうして発生したサトペンの野心は、彼自身を引きずって運動していきます。「人が理想を掴むのではない。理想が人を掴むのだ」という言葉がありますが、野心とか夢とかいったものも、それが成長していくと、それ自体がその本人を操り、動かしていくものとなります。私は、ナポレオンのような人は、彼自身が彼の夢の一兵卒だったと考えています。ナポレオンが理想を掴んだのではなく、理想がナポレオンを掴んだのです。
ナポレオンは自らの理想の為の第一の奴隷となって働きました。彼は他人から見れば恐ろしいエゴイストに見えたでしょうが、本人からすると無私の人だったのでしょう。ナポレオンの野心は、ナポレオンその人を道具として酷使し、最後にナポレオンを殺すところまで行きました。ナポレオンが悲劇的な人生を生きたように見えるのは、彼が恣意ではないものに自らを委ねた為なのではないでしょうか。
サトペンはナポレオンほどに巨大な人間ではないですが、自らの野心に取り憑かれたという意味ではよく似ています。もちろん、彼らの野心は結局は彼らが生み出したものなので、同情できるとはいえ「自己責任」なのは間違いないですが、もう少し考えると、これらの悲劇的な人生はそもそも「自己とは何か」という問いを孕んでいると思います。
私はこの文章の最初で、「「アブサロム、アブサロム!」は文学としてオーソドックス」だという事を言いました。この作品がオーソドックスだと言ったのは、こうした人間の悲劇を的確に描いているからです。人間が自らの夢に捉えられ、それ故に破滅するという普遍的な悲劇を取り扱っているからです。
「オイディプス王」のような作品においては、人間の運命を規定するのは神の託宣ですが、近代においては人間の意志=欲望が人間を決定していきます。人間という相対的な存在に対して、人間が勝てっこない神とか、自然、歴史とかいったものが人間の運命を規定する。それが古代の悲劇の主調音でしたが、近代においては人間の力がより自覚されてきた為に、人間が自らの力の強さ故に滅ぶという事がテーマになっています。
そのテーマを偉大に展開したのがシェイクスピアだと私は思います。ただ、シェイクスピアにおいては人間の意志は、客体的なものとまだ融合して存在しています。「マクベス」において、マクベスは魔女の言葉に従って成功しますが、魔女の言葉に従って破滅します。魔女は、マクベス自身の秘められた欲望を語るものであり、同時にマクベス自身の運命を決定する客体的な存在です。シェイクスピアにおいては、人間の意志は完全に自立したものとして現れてはいません。
シェイクスピアを越えた作家と言ってもいいドストエフスキーは、人間の意志の問題を更に強く展開しました。「罪と罰」のラスコーリニコフは、自らの肥大した野心に自らが耐えられず、最後には罪を自覚し、自首します。ここでは、人間が自らの意志を絶対視する危険性そのものが物語として展開されています。
その他にも色々言えるでしょうが、そうした人間の悲劇を取り扱っているのが「文学」だと私は考えています。そういう意味において、「アブサロム、アブサロム!」はオーソドックスな文学作品であると思います。この作品はアメリカ南部の盛衰をトマス・サトペンという一人の人物に託して描いたものでしょうが、同時に、そうした個別的な物語を普遍的な人間の作品に仕上げる事が、作者フォークナーによって目指されています。
だからこそ、私が大仰な比喩と呼んだ、抽象的な比喩を作品内にふんだんに散りばめたのでしょう。現実的、個別的な事柄を、その奥底にあるものを描く事によって、違う民族、違う時代の人々にも通じる普遍的なものに昇華しようという欲求もまた文学の基本と言えます。そういう意味でも「アブサロム、アブサロム!」はオーソドックスな文学作品であると感じました。
「アブサロム、アブサロム!」がオーソドックスな文学作品だと感じた、というのは大体そういう意味です。この作品の中心に位置するのはあくまでもトマス・サトペンであり、その野心が紡ぎ出すドラマですが、彼よりも精神の弱い人は、彼の傀儡となりながらも、彼に歯向かっていきます。この世界の複雑性は強いものが弱いものを支配するという一方向に運動するだけではなく、弱いものが弱さ故に強いものを支配する事もあります。西郷隆盛と弟子の関係もそんな風だと思います。
私にとっては「アブサロム、アブサロム!」はそういう作品でした。語りの複雑性と間接性によって多少薄れているものも、その奥にあるのはオーソドックスかつ本格的な文学作品としての相貌であると感じたので、私にとっては良い読書体験でした。この作品を通じて私はより、文学とは何を描くのか、その事に対するヒントが与えられたように思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
