
中医学の考え方と現代医学の根本的な違い
薬膳の基になるのは中国伝統医学で一般的には中医学と言われるものです。
医学が発展する前は、人間が病気になり苦しむ姿は、何か魔物が取り付いたと考えられて、世界のいたるところで呪術などで解決しようとしていました。
現代医学が発達する前は、この呪術での解決から、その土地で採れる植物などを使ったその土地ならではの文化に根差した「伝統医学」が発達したようです。
中国の中医学、インドのアーユルヴェーダ、エジプトなどイスラム圏のユナニ医学が三大伝統医学と言われるもので、ここにチベット医学を入れて四大伝統医学と呼ばれます。
それ以外にも、インドネシアのバリ島ではジャムウという伝統医療がありますし、タヒチやハワイなどにも伝統医療が残っています。
日本には一番近い中国の中医学が7世紀頃から伝わり、鑑真などの僧侶も遣隋使や遣唐使などもそれを伝える一端を担っていました。
その後、江戸時代の鎖国で、中医学が日本独自のものになり発展しました。
これは、中医学と区別するために漢方とか、和漢方、日本漢方と呼ばれます。
若干違いはありますが、中医学と漢方の大元は同じなのです。
広い意味で「東洋医学」と言うと、アーユルヴェーダやユナニ医学などアジア全体の伝統医学を指しますが、一般的に東洋医学と言うと中医学や漢方をイメージするのではないでしょうか。
現代医学の事を西洋医学と呼ぶこともありますが、ここでは、私達が医療機関に行った際に治療を受けたり服薬する医学を現代医学とし、中医学との考え方の違いを書いて行きます。
一人一人の体を違うものと考える
中医学では、一人一人の体は違うものだと考えます。
同じ頭痛を訴える人が3人居たとしても、それぞれの頭痛はそれぞれ違うと考えるのです。
ある人は、要らない水分を多く溜めていることで頭痛を招いたかもしれないし、別の人は、寝不足や食事の偏りから栄養となる「血(けつ)」の不足で頭痛が起こったかもしれません。
また、別の人は、ストレスから「気」の巡りが悪くなり頭痛になったかも。
同じ頭痛でも、人によってその時の体の中の状態は違い、同じ頭痛でも出される漢方薬が変わります。
一つの症状でも、一人一人に合わせた治療法、漢方薬が処方されるのです。
また、逆に別の症状でも原因が同じなら、症状が違うのに同じ方針で治療を進めることがあります。
例えば、Aさんが便秘、Bさんが頭痛、Cさんが肌荒れを訴えていたとしてもその原因が三人とも貧血(血虚)だったら、血虚を治す治療が行われるということです。
一人一人の体の状態を見て、中医学の系統立てにより分類していくことを弁証と言います。
これがあって初めてその人に合わせた漢方薬や鍼灸、食事(薬膳)が意味をなすのです。
不調はバランスの崩れだと考える
普通、私達は、何か不調が出た時、下痢には下痢止め、頭痛には頭痛薬のようにその症状を取る方法をしているかと思います。
中医学では基本二段構えで考えます。
痛みや痒みなどの今辛いことの解決、その上でその原因となることを突き止めて繰り返さない、もっと酷くならないための行動を起こします。
これも弁証が重要で、よく東洋医学は根本治療や体質改善が得意と言われるのはこの特徴からです。
表面にある直接的な症状だけを取り去るのではなく、原因も解決するということです。
弁証をする上で、大切なのは体の中のバランスの状態を見て行くことです。
バランスですから何かが軸になり、そこを中心にズレがあれば「バランスが崩れている」となります。
軸になるのは大きく言えば、陰陽、体の構成要素「気血津液」、「五臓」、体の抵抗力とウイルスや細菌などの邪と言われているものとの強弱などです。
この考え方が中医学独特なので、中医基礎理論で陰陽論や五行学説などを学ぶのです。ここだけがクローズアップされ、一人歩きしてしまっているような節もありますが。
これに基づいた考え方をする医学と言うだけでなく、最初の一人一人に合わせて進めるということは大きな特徴です。
弁証により、乱れたバランスが分かったら、足りていないものは補い、多すぎるものは排泄する方法で元のバランスに戻して行きます。
また、体の構成要素「気血津液」は体の中を巡っているものだとされているので、巡らない理由を探して巡るようにさせることで元の状態に戻すこともします。
一人一人の乱れたバランスに合わせて、元の状態に戻すために足したり引いたりするのが中医学の考え方の特徴です。
人も自然の一部と考える
中医学では、人も自然の一部と考えます。
自然の影響が体に及び、体調が変化しますし、影響が強すぎると不調となって現れます。
そのため、季節や天候を意識して、体との関係性を知っていると起こりやすい不調を事前に予防することもできるようになります。
これは、私の考えですが、良い薬が簡単に手に入らなかった時代に、中国の古代の人々が少しでも病気にならないよう身につけて行った知恵が発端ではないかと考えます。
季節と人の健康の関係は、その場所にその季節にもともと育つ植物や、その季節にその土地で獲れる魚や動物が、その土地の人の健康を守る働きがあること。
これも人が自然の一部であると考えられる根拠ではないでしょうか。
野生の動物や昆虫はもともと住む地域も決まっていて、暑い土地の昆虫や動物は一定の温度以下のところでは見ることがありません。
寒い場所には暑い土地に住む生き物に必要な食べ物が育ちません。
西日本でしか見ることのないクマゼミがここ数年、北上し東日本で見られるそうです。
これは温暖化の影響とも言われています。
クマゼミのエサとなるものが東日本でも育つようになったり、繁殖の環境が適するようになったのかもしれません。
人も、基本的には育った土地で摂れるものや昔から食べられている食材がその土地の人に合っていると考えるのが中医学を基にする薬膳の考え方です。
中医学は直ぐに根本原因がわからないことがある
中医学では、レントゲンや血液検査などの数値や画像を見て判断をしません。
観察の医学と言われる所以は、その人の身体の外に出ていることを気血津液の過不足や五臓の状態と照らし合わせることで弁証して行きます。
そのため、検査で数値やその臓器の実際の画像で見て悪い箇所がはっきりわかる現代医学の方が早く治療に入れることがあります。
病気とは言わないまでも何らかの気になる不調があった場合は、一度医療機関の検査を受け、異常が無いのに不調が続く時は中医学で解決できるかもしれません。
中医学では、検査結果には現れていない未病の状態を、その人の身体に出ていることから総合的に判断し(弁証)早めに、バランスの崩れを元に戻すための行動を漢方薬、鍼灸、薬膳でできるからです。
どこが悪いと画像や数値で明らかになったら、その部分を治療する現代医学が得意ですし、検査結果に出ない不調は中医学が得意と言われるのは、この違いです。
まとめ
これまで述べて来たように、中医学は一人一人の体は違うと考えるので、その人に合わせた治療をします。
治療の考え方の基本は、バランスの崩れを元に戻すということで、その方法は足りないものは補い、多すぎるものは出す。巡っていないものは巡らせることになります。
また、人は自然の一部と考えるため体調は天気や気候の影響を受けると考えます。これが分かっているので、雨の前の日には湿度で弱る不調の予防などが可能になるのです。
ただ、中医学にも不得意分野があり、それはなぜその不調(病気)が発生するのかがすぐにわからない時があること。
そこは、数値や画像で直接見て判断する現代医学が得意な分野です。
ですが、現代医学ではストレスのせいと言われて自分では解決できない不調があります。
中医学では病気になる前の未病を病気に進ませないために、また手術や治療で一旦治っても繰り返す人の体質改善。
手術をした方が明らかに早い、特効薬がある病気には現代医学。
よく言われているように得意な分野があるので、両者が上手く取り入れられると人の健康維持には有効ではないかと考えます。
どんな時にはどちらを選ぶと良いか、普段から何をしておくと健康でいられるかなど、一人一人が自分の健康にもっと関心を持てるように、中医学の特徴と現代医学の違いをご紹介しました。
薬膳は漢方薬の考えと同じ方針で、普段の食事で病気になりにくい体づくりに使えます。
また、漢方薬の効き目を良くさせるためには、普段からの食事(薬膳)や睡眠などの養生が大切ですし、方針を合わせた漢方薬、薬膳、鍼灸を同時に行うことで回復が早いと言われています。
【関連記事】
無料診断をリニューアルしました。
簡単な7つの質問に答えるだけで、あなたのキャラタイプから起こりやすい不調アドバイスをします。
▼下のバナーをタップして7つの質問にお答えください▼

食べたいものをストイックに我慢するのではなく「なかったことにする薬膳」のメソッドでプラマイゼロにする方法を無料で学べる7日間のメール講座です。お申込みはこちら▼
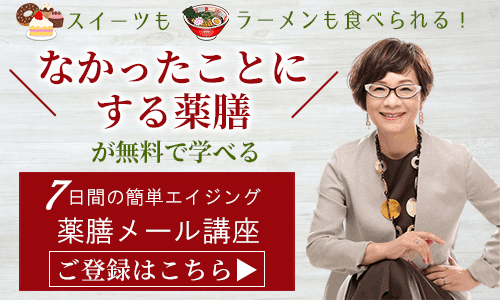
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
