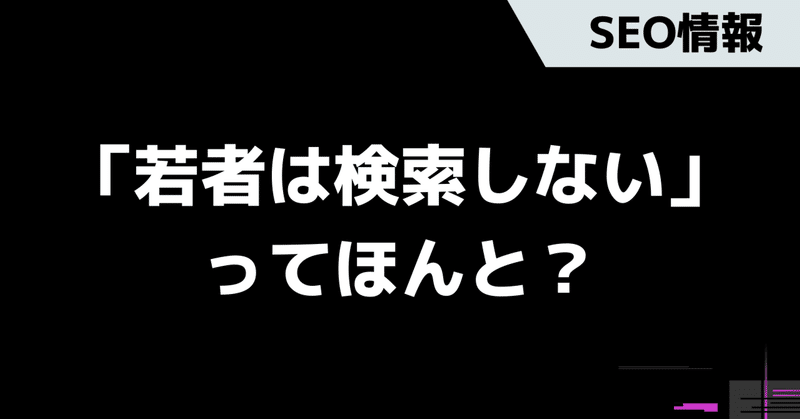
「若者は検索しない」は本当?現役Z世代のマーケターが経験とデータの両面で徹底解説!
こんにちは!
今回はZ世代の検索についてです。
SNSが発達した現代では、Z世代を中心とする若者は「レコメンド」から多くの情報を取り入れています。そのため最近は、「若者は検索をしない」と言われることが増えています。
しかし、現実は逆なのです。
僕はよくブラウザ検索(Google、Yahooなどでの検索)をしますし、僕の友達、妹もブラウザ検索をしています。また、実は「ブラウザ検索が増えている」という事実は僕の肌感だけでなく、データも示しています。
"レコメンドが発達し、情報を掴みにいかなくても手に入る時代に、
なぜ検索回数が増えているのか。"
これは、「若者の消費行動の変化」が関係しているのです。

そこで今回は、
「若者の検索回数は増えている」
ことを数値を用いてしっかりと示し、僕の肌感と共に現代の若者の消費行動を説明していきます。
この記事を読めば、若者の消費行動を正しく理解でき、若者向けマーケティング活動を改善することができるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
若者の検索回数は5年前より増えている
先述した通り、「若者の検索数」は増加しています。月間で何回検索を行うのかを年代別にまとめたグラフがあります。

2016年の時点では、20代はブラウザ検索を月に25~30回ほどしていました。しかし、たった4年しか経過していない2020年には、最多40回を記録しているのです。つまり、
「若者の検索離れ」は"嘘"だったのです。
読者の皆さんのなかに、この嘘を信じていた方も多いのではないでしょうか。
では、なぜ検索回数が増えたのか。結論の前に、もう一つのデータをお見せします。
若者の検索は、Google+α
現代の若者は、検索媒体を
「用途によって使い分けたり、複数使用したり」する傾向があります。
以下のグラフは、20代の若者100人にアンケートを行った検索に使う媒体を表したものです。

このグラフから分かるように、
"若者が使用する検索媒体は分散しています。"
では、どのように使い分けをしているのでしょうか。その答えが以下のグラフです。

20代の2人に1名はブラウザ検索と同時にTwitter/Instagramも使用しているということがわかります。また、4人に1名はブラウザ検索と同時にLINEやYouTubeを使用しています。
つまり、若者は、
ブラウザ検索+α
で情報を収集する時代なのです。

では、なぜこんなにも検索媒体をまたぐのでしょうか。これは、SNS/ブラウザ検索ごとに「役割」があるためです。
SNS検索で媒体を使い分ける基準
使用する検索媒体は「ブラウザ検索+α」のパターンが非常に多いことが先述のグラフでわかりました。ここからは、「+α」の検索媒体(SNS)がどのような基準で選定されるのかについて説明していきます。
Twitterは豊富な情報を素早く大量に得られることが持ち味の媒体です。「新作コスメ」や「裏技」などを検索し、短い時間で大量に情報収集することに優れています。

このように短時間で大量に情報収集することで、「詳しく知りたい事柄/情報」をピックアップするために使われるのです。

また、電車の遅延などの「リアルタイム性」のある情報を検索する際にも使用されます。
Instagramでは、「可愛い」「おしゃれ」などの「直感的な検索」が多く行われています。

また、飲食店を探すために「#〇〇グルメ」などで検索する人も多いです。

Instagramでは興味関心に従ってジャンルを検索し、その中から
「これから(未来)」体験するモノ・コトを知る
役割があるのです。
新検索時代の消費者検索行動はGoogle検索+α
結論、新時代の検索行動は以下の通りです。

このように、
SNSで見つけたサービス・商品の"真偽"を確認するために
Google(ブラウザ)検索を行うのです。
最後に、新しく登場した「TwitterやInstagramでの日々の情報収集」を更に深ぼって若者の検索行動の理解を終わりましょう。
新検索時代は既に情報を得てから検索している!?
ここまで、若者の検索行動(ブラウザ検索+α)を説明してきました。しかしこれだけでは若者の検索行動を理解し切ったとは言えません。
今の若者の検索は、「検索前から始まっている」のです。
スクショで情報を取っておく
現代の若者は、
"情報は普段から集めておくもの"
という認識があります。この行動はSNSでの情報収集で現れます。
若者は、毎日SNSを見ています。Twitter・InstagramをはじめとするSNSのレコメンドによって、大量の情報収集を毎日自然と行っているのです。
その中で気になった情報は「スクショ(スクリーンショット)」で保存しておきます。

このスクショが溜まっていき、「どれを購入しよう」と考え始める時に、スクショをチェックするのです。

スクショで情報を取っておき、スクショを確認してから検索を始めることで、
"前提知識を持った状態で検索する"
人が増えているのです。
まとめ-今の新検索時代の戦い方
まとめると、現代の検索行動は以下のようになっています。

Googke(ブラウザ)検索は現代の若者に訴求する上でも「対策すべき」媒体なのです。SNS+SEO(ブログ)の2軸対策をすることで、若者が求める検索行動へ対応することが出来るでしょう。
SNS×SEOの2軸対策方法
SNSとSEOの2軸対策を行う際、「SEOをどれだけ楽に整備できるか」が重要になってきます。
これは、先述の検索行動からよく理解できます。(以下再掲)

つまり、ブラウザ検索の目的はただ一つ。
「サービス/商品が信頼できるか確かめる」
たったこれだけです。
そのため、SEOでは「信頼できるサイト」を作ることさえできれば十分なのです。
SNSは定期的に投稿を続けなければ効果は大幅に落ちてしまいます。しかしSEOは一度整備したら1ヶ月に1度ほどのメンテナンスで大きな効果を発揮できます。

SNS×SEOを最低限の労力で効果最大化するには、
"サイト(SEO)を一度ガッツリ整備してあとは定期メンテナンス"
これが最適解です。
ぜひサイト(SEO)の整備方法やSNSとの掛け合わせについては弊社yadosにお問合せください。
SNS総フォロワー数50万人
ブログメディア経由売上四半期1億(前年比4倍)
の実績を持つyadosがSNS×SEOの効果最大化を実現します。ぜひ一度お問合せください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
