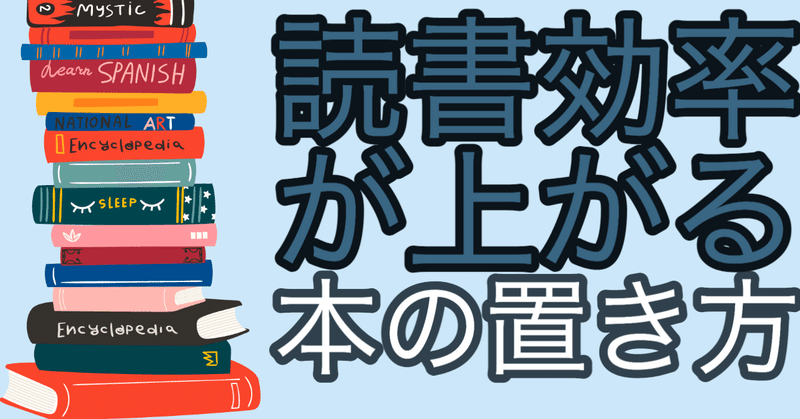
本の置き方をとある型式に変えたら読書効率が上がった件
2020年に入ってから、Kindleで本を読むよりも紙で本を読むのを好むようになったんですよね。ただ紙で読むとなると置き場に困るようになりまして、どうにか置き方で読書の質を上げられないか考えていたんですよ。
そこでひらめいた本棚の使い方が押し出し型式でした。試してみたところしっくり来るので、紹介します。
紙と電子のメリットデメリット
まず簡単に紙の本のメリットを説明しておくと、すぐに手に取って読めるのは電子書籍にないアドバンテージですね。数秒でペラペラめくって読めるのは、読書のしやすさを加速させているはずです。
そしてもう1つ大事なのが、本が可視化されること。電子書籍は、kindleやウェブブラウザを開かなければその本に出会えないのと、ウェブ上のものなので形としては存在しないんですよね。なので本を買っても買ったことを忘れてしまったりとか、積ん読されているかも覚えていない状態が続くんですよ。
もちろん電子書籍もメリットあって、どこでも読めますし場所も取らないので便利なわけなんですけど、読むきっかけは起こりづらいんですよね。それに比べると紙の本は置き場所には困っていくんですけど、読み続けるモチベーションやきっかけは作りやすいわけなのです。
押し出し本棚を作ってみた
紙の本のメリットとデメリットを上手にカバーする本の置き方ってないのかなと考えていて、それが見つかれば紙の本をさらに使いやすくできるんじゃないですか。それでいろいろ試したところしっくりきたのが、押し出し本棚という形です。
やり方はカンタンで、まずは読んだか読んでいないのか、そしてこれから何回も読み続けたいのか、という軸で本を分けます。
1.未読
2.もう読まないかも
3.何回も読みたい
4.今月集中して読む
5.愛読
僕の軸はこんな感じですね。この5つの部類に分けて本を本棚に置いていきます。

やり方としては目に見えやすい場所にこんな感じで、左側にまだ読んでいない本を置き、右側には何回も読みたい本を置くきます。そしてもう読まなくていいかなと思う本は、目に入りづらい別の本棚に移動します。

今月集中したい本に関しては、画像のように1つだけ浮かんで見えるように置いておきます。この本はnoteで連載をやる本やこの本の内容を集中して身に付けたいと決めた本。愛読書は、また別の見やすい場所に置いておきます。

そしてぼくが押し出し形式の本棚と呼んでいるのは、このように左側の未読本は左から新しい本を置いていく形にし、読んだら1番左にまた戻し法式のことです。
右側の本も同じように、右端に新しい本を置いていき、読んだら右端にまた戻します。
このやり方が良いのは、未読本であれば手を付けていない積読本がどれなのか一目瞭然になりますし、よく読みたい本も、実際にどれを読んでいるかは右側を見ればわかるでしょう。
このように自分なりに分類した後、時系列順に本を置いていくと、自分の読書行動が一発でわかります。「買ったのに読んだっけ?」が減りますし、「熟読しようと思ってたけどしてないな」もわかります。
ぜひ試してみていただければと!
ちなみにこのやり方は、超整理法の押し出しファイリングを参考にしていますので、詳細記事もぜひ!
読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。
