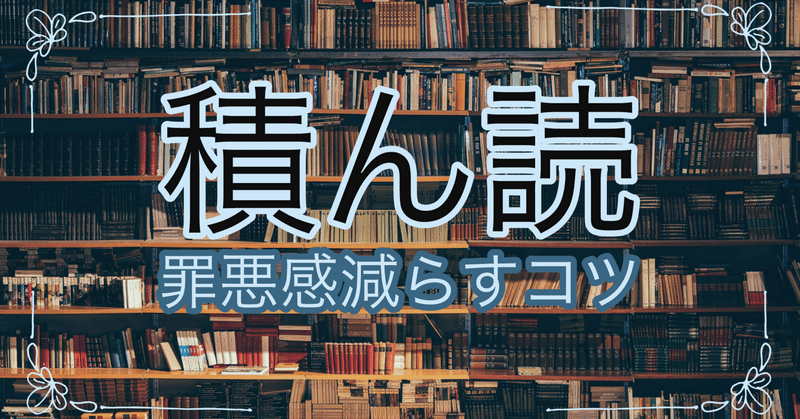
積読を罪悪感なく楽しむためのアドバイス
最近、電子書籍の読書を止めて紙の本にチェンジしました。理由はいくつかあるんですけど、大きな要因は「積読」がしやすいからです。
積読って、本を積んでおくだけじゃないと思うんですよ。本を積んでおけばその本の存在を認知できて、「そういえばこの本って」と1回思考が通るんです。
積読を見るたびに想起できる
「そういえばこの本って?」と考えるきっかけを作れる。これが積読のパワー。そこに本があるだけでぼくたちの好奇心を刺激してくれている。つまり積読とは、「そういえばこれって」と想起しまくれる「そういえば読書」なのです。
なので本を買ったまま読まなくてもOK。積み立てられた本は、内容を想起させてくれる役割を担っています。これに気づいてからぼくは、部屋のあちこちに紙の本を置いています。
読まなくてもいいんです。タイトルや表紙を見るだけでも、いつもと違うアイデアが浮かび上がる。しかも積まれている本たちは、いつでもそこにいてくれるのです。とても役に立つ、優秀なアイデア箱と言えるでしょう。
本のタイトルを見る効果
本屋や図書館に行くのが楽しいのは、「そういえば読書」を楽しめるからではないでしょうか。たくさんのタイトルからいろんなワードで想起できるので、いつもと違った角度から考えが深まります。
電子書籍では、そういえば読書ができません。目に見える場所にないですしアプリを開かなければ本を読めませんよね。だから一度読んだだけで内容も忘れがちになる。つまりアイデアを生み出す効果もなければ、リマインダーとしても使いづらいんですよ。
もちろん電子書籍にも利点があるので、漫画や雑誌は電子で読むほうが楽だったりしますね。
単純に接触回数を増やせる
例えば、「この本について今月考えるぞ!」と決めたら、家の玄関に置けばイヤでも目に入りますよね。つまり最低でも1日に2回以上は思い出すわけです。それを1ヶ月行えば、60回以上はその本について考えられます。いいですねぇ。
読んだ本は1ヶ月目に見える場所に置く!とかルールをつくれば、その本の内容を忘れづらくなります。もっと言えば、「玄関の本を見たら1分思い出す」ってルールを作るのも良いですよね。
紙の本であれば、「読んでそのまま」をかぎりなく減らす工夫がしやすいのです。記憶の定着率も上がるのではないでしょうか。
まとめ
去年まで紙の本を一切読まなかったんですけど、置いておくだけで価値があると知ってから、すべて紙の本にシフトしました。置いておけば手に取りやすいですし、その本への愛着もわきます。
個人的には、その本に書かれているtodoをやりたい気持ちが強くなりますし内容を理解しやすくなると思っています。
読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。
