
宇宙島へ7「アルツターノフの『電車に乗って宇宙へ』」
どうやら地上から塔をたてるというのは不可能に近いということがわかりました。それでは、ほかに方法はないのでしょうか。
実は、画期的なアイディアを思いついて人間がいるのです。
「宇宙開発の父」ツィオルコフスキーがより現実的なロケット開発に注力したこともあり、またロシア語での発表であったために、この「宇宙塔」構想は世界に広がって深められることなく、数十年のときが流れることになりました。
転機が訪れたのは、ツィオルコフスキーの著作集が出版された1959年でした。ツィオルコフスキーと同じロシアの研究者(といっても、当時はレニングラード工科大学の学生でした)ユーリー・アルツターノフが、ツィオルコフスキーの構想を再検討したのでした。そこで彼は、ツィオルコフスキーも思いつかなかった、逆転の発想にいたります。
ツィオルコフスキーも記しているように、赤道上空36000kmでは、地球の引力と遠心力がつりあっているので、静止していることができます。つまり地上から見れば、天空の一点にとどまって動かないということです。この高度を「静止衛星軌道(GEO)」といい、現在地球の周りを回る静止衛星はすべてこの軌道上を回っています。
そこで、アルツターノフは、地上から塔を建築するのではなく、静止衛星軌道上から地上に向かって索道(ロープウェイ)を建築することができるはずだと考えたのです。
そして、そこからアルツターノフは具体的な「宇宙索道」の姿を次々にまとめていきます。
・重心を静止衛星軌道に固定するためには、反対側にも同じような構造物を伸ばす必要があるが、同様の構造では外側の方が長くなるため、先端に重い構造物である宇宙ステーションを設けて遠心力を増して、全体の長さを60000kmに抑える。
・強度を保つために重心部分が太く、両端にいくほど細くなる形にする必要があること。
・高度5000kmの地点、最先端に太陽光発電所を設け、電力をまかなう。
・索道を移動する輸送装置は、電磁場によって走る「リニアモーターカー」で、ゆっくりと加速して宇宙に至る。静止衛星軌道から先は遠心力で進むことができるので電力を使わない(戻ってくるときは逆で、静止衛星軌道より内側では重力に引かれて落ちるので電力を使わない)。
・外側の先端宇宙ステーションの速度を利用して、何のエネルギーも使わずに太陽系内の惑星に宇宙船を送り出せること。
・同様に月にも塔は建築可能で、引力が小さいため地球よりも建設は容易である。長さを調節すれば、地球側の塔と月側の塔の先端を接触させられえるので、月までの直通も可能であること。
アルツターノフはこうした構想をまとめ、1960年7月31日に新聞「プラウダ」の日曜版に「電車で宇宙へ」という短い読み物として発表しました。
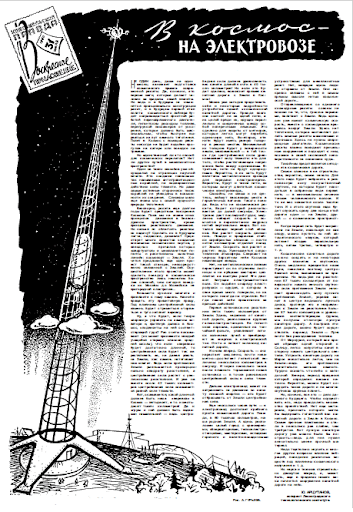
この記事は同年にアメリカの科学雑誌「サイエンス」や日本のSF雑誌「SFマガジン」にそれぞれ独自に翻訳掲載されました。

米ソ冷戦下ということを考えると、きわめて早い紹介と言えます。特に、日本での紹介がSF小説の専門雑誌だったというのは、当時の翻訳者・編集者の目の付け所の鋭さに感心するしかありません。
これが現在「宇宙エレベーター」あるいは「軌道エレベーター」と呼ばれている建築物の基本構想となりました。細部にわたる研究は進んでいますが、基本的な考え方は、このアルツターノフの構想の時点でほとんど固まっています。
ロケットでは、絶対に地球の重力を振り切るスピードが必要なので、約4G(地表の重力の4倍)の力が加わり、激しく振動します(宇宙飛行士の訓練では9Gに耐えることが求められます)。そのため荷物も乗員もしっかりと固定されていなくてはなりません。
しかし、「宇宙エレベーター」は、完成さえしてしまえば、「電車で宇宙へ」というタイトルどおり、鉄道あるいはエレベーターのようなものなので、非常に安価に安定して大量の物資をゆっくりしずかに静止衛星軌道まで運ぶことができます。時間がかかるのはデメリットですが、大量輸送でコストが下がり、大きな力がかからないので壊れやすいものや、体が丈夫でない人でも宇宙にいけるというのが、「宇宙エレベーター」構想の最大のメリットといえます。
現在では、静止衛星軌道から両側に伸ばす部分は、地球に向かってたらす紐のようなものなので「テザー」、そのテザー上を移動する輸送装置を「クライマー」と呼ぶことが一般的になっています。
その後、何名かの研究者たちが、「宇宙エレベーター」にまつわる論文や構想を発表します。
1964年にはイギリスのSF作家アーサー・C・クラークが、静止衛星軌道上の人工衛星からケーブルで低軌道までぶら下げた通信衛星を構想します。これはクラーク自身が1945年に発表した通信衛星の構想(これ自体はヘルマン・ポトチュニックの構想が元)を発展させたものでした。地上までケーブルを下ろすことは想定していませんが、物理学的な観点は「宇宙エレベーター」と同様といえます。
1966年にアメリカのスクリップス海洋研究所の4名の研究者が発表した短い論文は、やはり地上までは達しない構造物で、「スカイフック」と呼ばれるものを想定していましたが、建築に使えそうな素材の性能を具体的に検証した点で画期的でした。
そして、1975年にはジェローム・ピアソンが静止衛星軌道から塔を建築する方法を検討した論文を発表しています。そこでピアソンは強度計算も行っており、必要な強度を算出しています。
しかし、スクリップス海洋研究所の研究者たちもピアソンもそれ以前の「宇宙エレベーター」研究については知らなかったようで、のちに本家本元論争がしばし繰り広げられることになりました。
特に、アルツターノフは正式な論文として発表したわけでもなく、記事の中にも現実に必要な数値の算出などが一切行われていませんでしたから、ピアソンらに攻撃される余地が大いにあったのです。
このように、研究は行われていたものの、この時代「宇宙エレベーター」はまだまだ一般に知られた存在ではありませんでした。その認知度が一気に広まるきっかけになったのが、2人のSF作家、イギリスのアーサー・C・クラークと、アメリカのチャールズ・シェフィールドです。
2人は1979年、まったくの偶然に、それぞれが「宇宙エレベーター」を題材にした作品を発表します。クラークの『楽園の泉』は、インド洋に「宇宙エレベーター」建設するプロジェクトとその完成が世界に与える影響をあつかった、やや堅い作品です。
シェフィールドの『星ぼしに架ける橋』はミステリー風の味付けがされた娯楽作品と、作風は違いますが、共に理論的に破綻のない描写で評価されています。
なにしろクラークは先にも述べたように通信衛星を構想したことでも知られるSFの大家です。一方のシェフィールドは作品数こそ多くないものの、本物の理論物理学者で、NASAでルナ・オービター計画にも参加したという宇宙開発の専門家です(ちなみに、シェフィールドは、この「宇宙エレベーター」の件だけでなく同じく、理論物理学者でSF作家のロバート・L・フォワードが至近距離を回る双子星を舞台にした『ロシュワールド』を執筆中に、同じ舞台設定で『Summertide』という作品を執筆していたというエピソードもあり、「タイミングの悪い作家」としても知られています)。
日本では、クラークやシェフィールドより早い1965年に、SF作家の小松左京が短編「道頓堀発掘」と長編『果しなき流れの果に』において「宇宙エレベーター」を登場させています。
しかし日本では、SF小説よりもむしろアニメーションで積極的に取り入れられており、『楽園の泉』『星ぼしに架ける橋』の出版と同じ1979年の『宇宙空母ブルーノア』に「宇宙エレベーター(作中では軌道エレベーター)」が初めて登場しています。これはもしかしたら世界で始めて映像化された「宇宙エレベーター」かも知れません。
数年後、『超時空世紀オーガス』(1983年)にも登場しました。
その後、1992年『宇宙の騎士テッカマンブレード』、1994年『勇者警察ジェイデッカー』、2001年『Z.O.E Dolores, i』、2006年には特撮作品『劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE』にも登場、その後も2007年『機動戦士ガンダム00』、2013年「翠星のガルガンティア」、2014年『ガンダム Gのレコンギスタ』などと、継続的に「宇宙エレベーター」が描かれています。そうした作品群のおかげで、イメージとして非常に浸透してきているといえます。
2008年には、日本で「宇宙エレベーター協会」が設立され、「宇宙エレベーター」実現に向けて、研究が行われています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
