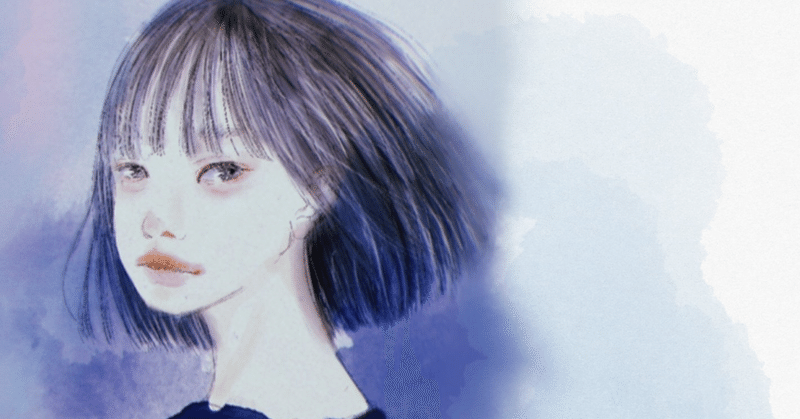
ユクスキュルとハイデガーの世界観についての考察
1.概要
本稿では、ユーコン・フォン・ユクスキュル(Jakob von Uexküll)の環世界論とマルティン・ハイデガー(Martin Heidegger)の存在論の比較分析を通じて、両者の理論がいかに異なるかを探究する。ユクスキュルの生物学的視点とハイデガーの哲学的視点の違いを明らかにし、それぞれが「世界」をどのように捉えているのかを論じる。
2.ユクスキュルの環世界論
ユクスキュルは、生物各自が「環世界」(Umwelt)という独自の知覚的世界で生活していると主張した。彼によると、この環世界は生物が持つ感覚器官によって限定され、生物個体によって異なる独自の感覚情報に基づいて構築される。この観点から、ユクスキュルは生物それぞれが主観的に経験する世界を強調しており、環世界は個々の生物が自身の生存戦略に適した形で周囲の環境を認識することを可能にする(Uexküll, 1934)。
3.ハイデガーの存在論
対照的に、ハイデガーは「存在投企」(being-towards)としての人間の能力を重視している。彼の理論において、人間は自己の存在を意識し、自分自身の可能性を追求し、積極的に「世界」に関与することが可能である。ハイデガーにとって、人間はその存在において自らの世界を形成し、これを超えて周囲の世界と交流する唯一の存在である。彼の見解では、人間のこのような世界への超越性が存在論的問いの核心である(Heidegger, 1927)。
4.理論の比較
ユクスキュルの環世界論は、生物がその感覚器官に依存して個別の環世界を形成するという点に焦点を当てている。これに対し、ハイデガーの存在論は、人間が自己の存在をどのように意識し、それをもとにどのように自己を超えて「世界」と交流するかを探求している。ユクスキュルは主観的な感覚体験を強調するのに対して、ハイデガーは人間の主体的な存在と世界との積極的な関わりを強調している。
5.結論
ユクスキュルとハイデガーの理論は基本的な前提と方法論が異なることが明らかになる。ユクスキュルが個々の生物の感覚に依存する世界観を提供するのに対して、ハイデガーは人間の存在そのものの深い理解を通じて、より哲学的な視点から人間と世界の関係を論じている。これにより、生物学と哲学の交差点において、両者の理論が持つ教訓と限界がさらに理解される。
参考文献
Uexküll, J. von (1934). Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre.
Heidegger, M. (1927). Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
