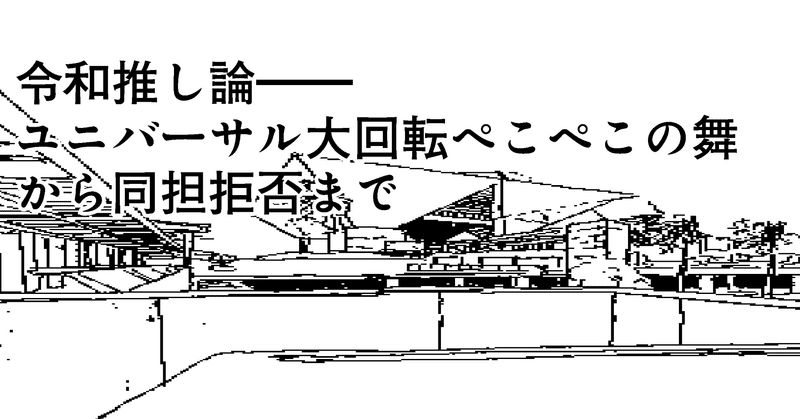
令和推し論――ユニバーサル大回転ぺこぺこの舞から同担拒否まで
このエッセイで分かること
・推しという言葉はどのようにして広まったのか
・ある存在が推しとなる条件
・様々な推し方(筆者の観測範囲内)
前書き
あなたに「推し」はいるだろうか?
1980年には存在していたというこの言葉は、アイドル文化としての出自を飛び出し、広く人口に膾炙した。自己紹介とともに推しが誰なのかを語ることは今や一般的な行為になり、女子大生・女子高校生の9割以上に推しがいるそうだ^1。そればかりか、推しがいないことはむしろマイノリティとなり、「誰を(何を)推しているか」は現代における1つのステータスとしての立場を獲得したと言っても過言でないだろう。筆者には明確に推しと呼べる存在はいないのだが、最近、初対面の同級生に推しがいないことを話すと「かわいそう。人生9割損してる。悩み事でもあるのか?」と言われ、その夜一人枕を濡らした。閑話休題。一億総オタク社会において、推し概念は広く受け入れられ、多くの人にとって日常を照らす豊かな光となった。
さて、先に述べた通り、私には自信をもって推しと呼べる存在がいない。それは別に困ることではないのだが、推しが良いものだ!と叫ばれるたび、そんなにいいのか……と興味を持ち、俺も推しが欲しい!と様々なコンテンツに入り浸り、かなり深いところまで潜った(つもりである)りする。しかし、何度試してみてもその光は私にもたらされず、再び凍えながら毎夜毎夜枕を濡らすことになった。そこで半年ほど前から、むしろ自分が推しを持てない原因に興味を持ち推しについて包括的な調査をするべく、周りのオタクに推しについてのインタビューを仕掛けるという簡易フィールドワークのようなことや、様々な文献をtwitterから本までを範囲に採取し始めた。本稿ではその調査から見えた推しの本質のようなものをつらつらとまとめたい。
推し、そのルーツ
所謂オタク第三世代(1980年代生まれ)は自らが拠り所とするサブカルチャーが徐々に市民権を得てきた環境で育った。バブルが崩壊しノストラダムスの大予言が流行り、地下鉄サリン事件といった象徴的な出来事が立て続けに起こるような自閉的時代精神を土壌として、『新世紀エヴァンゲリオン』や『カードキャプターさくら』といった作品が生まれた。萌え文化が明確な物として発生し、社会的なムーヴメントとしてセカイ系が受け入れられた。また、この時代はテクノロジーの発展により家庭用ゲーム機やビデオデッキの普及からそれらの技術が広く普及した。その結果として、サブカルチャーとメインカルチャーの境目が薄れていく。そんな平成初期~は「日本=アニメ」イメージの始まりとも呼べる時代となった。その広く普及した技術のなかにインターネットがある。それまで、独立した1つのメディアであったパソコンは、道具として用いられるようになり、そのサービス、2ちゃんねるの狼板という『モーニング娘。』専門の掲示板で推しという言葉は産声を上げた。
当時、2次元オタク=アニオタは「推し」に代わる言葉として「嫁」を用いていた。令和において、2次元オタクはその対象に対して推しという言葉を使うことが多くなり、嫁は死語として扱われている。推しのルーツは嫁から推しへの転換の歴史とも言い換えられるだろう。では、なぜアイドル文化の中で推しという言葉は生まれたのか。アイドル文化は「ナマモノ」である。自分が崇拝する象徴の向こうにそれを実行する実在の人物がいる。実在の人物を対象として推し活を行う場合、最低限倫理的な行動を求められる、あるいは意識的/無意識問わず自ら行動を制御してしまう。社交性仮面(ペルソナ)は単純な一対一のコミュニケーションにも発生するように、公衆に対しても発生する。エレベーターに相乗りした時に互いに無関心を装う行動など、身に覚えがあるだろう。それは生得的に発生するもので、象徴という名のヴェールを推しとの間に挟んだとしてもそれは発動する。判りやすいものでは公式の活動の差異として、乃木坂は抱き枕にはならないし、AKBのおっぱいマウスパッドは発売されない。二次創作文化にもそれらは見られる。一部例外はあるとはいえ、アイドルオタク界隈にはルイズコピペのようなものは多くは出回らないだろう。さらに、「嫁」という呼称は暴力性を伴う。オタクが相手の了承を取らずに対象に対して自らとの役割を押し付ける。しかも「嫁」というのはジェンダー視点で差別的であると言われる言葉である。これは非常に無責任な態度であり、「嫁」は社会が存在しない、オタク単一の閉じた世界だからこそ用いることができた言葉であると言えるだろう(2次元キャラクターは実際には存在しない為、どんなに愛していても画面からは出てこない)。つまり、アイドルオタクは対象が実在する人物であるから最低限の社会性・公衆性を持たざるを得ず、そのために好意を寄せる対象に嫁という呼称を用いることができないため、推しという表現を代替として用いるほかなかったのが「推し」の始まりと呼べるのではないだろうか。
そこからの浸透は早いものであった。オタク人口が増えるにあたって、エチケットは一般化されてゆく。2次元キャラクターといえどもそのキャラクターを作る作者が、それを描く絵師が、それを演じる声優がいるわけで、さらなる倫理性、社会性を求められた結果、「嫁」という呼称は淘汰され、多くの「推し」が生まれる時代に代わっていった。
推しの条件――あるいは多義性を殺された推しは推しではない
推しに関しての簡易フィールドワークを続ける間、推すことの本質は何かという疑問が常に頭の中にあった。推し/推すことは非常に多義性を伴った概念である。人の数だけ推しと推し方があるだろう。自分の熱烈さを表現するために推しへ、貢ぐ、追いかける、ファン広告を出す等々様々な方法が取られ、推しに対する態度も単純に応援しているといったものからガチ恋と呼ばれるものまで多種多様に増えた。しかし、それとコンテンツに対する態度は相関がそこまでなかったりする。応援ぐらいの軽い気持ちでコンテンツを追っている人が配信を全てリアルタイムで視聴してコメントを1コメ/mで書き込んでいたり、ガチ恋だからこそ配信を直視で見られず、アーカイブを覗き見るという形でしか推しを見られないという人がいたり、と様々な態度がある。人口に膾炙した推し概念はそれだけ多様な推し方を生み出した。正確には「推す」という言葉がどんな多数多様な推し方でも受け入れることができるために人口に膾炙したといった方が正しいだろう。
話が前後するが、筆者は推しが作れないことに悩み、推しに関する調査を始めた。前記のような推しの多義性を考えたときに、私も他のオタクたちと同様の行動を取っているはずで、しかも推しという言葉は多義性を含むのだから、自称人より数倍オタクである私もそろそろ推している感覚を感じられても良いのではないかと、推し感覚を得られない事に不満を覚えた。なんだかもう、悲しみを通り越して怒りすら覚えた。
この章ではフィールドワーク等で採取した様々な人物の多様な推し方をいくつか記述しながら推しの条件・本質に迫っていきたい。
ホスト通いの女子大学生――推しと恋
ホストの世界にも「推し」という言葉は現れる。ホストクラブでは基本的に、客は自分を接待させるホストを「担当」と呼ぶが、近年は自分の担当に対して推しという呼称を用いる人も増えてきているという。その呼称を用いる人は、比較的ライトなホスト通いに多く、また、中には複数「推しホスト」がいる人もいるそうだ。「推しホスト」についての調査をするべく、月平均100万円、最高250万円を「担当」ホストに貢ぐホスト通いの友人に話を聞いた。
始めに彼女に、ホストを推し扱いする客についてどう思うか尋ねると、肯定的な感情も否定的な感情も抱いていない様子で「まぁいいんじゃない?そういう付き合い方もあると思うよ」と答えた。ホストコミュニティは客―ホストで閉じた環境なのであまりパラレルに存在する他のホスト通いについてどうこうと感情を抱かないのかもしれない。
あなたは担当に対して推しという態度で接しないのか?という質問に対しては、「推しという呼称は金銭的に余裕があって、時間が無い人(太客)が用いることが多い」「私は時間の余裕はあるし、お金がないから(担当関係を持っている)」「別に推しはうらやましいとは思わない、ガチ恋の方が幸せ感じるし」との回答を得た。詳しく話を聞くと、ホストに対して「推し―ファン」関係を求める客層には、ライトなエンタメ(イケメンに親身に話を聞いてもらって気持ちよく飲む)を求めホストに通う人が多く、そのためアフター(店外での性的交渉)や同棲もしない人が多いそうだ。これは、自分はファンであり、客であるという意味合いの呼称を自覚的に用いることで、ある一線をホストとの間に引く、関係性の変化に対してのセーフティーネットとして機能しているのだと考えられる。
関係性がライトなもので済んでしまうことについて、店としては客とホストの関係性がより深くなり、お金を落としてほしいという原則から外れるはずであるが、店側はこれをどう考えているのかについては明確な答えが得られなかった。また、推されることに特化した「アイドル化したホスト」も存在するようで、そのホストにはメインの客がつかず、多くの客に対してライトなエンタメを提供する「薄利多売」戦法を使っているそうだ。その営業方法の多様さには、ユーザーに合わせてその商売の在り方を素早く変えられるホストクラブならではの対応力を感じた。
ホストクラブにおける推し関係が一般化しない理由としては、ライトなエンタメを享受する目的ではホストクラブはコスパが悪い、習慣化するので危険性を伴う、そして、大抵の客はホストとのより深い関係性を望んでおり、彼女もその一員である。と締めくくった。
推し関係を脱してアフターや同棲をも視野に入れると、あくまで商売上の付き合いだとしても、相手に対して求める要件が変化する。相手の事を仔細に知り、生活における適正のマッチングとキャリブレーションをする必要が生じる。推し関係を脱するまではある種、向こう見ずに相手のことを全肯定しておけばよかったはずであるが、生活にあたっては不快の念が生じざるを得ない。この構造は恋と愛の関係性にも見出せると感じる。一目惚れという恋の形からもわかるように、恋は自分の中の好意の象徴として相手を肯定していればその思いは成立する。つまり、相手の事は最低限の情報だけ(曲がり角で運命的にぶつかった相手!程度の情報)で問題がない。直観に従い、単視点的に「かわいい!/かっこいい!」と思えばいいのである。しかし、相手を現実として捉えた時、そこには多くの評価軸が足され、多視点的な見方を余儀なくされる。そのうえで、相手の存在そのものを肯定でき、積極的に気に掛けることが愛なのだろう(エーリヒ・フロムも『愛するということ』で「愛とは、愛する者の生命と成長を積極的に気に掛けることである。」と述べているのであながち間違っていないのではないか。)。ここでの推しや恋に見られる単視点性の代表的なメリットは陶酔とそれによる勢いだろう。それらは非常に感情的な行動で、とても自然な行動だ。つまり、それは処理が軽く、行動目的として燃費が良いということである。しかし、それには危険性も伴う、視野が狭まるために、突飛な行動に出ることがあるのだ。そこを考慮し、ホストに対して推し関係を求める客は、あくまで疑似恋愛としてそれを楽しむという宣誓として相手を推しと呼称するのだろう。つまり、ここでの推しにはある種相手の情報量を絞るバルブとしての役割を見出せる。
同担拒否を叫ぶ女子中学生――推しと自分
同担拒否という推し方がある。もとはジャニオタ(ジャニーズ事務所に所属するアイドルグループのファン)の間で使われていた言葉で、同じ人物を推しているファンを認めないという姿勢である。認めない理由は様々あるらしく、男性アイドル界隈に詳しくない著者はあまり詳しくないために明言を避けるが、その感情自体は一般的であり、女性アイドルオタクのように「親衛隊」などを作って組織だって特定の対象を推す推し方とは根本的に異なったものである。また、好対照に男性アイドルオタクは少人数グループで行動し、なるべく推しが被らないようにファン同士お互いの推しを常時監視・把握してグループ内での良好な関係性を維持する(インタビュアー談)。
彼女は、「だって推しを知っているのは自分だけであって欲しいじゃん」と言った。「推しの良さを他の人は知らなくていい」「推しは適度に有名になって欲しい、でも古参は私だけ」と。自称古参歌い手厨であり、同担拒否の態度で推し活に励む彼女は、今まで見てきた典型的な推しのいるオタクと違い、特異な存在に見えた。つまり、推し活の焦点がはっきりと推しに合っていないのだ。普通、推し活には盲目性が伴う。前述した単視点性だ。例えば、ユニバーサル大回転ぺこぺこの舞というインターネットミーム(VTuber「兎田ぺこら」の配信にて、視聴者が投稿したクセの強いスーパーチャット)を生み出したおせう氏は後に自身のブログで当時の心境を振り返り^2、ネット民に馬鹿にされても変わらぬ推しに対する熱い想いを綴っている。1万円と熱意がネットミーム化され、いじられ、馬鹿にされてもおせう氏の想いは絶えることがなかった。そこにはある種盲目性を伴う推し活があるだろう。オタク活動は宗教と準えられることがあるが、原典(推しそのもの)を自身が肯定できるように「解釈」する必要が生じるという点において共通している。それは自身の盲目性を担保するための崇拝行為でもある。そのような推し方には、推しのアウトプットをどこまで受け入れられるかという柔軟性≒盲目性が重要となるのだ。しかし、彼女の推し活は推しを「マジかっこいい」としつつも、「ここは微妙」という点も自覚的かつ冷静に挙げており、それを加味して肯定することで、ある種推しを可愛がる/見下すことによってその好意を維持しているようだった。少なくとも、彼女の推し方に宗教性は感じられない。どんな信徒も私は神の最古参で、神は私だけが信じてればいい、とはならないだろう。
このような推し方になった要因は彼女の年齢の低さとそれ特有の問題、つまり青年期としてのアイデンティティー獲得過程における特異性が絡んでいるのではないかと私は考えた。彼女は、「推しを推していること」を自身のアイデンティティーとするのである。彼女の目線は推しを通り越し、推しを推している自分を向いていて、マイナーな対象を推している自分を肯定するために推しは消費されている。エリク・H・エリクソンは発達課題という概念を提唱し、青年期は自分が何者なのかを定義するために悩む時期で、(自己同一性=アイデンティティーの確立)という葛藤を経験する、とした。これに照らし合わせれば、彼女はその葛藤を解消するために、自分を古参として定義し、古参としての自分を維持するために推し活というロールプレイを行う。そのために一般的な推し方である盲目性を排し、自己参照的な同担拒否を行うのだ。勿論、彼女の同担拒否の姿勢には特殊なもので、一般的なものではない。しかし、推しの1つの用法としてこのようなものが定義できる。決して盲目的であることだけが推すことではないのだ。
腐女子の女子大学生――推しとグループコミュニケーション
推しはコミュニケーションに使われ得る。特定コミュニティに所属することでファン同士にも連帯感が生まれ、ファングループが発足する。かつての「親衛隊」などがそれである。
話を聞いた腐女子の女性によると、twitterなどのSNSで交流をもつ「オタク仲間」の中には数多くのルールが存在していて(「推し変」をしないなど)、それを破ると仲間からのバッシングを受けるそうだ。彼女は「言われてみれば推すことよりも、それについて会話する、グループ内でお絵描き会を楽しむという方に私は価値を見出しているかも知れない」と言った。例えば、内内での関係性の調整や、グループ内での圧力関係等、そのようなコミュニティの運用・所属すること自体に快感を見出すそうだ。特に象徴的な事として語られたのが「推しアニメ、そういえば一周しか観ていないなぁ」という発言だった。彼女たちは「推しアニメ」に会話トピックとしての役割を見出し、それの物語的な本質を消費するよりも「データベース消費(東浩紀)」のような方法でコミュニケーション材料としてアニメを消費している。また、彼女が所属していたのは二次創作コミュニティだったため、BL読者+BL批評というその生産―消費サイクルが確立されているそうだ。つまり、コミュニティではほぼスタンドアローンに生産と消費を繰り返すことができる。そして、そこにも物語自体というよりもキャラクター同士の関係性を消費するという態度が見いだせるだろう。内容よりもその内容から発生するコミュニケーションに価値を見出す。そういった触媒としての「推し」の役割もある。
こういった内向きかつ村社会的なコミュニケーションは非常に女性的なコミュニティでのイベントで男性コミュニティ(ホモソーシャル)では再現性が低い。「親衛隊」のようなオタクグループはその視線が推しへ向かっているが、この項で取り上げたグループは推し仲間へと向いているのだ。これは男性オタクが推し―自分という一対一の関わりを持つことが多いのに対して、女性オタクは同じオタクで「推し方」などの共通点からネットワークを作ることが多いという決定的な構造の違いが見いだせる。
補足――男の推し
ここまでいくつかの推しの在り方を述べた。それの全てが女性による事例だったのは偶然ではないだろう。フィールドワークでは筆者が男性であることから、自然と男性のケースを採取することが多かった。勿論その中では多くの特殊な推し方が見受けられ、考察に値する価値があるものも多く存在した。しかし、今回男性の事例を取り上げなかったのは、多くの男性のそれがどうしても「自分の推しに対する態度が特殊性を帯びた」というだけで、推しそのものの在り方は一貫して好意を寄せる対象でしかなく自身と推しの関係性は自分―推しといった1次元的構造だったためである。どんなに特殊なバックグラウンド、態度、手段で推していても、それらに構造的な差異は見られなかったために採用を見送った。ここで、詳細に記述できなかったそれらの一次元的だが興味深い推しの在り方も軽くまとめておきたい。
好きな子よりも運命性を
ラブライブオタクの男子中学生は、「性格と顔が本当に好きなのは桜内梨子(ラブライブサンシャインのキャラクター)だったが、ラブライブというアニメを知ったのはにこにー(矢澤にこの愛称、ラブライブのキャラクター)が駅の広告に出ていたからで、彼女はちょっと痛い女だったけれど、自分をオタクという存在に導いてくれたのは彼女で、にこにーは特別な存在である。そのために絶対に一番の推しはにこにーで、それは揺らがないのだ。」という発言をした。必ずしも推しに至る要因がその存在と自分との相性ではなく、運命性も含まれるということだろう。これは推しに「どこまで尽くせるのか」という根本的な盲目性の問題の中で、恩義ゆえの特別性を多数いるアイドルメンバーの中で見言い出すことができるということの表れだ。直接的な肯定というよりも象徴化された肯定である。
ヴァーチャル(仮想)としての推し
湊あくあ推しの男子大学生は、かつてどうしても告白できずに、連絡先も交換できなかった後悔が残る恋愛の影を推しに重ねている、と言った。始めはその過去の片思い相手と推しの性格や声が似ており、湊あくあを見始めた頃はなんとなく「あの子っぽいなぁ」と感じる程度だったが、次第に両者を重ねてみるようになった、と語った。この場合の推しは仮想化だろう。推しをオルタナティブな世界線での彼女として捉えることで、自分にとって納得のゆく仮想環境を作り出す。推しに対して自分だけのバックグラウンドを付与し、自分だけの関係性を補完する。記憶からエピソードを切り離し、再び合成することによってより思いを強固なものとする。彼はその行為に対して自覚的で、「これはある種のリハビリだと思っている。うまく行かなかった恋愛にこうやって踏ん切りをつけるための儀式的な物なんだ」と語った。
まとめ
この章では推しという存在を構造的・その周縁・推し/非推し・男女、という多種多様な視点から語った。推しには明確な条件はなく、間違いなくその多義性が本質であるものの、その輪郭のようなものがぼんやりと伝えられていたら嬉しい。また、現在令和での推しの一般的な意味合いは盲目性によるところが大きいのだろうというのが著者の結論だ。
豊かな「推し」という概念について考えることは自分の推しに対する解像度を増し、推し活に新たな手段を与えてくれる。本章が推しとのかかわり方に新たな視点を増やす例として、あなたの推し活の一助となれたら幸いだ。
あとがき
まず、今回の取材に協力してくださった皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げたい。
皆様のおかげで面白いエッセイになったのではないかと思います。本当にありがとうございました。
推しの在り方の簡易フィールドワークでは、その多種多様な推しの在り方、推しと自身、コミュニティの構造や、なにより取材させていただいた皆様の推しへの熱い想いを肌で感じることができた。非常に刺激的かつ示唆に富んだ経験で、物心ついてからオタクを15年近くやってきたつもりであったが、取材を続ければ続けるほど新たな気付きを得ることができ、この文化の情報量の多さ、重ねられてきた歴史の厚さと奥深さに改めて感動した。
最後に、原稿執筆のため調査をまとめている最中、筆者にも中学生、高校生の頃、推しがいたことを思い出した。当時は「嫁」と呼んでいた彼女への情熱を今でもはっきりと思い出すことができる。なぜ今まで「推しができない」などとのたまって、心の支えとなり、暗い気分も吹き飛ばして日々を明るく照らしてくれた推しの存在を忘れていたのだろう。大学生になって、忙しさから推しを持つ余裕と覚悟を失っていただけでその原因は自分にあった。物事を正面から見つめ、愚かであったとしても、盲目的に、単視点的にのめりこむ、そのようなパッションを持てた輝かしい日々を懐かしく思う。この夏は何にも考えずに、アイスを食べながらラブライブサンシャインを見直そう、そんな気持ちになった。
参考文献
^1: 女子大生・女子高生の9割以上に「推し」がいることが判明!女子学生マーケティング集団「Trend Catch Project」が「推し活」に関する調査結果を発表|RooMooN株式会社のプレスリリース (prtimes.jp)
^2: https://archive.vn/zFBsV
著者情報
はくしょおおき。普段はSFを主ジャンルとし、漫画、小説、論考などを書く。C102では半知半会というサークルで同人誌を発行しました。感想お待ちしてます。
Twitter::@wp_041
メール:041.whitepaper@gmail.com
初出情報
この文章はコミックマーケット102にて早稲田VTuber研究会から頒布された『VTrue vol.1』に収録されたものを再掲載にあたって改稿したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
