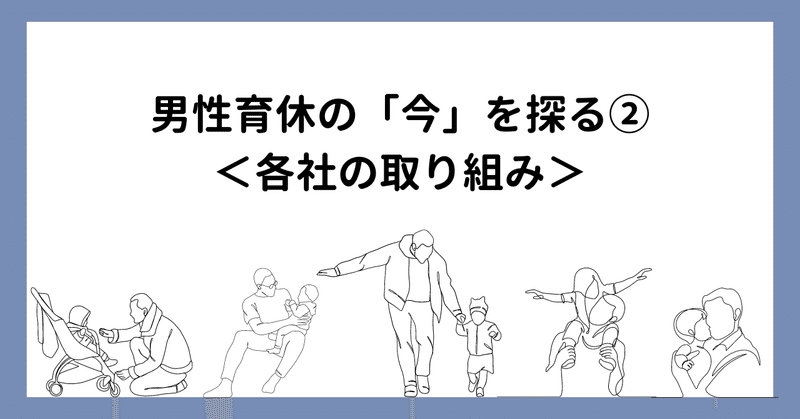
男性育休の「今」を探る② <各社の取り組み>
こんにちは。ワークシフト研究所の広報担当です。
皆さんの周辺で「男性育休」を取得する人は増えていますか?
前回こちらの記事では、男性育休が推進される背景と男性育休の取得を阻害する要因をご紹介しました。今回は、男性育休に対する各企業や団体の取り組みをご紹介します。
男性育休、各社の取り組み<2024年版>
伊藤忠商事の場合
伊藤忠商事では、2024年4月から男性社員の育児休業取得を必須化、パートナーの出産から1年以内に5日以上を取得させます。
「職場に迷惑をかけないかと気にして取得をためらう社員がいるため、必須化によってハードルをなくす」ことをねらっているそうです。
丸井グループの場合
丸井グループでは、男性育休は優秀な人材の確保や離職防止につながる経営戦略の1つであることが明確にされています。
育休を取りにくい一番の理由「職場に迷惑をかける」を解決するため、業務割り当てを担う管理職に研修を実施し、長期育休取得を重視する意義を伝えています。
半期毎に行われる部下との面談では、子供が生まれる予定があるかどうかも確認するそうです(注)。育休を取得する可能性のある社員を早めに把握しておくことで、業務の引き継ぎなど長期取得に備えやすくなるためです。従来は出産後に育休取得を申請する社員もいて対応が難しかったとのこと。
(注)プライベートなことなので、タイミングや聞き方によっては、ハラスメントになってしまう場合があることをご留意ください。日頃から全社的に周知しておき、社員から早いタイミングで教えてもらえる仕掛けづくりをしていきたいですね。
また、同グループでは売り上げなどの数値目標を個人ではなく、チームで評価するなど、日頃からサポートし合う文化が根付いており、普段から「いつ誰が抜けてもいいような体制」を取っていて、業務分担のハードルを下げているそうです。理想的です。
野村証券の場合
上述のNewsPicksの記事では、野村証券の例も紹介されていました。野村証券では、2023年10月から、1カ月以上の育休を取得した社員に対して、男女を問わず年収の1割を補助しています。これにより、制度を導入した10月から2024年1月までの育休取得者数は前年より大幅に増えたそうです。
また、上司がワークライフバランスの重要性を理解して、休んでいる社員をカバーできるようなリソースマネジメントを高めることが社内で徹底的に共有されています。
石井食品の場合
ミートボールでおなじみの石井食品では、育休に限らず長期休暇の取得が推進されていて、全社員に毎年2週間程度の休暇を取ることが推奨されています。
一人がいなくなったらまわらない組織は、それこそ危険です。日ごろから、個人に依存しない体制と情報共有の仕組みをつくっておくことを強く意識しています。
業務の属人化を防ぐよい取り組みだと思います。日頃からこれができていれば、育休に限らず、感染症対策にも増加が見込まれる介護離職の防止にも応用できそうです。
メットライフ生命の場合
メットライフ生命では、管理職が「育児中の社員の1日」を経験して、両立生活を送る社員の日常や気持ちを知ってもらう研修が行われています。「保育園から緊急の電話がかかってきたら?」を想定した研修では、2週間にわたって定時に帰る生活を続けます。
昭和生まれの管理職は、育児をパートナーに丸投げできた世代なので、個人的にもこれはなかなかよい取り組みだと思いました。
群馬県高崎市の場合
群馬県高崎市では、これまで育休を1日でも取得すれば昇任・昇格が1年遅れるとしていた制度を廃止、育休取得が昇任・昇格に影響を及ぼさないよう制度を変更しました。これにより、男性育休の取得率は、前年度の約4倍、約83%に。取得日数にはばらつきがありますが、平均は39日だそうです。
1日休んだら1年遅れるって、かなりしんどい制度でしたね……。
―――――
今回ご紹介した企業や自治体の取り組みをまとめると、
男性育休の取得を必須化
社内で男性育休の位置付けを明確にし、理解を促進
日頃から業務の属人化を防ぎ、引き継ぎがしやすい体制を構築
育休に限らず長期休暇の取得を推進
育休が昇進・昇格に影響しないように制度を変更
といった点がポイントになっていました。
前回の記事で男性育休を阻む要因を分類し、会社が解決すべき問題を整理しましたが、上記のような取り組みでおおむね解消されるのではないでしょうか。

そうはいっても、こういった施策は大企業だからできること、とお思いの中小企業の皆さん。
来年、2025年度からは、従業員が300名を越える企業に育休の取得状況の公表が義務付けられるのをご存じですか?(従業員数1,000名以上の企業は2023年度から実施済み)
これからの世代は、女性に限らず男性も当たり前に家事を分担して育休を取得する世代です。実際、こちらの記事では、共働きで役割分担もフェアな「3.0世代」が増えていることが説明されています。
厚生労働省のイクメンプロジェクト推進委員会で委員を務めている弊社 所長の国保祥子(静岡県立大学経営情報学部准教授)も次のように話しています。
今の若い世代は、男だからとか、性別に基づいた役割意識が薄れてきています。産後も働きたい女性は6割いて、育休を取りたい男性も6割います。若い世代を採用したい職場の方に肝に銘じていただきたいのは、こういう若い世代が入社してくるということです。男性育休の前例がなかったり、女性が男性のサポート要員になってしまって、性別分業のある会社には、学生は来なくなります。
すでにあちこちの業界から人手不足が声高に叫ばれており、育休取得者の不在を気合いで乗り切るのは困難な状況となっています。
男性育休は職場改革のきっかけ、職場に業務効率化・人材育成をもたらす機会と捉えて、魅力ある組織をつくっていきませんか?
ワークシフト研究所では、管理職向けのダイバーシティ研修など承っています。
ワークシフト研究所からのお知らせ
育休プチMBA 父の日スペシャル回を実施します
弊社が運営する育休者向けのセミナー「育休プチMBA®」にて「男性育休あるある」を考える父の日スペシャル回を6月29日(土)に開催します。
男性育休を取りたい当事者の方も、男性育休に備えたい企業の方も、どなたさまもぜひご参加ください。
男性育休にまつわる皆さまの声をお聞かせください
ワークシフト研究所では、男性育休に関するアンケートを実施しています。育休と仕事と家事・育児の両立についてなど、皆さまのご意見をお聞かせください。
こちらのフォームから回答いただけます。
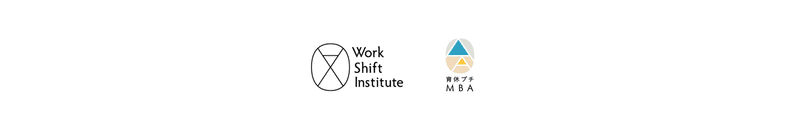
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
