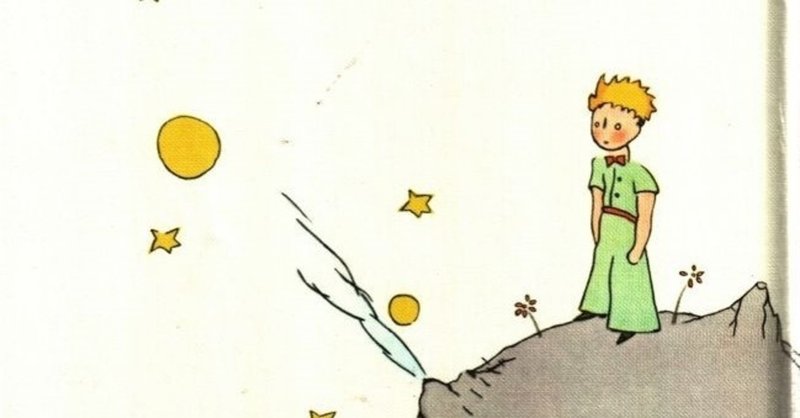
みんなひとりぼっち ―サン=テグジュペリの『星の王子さま』とシュペルビエルの『海に住む少女』を比較して―
序
私は今回サン=テグジュペリ(Antoine de Saint-Exupèry 1900-1944)の『星の王子さま』(Le Petit Prince)とジュール・シュペルヴィエル(Jules Supervielle 1884-1960)の『海に住む少女』(L’ENFANT DE LA HAUTE MER)の二作品を比較しながら、それぞれの作品に描かれている「孤独」というテーマについて考えてみたい。
それぞれの作品とも20世紀のフランス文学の作品で、少年少女を主人公としている。しかし、ありふれた日常をテーマにしているのではなく、現実とは離れた非現実的な世界を描写している。
不思議な世界で生きている彼らは、自分たちが生きている世界で孤独やさみしさを感じているという点で共通している。海の少女が住む世界、星の王子様が住む世界で、彼らはなぜそのような感情を抱いてしまうのか考えてみたい。
1 親のいない少女と王子さま(心を打ち明ける存在の不在)
『星の王子さま』の物語の中には父、母という表現が全くと言っていいほど出てこない。むしろ、王子さまと一緒に住んでいる人間はだれもいないのである。
『海に住む少女』の少女は、「そこにまったくのひとりぼっちで暮らす、十二歳くらいの少女 」であり、「大西洋でいちばん孤独な少女 」である。両親については、最後に父親の説明が少しある程度で彼女が暮らす街には両親どころか他に住んでいる人はいない。
つまり、彼らには本来子どもが必要とする「親」という頼れる存在がいないのである。
誰にも頼らず生きていかなければいかないことが、彼らのさみしさや孤独を生む原因になっていたと考えられる。言い換えると、孤独とは「心から話が出来る人もいないまま、一人で生き 」ることと言えるのではないだろうか。
2 夕陽と例題一六八―(さみしさを癒す存在)
『星の王子さま』で王子さまがぽつりとつぶやいた「ねえ・・・・・・悲しくてたまらないときは、夕陽が見たくなるよね・・・・・・ 」というセリフや語り手である僕の「きみには長いあいだ、やさしさに満ちた夕暮れどきの景色しか、心をなぐさめてくれるものがなかったことも。 」という言葉からもわかるように、王子さまにとって唯一心を癒してくれる存在は「夕陽」だったのである。
逆にいえば、王子さまが夕陽を見たい時というのは、彼がさみしさや孤独を感じているともいえるだろう。
王子さまは旅をして新しい人に出会うたびに「夕陽」について質問する。王子さまにとってどんなに夕陽が大切だったのかは、最初の星で王様の権力について聞いたときに彼が思ったことを引用して考察してみたい。
「もしぼくにそんな力があったら、一日に四十四回どころか、七十二回でも百回でも、いや二百回でも、いすさえ動かさずに、日が沈むところを見られただろうに 」。(サン=テグジュペリ、『星の王子さま』河野万里子訳、新潮社版、2006年、55頁)
この言葉からもわかるように、王子さまは自分が暮らしてきた星でたくさん孤独やさみしさを感じていた。そして夕陽こそが、孤独な、ひとりぼっちの王子さまが悲しみを紛らわせることが出来る存在なのである。
しかし、結局王子さまは心を打ち明けられる存在が無いまま、孤独に生きてきたのだ。
『海に住む少女』の少女が、文法書を開き例題を見つめるのは彼女がその問題が好きだからである。彼女はなぜこの例題が好きなのであろうか。後の引用から考察したい。
「あなたは・・・・・・ですか」「あなたは・・・・思いますか」 「あなたは・・・・・・話しますか」「あなたは・・・・・・・ほしいですか」「・・・・・声をかけるべきですか」 「いったい・・・・・・あったのですか」 「・・・・・・責めているのですか」 「あなたは・・・・・・できますか」 「あなたは・・・・・・しでかしたのですか」 「・・・・・・問題ですか」 「このプレゼントを・・・・・・・もらいました」
「あなたは・・・・・・つらいのですか」
(ジュール・シュペルヴィエル 『海に住む少女』 永田千奈訳、光文社古典新訳文庫、2006年、15頁)
この問題の内容から、彼女は自分に語りかけてくれる、自分の気持ちを理解してくれる存在を求めていると捉えることが出来るのではないだろうか。
少女は、「時おり、少女はどうしても、何か文章を書かずにはいられない気分 」なり、「一生懸命に文字をつづ 」るのである。この行動からわかることは、彼女には話しかける存在、自分を心から打ち明けることが出来る存在がいないということだ。
星の王子さまに心を打ち明ける存在がいないように『海に住む少女』の主人公の少女にもそのような存在はおらず、自分の気持ちを打ち明けられる存在を求めていた。少女もやはり孤独なのである。
結論(死と孤独)
ここまで両作品に描かれている孤独、またそれを癒す存在について考えてきた。王子様には夕陽、海に住む少女には問題集と彼らのさみしさを癒す存在はあった。
しかし、本質的には星の王子さまも海に住む少女も、「天涯孤独 」であり心を打ち明ける存在なしに生きてきたのである。
最後に、両作品の終わり方を比較し、死と孤独の関係を考察したいと思う。
王子さまは最後にヘビに噛まれて死をもって自らの星に帰っていく。つまり、王子さまはさみしさや孤独という感情から死を持って解放されたのである。
これに対して、『海に住む少女』では波が「死の力を借りて、連れ去ってしまおうとした 」。波は海に浮かぶ町にひとりぼっちで暮らす少女の孤独を死によって、終わらせようとしたのだ。ここでの共通点は、さみしさや孤独といった感情が「死」によって終結するということである。
言い換えると、心を打ち明ける存在がいない彼らにとってこのような感情は死ぬまで抱き続けなければいけないと言える。ここでの相違点は、王子さまが死を向かることが出来たことに対して、少女は死を迎えずこれからも不条理な世界で孤独を抱きながら生きていかなければいけないということである。
二つの作品を比較してみて、小さな星に住む王子さまも、海に浮かぶ不思議な町に住む少女も孤独を感じていることがわかった。そして、その理由は「心から話が出来る人がいないまま 」生きてきたことにあると言える。
彼らは一人ぼっちで暮らし、「親」という本来子どもが頼るべき存在がいなかった。しかし、「親」や周りに人がいたとしても「孤独」は感じるものである。なぜなら、『星の王子さま』の語り手である「僕」もまた孤独を感じていたからだ。
「僕」は「こうして僕は、今から六年前、サハラ砂漠に飛行機が不時着するまで、心から話が出来る人もいないまま、一人で生きてきた 」のである。王子さまや少女とは異なる、人の住んでいる町で生きていた彼にもまた「孤独」という感情があったのである。
つまり、「孤独」という概念は実に普遍的なものである。大海原に住んでいても、砂漠にいても、人がいる町に住んでいても「本当に話の出来る相手なしに 」生きていく限りみんなひとりぼっちであり、この感情からは逃れられないのである。
今回の考察からは、非現実的な世界に住む少年少女にも、人のいる町で暮らしてきた「僕」も同じように孤独を感じるものだと理解できた。そして、自分の気持ちを打ち明けることが出来ないことがこの感情を生み出すのだとも考えられた。
しかし、非現実的な世界を描く作品を比較してしまったため、子どもが本来頼るべき家族のいる少年少女は、どのような時に「孤独」といった感情を抱くのか考察することが出来なかった。機会があれば、一人ぼっちで暮らす彼らと、家族の中で生きている少年少女について考察してみたい。
*以下の2冊を参考に、当該記事を作成させていただきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
