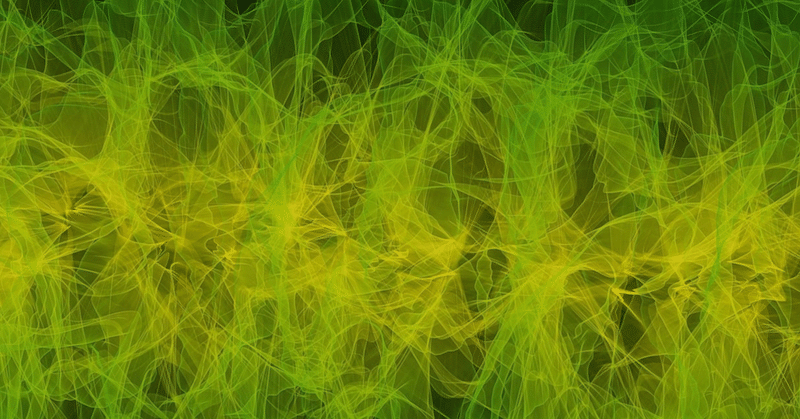
GREEN MIST【短三編・二】
(二)
ある日、彼女はこんな事を言い出した。
もし世界が終わる瞬間に、
まだ二人が一緒にいたら、その時は思いきり笑って終わらないかと。
僕は、仮想世界での、薄くも濃い時間を終えたばかりだったのもあって、いつにも増して、ぽっかりと口を開いていた。
自分の台詞のせいじゃない、とでも言うかのように、
彼女は、突き刺した漆黒の一切れを、僕の口の中へ入れた。
それはいつになく、苦みが残り、やや焦げてもいた。
エスプレッソは、シナモンティーに変わっていた。
月が代わり、街はハロウィンのデコレーションと、クリスマスや正月のカタログを並べ始めた。
どんなにさりげなくコーナーで仕切っても、節操のない立体カレンダーを見せられているようだった。
外気は待っていたかのように肌寒くなり、曇天が続いた。
二人の距離もどこか空々しく、全く別の考え事をしているようだった。
僕が10年後の未来を描いている時、彼女は終末の喜劇について夢想していた。
彼女が言うには、この人生の最期の瞬間が、愛する人の顔を見ながら終われるのなら、それは幸福であり、
その瞬間の瞳には、とびきりの笑顔が映っていて欲しい、という事だった。
そうだ、、とは思う。
もし仮に、それが明日だったなら、どうだろうか。
別に、悲壮に包まれて終わる必要はないのかも知れない。
けどそれは、夢や、自由を味わい尽くしていたらの話だ。
いつもの突飛な会話に、すんなりと僕が乗れないのは、
まだ何も人生を味わえていないからかも知れないし、
それまで自分は彼女といれるのだろうかという、不安があるからかもしれなかった。
互いの存在が、まだそれぞれの人生に入りきれていない気がしている。
僕らはまだ年を跨いでいないし、互いに恋愛主義でもなかった。
自由に対する姿勢とか、順を追ったような関係性に縛られるのを拒むのは、どちらも一致していた。
僕らは一度も告白なんてしていないし、将来について語ったこともない。
明日、喧嘩別れしたって、それまでの思い出が尊いことに変わりはない。
けれど、不意にこの会話が現れてから、
その問いは稚拙なようでいて、核心でもあると思った。
僕は思いの外、自分がいかにも純粋な気持ちでいるのではないかという疑問と、
約束もなく"愛する"という言葉は、彼女の中で、一体どういう位置付けであるのかという、疑心に近い何かが交差していた。
僕は、シナモンの香りが苦手だ。
どことなく、明るさを演じているような恋人の笑顔と、
秋めいた曇り空のせいで、この数日、
それが言えないでいる。
電脳世界のクジラは、禍々しいほどの極彩色を放ちながら、
プラネタリウムの夜空を泳ぐ。
一方で、彼女が描く夜空は、その記憶や、夢から写し取られていた。
切り取られた神話や星座は、全部で48つある。
僕の好きな4番目の夜空には、神獣ケートスが、僕の脳内を港にして、異世界を行き来していた。
初めてその絵を眺めた時のイメージは、今も変わらず僕の中で生きている。
遅咲きのペインターは、それまで隠していた才能に引き裂かれたり、結合したりしながらも、これらの空を売らずに済んでいた。
というより、売れていたのは、もっと退廃的な、これらを生み出す過程の、無機質な叫喚の方だった。
僕は、この4番目の空だけは、
いつか自分が買うからと話していた。
僕は、彼女より少し遅れて生まれてきた。
このわずかな間に、世界は膜に包まれた。
だから、星座というものを、僕は映像でしか知らない。
しかし、もはや映像はリアルを越えて、過剰な景色を量産している。
知らないままの現実も、少しくらいなら、あってもいいと思う。
一つ、僕の見えていない現実があるとするならば、
僕が、シナモンを苦手だということを、
彼女が知らないワケがない、ということだった。
この世界は、花が咲くことはもうなくて、
あらゆる鉱物も、結合する有機体を失っており、特殊な技術で補っていたエネルギーも、その循環の終わりを迎えていた。
いつかこの星は抜け殻になって、マグマに恋しながら眠りにつく。
今日、飛び込んできた、ニューストピックの一つ目は、休日の下敷きに寝そべる僕の、視線だけを動かした。
"世界は縮んでいる"
どれだけ議論しようとも、起死回生を図ろうとも、僕らが現実を認識した時には、
そんな分かりきった一つの感想が浮かぶだけだった。
世界は、確かに縮んでいた。
僕らはそれを圧縮と捉える。
星を脱いで、どこかで生き続ける夢を見る。たとえ僕らが絶滅しようとも、別の次元に生きながらえようとも、
この世界の色彩は潰えて、思い出の中に咲いていく。
それを見越していたビル群は、明らかに、言われてみれば灰色だった。
それでもまだ、此処には人を人らしくする何かが眠っていると、大勢の人たちが信じている。
今月の僕の思考は、否が応にも死生観になってしまった。
死という概念に怯えながらも、その瞬間を望み、あるいは執着して、人は来世を見ようとする。
僕は随分前から、死への恐怖は消えていた。
身体は、たとえ無惨な死に方をしても、痛みが限界を越えさえすれば、
飽和した後に、変性してゆくのだろう。
快楽か、あるいは生温かい微睡みへ。
誰もが前世の終わりで知り、忘れてきた事だ。
忘れた後にも、今ある生の中での眠りや、
絶頂の直中に、仮の死をみている。
何千回、何万回と。
暗闇が心許ないのも、胎内で眠っていた記憶の忘却に過ぎない。
そんな僕も、愛する人の死は到底乗り越えらないだろうと思う。
また会えるかも分からない、覚えていられるのかも分からない、その壁を越えていってしまう。
だから、
一秒でも長く繋がっていたいと思う。
その虹彩の奥に、宿されていたいと願う。
魂が無限に分岐して、
それぞれの次元でひしめき合いながら、
誰もが永遠に生き続けるのだと、
神様が直接、僕に教えてくれるまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
