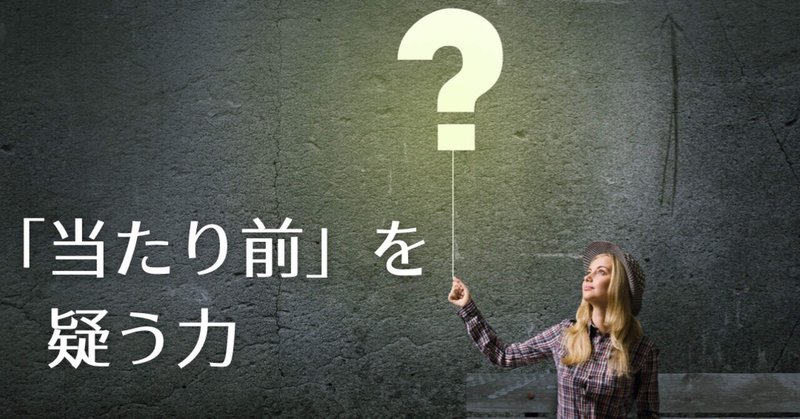
自分の当たり前や周りの当たり前への違和感って大事
本日から新年度のスタートですね。
曲がりなりにも「福祉の枠組みを外す」、なんてことを謳っているもので、新年度のスタートにあたって、自分なりにも初心に還る、という意味もあってこんな話を。
先日、新しい活動のための打ち合わせをしているときに、普段は福祉にあまり触れることがなかった方にふと「障害のある方が彼氏や彼女を作りたいと思ったり結婚したいと思ったり、セックス したいと思うって、そっかそうだよなと思った」っていう話をされて、僕自身も実はハッとしたんです。
僕らは自分の「当たり前」について実は結構無自覚です。
自分の価値観、生活環境の文化や風土、慣習になっていることを知らず知らず「当たり前」と名づけて無意識下に落としているのがいわゆる当たり前、ということなんだと僕は考えています。
だからこそ改めて自分や周りの「当たり前」というものを振り返ることも少なかったり、誰かの当たり前にかつては違和感を持っていたはずなのに、良くも悪くもそれに適応してしまい、気が付いたら違和感も感じなくなってしまったりしているんです。
今の僕にとっては障害の有無や生きづらさを抱えていたとしても選択肢がある、という環境を作ることの必要性はそれこそ「当たり前」なんですが、まだまだ一般的には障害者が恋愛や結婚、というものに踏み出すことも性に関心を持つこともないんだろうし実際難しいよなぁ、という感覚の方が当たり前なんだろうな、というのを改めて痛感したんですね。
人の支援をしていく上で、僕ら支援者は知らないうちに「自分や周りの当たり前」を押し付けてしまうことがあるのかも知れません。
当事者の方に「あなたは当たり前な人ではないんだよ」という無言のメッセージを突きつけることがあるのかも知れません。
僕らが当たり前、と思っていることは実は結構往々にして支援の対象の方にとっては全然当たり前、じゃなくてむしろそれが生きづらさに直結していることも少なくないんだと思います。
ちょうど新しい年度になって、新しい職場や新しい仕事に変わる人も少なくないと思うんですが、僕らも確か新しい環境に身を投じた時に、そこでは当たり前になっていることに違和感を感じたことがあると思います。
おかしいんじゃないかな、と思いつつも意見することができず結果それに順応して自分もそれを当たり前、にしてきてしまっていたこともあると思いますし、その違和感が解消できずにモヤモヤしっぱなしだったこともあると思います。
僕も当時はあまりそこまで深く考えたことはなかったんですが、この「違和感のセンサー」って対人援助職には実は結構大事な感覚で、当たり前に疑問を持つことってありきたりだけどやっぱり大事なんだと思います。
当たり前、ということにして無意識に置いてしまった感覚の中には、実は生きづらさを抱えている方を支えていくためのヒントになる「違和感」がいっぱい埋もれています。そしてつまりは無意識に置かれているからこそ目を向けられずにいる課題がたくさん「スキマ」として今も残っているんだと僕は思います。
当たり前を疑う、違和感のセンサーを大事にすること。
支援の上でも、そして新しい利用者さんやスタッフを迎え入れる者としても、改めて意識に置いておかないといけないな、と思います。
そんな話を喋っています。
※standfmのメンバーシップを始めました。
このメンバーシップでは、福祉の枠組みを外して、地域の福祉を前に進めたり、まちづくりに踏み出したりしているパーソナリティの、いわば奮闘記です。
- まちづくりについての話
- 支援について
- 福祉経営についてのマジ話
- 粗挽きアイデアや実験の共有
- よろず相談
- 新人支援者さん向け 養成機関じゃ学べない福祉の話
- 対談ラジオ
- たまには弱音
- 最近仕入れたちょっとした話
- 深夜ラジオ
こんな感じの話を思いついた都度、最低でも週に2〜3回、もしかしたらそれ以上、話したいと思ったときにランダムに配信します。ライブ配信もしたりするかもしれません。
福祉や地域をもっとワクワクするものにするためにあれやこれやと活動をしています。
こんな僕の配信に需要があるのかどうか分かりませんが、よかったら「応援」してください。
いただいた料金は、これからのソーシャルアクションに係る事に使わせてもらいます。
もしよければ応援よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
