
私たちは、なぜ、こうも早く、 援助者面(ヅラ)をするようになっていくのか?
※2013年に書いた文章をnoteに転記したものです
『枠組み外しの旅―― 「個性化」が変える福祉社会』著:竹端 寛氏を、読了した。
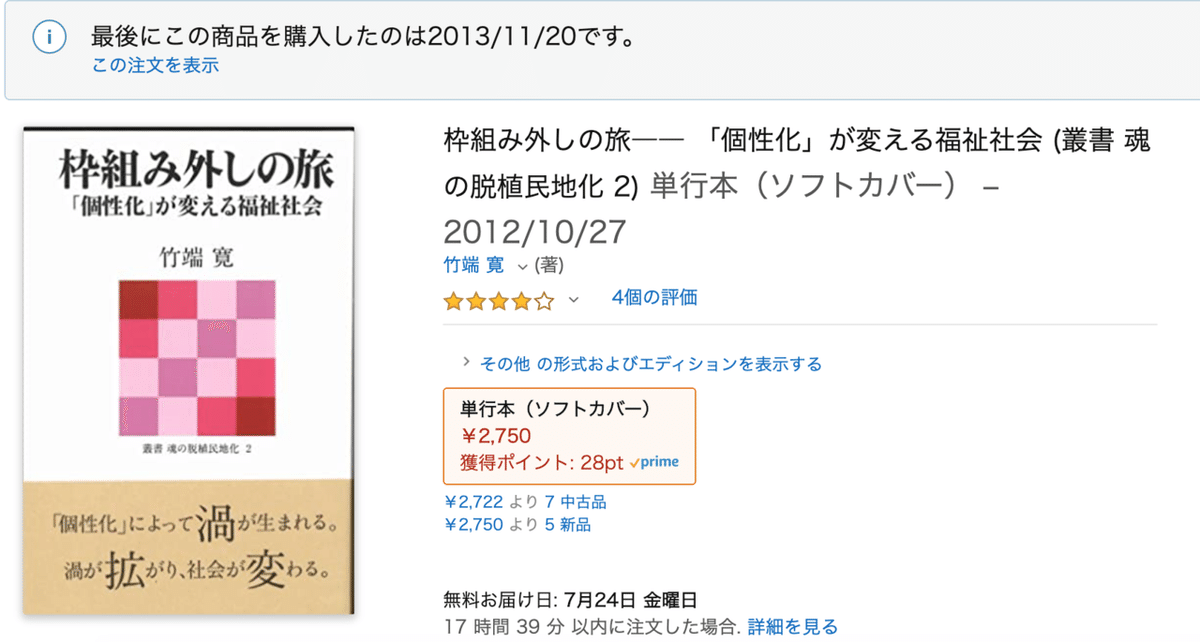
本作のテーマが、個人の問いが社会変革へ向かうプロセスを考える上で、
多くの人たちの思考の補助線になるのだろうな(私もその1人だ)と思いながら読んだ。
詳細の読後エントリは、後日書かせていただくとして、著作内にて語られていた「エクリチュール」という概念を、対人援助職に引きつけて、自分の経験と関連づけて記しておく必要があると考えた。
………………………………………………………………………………
目次:
1.「社会的に規定された言葉の使い方」=エクリチュール”という概念
2.「対人援助職というエクリチュール」は、対人援助職の初期設定OSだ。
3. 対人援助職の初期設定OSは保護膜であり、時と共に”垢”となる
4. 初期設定OS「対人援助職というエクリチュール」を書き換えるための”言葉”
5. OSを書き換え続けた未来にあるもの
………………………………………………………………………………
1.「社会的に規定された言葉の使い方」=エクリチュール”という概念
少し自分語りをさせていただきたい。
私は医療現場のソーシャルワーカーとして入職した。
新卒で現場に入り、最初に抱いた問いは、
「同業者たちは、なぜ、こうも早く、
援助者面(ヅラ)をするようになっていくのか?」
というものだった。
入職1ヶ月の新人援助者たちが、さも当然のような顔で、
現場の理不尽さ、制度設計のおかしさを語る。
その姿を、尊敬と嫉妬がおり混ざった感情で聞き眺めていた。
同時に、いつかどこかでだれかから聞いたような、”焼き増し”のようにも思えた。
「同業者たちは、なぜ、こうも早く、
援助者面(ヅラ)をするようになっていくのか?」
こたえは簡単だった。
そうでなければ、現場に立ち続けることが難しいからだ。
現場で、対人援助職としてのカラダを稼働させ続けるためには、
「自らを”同期”させる先としての言語」が必要なのだ。
そのことに気づいた時には、自分も、一丁前の援助者面(ヅラ)になっていた。
新卒だろうが、他領域からの転職者だろうが、援助者であるという社会的肩書きを得た瞬間に、対人援助職として相応しい社会的な振る舞いや言語もセットでインストールされる。
"対人援助者として相応しい振る舞い、言語"
俗にいう業界の内輪言葉が、その最もたるものだ。
その言葉をしたり顔で使えなければ、同業者の仲間入りができない。
端的に言えば、そんなことだ。
これを、エクリチュール(社会的に規定された言葉の使い方)と呼ぶ。
そして,私は、エクリチュールを「自らを”同期”させる先としての言語」と意訳した。
竹端氏の著作内で、内田樹氏の街場の文体論の一部を抜粋されている。
私も、内田氏の同作を読み、上記「エクリチュール」の概念を知った。
竹端氏の著作でも引用があるが、以下同様の箇所を引用する。
………………………………………………………………………………
「エクリチュール」というものが存在する。これは「社会的に規定された言葉の使い方」である。ある社会的立場にある人間は、それに相応しい言葉の使い方をしなければならない。
発声法も語彙もイントネーションもピッチも音量も制式化される。さらに言語運用に準じて、表情、感情表現、服装、髪型、身のこなし、生活習慣、さらには政治イデオロギー、信教、死生観、宇宙観にいたるまでが影響される。
中学生2年生が「やんきいのエクリチュール」を選択した場合、彼は語彙や発声法のみならず、表情も、服装も、社会観もそっくり「パッケージ」で「やんきい」的に入れ替えることを求められる。
「やんきい」だけれど、日曜日には教会に通っているとか、「やんきい」だけれど、マルクス主義者であるとか、「やんきい」だけれど白川静を愛読しているとかいうことはない。
そのような選択は個人の恣意によって決することはできないからである。エクリチュールと生き方は「セット」になっているからである。
バルトが言うように、私たちは「どのエクリチュールを選択するか」という最初の選択においては自由である。けれども、一度エクリチュールを選択したら、もう自由はない。
私たちは「自分が選択したエクリチュール」の虜囚となるのである。つまり、私たちの自由に委ねられているのは「どの監獄に入るか」の選択だけなのである。
内田樹氏:「街場の文体論」より(氏のBlogでも読めます)
………………………………………………………………………………
2.「対人援助職というエクリチュール」は、対人援助職の初期設定OSだ。
上記を踏まえ、以下、私が考える
「対人援助職というエクリチュールを纏うこと」について記していく。
現場1年目、新人研修での出来事。
研修の内容については、本旨ではないのでここでは触れないが、
私は、恥ずかしながら、この研修を、数回でドロップアウトすることになる。
ただただ、悶々としていた。何かがおかしいと。
1ヶ月前は学生だった新人たちの会話…
「おたくの病院は、気管切開の人の受け入れはOKですか?」
「ケアマネが動いてくれなくて困る」
「このケースは、危機介入的には…」
今聞けば、なんてことはない、日々現場で交わされるような、内輪言葉の応酬だ。だが、2ヶ月前まで学生だった私は、なんだかどうしようもない、途方のなさ、強烈な違和感を感じた。
この違和感の集合体こそが、新卒の援助者たちが、こぞって一斉に
「対人援助職というエクリチュール」を身につけたことによる、
なんともいえない圧迫感と、そして孤独感だった。
今思えば、私は、対人援助職というエクリチュール(社会的な振る舞いや言語)を纏うことに、少しばかりの時間的抵抗をしたかったのだろうと思う。
だが、対人援助職というエクリチュールを纏うことに抵抗した
私の現場一年目は散々なものだった。
気づき、傷付き、疲弊する。摩耗する精神。
対人援助職というエクリチュールを纏うことは、
対人援助者としてのカラダを守ることに寄与する。
対人援助職としてのカラダを保護するための防具を
身に纏わずに立つ現場は、私を消耗,摩耗させた。
3.対人援助職の初期設定OSは保護膜であり、時と共に”垢”となる
だが、今だからこそ言えるのは、対人援助職というエクリチュール(社会的な振る舞いや言語)は、援助者自身のカラダを覆う”保護膜”くらいに考えておくべき、ということだ。
対人援助職であると名乗った瞬間にインストールされる社会的な振る舞い・言葉というエクリチュールが、保護膜として援助者の身体を守る。
しかし、纏い続けると、”垢”として堆積し、皮膚となり、皮膚呼吸ができなくなる。
皮膚呼吸のできない援助者のカラダのセンサーは鈍り、弛緩していく。
弛緩し、皮膚呼吸のできなくなった援助者のカラダは、いずれ窒息する。
それゆえ、初期設定として与えられた「対人援助職というエクリチュール」にしがみつくしかなくなる。そうしないと、援助者としてのカラダは稼動しなくなってしまうからだ。
「対人援助職というエクリチュール」という保護膜は、耐久期間を過ぎ、”垢”となる。”垢”は、援助者の皮膚呼吸を不可能にし、窒息させる。
それは、「援助者としての問い」の発露を封印させる、ことと同義であるように思う。
初期設定としての援助者を保護する「対人援助職というエクリチュール」は、長く身に纏い続けることで、援助自身を窒息させ、”問い”の発露を妨げてしまう。個人の人生に関わる支援がルーティンワーク化し、サラリーマン化することは悪いことではないけれど、それがプロフェッションと言えるのかどうかには疑問だ。
4.初期設定OS「対人援助職というエクリチュール」を書き換えるための”言葉”
私が、過去エントリ「認定社会福祉士制度という名の”内輪のパーティゲーム”はいつ終わるのか?」において、日本のソーシャルワーク業界が、リソースを投入すべきは新人〜中堅以前の人たちであり、5年目以上では遅すぎると述べたのは、本エントリにも関連する。
初期設定として与えられた「対人援助職というエクリチュール」(つまりはコンピュータでいうOS)を、アップデートする時を逸すると、弛緩し、皮膚呼吸ができなくなった援助者としてのカラダは窒息への道程を辿るしかなくなるように思う。
「対人援助職というエクリチュール」を、アップデートするには、
”自らが紡ぎだした、自らの価値観に連動する言葉”が必要だ、というのが現時点での暫定解である。
耐久期間の過ぎた「対人援助職というエクリチュール」という保護膜を1枚、1枚剥ぎ取り捨てる過程に沿った、言語化のプロセスを経ることが、援助者としてのカラダの窒息を防ぐ。
「対人援助職というエクリチュール」を纏うことを可能な限り抵抗し、耐久期間切れの保護膜を、剥ぎ取り、自らの言葉でOSをアップデートすること。
そのためには、自分には、”問い”が必要だった。そして、私の現場で得た”問い”は、目の前の現象や当たり前の概念を疑うことからはじまった。
勇気を出し、「対人援助職というエクリチュール」を1枚1枚、剥ぎ取る。
初期設定のままのOSで稼働し続け、窒息したくない故にそうするほかなかった。
5.OSを書き換え続けた未来にあるもの
問いの立て方は、社会の捉え方に近しい。
だが、「対人援助職としてのエクリチュール」の溢れた場に身をおくことで、問いの射程距離はどうしても短くなる。
(この患者さんを1日でも早く退院支援するにはどうするかということに頭が埋め尽くされると、問の射程距離を伸ばすことはとても大変になる)
援助者としてのカラダを守る保護膜としての、社会的な振る舞いや言語という「対人援助職というエクリチュール」は、定型的な同一のOSを搭載した対人援助職を量産することには寄与する。
けれども、保護膜として機能した対人援助職というエクリチュールは、長く纏うことで、対人援助職のカラダを、初期設定からの書き換え・アップデートを不可能にするカラダにしてしまうこともまた事実であるように思う。
竹端氏の言葉を借りれば、
個人の”問い”はときに、既存の社会システムに向けられ、
それが、大きな渦を生み、社会変革へのプロセスを生み出す。
そのためには、耐久期間の過ぎた「対人援助職というエクリチュール」を剥ぎ捨て、疑問に真っ向から、自分の言葉で対峙すること。今のところ、それ以外の援助者のカラダの窒息を防ぐ術を、私は知らない。
自らを”同期”させる先。
最初は、それが、初期設定としての「対人援助職としてのエクリチュール」であってもいい。
だがしかし、自身を含め、中堅に足を踏み入れた者たちはみな、
「問いによって、社会に自らを”同期”させる」ことに、自覚的であるべきだ。そのように思う。
同時に、「対人援助職としてのエクリチュール」自体を更新していくのも、中堅以降の人たちに課せられた大切な仕事のひとつなのではないだろうか。
法人事業や研究に関する資金として大切に活用させていただきます!
