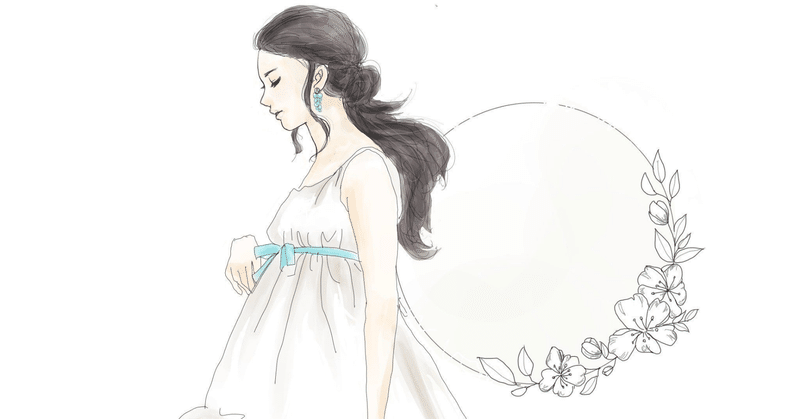
太陽の種を目の当たりにしてるかもしれない
ここ最近、「女性」に焦点をあてた話を聞くことが多い。仕事の話でも、恋愛の話でも、プライベートの雑談のなかでも、大きく括ると「女性」に集約される。
女性として、不遇な社会人生活を送ってきたから、自分よりも下の世代にはそんな思いをさせまいと奮起する話。男性よりも女性のほうが繊細で、そして気遣いができるという話。ただ、女性は移ろいやすく不安定で調整が難しい。だからこそ、そんな女性のためになる何かをしたいという話。
そういった話を聞くと、私の中でかつて聞いた鮮明な一文が頭に浮かぶ。
女性推進運動家の祖とも言われる、平塚雷鳥が書いた一文だ。
元始、女性は実に太陽であつた。
女性は、太陽であった。
この当時の女性といえば、働くことはもちろん、選挙権もなく、場所によっては女人禁制を強いられ、家を守ること以外のことは許されていなかった。子孫を残す、そして育てる。男性が働きやすく、生きやすい環境を整えることが女性の仕事とされていた。
そんななか、その状況に異を唱えたのが平塚雷鳥だ。この一文の後半も、私は好きなんだよね。
元始、女性は実に太陽であつた。真正の人であつた。今、女性は月である。他に依つて生き、他の光によつ て輝く、病人のやうな蒼白い顔の月である。
偖(さ)てこゝに「青鞜(せいたふ)」は初声(うぶごゑ)を上げた。現代の日本の女性の頭脳と手によつて始めて出来た「青鞜」は初声を上げた。
女性のなすことは今は只嘲りの笑を招くばかりである。私はよく知つてゐる、嘲りの笑の下に隠れたる或(ある)ものを。
この文章は、平塚雷鳥が指揮をとり、女性だけで作られた文芸誌「青鞜(せいとう)」の初出版に寄せられた文だ。
なんと、26歳。私と同い年あたりで女性思想家として社会運動を先導、こんなに力強い文章を書いていた。
元始、女性は実に太陽であった。
今、その想いはまさに近づきつつあって、たくさんの太陽が社会にはある。もちろんもっともっと改善しなければならないこともあるかもしれないけれど、その一歩となりそうな太陽の種を私は目の当たりにしてるかもしれないなと思う。
”終わりよければすべてよし” になれましたか?もし、そうだったら嬉しいなあ。あなたの1日を彩れたサポートは、私の1日を鮮やかにできるよう、大好きな本に使わせていただければと思います。
