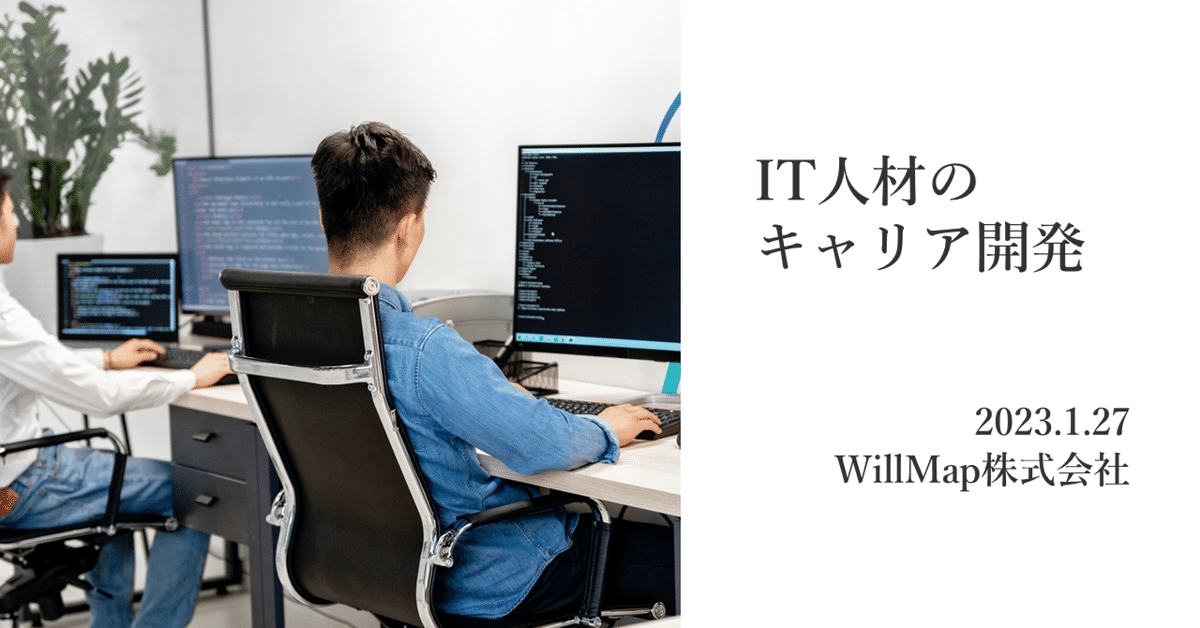
IT人材のキャリア開発
私が長らく軸足を置き続けてきた人事の領域というものは、新しい概念・言葉が頻繁に出てくるものの、ベースとなる理論や考え方は変わらず、長く居ればいるほど知見が蓄積され、長く仕事をし続けられる領域と言えます。恐らく、他の多くの分野も同じことが言え、継続的に知識や経験を積み重ねていけば、その分野に居続けられるでしょう。
「35歳定年説」と人材不足
しかし、IT分野は違います。環境変化や技術革新の速度は頗る速く、長くで働くことが難しいと言われ「35歳定年説」という言葉があるくらいです。そして、そのIT分野を担う人材は、現在でも不足しているにも拘わらず、2030年には最大約79万人不足(2018年の約3.5倍)すると見込まれ
(※)、人材人材不足がより深刻化する分野とも言えます。
企業にとっては、今後、ITの専門スキルを持った人材獲得がこれまで以上に難しくなると考えられ、現社員一人ひとりを大切にし、より長く活躍してもらえるような支援をしていく必要が出てくるでしょう。
※)『IT人材需給に関する調査』(みずほ情報総研)
IT人材に長く活躍してもらうには?
では、IT人材により長く活躍してもらうにはどうしたら良いでしょうか?一つの答えが示されている論稿を紹介したいと思います。法政大学吉田康太氏によって書かれた『IT人材の長期戦力化に向けたキャリア開発』という論文がそれになります。この論文では45歳以上のIT人材を調査し、それまでのキャリアの特徴を分析しています。そしてそこで発見された特徴は次のようなものだったと述べています。
キャリア早期(~5年目)に一つの担当分野から他分野へ領域を広げていく経験をし、さらに、リーダー格となるなどし顧客ニーズを仕様に落とし込む上流工程の経験をすること。さらにキャリア中期(~11年目)には、こ れまで経験しなかったような未知度の高い難しい業務を経験する。といったものでした。20代、30代を通じてこういった柔軟な職域移動をしていくことが長期に活躍する上で大切だと書いています。
顧客折衝経験の重要性
これの考察を見ると、自分の専門分野を持ちながらも、ITという範囲の中で、縦横両方にキャリアを拡大し、知識の幅を広げることが大切と言えるでしょう。また論文では移動の中でも上流工程、つまり最初の対顧客折衝の経験の重要性を強調しており、この経験が本人に対応の幅を持たせ、技術進歩があったとしても、戦力として活躍できる下地を作っていると言えるかもしれません。
会社の事業拡大がキャリアを支援する
この論稿を踏まえるなら、企業が若手のキャリアを考えるとき、一つの担当分野に留め置かず、戦略的に担当分野を変え、早期に昇進させていくことを検討していくことが必要です。そして社員が様々な経験を積めるよう、企業としても積極的に事業拡大(上流工程への進出等)を行っていくと同時に、社員一人ひとりのこれまでの事業ドメインに拘らない新たなチャレンジを後押ししていくことも大切になるでしょう。
