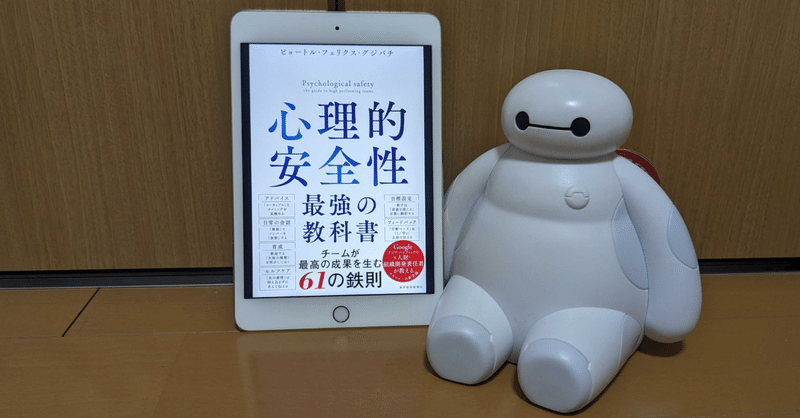
#16_心理的安全性に最強の教科書が登場!?
こんにちは、ライトフライヤースタジオで主にエンジニアの組織作りを担当している井田です。自称「心理的安全性おじさん」的に、注目の1冊が先月発売されたので、早速拝読しました!
その1冊がこちら
人材育成や組織開発などの分野で著名な、元Googleのアジア・パシフィック人材・組織開発責任者のピョートル・フェリクス・グジバチさんが、Googleでの経験や、これまで関わってきた会社での経験を通して得られた知見をぎゅっと詰めこんだ1冊となってます。
心理的安全性は、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソンさんが提唱された概念で、今から10年ほど前に、Googleが「プロジェクト・アリストテレス」の研究成果の中で重要性について報告されたことで世界中で話題となりました。
心理的安全性という言葉が日本でも脚光を浴びて以来、従業員のエンゲージメントやチームのパフォーマンスのさらなる向上を目指して、私たちライトフライヤースタジオも、心理的安全性の確保を大切にしたマネジメントに取り組んでいます。
人材・組織マネジメント関連の分野で近年話題となっているものは、欧米の研究者や著名人から発信された情報がほとんどであるように感じます。一方、国が違えば、歴史的背景や文化、組織に集まる人々の志向や属性も様々です。どこかでうまくいった手法だからと言って、単純に輸入しただけでうまくいくような、万能の特効薬があるわけでもないですし、多くの方が苦労されている分野ではないでしょうか。
「心理的安全性はGoogleだから効果があったのではないか」
「意識が高い人たちばかり集まっている組織でないと実現できないのではないか」
といった疑念を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。
でも、もしかしたらそんな方でも本書は期待を持てるかもしれません。Googleにおける成功事例だけでなく、その後も数々の国内外の企業を見守られてきたピョートルさんが、日本で20年間働いた経験を元に、とりわけ日本で働くマネージャーに向けて書いてくれた教科書だからです。
さて、本書は私たちの組織でも教科書にもなりえるでしょうか。
一個人の感想ですが、心理的安全性を学ぶ教科書として申し分ないと思います。
小難しい理論も挟まず、わかりやすい言葉で綴られていて、欧米の書籍の翻訳書と比べても読みやすく、初学者にもとっつきやすそうです。
そして、「阿吽の呼吸」のような日本的な美徳や価値観などにも触れつつ、その落とし穴についてもカバーされていたり、上で期待したような内容もしっかりと盛り込まれています。
初版から100年近く経った今もなお名著として名高い、デール・カーネギーさんによる「人を動かす」の中でも基本とされる「人の立場に身を置く」の姿勢は、現代のマネジメントでも変わらず必要とされ続けています。
表現は違えど、
「自分起点ではなく、メンバー起点で話を聞く」
といった表現を使って、そのような普遍的な課題も取り扱いながら、これからの時代に重要なダイバーシティを実現するために必要な現代的な課題に対しても
「異なる価値観に対して寛容であり続ける」
のような形で対応しています。
私がこれまで管理職向けの研修や書籍などを通じて学んできた、傾聴や対話、相互理解に向けた自己認識や自己開示など、マネージャーに求められる対人スキルのいろはについて、丁寧に広くカバーされています。
そのように、本書はマネージャーが学ぶ最初の教科書として価値ある1冊になりそうです。
個人的に気に入ったのは
「人にやさしく、結果に厳しく」
のフレーズです。
「人」と「タスク」を区別して、ネガティブフィードバックは結果に対する指摘に閉じて、人格まで否定したような伝え方をしないための教訓ですが、私はこれまで同様の課題に対して、幼少期にテレビで見た時代劇の決め台詞
「罪を憎んで人を憎まず」
の精神を、「大岡越前の原則」と名付けて度々引用させていただいてました。ただ、失敗や課題を「罪」という言葉に読み替える必要があるのがあまりにも乱暴で、それこそギルティに感じてややしっくりこない部分がありました。
「人にやさしく、結果に厳しく」はキレイな表現で、読み替えもなく素直に使えそうなので、今後は是非そちらをパクらせて引用させていただきたいと思います。
本書は心理的安全性についての理解を深めたいとか、チームのパフォーマンスを向上させるためのチームビルディングについて考えを整理したいという方にお薦めできます。
一方で、リモートワークなど働き方の多様化について触れた部分は若干はありますが、リモート越しのマネジメントについて特に踏み込んだ内容はありません。また、会議のファシリテーションや、工数管理といったようなプロジェクトマネジメントなどの実務については本書では触れられていませんので、1冊で最新のマネジメント業務全体をカバーできる訳でもないということは誤解のないように一応付け加えておきます。
実は、つい先日、一回り以上年齢の離れたメンバーから
「あの時、〇〇って言われて、めちゃくちゃムカつきました。」
ってめちゃくちゃまっすぐな言葉をもらいました。
おかしな話かもしれませんが、役職などの肩書きや年齢差のせいで変な忖度や萎縮ムードを作ってしまわないかと普段から多少気にかけていたので、ある意味救われた気持ちでした。(多少アルコールが入ってお口のガードにデバフがかかっていたのかもとは思いつつ)関係性の悪化や対立を恐れることなく、ネガティブなフィードバックもちゃんとできる環境なんだって再確認できたことが嬉しかったし、配慮にかけた自分の言動に気づきを与えてくれた彼には何より感謝しています。
ライトフライヤースタジオではバリューとして掲げている3R(RESPECT、RETRY、REFLECT)がよく浸透していることを感じます。中でも「RESPECT 互いを尊重し、わかりあう」のバリューを体現されている方が多く、自然と心理的安全性が確保されやすい環境になっています。
本書の面白かったポイントの1つとして、身に覚えがあるわーって内容がたくさんあったこともあります。あの人と仕事した時は本の内容の通りで、確かに心理的安全性に課題があったなーと、いくつか過去の苦い思い出が蘇って妙に納得してしまったり、ライトフライヤースタジオではここは実現できてて良かったなーと再確認するような内容もありました。本書をきっかけに、いずれの経験も心理的安全性の理解を深める意味のあるものだったと思えるようになりました。
「心理的安全性 最強の教科書」
チームビルディングの振り返りに、この春1度読んでみてはいかがでしょうか。
最後に勢いで告知ですが、そんな意見を言い合って、お互いを高め合える強いチームを作って、一緒にゲームを作りませんか!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
