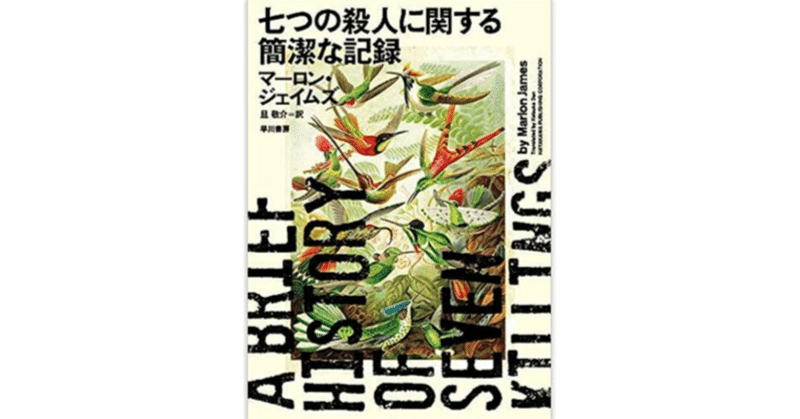
『七つの殺人に関する簡潔な記録』 マーロン ジェイムズ (著), 旦 敬介 (訳) ボブマーリー暗殺未遂事件を追いかけるその向こうに、ジャマイカ社会の深部暗部、さらには米国・世界の構造まで見えてくる。本文700ページ二段組の超重量級小説。
『七つの殺人に関する簡潔な記録』
2019/6/20 マーロン ジェイムズ (著), 旦 敬介 (翻訳)
Amazon内容紹介
1976年12月3日、レゲエ・スターにしてジャマイカの英雄ボブ・マーリーが襲撃された。その日は、高まる政治的緊張を鎮めるためのコンサートの2日前であり、総選挙が控えていた。ボブ・マーリーは一命を取り留めるものの、暴力は加速する。国を二分し、やがてアメリカ合衆国をも巻き込んでゆく。襲撃したギャング、裏で操る政治家、CIA工作員、アメリカ人記者、事件を目撃してしまった女性、さらには亡霊まで、70名以上の人物が闘い、血に塗れながら己が見た真実を語る。現実の事件をもとに、語られざる歴史をつむぐ途方もない野心、禍々しくも美しいディテール、多彩に鳴り響く音楽的文体に、世界の文学ファンが狂喜した!ジャマイカ出身の作家では史上初のブッカー賞を受賞した巨篇。
ここから僕の感想
しむちょん、読んだよー。読書師匠しむちょんに教えてもらって、読み始めたのはいいが、まるまるひと月かかってしまった。二段組700ページある超重量級(ほんとに重くて、寝っ転がりながら読もうとすると重くて持っていられない)の小説でした。いや、内容も超重量級、「ブッカー賞に外れ無し」、傑作でした。全然、簡潔ではない。長いし、複雑極まる、社会全体、世界全体を小説の中に描き切ろうとした巨編でありました。
ジャマイカというと、レゲエと陸上短距離ウサイン・ボルトくらいしか頭に浮かばない状態で読み始めたので、いろいろ知らないことが出て来て、例によってWikipediaで「ジャマイカ」と「ボブ・マーリー」を読んでにわか勉強しながら読み進めた。小説内に出てくる首都キングストンの中の、ふたつのギャング団の本拠地の街の名前を入れてグーグルアースで見てみようとするが出てこない。翻訳者のあとがきを読むと、ギャング団については本当はもっと複雑で、人命も地名も創作、実在のものではないのだそうだ。出てこない筈だ。しかしまあ、「ジャマイカ、キングストンの危険地帯在住・日本人」のYouTubeなんかを見て、現地の雰囲気(現在のだけど)を見てみたりもした。
翻訳者 旦敬介氏のあとがきが、すごくよく出来ていて、「小説が始まる前のジャマイカについての前提知識の整理」と「この小説の構造」それぞれがきれいにまとまっている。それも参考・引用しながら、書いていこうかな。もしこの本を読もうとする人、ネタバレを気にしないなら、「ジャマイカの前提知識」部分だけでも読んでから読み始めた方が分かりやすいかもしれない。
まず、これは僕がほぼ無知でお馬鹿さんなのでびっくりしたのだが、ジャマイカ人全員がラスタファリではない。ジャマイカは元イギリスの植民地で、今も英連邦の一員。元首は英国王。そういえば、エリザベス女王が死んだ後、「英連邦から抜ける、抜けない」っていうのがニュースになっていたな。なので、ほとんどがプロテスタントなんだそうだ。ラスタは5~10%くらいしかいない。みんながドレッドヘアなわけではありません。そりゃそうか。
で、黒人奴隷が先祖の黒人が90%、混血のムラートが6%くらい。あと、インド系とか中国系とか中東系とかがほんのすこしずつという人種民族構成。元支配層の白人との混血のムラートの方が上流、中流階級、つまり肌の色が少しでも薄い方が上流中流で、肌の色がより黒いということは、下層階級であるという「肌の色のグラデーションが階層を表す」という、ほぼみんな黒人なのに肌の色と社会階層が相関している。この「肌の色」への言及は小説中に何度も出てくる。
この小説でさらに大事なのは、ジャマイカの言語。学校教育では、非常に正統な(現代のイギリス英語や米国英語より格式の高い古めかしい)英語教育されている一方、実際の日常会話はパトワという、植民地言語、英語ベースで発音や単語が簡略化され、かつスペイン語などの語彙が混ざった現地語が話されている。初等教育から学校は英語なので、高等教育を受けていなくても、中学高校まで学校に通っていれば、きれいな、米国人が聞いても「すごく上品」な英語が喋れる。というのがこの小説を読む上で、結構大切なポイントになる。
ものすごくたくさんの登場人物が各章、各節の話者となるのだが、それぞれがどんな肌の色でどんな言葉をしゃべるかで、社会階層や、その中でどういう志向を持っているか(ギャングでもきれいな英語を主にしゃべる人もいるし、パドワしか喋らない人もいる。)
そしてWikipediaによると、世界でも三位の殺人の多い国(上位はあとコロンビアと南アなんだそうだ)で、その主役のギャングたちがこの小説の主要登場人物たちの多くを占める。
しかし、この小説、別に、ギャング小説ではない。凄惨なギャングの抗争、殺人も描かれるが、それはこの小説の一部分であり、なぜならそれはジャマイカと言う国、社会の一部分であるからだ。この小説はもっと大きなスケールでジャマイカという国、社会の成り立ちを描いていく。ただし、高所大所からではなく、多くの人の語る言葉によって。
1962年にイギリスから独立した後、名前とは反対の保守政党・ジャマイカ労働党(JLP)と、左派政党・人民国家党(PNP)の二つが対立する。イギリスの植民地から英連邦国家になったので、議院内閣制である。ちゃんと選挙は機能している。有権者の大半は貧困層である。なので、両政党が貧困層を支援する。ちょいとあとがきから引用する。
〈それぞれの政党が、市民の大部分を占める貧困層の支持を集めるために、ゲットーの住宅建設や、環境整備策(トイレや浴室の設置など)を競うようになった。それに伴って、キングストンのゲットーは、政党のイデオロギーとはほぼ無関係に、ただ単によくしてくれた政党の側を支持するようになり、ゲットーは支持政党によって細かく色分けされていく。たまたま政権を取った側の党は自党を支持する地区の整備を優先したり、その住民に優先的に仕事を斡旋したりして、敵対する地区を放置するなど、えげつない差別的扱いを繰り返したため、政党の抗争は、ゲットー間の抗争になっていく。また、各地区の町会長のような役割を果たして利権の分配や票のとりまとめなどをおこなっていた地区のボスたちと政党の癒着が進んで、ボスたちの力が強まり、その配下の男たちが愚連隊化していく。〉
というわけで、ギャングというのが、「政党の争い」→「町会長的ボス」→「若い鉄砲玉的愚連隊」という構造になっているわけだ。
そして冷戦、キューバが共産化した時代、より左翼的なPNPが政権を取る。
〈72年にPNPが選挙に勝ち、カリスマがあって貧困層の人気の高いマイケル・マンリーが総理大臣の座につくと、農地改革などの社会主義的政策を導入しようとし、キューバへの接近も進めたため、この政権を失墜させるべく、CIAが盛んに暗躍し始め、国内政治に介入してJLPの支持勢力に武器や訓練を提供し始めた。そのためマンリーの再選をかけた1976年の総選挙に地区間、ギャング間の抗争は複雑化し、急激に激化することになった。〉
つまり、さっき書いた「政党の争い」→「町会長的ボス」→「若い鉄砲玉的愚連隊」という構造の、さらに背後に、CIA、アメリカの存在がいるのである。
ちなみに産業でいうと、ジャマイカはボーキサイト(アルミの原料)の生産量が世界第四位であり、これがほぼ国の経済を支えている。コーヒーのブルーマウンテンはジャマイカの山で、世界最高級品腫ではあるが、それ以外のコーヒーの生産はあんまりなくて、産業として大きいわけではない。(ちなみにブルマンコーヒーの大半は日本が輸入しているそうだ。)で、ボーキサイト採掘は当然アメリカの大企業が独占的にしていて、それが共産化国有化されちゃうんではないか、ということもあって、CIAはPNP、キューバ寄りになりそうな政権を妨害するわけである。
で、ちょうどその総選挙の1976年12月、ボブ・マーリーは「政治的には中立」という立場で「スマイル・ジャマイカ」という無料コンサートをキングストンの公園で企画するのだが、ボブ・マーリーの出身地トレンチタウンはPNPの配下にあったし、政権側は政治利用する気まんまんだったわけだ。
というわけで、ボブマーリーの暗殺事件の裏には、両地区のギャングの対立、その裏に、二大政党の対立、その裏に米国CIA、と、当然、そういう事情が複雑に絡んでいたわけである。
でもまた、これが「暗殺成功」ではなく、ボブマーリーも胸を撃たれたのに生きていて、銃撃された直後なのにコンサートにも出演するのだな。「なんで重武装したたくさんのギャングたちが丸腰の歌手を襲撃したのに、失敗したの」というのも、かなり深い謎なのである。このあたりに、この小説は、小説的想像力で迫っていくのである。
ギャングの平和協定とピースコンサート
そして、この1976年の「スマイルコンサート」後、対立するギャングの親分同士が、二人とも警察に捕まって監獄に放り込まれていたのだが、監獄の中で手打ちをして「平和協定」が結ばれる。
この二人の親分、両方と話ができるボブマーリーは、二年後の1978年に、今度はギャングの平和協定を国民みんなに伝える「ピースコンサート」というのを企画して、ジャマイカに戻ってくるのだな。ギャングだけじゃなくて両方の政党の党首も、このコンサートには顔を出すのである。
これだけだとめでたしめでたし、みたいだが、「町会長的ボス」よりひと世代若い片っ方のボスが、それが気に喰わないわけだ。ここから、この若いボスが、上の世代のボスをかたづけて、その後の麻薬ビジネス、コロンビアの麻薬をマイアミに運び、ニューヨークでも麻薬ビジネスを拡大していく、という展開をしていくのである。
はじめにも書いたけれど、国籍も社会階層も性別性的嗜好もも様々なものすごくたくさんの話者人物が登場して、この複雑な話を進めていく。
CIAのアメリカ人は、ジャマイカ以前には南米でも、その後はユーゴなどでもアメリカの陰謀謀略に深くかかわった人物なのだが、妻と子どもを連れての「駐在員」みたいな雇われ人的悲哀を漂わす人物として描かれる。妻は早く本国に戻りたいと不平不満をいい、子どもの送り迎えをし、そういう家庭生活をしながら、国家謀略を淡々とこなしていく。
ジャマイカの中流家庭の若い女性は、ひょんなことからボブ・マーリーと一夜をすごし、ボブ・マーリーの家の前を「もういちど会えないか」とうろうろしているうちに襲撃事件の目撃者となってしまい、ギャングに追われるのではないかという恐怖から、その後、点々と名前を変えながら逃げ続けることになる。彼女はきれいな英語をしゃべる人である。
ギャングの鉄砲玉の若造たちも、ほんとうに最底辺の暮らしの中で、そのまま使い捨てにされていくものもいれば、そこから抜け出そうと学業をがんぱって、もうすこしでぬけだせそうになるのに、警察に(ジャマイカ警察はもうめちゃくちゃである)、無実の罪で刑務所に放り込まれ、やむなくギャングになってしまったものもいる。
ほんとうにいろんな人物の一人称の語りによって、ジャマイカ社会の複雑さ、絶望的な状況が塗りこめられていく。
読んでいるうちに、僕の頭の中は、ここ最近ずっと考えている、「人間はどうして、いつまでも戦争をやめられないのだろう」という問いに向かってしまう。
この小説を読んでいる期間、大河ドラマ「どうする家康」で、家康の妻、瀬奈が徳川と武田の和平交渉をまとめ上げようとする。それがいったんは実を結ぶかと思われた。が、武田勝頼が、「いや、この世は戦である。戦こそが人生だ」みたいなことを言って和平をぶち壊してしまう。という展開をしていた。
この小説も、絵空事のような、奇跡のような、ギャング団同士の和平交渉、平和協定が、ボブ・マーリーの仲介もあり、一瞬、成立する。そのごく短い期間の平和、そのときどんな希望をジャマイカの人が抱いたかが描かれる。
しかし、この小説の主要人物、ギャングの若き野心家ボス、ジョーズィ・ウェルズは、武田勝頼同様に、「戦こそがスラムの、ジャマイカの現実だ」と、平和協定をぶっ壊していく。そこからジャマイカのギャングは、コロンビアから米国への麻薬ビジネスの中での重要な役割を果たす方向に突き進んでいく。そして世界最悪の殺人の応酬を、ジャマイカの中だけでなく、アメリカの中でも繰り広げるということになるのである。
この若頭、極めて知的な人物として描かれる。正しい英語をしゃべり、冷徹に現実を見つめ、考える人物なのである。
彼が平和協定を否定する言葉を引用して、感想をおしまいにする。僕はこの本を読んでいる間も、戦争について、悪について、いろいろ考えてきたのだけれど、どうしようもない悪と戦争がこの世界に存在し続ける理由を、この若いボスはこういう言葉で語るのである。「良いと悪い」についての若いボスの言葉。
ちょうど、この平和だの愛だのというおふざけに、まともな感覚を持った人間がみんな、いいかげん飽き飽きし始めたころだ。コパ―が丘の上から下りてきたころだ。まるで誰もが、というのはオレのことだが、平和の前にやつがどんなひどい腰抜け野郎だったか、男を殺した後にその女を強姦してまわったりしていていたことを忘れてくれると思っているみたいに。パパ=ローまでもが、あのミスター「女を強姦する男は全員ぶっ殺す」までもが、コパーを見逃して、ワイレカ・ヒルズに上がるのを許した。いい時代は誰かにとっては悪い時代だ、だから、これから悪い時代を経験しようとしている人は、新しくやってきたアメリカ人が臨界質量と呼んでいるものにいずれ到達する。臨界質量に達した大衆は、いつも男に殴られている女が気づくのと同じことに気がつく。そりゃあものごと悪い。でも、それが自分にとってなんとか機能しているなら、いじらないでおけ。この種の悪さなら、あたしらはみんなよく知っている。もっと良いもの?良いってのはもちろんいいけど、でも、良いっていうのは誰も経験していないから知らない。良いってのは亡霊みたいなものだ。良いからって、ポケットに金が入るわけでもない。ジャマイカは悪いほうがなんとかなるんだ。なぜなら、この種の悪さはなんとか機能するから。だから、最近のいいヴァイブレーションとかなんとかのせいで、次の選挙が危うくなってきたのを見て、一部の人間はほとんどパニックに陥って、するとオレの電話が鳴りだすわけだ。
あ、それから、最後に、主要登場人物のうちの1人、白人のジャーナリスト、初め、雑誌「ローリングストーン」の記者としてスマイル・コンサートの取材に来ていて、暗殺未遂事件に遭遇し、その後ずっと取材を続けるうちに麻薬戦争の激しい暴力にまで巻き込まれていくアレックス・ピアスというのがいるのだが、この人が「取材し、書こうとするうちに、ものすごく怖い思いをする」ということ。この小説の作者、マーロン・ジェイムズはジャマイカ出身の黒人なのだけれど、そうであったとしても、この小説のために取材をしたり執筆したりする中で、ずいぶん怖い思いをしたんじゃあないかなあ、と心配になってしまった。暴力むきだしの世界に生まれ、その暴力について書こうとする小説家というのは、命がけなんだろうなと思う。人口あたりの殺人件数が多い南アフリカのクッツェーや、コロンビアの多くの作家だちのことも考えてしまいました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
