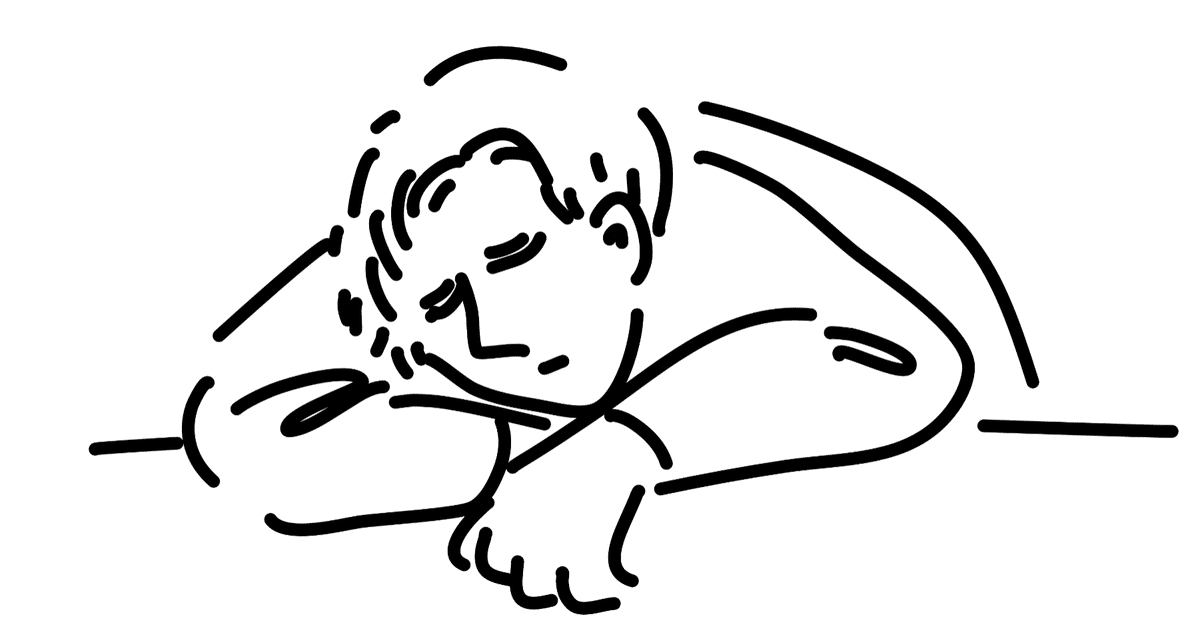
居眠りする議員について考えているうちに、議会⇔会議について、その意味と非効率について、考えてしまった。
二日前の、国会厚労委員会のYouTube動画、三原じゅんこの厚労委員会行方不明問題とその謝罪をぼんやり見ている。
野党議員は「なぜ国会を優先しないといけないかわかりますか」と詰問、三原じゅんこ答えられず、官僚が助け舟を出す、というようなやりとりが続いたわけだが。
ぼんやりと見ながら、心と頭は、別の問題の方にふらふらと迷いだすのである。
国会議員、に限らず、地方議会でも、議員さんの居眠り問題、というのはある。たいてい、「けしからん」という文脈で取り上げられるのであるが。
もし自分が議員だとしたら、寝ないかなあ。 「だって、一日中、発言もしないし、それなのに座っていないといけないんだもん」というような気がしてくる。
国会も地方議会も「会」なわけで、まあ、「会議」なわけだ。
世の中には「無駄な会議をなくせ」とか「会議は短く」とかいう類の言説というか、「会議生産性向上運動」的なものがある。ここ数年だと電通の会議室にも「会議を短く効率的にするためのルール」みたいなポスターが貼ってあったりした。
そういう運動がたくさんあるということは、実際には「無駄で長い会議が多い、ほとんどだ」という共通認識があるようなんだな。
私の勝手な分類では、会議には5つのタイプがあって
①儀式的会議(根回しが済んでいて、いくつかの連絡事項と、議決、承認していく議題を、予定手順に従って、淡々と進めていくもの)
②急に生じた重大な問題についての対応策、方針を、早急に決める必要があって招集される緊急会議
③何らかの課題を、より細分化された専門的能力を持つ部署、人に発注を出す発注会議(いわゆるオリエンテーション)
④何らかの課題に対する解決策のアイデアを出していくための、創造的会議(ブレーンストミング的)
⑤実施部隊が考えた解決案を、決定権者に提案する会議、いわゆる「プレゼンテーション」
広告屋の現場の仕事というのは、②~⑤がループしてまわっているので、私がしてきた仕事というのは、ほぼ会議の連続と言えばそうなのだが、会議が無駄とか長いとか思ったことは、基本的に、ない。大抵の会議で、私はいつもいちばんたくさん発言する一人だったし、頭は常にフル回転だったし、プレゼンでは常に「戦略パート」を15分~30分語る出番が必ずあったし。
たしかに振り返れば、長いと言えば④の創造的会議、アイデア出し会議は、だらだらと長いことが多かった。徹夜でとか、一日中、とか、休憩を挟んで深夜まで、とか、まあ将棋のタイトル戦くらい長時間かかった。
これはその必然性があって、「一見、関係ない、いろいろなことを雑談している状態と、そこからアイデアが生まれる状態」を行ったり来たりして会議が進むので、この段階だけは、「無駄な雑談」を排除すると、あんまりいいことがない。
また、一旦、まとまりかかっても、もっと面白いことを思いついてしまうと、一からやり直しだったりするから、時間がかかる。
電通も「夜10時には全員帰る」働き方改革以降、この④が「最悪の長い会議、残業のもと」として、しなくなった。できなくなった。
この創造プロセスを、各個人がどこかで密かにしているのだと思う。それはそれで大変なことだと思う。将棋指しが長時間、時間のある限り手を読むように、戦略プランナーや広告クリエーターは時間の許す限り、とことん考えるので、このプロセスの会議または個人作業が長時間にわたるのは、当然なのである。
⑤のプレゼンテーションなんかは、前半は、会議と言うより、「演じ手」と「観客」のいる出し物、パフォーマンスである。いかにびっくりさせたり楽しませたり、感動させて「この仕事、任せた」と言わせるかの勝負の場だから、エンターテイメントとして必要適切な長さになる。
つまり、私が現役時代してきた②~⑤の会議、退屈とか長いとか眠いとか思ったことは全然、無かったのである。
反対に、現役時代、①のような儀式的会議というのは、ほとんど経験したことが無かったのである。
のだが、世の中のマジョリティにとっては、会議と言うのは①なんだな、ということに、隠居して、町内会、自治会というものに出てみて、この年齢になって気が付いた。
そうして見てみると、国会の本会議なんかは、もう、典型的に①である。いや、日本に限ったことではなくて、北朝鮮や中華人民共和国の、「人民最高会議」とか「全人代」みたいなのは、みんな、こういう会議である。
株主総会も、①だな。できるだけ余計な質問がなく、すべてが円滑に「承認」されていくのが理想、な会議なんだと思う。
①のタイプの会議というのは、
⑴司会によって会議の開会が宣言され、今日の議題が説明され
⑵いちばん偉い人が冒頭に偉そうに挨拶をし、議会参加者はパチパチと感心した顔をして座っているのが仕事なのである。
⑶あとは主催者の予定した手順で議題が淡々と進む。各議題について説明する役割の人が入れ替わり登場する。かれはそのためにこの会議に出ているのであり、他の議題のときには、静かに観客に戻る。
⑷できるだけ質問も意見もでないのが最高なのである。そこの流れを崩す質問をするやつは、空気を読めないやつで「またあいつか」とみんな心の中で思ったりするのである。
⑸最後に、もう一回、偉い人が締めの挨拶をして、司会が次回の予定だなんだの事務的整理をして、会議は終わるのである。
つまり、国会も地方議会も、基本、こういうものだとすると、「今日は何らかの議題の説明もしないし、私は空気を読む人だから質問もしない」という人にとっては、誰かのつまらない話を聞いて、パチパチと拍手をすることだけが、その会議における仕事になるのである。
それは、居眠りするよね。それは、他に別に大事な、自分がいなきゃダメな会議、自分がたくさん話したり決断したりしないといけない会議を優先したくなるよね。なんか、俺、三原じゅんこのことを擁護してる??!!
そういうものが会議だと思い、そういう会議で、ただ座って、パチパチと拍手することだけをしているうちに、日本では、だんだんと出世していく。
なぜかというと、権力者からすると、①の会議を円滑に進め、権力者のポチとして、熱心に拍手して、頷いて、権力者を、その決定を、権威あるものに見せてくれるやつは、かわいい奴だからである。無能でもいいのである。員数だから。
ただ、この員数で年を重ねた議員が、長年の貢献のご褒美で大臣になつたりすると、えらいことになる。安倍内閣のときの北村地方創生担当大臣みたいなのが、間違って大臣になっちゃうと、答弁もできない、どこを読んだらいいのかもわからない、今、何を議論しているのかもわからないようなじいさんが恥をさらしたりするわけだよね。あの人、本当に酷かったよね。
逆に、茂木大臣みたいに、経営コンサル出身で頭の良さが自慢で、どの議題に対しても、くるくる頭が働いて、「質問するやつもバカだが、答えてる大臣も役人もバカだな、俺ならこう答えるのに」と、ついつい思ってしまう人だと、そういうのが態度や表情に出ちゃって、「この人、嫌な奴だな」ってなっちゃうんだよな。(あれ、俺、茂木大臣に、共感、親近感覚えている。やばい。)
こういう人にとっても。ずっと黙って座って聞いてなきゃいけない、自分に活躍の機会のない国会だの委員会だのは、苦痛だと思うよな。こんな議論は片っ方の耳と脳みそ1/4で聴いていれば十分で、その間に20個くらい、仕事ができちゃうのにな。そう思うよなあ。
そもそも、こういうことを初めに思ったのは、国際ニュースで北朝鮮の人民最高会議や中国の全人代の様子を見るたびに「偉そうな軍人やおじさんたちがずらっと並んで、一言も発さず、金正恩や習近平が演説すると、大げさに感嘆したような表情で、拍手したりする。おそらく、あの会議の一日、あの人の仕事は生真面目な顔で、絶対居眠りなんかせず、偉い人の話を聞いて、大げさに拍手することなんだよな。北朝鮮だと、ぼんやりしてたり、拍手が気乗りしない雰囲気だったりすると、後で左遷させられたり、失脚したり、下手すると粛清されたりするのかなあ。大変だなあ、一党独裁国家で、偉いさんをするというのも」と思ったわけだ。
日本は、もうすこし規範がゆるいから、大きな会議でも、退屈だと寝ちゃう人が出るわけだけれど、よく考えると「一日中、一言も発せず、その他大勢の1人として、ただただ座っている」というのが、国会質問に立たない日の、国会議員の、国会や委員会の仕事、ということになるんだよな。それは、なかなか苦痛だなあ。権力者を偉く見せ、決定に重みを与えるための「員数」にしか過ぎないんだもんな。
町内会の会議も、PTAの会議も、そういう①型会議というのが、ものすごくたくさんある。そういうものの集積で、この社会は回っているのかもしれない。
え、これって大人の常識なのかな。②~⑤の会議ばかりの広告屋の世界で生きてきたので、①のような会議が、そんなに幅を利かせているって考えたことがなかった。そういえば、地域の柔道協会の会議とかも、そういう感じだな。げーーーーー。ほんとうに嫌な世の中だな。人間の世界って。
民主主義であっても、議員の仕事のいちばん大切なことが議会に出席することで、それは権力が正しく行使されているということを、手続きとして、可視化するために必要なのだ。うーん。理屈としてはわかるが。なんか、非効率的だなあ。
いや、もちろん、議会にいないときに、国会議員がいろいろ働いていることは分かっているけれど。しかし、会議における「質疑に参加する人」と「ただ座っている人」両方いないと会議が会議として機能しないという問題。「ただ座っている人」も、欠席しても居眠りしてもいけない問題。なんか、非効率で前時代的な感じがするんだけれどな。なんとかならないのかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
