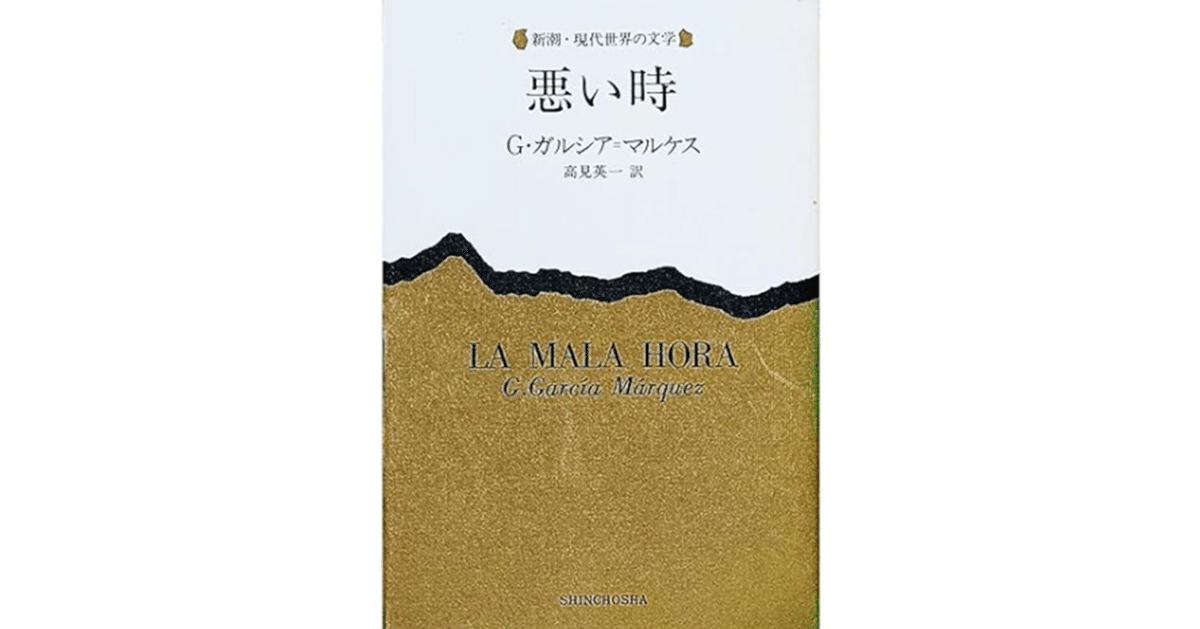
『悪い時』(新潮・現代世界の文学) 1982/9/1 G・ガルシア=マルケス (著) 高見 英一 (訳) 閉鎖的な町で、政治的対立と性的なスキャンダルが鬱々と重なることで起きる惨劇を、群像劇として描く。と分析すると今年ヒットした日本映画『福田村事件』になんとなく共通するものがある。
僕が持っているのは、まさにこの装丁の。1982年に買った本。第2刷1982.11.5のもの。買ったのは大学二年生の秋である。そのまま読まずに41年。やっと読んだ。Amazonでは古本1円からある。
今、出版されているのは、新潮社の「ガルシアマルケス全小説」シリーズの、他の初期小説と一緒になった本『悪い時 他9篇』。
内容紹介はそっちしかないので、そちらを引用、
Amazon内容紹介
血の粛清から、ようやく立直りかけた町。殺した者。遺された者。没落に怯える者。成りあがり者。恨みを深く潜ませた者。それぞれの心に、誰の仕業とも知れぬ中傷ビラが不穏な火を放つ時――。そして、届くあてのない手紙を待ち続ける老人も。死してなおマコンドに君臨する太母も。物語が虚実の間に浮びあがらせる人世の裸形。
ここから僕の感想
「死してなおマコンドに君臨する太母」は「他9篇」の、別の小説の話。この小説にはマジックリアリズム的要素は希薄で、どちらかというと『予告された殺人の記録』なんかに近い、村で殺人が起きるなかでの多人数群像劇である。
『予告された~』の方は、その殺人に至るドラマが緻密に組み上げられた、非常によくできた舞台劇のような小説だが、こちら『悪い時』は、解説にもあるが、映画のイタリアで生まれた「ネオレアリズモ」という潮流に影響を受けたもの、と言うことらしい。コロンビアの歴史は陰惨な殺し合いの政争内戦が繰り返し繰り返し、何層にも積み重なっているが、これはどの時代の話なのか。1800年代にも何度も保守派保守党と自由党の争いがあり、1900年代前半にも何度もあり、1945年以降にも何度もあり、この小説が書かれたのは1962年。1950年代の政争をWikipediaのコロンビアの歴史から引用すると
地方での暴力が拡大し、ゴメスの独裁が自由党だけではなく、保守党や支配層からも受け入れがたいものになっていくと、事態を収拾するために両党が軍部に介入を要請した。このため、1953年6月14日に軍事クーデターにより朝鮮戦争の英雄 グスタボ・ロハス・ピニージャ将軍が政権を握り、コロンビア史上三度目の軍事政権が発足した。
ロハスはカリスマを発揮して民兵の武装解除を行い、部分的に「暴力」を収めることに成功したが、 1955年ロハスが人民弾圧をおこなった地主達に恩赦をかけたために農民が蜂起し(ビジャリカ戦争)、1956年ロハスに敬意を示さなかったという理由で多数の市民が虐殺される「牛の首輪」虐殺事件の発生などにより、次第に民衆の間でも反ロハス感情が強まって行った。また、ロハスは労働者保護に努める中で、次第に自由党、保守党から離れてアルゼンチンのフアン・ペロンのような独自のポプリスモ的支持基盤を労働者に持とうとしたため、両党の寡頭支配層も反ロハス感情を抱いていった。こうして反ロハス勢力が結集したため、1957年にロハスは大統領を辞職しスペインへ亡命した。絽1958年には、寡頭支配層によって自由・保守両党による「国民戦線」体制が成立した。これは両党間で4年毎に政権を交替するという「たらいまわし」連立政策であった。背景にはロハスのような自由党と保守党の特権を侵しかねない政権の成立を寡頭支配層が恐れたことがあるが、しかし、これに反対する自由党系農民の蜂起が相次いだ。1959年のキューバ革命の影響を受けて、1961年にアメリカ合衆国のケネディ大統領主導によって「進歩のための同盟」が発足すると、コロンビアは同盟のモデル国家となったが、社会問題の根本的解決には至らずゲリラ活動は活発化し、1966年にはコロンビア革命軍(FARC)が発足した。
何が何だかわからないですよね。僕も分からない。19世紀から20世紀、何度も何度も同じような構造の政争、権力による民衆の弾圧だけでなく、民衆同士の殺し合いも頻発する。20世紀後半から21世紀にかけてはそれに麻薬カルテルの抗争が加わって、今でもコロンビアは人口当たりの殺人件数世界一を南アと争う殺人多発国である。あまりに繰り返されるので、こうして小説になっても、事情がよく分からないで読むと、どの時代の話なのか、はっきりしないのである。この混沌ぶり、『百年の孤独』はその反復と混沌を意識して、面白がって強調しているわけだが、この小説ではまだそこまでの遊び心はなくて、単に、靄がかかったように分かりにくいのである。
政治的対立で殺人者としてやってきた軍人が町長になっている小さな町の話である。殺人者が町長と警察官をしていて、殺された反逆者側の生き残りがまだ町にしぶとく残っている。歯医者がそうである。町長はひどい歯痛に悩まされているが、歯医者に行くわけにはいかない。
小さな町で、不倫だの隠し子だの、あの子の父親は本当は誰だ、と言うようなスキャンダルは実は誰もが知っているがあえて言わない、そのことを貼り紙にしてその当事者の家の戸口に貼ってある、という謎の連続事件が起きる。そのせいでついに殺人事件が起きる。
政治的暴力と、性的スキャンダルと、謎の貼り紙と。そして古くからの町を作った古くからの金持ちと新興の金持ちと。人種も出自も様々な人たちがいるので、それもまた複雑な微妙な階層と対立をはらんでいるようだが、読んでいてもはっきりとはしない。
神父、医者、判事という町のリーダーたちもそれぞれに頼りなく、それぞれにいろいろだらしない。
『予告された殺人の記録』の原型のようでもあり、『百年の孤独』のある部分の元になっているようでもある。それら代表作に先立って書かれたものなので、
こうして書いてくると、今年話題になった日本映画『福田村事件』と、なんだかいろいろ似ているなあと思う。閉塞的な村の群像劇で、政治的な対立と、性的なスキャンダル、誰もが知っているがはっきりさせるとトラブルになる、そういう負のエネルギーが満ちた閉鎖空間で、避けようもなく、惨劇が起きてしまう。その状況全体を「悪い時」として、、その国の社会の持つ病理として、描いているわけである。
ガルシア・マルケスも初めはあんまり小説が上手じゃなかったんだなあ、悩みながら模索しながら自分らしいスタイルを作ろうとしていたんだなあ、そんな感じがする小説。なので、他の、ほんとに面白い『百年の孤独』とか『コレラの時代の愛』なんかで、ガルシア・マルケス、好きだなあ、と思った人が、「全部読むぞ」と決意したら読むのがいいのではないかなあと思った。この小説から入ると「分かりにくい」でガルシア・マルケス嫌いになるかも。あるいは「マジックリアリズム」荒唐無稽で面白い、を期待すると、全然そうじゃないから、肩透かし喰うかも。
というわけで、「みなさんに勧めます」という感想にはならなかったのである。でもね、この混沌とした、コロンビアの暑くじめじめとした10月の空気の中をさまようのが、もしかすると気持ちよくてハマる人も出てくるかもなあ、と思うのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
