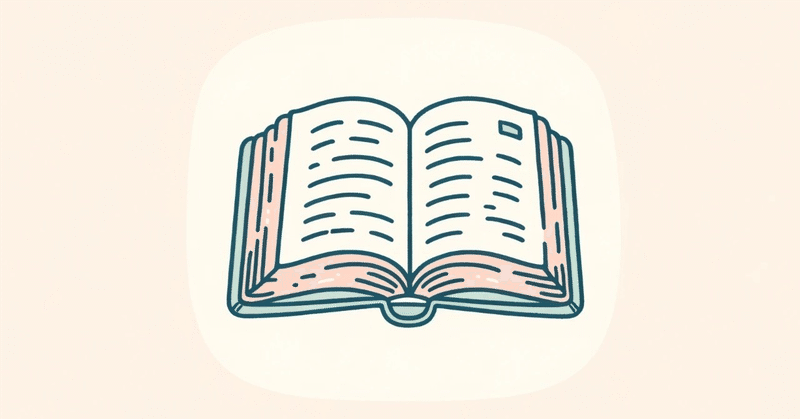
GPT-4oを使ってみた感想と、自身の文章力や言語化力の鍛え方
昨日リリースされたGPT-4oを、Webディレクターの業務やアイディアの壁打ちで使ってみたので、思ったことについてまとめてみる。
やってみたこと
過去のGPT-4との性能からどれくらい変化しているかを試そうと思い、以下の2点を試してみた。
会議の議事録から、次回定例会議のアジェンダを整理・作成させてみる
アイディアの図解メモを書いて、その内容にいて考察させてみる
会議の議事録から次回定例会のアジェンダ作成
今までよりも、より情報整理の精度が上がっている、かつ生成スピードが倍くらいになっている印象だった。
GPT-4の時は、流石に自分で書いた方が早いかも、という感覚ではあったが、GPT-4oでは、議事に書いている内容を元に、次のステップのタスクや議題も生成することができた。
「まだ来週はこのアジェンダを説明するまで進まないだろうから、省く」といった微調整をする必要があり、書かれている内容を少し手直しして、一旦メモに放り込んでおく。
といった活用を見込めそうだ。
特に、会議が立て続けに入ってしまう場合、次回の会議内容を考える時間が取れない場合がある。まずGPT-4oにアジェンダを整理しておいてもらうことで、先の計画を立てておく余裕が持てる。
アイディアの図解メモを書いて、その内容について考察させてみる
今回の生成AIの進化で、自分たちは何を考え、何に気をつけながら生きていくべきなのか。ということをぼんやり考えていた。
そこで、「生成AIがない時代とある時代でどういった変化があるか。今後生成AIを使って発話・チャット送信をする場合、どのようなことに気をつけるべきか?」について図解に走り書きしたメモを、GPT-4oに考察させてみたのだが、その画像解析能力に驚いた。

以下がGPT-4oの考察結果である。
図の内容を確認し、考察を以下にまとめました。
1. 過去と生成AI時代の比較
過去: 図の左側には、文章の作成から発話、文章の作成から送信のプロセスが描かれています。これは従来の方法で、手書きや自分の言葉で表現することが強調されています。
生成AI時代: 図の右側では、AIを活用して文章を生成し、それを送信するプロセスが示されています。AIの補助を受けることで効率化が図られる一方で、自分のフィルターを通さずにそのまま送信するリスクが指摘されています。
2. 生成AI活用のフロー
AIを使う場合のフロー: AIで生成した文章に対して、自分のフィルターを通して内容を吟味し、その上で発話や送信を行うプロセスが重要とされています。これにより、AIの出力を盲信せず、自分の考えを反映させることが強調されています。
3. 重要なポイント
自分のフィルターを通すこと: AIが生成した文章に対して自分の視点で確認・修正を行うことで、内容の正確性や独自性を保つことが重要です。これにより、AIのバイアスや誤りを修正することができます。
発話と送信の違い: 発話の場合は自分のフィルターを通して表現することが自然に行われやすいですが、送信の場合はAIの出力をそのまま送るリスクが高いため、特に注意が必要です。
AIと自力のバランス: 自分の力で考えることと、AIの補助を受けることのバランスを取ることが、今後のスキル維持・向上において重要です。
4. 改善点と提案
フィルタリングのプロセス強化: AIの出力を必ず自分で見直すプロセスを明確に設けることで、質の高いコンテンツを作成する習慣を強化する。
教育とトレーニング: AIを補助ツールとして使用する方法について、定期的にトレーニングやフィードバックを受けることで、スキルの向上を図る。
まとめ
図に示されている内容は、生成AIの時代において自分のフィルターを通す重要性を強調しており、非常に適切な視点です。このフローを実践することで、AIの利便性を享受しながらも、自分の思考力や表現力を維持・向上させることができるでしょう。
・・・
正直驚いた。
文字もキレイに書いたつもりもなく、図解も思いついたことを走り書きしたような状態だったので、ここまで整理された考察に仕上がるのかと。
文章としてテキスト化をしなくても、図解や走り書きのメモのような内容、作った設計・デザインなどを元に、アイディアの壁打ち相手として活かすことができると思った。
無意識な生成AI依存について考える
ここまで生成AIが進化してくると、無意識な生成AI依存が今後増えてくるかもしれない。
特にWeb制作業界やデジタルマーケティング業界といった仕事は、人日単価である以上、自然とタイパやコスパが求められる。
業界全体が、生成AIを活用する前提のスピード感になることで、自身も生成AIの業務活用方法をいまよりも積極的に見いだす必要がある。
そうなると、特に文章作成やアイディア生成においては、容易に生成AI依存してしまうだろう。
自分で考えたり表現したり、言葉の表現の幅などを日常的に、無意識に鍛える時間が減り、能力が減退していくのが目に見える。
じゃあどうしたらそのような能力減退の波に飲まれずに、自身の力を身につけていくか。
2つあると自分は考える。
自分自身の知識のインプット方法や知識を深める方法を見直したり、生成AIを介さないアウトプットのトレーニングと通じて、思考力や言語化トレーニングを習慣化。型を身につける。
人としての魅力。AIとの壁打ちで得られないような体験を相手にも感じてもらえるユーモア、独創性、人間力を磨く。
業務日常的に生成AIを使う一方で、意識的に生成AIを介さないアウトプットやトレーニングを習慣化できること。
自分の感情や考えを言語化できる感受性の豊かさ、言葉の表現の丁寧さを磨く必要があると思った。
電卓があるのになぜ筆算を学ぶのか
「小学生の算数で、電卓を使えばすぐに求められる計算を、なぜ筆算で計算をするのか」といった例が、今回の生成AI依存と話と近いと感じた。
算数の基礎を習う際に、積極的な電卓の利用を推奨しない。
「時間をかけて計算することは無駄なことである」といった考えになってしまっては、基礎を身につけることができないのと同じ。
仮に電卓を叩くことだけが習慣化すると、ふと暗算が必要になったとしても、自分の頭で考えて計算することができない
この話は、生成AIを積極利用する場合でも同じ事がいえそうだ。
「時間をかけて文章を書くことは無駄」という無意識の感情が芽生えるような習慣化は非常に危険だ。
コスパ・タイパを意識しすぎた生成AI利用・依存は、自身の考えや感情、アイディアを文章にしたり、その内容を発話して相手に伝える力自体を減退してしまうと考える。
生成AIの利活用を進める一方で、非効率ながらも自身の表現力や言語化力を能動的に鍛えていくと、うまくバランスが取れるのではないだろうか。
自身の考えや感情を文章化する=言語化する力を鍛える
今回の話と関連して、最近本や雑誌の中でも話題に上がることが多い「言語化」についても考えてみる。
人は発話する際に、頭の中では必ず文章にする。
この文章にする際に意識しておきたい点がある。
言葉を雑に扱わない
言葉のニュアンスや面白さを日頃から大切にする
すぐに始められそうな表現トレーニングとして考えたこととしては以下。
何かに触れて自身の感情が動いたときに、ヤバい、エグい、すごい、エモい、といった雑な言葉でまとめてしまう癖をやめるとかは習慣化しやすいかも。
よくSNSや会話の中で、状況を手早く、コスパよく伝えたいがために、こういった短い単語を使う事はやりがちだが、こういった表現は自身の考えや感情を伝える文章力や言語化力を段々と乏しくしてしまう可能性がある。
生成AI云々以前に、普段から気をつけていきたい。
・・・
補足:生成AIを使わない、自力で考える力を養うトレーニングの手法例
今回の内容を考える上で、GPT-4oを壁打ちして出てきた、日々のトレーニング方法のメモを添付する。
※以下はGPT-4oで出力した情報を転記したものとなるため、日々取り入れやすいトレーニングなど、さらに気になる方向けの内容となる。
1. AIを補助ツールとして使う場面を選ぶ
AIを使用する具体的な場面を決め、その他の場面では自分で作成するようにします。例えば、アイデア出しの際にAIを使い、そのアイデアを基に自分で文章を構築する。
2. 定期的なライティング練習
毎日または週に数回、自分で文章を書く練習を行います。日記を書く、ブログ記事を作成する、短編小説を書くなど、自分の力で表現する時間を確保します。
3. 批判的思考の実践
AIが生成したコンテンツを読み、それを批判的に評価する習慣を持ちます。AIの出力を参考にしつつ、自分の意見やアイデアを追加することで、思考力を鍛えます。
4. スキルの向上を目指す
ライティングや思考力を向上させるための本を読む、オンラインコースを受講するなど、学習を続けることが重要です。特に、構造的な文章の書き方や論理的思考のトレーニングに焦点を当てると良いでしょう。
5. フィードバックを求める
書いた文章や考えたアイデアについて、他人からフィードバックを受けることで、自分のスキルを客観的に評価し、改善点を見つけることができます。
6. 制限時間を設ける
AIを使用する時間を制限し、一定時間内で自分の力でタスクを完了させる練習をします。これにより、効率的に考える力が養われます。
7. 読書と分析
さまざまなジャンルの本や記事を読むことで、言葉の使い方や構成を学びます。読んだ内容を要約したり、分析したりすることで、自分の表現力と理解力を高めることができます。
8. アイデアノートの活用
日々の生活で浮かんだアイデアや思考をメモしておくノートを持つことで、創造的な思考を習慣づけます。定期的にそのノートを見返し、新しいアイデアを展開する練習をします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
