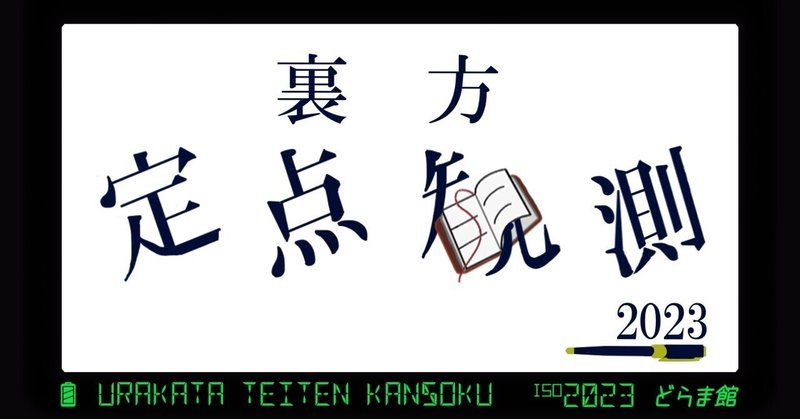
【裏方定点観測】第2回 <照明>
こんにちは、どらま館制作部の大澤です。
2023年度、どらま館は【裏方定点観測】と題した記事企画を行っています。
早稲田演劇で活躍するスタッフに長期間取材を行い、その人の作業や試行錯誤の過程、考え方を探る企画です。
第2回も引き続き、様々な現場で照明を担当されてきた舞台美術研究会OGの平田清夏さんを劇団森2年代の大塚光一郎さんがインタビューしています。
平田さんのプランの考え方や舞台美術研究会引退後の現場観を中心に取材してくれました。ぜひご覧ください。
早稲田の演劇サークルで活動するスタッフに焦点を当て、その人の活動の様子を長期間取材する「裏方定点観測2023」。今回は前回に引き続き平田清夏さんに、「照明」セクションの仕事についてお話を伺いました。
今回密着した公演は、鶴の一声×演劇ユニット两『ユリイカ』です。
劇場に入ったらまず、上を見上げるという人は多いのではないでしょうか。
筆者は開場したら早めに劇場に入って、灯体多いなとか考えたり、本を読んだりしながら開演までの時間を過ごしています。まず始めに、『ユリイカ』観劇にあたって劇場に入った時に感じたことから質問してみました。
ムービングがあると落ち着く
大塚:
『ユリイカ』では、灯体の数が少なく感じました。
平田:
今回の公演ではムービング※1をサスとして使ったので、灯体の数が少なめになっています。
大塚:
そんな使い方もできるのですね。
平田:
そうですね。役者がどこでアクトするのかわからないときは、フォローとしてムービングを使います。また、今回の公演では仕込みの人員が確保できなそうだったこともあって、吊る灯体の数を少なくするためにもムービングを使いました。一般灯体のサスは1つだけでした。
大塚:
名前の通り、動かすものだとばかり思っていました。
平田:
例えば演劇でのダンスシーンやライブ照明では、光の動きを見せるためにムービングを使います。『Automato-n/s』※2の時も使ったのですが、ムービングを使うのが初めてだったこともあって結構ブンブン動かしましたね。
大塚:
今回のような使い方には、どのようにしてたどり着きましたか。
平田:
以前にも何人かの先輩は使っていましたが、ムービング自体はぶたび※3の後輩の子に教えてもらいました。その後、外部の照明チームの方を講師として招き、ぶたびとしてムービングの講習会を行いました。発案者は私だったと思います。
また、自分がムービングの扱いに慣れてきたこともあります。『Automato-n/s』、秋研※4、『あはひ』※5と連続して使っていました。自分の経験と講習会の時に聞いた話を組み合わせることで、今回のような使い方ができたと思います。
今ではムービングがあるとどうにかなるだろうという気持ちになれて心が落ち着くまでになりました...笑
アップのあかりを応用
大塚:
今回の照明のこだわりポイントを教えてください。
平田:
まず、月のあかりがこだわりです。月面でのシーンがあると聞いてすぐに思いついたのですが、具体的すぎることが懸念点でした。作演さんに見てもらい、気に入ってもらえたので採用しました。月に行った感じが出ていてよかったと思います。



大塚:
アンケートでも好評でした!
平田:
また、月面ということで宇宙っぽいあかりになるように工夫しました。
どらま館の場合は学生会館より高さがあったり、サイドバトンがあったりするので、それも活用しました。サイドバトンを使うとシーリング※6とはだいぶ角度が違うので、他のシーンと比べて違和感を感じるようになっていると思います。
クイズシーンの照明もこだわりです。最初は、お客さんの注意が照明に向いてしまうのは良くないと考えて控えめにしていたのですが、作演さんにもう少しやかましさが欲しいと言われ、黄色と白を足しました。原色のイメージです。マチネの直前に言われたのですが、アップ用に作っていたあかりを応用することですぐに作れました。
大塚:
経験のなせる技ですね。


平田:
今回は経験を積んでいたからこそできたことも多いです。最初は方法通りにやることで精一杯でしたが、余裕が出てきて新しいことにもチャレンジできるようになりました。
あと、卓のぬいぐるみデビューをしました!音響や映像の方が卓にぬいぐるみを持ち込んでいるのに憧れがあったので、今回持ってきてみました。補佐の子が遊んでいるのを見るとほっこりします。

個人の力で現場を掴む
大塚:
秋研を終えて平田さんはぶたびを卒団されたわけですが、在籍時と変化はありましたか。
平田:
つながりが”縦”から”横”になったことですね。ぶたび在籍時は人員で来てくれるのはOB・OGや後輩に限られていたのですが、個人の現場になったことで他の団体の子も来てくれるようになりました。
車を使わないと借りられない機材があった時も、てあとろの子が運転してくれました。ちょっとずつ、他の団体の方達とも良い関係を築けています。
大塚:
平田さんが照明チーフを務めるのは何回目ですか。
平田:
8回目です。最近は回数に気づいてから、頑張ってきた甲斐があるなと思うようになりました。もうぶたびとしてオファーを受けることはないので、個人の力で現場を掴むしかありません。
大塚:
今までの積み重ねが、オファーにつながるというわけですね。
大塚:
平田さんが得意としているあかりはありますか。
平田:
しっとりとしたあかりが好きです。ライブっぽいものよりも、場を作る方が得意ですね。宇宙はさすがに初めてですが...笑 その点で言えば、得意なあかりとハマっていたのは『あはひ』です。
逆にダンスのあかりは苦手ですね。ただ、この前観た舞台で一般灯体のみでダンスのあかりが構成されていたので、得意を伸ばせばダンスのあかりもいけるかも、という気持ちになりました。
プランは具体的に教わったものではない
大塚:
今回のあかりができるまでのお話を伺いたいと思います。ざっくりした聞き方で申し訳ないのですが、照明プランはどのように組むのでしょうか。
平田:
最初は、脚本が完本しているか否かにかかわらず、主宰さんに特にやって欲しいことを聞きます。今回の場合は、月の照明でした。
次に、台本から照明変化が必要なところを読み取ります。照明変化について細かく書かれていなくても場面の変化は書かれているので、そのタイミングを読み取ります。
大塚:
今回の公演の作演さんはぶたびの出身でしたね。
平田:
はい。しかも照明出身だったので、照明変化についてはけっこう細かく書いてありました。
次に通しを見てきっかけを決めていきます。初回通しでは具体的なきっかけを決めるというよりは、ここは絶対に変わるというところをざっくりと脚本に書き込みながら見ます。主宰さんとも相談しながら、最終通しまでにはきっかけ箇所を確定させます。
大塚:
良い照明プランを組むために、通しは重要ですね。
平田:
通しを行う部屋も意外と重要です。狭かったりするとアクトスペースがわかりにくいです。
照明プランは主に、パソコンで組みます。フェードの時間まで秒単位で決めることができます。最初はなんとなくで決めて、確定するのは小屋入りしてからです。
大塚:
図面はいつごろ書くのですか。
平田:
だいたいのプランが出来上がったら図面を書きます。プランを実現するために必要な機材や予算を考えながら書いていきます。図面提出は機材発注とほぼ同じ時期に行います。機材を発注してしまうと照明プランの幅が狭まってしまうので、主宰さんとの話し合いは早めに行います。
大塚:
照明チーフとして忙しい時期は図面提出のころということですか。
平田:
そうですね。あとは、小屋入り前日も忙しいです。最終通しが小屋入りの直前に行われることが多く、それを見て図面を書き換えることもあるためです。サスの位置が全く違っていたりすることもあります。
大塚:
最後に、照明プランのおもしろさについて聞かせてください。
平田:
プランは具体的に教わったものではなく、各チーフの裁量が大きいです。庭っぽい照明、教室っぽい照明など、主宰のオーダーにどう応えるかはチーフ次第なところが面白いですね。場当たりで自分のあかりを主宰さんに披露するわけですが、そこからさらに主宰さんの意図に近づけていきます。そうした作業も楽しいです。
大塚:
ありがとうございました!
編集後記
演劇関係者なら誰でも憧れる照明セクション。
一連の取材を通して、なんとなくかっこいい、と感じていた照明の魅力が、以前よりクリアに見えてきた気がします。
みなさんも、次に劇場に足を運んだ際は照明にも着目してみてくださいね。
※1・灯体自体が動き、照射範囲を自由に決められる灯体のこと
※2・生粋工房×劇団森8月企画公演『Automato-n/s』
※3・舞台美術研究会の略称
※4・舞台美術研究会二〇二三年度秋季研究会公演『整う!秋研』
※5・虚仮華紙×劇団森12月企画公演『あはひ―その折々に―』
※6・舞台を照らすために、客席の天井部に設置する灯体のこと
取材した人:
大塚光一郎(劇団森2年代)
取材された人:
平田清夏(舞台美術研究会OG)
企画担当:
大澤萌(どらま館制作部/舞台美術研究会OG)
ヘッダー画像作成:
大江飛翔(舞台美術研究会OB)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
