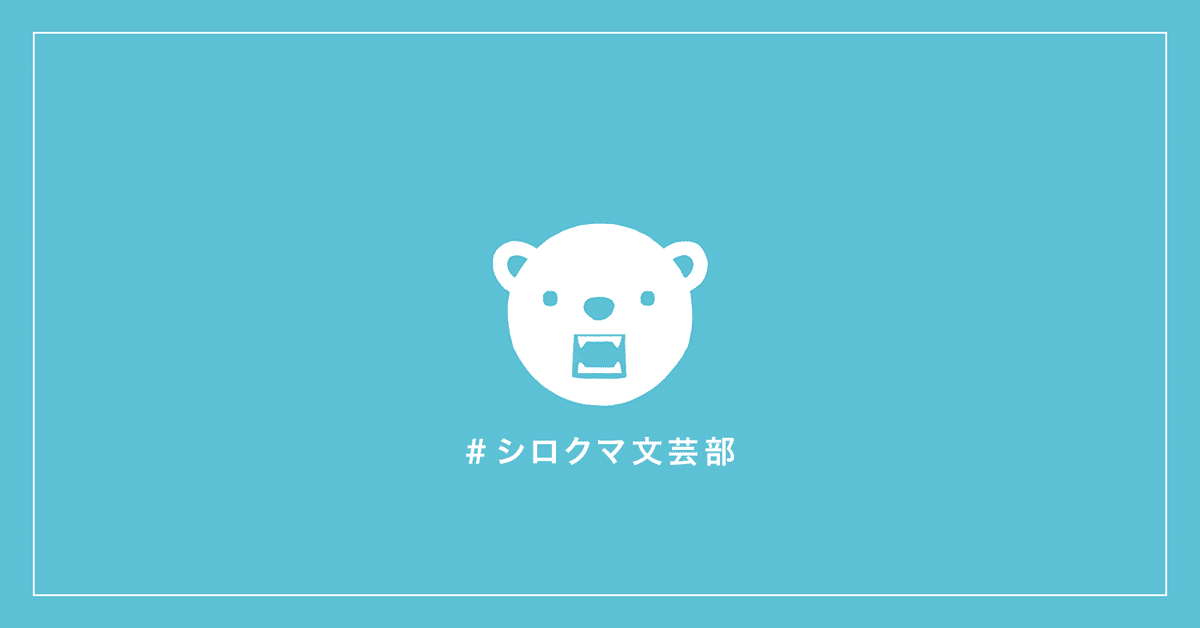
【短編小説】遅れてきた文芸部員~読者は姪っ子 #シロクマ文芸部
文芸部だったことがバレた。
九つ離れた姉にバレた。
ぼくの文芸部としての履歴は消去したい。言っちゃ、それは黒歴史。たいした作品も残せず、ただただ本をむさぼり読む毎日を部が許してくれただけ。理想的なきらきらした学園生活とは離れた、象牙の塔の集団だったから。大学二年になった今、新たなスタートとして過去を忘れ去ろうとしていた矢先のことだったのに。
「だったらさ。花音にお話書いてあげてよ」だとよ。
「文芸部だったら、お話書くのちょちょいのちょいだよね?」
ふざけろっ。
簡単にお話書けてたまるか。だから、文芸部の過去を消したいってのに。
花音はぼくの姪っ子だ。ぼくが文芸部に入った時に生を受けた、かわいい幼稚園年長組だ。聞くとこによると、利発で賢い子だとか。そこんとこ、親……つまり姉に似なくてほっとしている。
正月に姉一家が実家、つまりぼくの家にやって来た。正月名物のおせちに鰤の刺身、筑前煮をたらふく食べ、ビールに焼酎と酒池肉林の贅を極めた時の事。
「あんたさぁ。文芸部に入ったんだって?」
姉は顔を赤らめて、ぼくがこのタイミングで耳にしたくない言葉を発した。姉は酔うと扱いが大変だ。国家資格がいるかもしれない。
「う、うん」
「まさか、えっちな小説とか書いてるんじゃないでしょうね!」
「どういう意味だよ」
「ぐへへ。そこは否定しろよ!」
と、まぁ。一言でいえば『面倒くさい』。
ご機嫌を絵に描いたような姉の横で、すやすやと姉のスマホを握ったまま姪っ子の花音は眠りについていた。よくも、まぁ、こんな乱痴気騒ぎの中、眠れるもんだと感心さえしてしまう大物感。
「だったらさ。花音にお話書いてあげてよ」
「はぁ?」
「花音ってね、本が好きなの。しょっちゅう何かしら読んでて、家中の本っていう本を読破するんじゃね?って」
「それはないだろ」
「だから、本を買うのも親として経済的にも労力的にも大変なわけ」
「図書館行けよ、図書館」
「もうすでに読破したってからさ」
「……え?」
「そこは否定しろよ!ぐへへ」
姉弟のばかばかしい会話を子守歌にして、花音はぎゅっとピンク色のスマホを握りしめた。
その日以来、ぼくは姪っ子の為に執筆活動を始めた。
一応、文芸部だった。物語の組み立て方のノウハウは一通り身に着けているつもりだ。だが、作品も自分も部員として地味だった。遅咲きの文芸部員がいてもいいじゃないか。起承転結、序破急……どれもが懐かしくも感じる。
まずは、花音ぐらいの子が好むストーリーを把握するために、書店の児童書コーナーを巡った。いい歳した青年がクレヨンのようなカラフルな場所に立ち入ることに後ろめたさを感じた。
ぼくは児童書を手に取る。「シンデレラ」「白雪姫」「人魚姫」などなど、作品とキャラクターの傾向を掴むためにと言い訳をして。
何日も何日も街中の書店に通い、これだと思った児童書を買い込み、ぼくは自宅に戻るとパソコンの前に座り、かたかたとキーボードを鳴らしながら物語を積み上げた。そのあとは早い。物語は一気に書くこと。
お正月から季節は移ろい、姉からの連絡は特になく、そして新学期が始まる準備を世間さまが始める時、お話を脱稿した。
出来上がってプリントアウトした花音だけのオリジナルストーリーをカバンに詰め込み、姉の家へと急ぐ。街路樹の咲き誇る桜の花が気分を高揚させる。
姉の家に上がると、花音は真新しいランドセルを背負い、にまにまとぼくに自慢をしていた。パール調のピンクのランドセルが眩しい。
「あんたもタイミングいいね。これから花音と公園に入学記念の写真撮りに行くんだよ」と、姉が呆れるように笑ったのをチャンスだと狙い、すかさずぼくは書き上げたばかりの『童話』をカバンから取り出した。
「なにそれ?」
「姉ちゃんが『花音にお話書いてあげてよ』って、言うから書いてきた」
待ってただろ?ここに襟そろえて用意したんだぜ。
元・文芸部だった実力がやっとここで花咲かせる。現役時代は燻っていたが、そのフィールドから離れると力を発揮するプレイヤーは意外と多い。
姉はきっと、歓喜するに違いない。この作品を書き上げる為に三か月も児童書を研究したんだ。世界で一番新しい童話を献上するから待ってろよ。
酒の入った時とは違う姉の破顔する姿を想像した。
「そんなこと、言ったっけ?」
ふざけろっ。
酔っていたからか、正月に言ったことを忘れてやがる。
姉の一言でぼくの三か月間が散った。「忙しいし」と口にはしないが、姉はリビングに向かおうとしていた。
「ってか、花音。わたしのスマホ知らない?」
「知ってる」
待ってましたと言わんばかりに、花音はランドセルを下す。
ランドセルのポケットの中から姉のピンク色のスマホを取り出した。
「だめじゃない!お母さんのを」
姉が姪っ子を叱りつける声をよそに、花音はスマホのアプリを起動させる。スマホから、姉の声がする。酔っ払い完全に出来上がった姉の声だ。
確かに言っている。『あんたさぁ。文芸部に入ったんだって?花音にお話書いてあげてよ』と、正月の宴で録画された動画が再生されていた。
何かの拍子で録画されたんだろが、花音はにんまりとスマホを手に頬を赤らめていた。
ご丁寧にも姉がぼくにからんでくるシーンまではっきりと動画として記録され、こちらまで恥ずかしくなってきたものの、これはこれではっきりとした証拠。
「ありがとう!!」
花音の屈託のない喜びをぼくは素直に受け取った。
「ありがとね。さすが、元・文芸部」
姉の恥じらいやひねくれにも似た感謝をぼくは素直に受けった。
数日後、桜に囲まれたランドセル姿の花音の写真が郵送にて送られた。
差出人はもちろん、姉。写真の裏には花音からの感想文がぎっしりと書かれていた。
文芸部の喜びを遅れて感じた春麗らかな日のことだった
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
