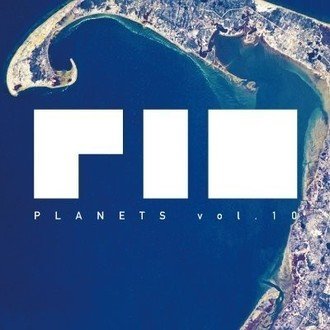中心をもたない、現象としてのゲームについて 第39回 第5章-5 ゲームを循環として再記述する|井上明人
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。
ゲームに「飽き」ることや「上達」「特殊プレイ」開始の過程、あるいは対戦/協力プレイヤー同士のコミュニケーション、それらに共通する構造をモデル化し、ゲーム/遊びの体験の普遍性に迫ります。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて
第39回 第5章-5 ゲームを循環として再記述する
5.5 ゲームを循環として再記述する
さて、「循環」の概念を捉えるための道具立てとして四つの観察モデルが整ったところで、ようやく「循環」の概念がなぜゲーム全体を統合的に捉えるキー概念なのかを示したい。
一言で言えば、ゲームを遊ぶというプロセスは、多様な循環プロセスであると言えるからだ。それゆえ、これまでの各章で議論してきた内容の多くを、循環プロセスとして再記述することが可能だという性質をもっている。
ここまで示してきた四つの観察モデルを用いて、ゲームの循環プロセスが実際にどのような形であてはまるのかを示したいと思う。この作業を通して、遊び-ゲームに関わる様々な概念が相互にどのように関係しているのかの関係性を理解することができる。すなわち、どのように様々な概念が繋がっているのか、ということが「循環」の概念を通して理解ができる、ということだ。なお、下記で再記述する対象とする学習説のプロセスや、非日常、コミュニケーション等の話は、いずれも第三章で一度長めに言及した概念である。
5.5.1 学習説のプロセスを循環モデルのバリエーションとして再記述する
まず、改めて学習説的なプロセスを四つの観察モデルによって整理してみよう。
本連載の中心的な論点の一つだった、ゲームの学習プロセスについて、そこで現れる様々な様態を四つの観察モデルによって、記述することができる。
基本的には、ゲームを遊ぶことはプレイヤーの認知が可塑的に変化していくプロセスである。[1]ゲームの学習説を純粋に認知プロセスの説明として見直した場合は、可塑的な複層モデルとして観察される。ここまで説明してきたように、気ままにゲームを遊ぶプレイヤーの多くは遊ぶ目標も、その手段も、ゲームへの理解へのあり方も、遊ぶうちに徐々に更新されていく。
その中でも、ゲームの学習の方策が固定的になったり、ゲームの上達の目標事態が固定的になるかどうかといった点については、ゲームプレイヤーによって異なり、可塑的な構造の中にも、変化を拒む構造が現れる。プロのゲームプレイヤーになろうという人は、どのようなゲームであれ、ゲームの大目標がある程度固定された形でゲームに向き合う態度を持つことになる。
学習することとは飽きることと、上達が交互に繰り返し、循環するプロセスとして記述することができる。
学習説が類似の行為の繰り返しから成り立つことは、学習説を論じる上での前提として提示してきた。学習説的な事態の中には、再帰的な反復によって、あるゲームに上達していくプロセスが含まれている。そして、また学習が止まったとき、そこには「飽き」が訪れやすくなるという前提にたっている。
「飽き」たときに、上達プロセスそのものから降りてしまい、ゲームをやめてしまうこともあるが、飽きた後にいわゆる「やりこみ」のプロセスに入ることもある。そもそものルールを少し改変した状態でゲームをしてみたり、少し似た別のゲームを開始するといったプロセスはまさにこれだ。
こういった「逸脱」は、「遊び」の領域における中核となる概念としてしばしば位置づけられる[2]。二次的現実からの逸脱(飽き)は、一次的現実からの逸脱(ふざけること、油を売ること)とは区別すべきものだが、前項で述べたように大きく「逸脱」という視点を設定したとき、両者は概ね似たようなものとされることが多い[3]。
「逸脱」(≒遊び)は、一次的現実からの逸脱であるにせよ、二次的現実からの逸脱であるにせよ、繰り返しの習熟プロセスにいったんリセットをかけて、別の形でプロセスを再起動させるための契機として機能しうるものでもある。そのため、逸脱それ自体に循環的な側面はない。「それ以上、上達をしなくなったとき」にフォーカスの方向性を変えることで「新たな上達プロセス」を開始することができる。新しい領域に向かわせるような機能をもっている。
そして、こうした様態は、逸脱行為(怠けてゲームをはじめる)→適応行為(ゲームに上達する)→逸脱行為(通常のゲームに飽きる)→適応行為(特殊ルールでのゲームプレイに上達)→…といった順序的プロセスとして適応と逸脱のプロセスを記述することができる。
もちろん、遊びはじめたゲームの中で何をやればいいのかわからないという、「どうやってゲームを遊んだらよいのか、わからない」という状態も当然あるし、上記のゲームにハマって、ゲームに飽きて…とかいうプロセスの中で、今までやっていたことをやめるという状況は具体的に、次に何をやろうか、というような行為の焦点が構成されないことももちろんある。
上達に向けてゲームプレイヤーが自己の身体を統御していくプロセスも、ゲームに飽きて逸脱をしていくプロセスも、いずれもゲームを遊ぶという行為の循環のうちの一側面としてここでは記述可能になる。適応と逸脱、シングルループとダブルループ、学習IIと学習IIIといった学習をめぐる様々な概念系を、いったんこの四つのモデルによって整理することができる。
上記の議論を簡単にまとめておこう。
・観察困難:(解釈が難しい逸脱)
・順序として観察:逸脱行為(怠けてゲームをはじめる)→適応行為(ゲームに上達する)→逸脱行為(通常のゲームに飽きる)→適応行為(特殊ルールでのゲームプレイに上達)→…
・可塑的な複層構造として観察:きままにゲームに上達するプロセス
・固定的な複層構造として観察:(※大目標が固定されたケースとしては、プロプレイヤーなど)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?