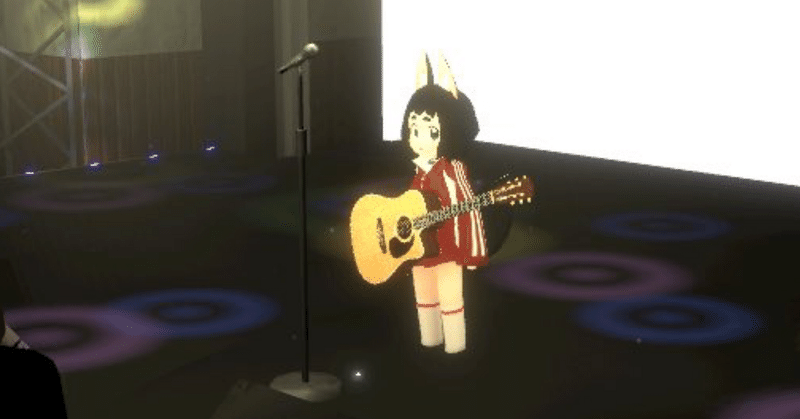
お孫様はミュージシャン
「おばあちゃん、孫が来ましたよ。」
老人ホームに入居した祖母を訪ねた。
そもそも高齢という事もあったが、
祖父が亡くなってから体調を崩す様になり、
父や叔父と話し合って決めたそうだ。
それが職場の近くの施設だったため、
仕事の合間に顔を出す事にしたのだ。
事前の連絡もなしに突然僕が現れたので少々驚きもしていたが、祖母は笑顔で迎え入れてくれた。
「仕事は出来るようになったのかい?」
おそらく祖母の中で、
僕は心身共に病んで、ろくに働けもしなかった引きこもりだった頃の記憶で止まっているようだ。
だから会う度に、現在は幾分かマシにはなった事と音楽講師として働いている事を説明するところから始まる。
「あらそう、ホントによかったぁ…」
初孫の僕がいつまでも自立できないでいる事で祖父母には大変心配を掛けてしまっていた。
祖父には最後までちゃんとした報告が出来なかった事を思うと、こうして祖母には話せた事は良かった事なのかもしれない。
「じゃあ今は毎日の様に歌ってる訳だ」
「まぁ、仕事柄そうなるかなぁ」
「そしたら、ここらで一曲歌ってもらおうかしらね」
「えー?そんなそんな、僕声でっかいからなぁ〜」
冗談だと思ってオーバーにタジタジになって戯けていたが、祖母の目はどうやら真面目にものを言っている。
「音楽でやっていくならチャンスはなんだって掴んで行かないとね、こういう施設で歌ってる人もいるしねぇ」
その言葉には、「音楽講師」としてではなく、
「ミュージシャン」としての僕にかける祖母の期待が見えた。
そんな純粋な気持ちを前に、
「いやぁ、あくまで自分は講師だし」
「そうは言っても僕なんかには難しいよ」
といった言葉を吐き出す訳にはいかず、
キュッと引き締めた胸から漏れ出た様な、湿り気の強い笑みを浮かべる事しか出来なかった。
「そうだ、レクリエーションルームにピアノがあったはずよ。弾き語りが出来るわ」
いかん、このままだとホントに行くとこまで行きかねない。
そう思った僕はスマホに保存してあった自作曲の音源を聴いてもらう事にした。
普段楽曲で取り扱ってるテーマがテーマなので、
聞かせられる内容の曲が半年以上前のデモ音源しかなかった。
「今ならもうちょいマシに歌えんだけどな…」
という苦々しい言い訳をしまいながら音源を再生した。
「他の曲はないの?」
曲の再生が終了すると、
これといった感想もなく祖母はただ一言そう言った。
「リアクションの取りづらい歌のレベルだったかなぁ…」
「歌詞の意味がわかんなかったかなぁ…?」
この寒い中、冷や汗が噴き出そうな思いをしながら、もう一曲聞かせられそうなものを流した。
「声がよく伸びる様になったねぇ」
二曲目の再生が終わると祖母がそう言った。
「"上手い"とか"良い曲"とかではないのね…!」
みたいな卑屈な言葉は、
泣けてくるほど優しく微笑むの祖母のために捻り潰した。
そうこうしてると、
施設のスタッフの方が洗濯物をしまいに部屋を訪ねてきた。
丁寧な話し方で祖母に洗濯物をしまった場所について話すスタッフさんへ
「ウチの孫がね、来てくれたんですよ」
「この子ね、音楽をやってるんですよ」
僕はずっと
学校に、社会に馴染めず
ずっと病に負けて言い訳をして
生きる事を何度となく放棄して
そんな孫が
世間的には取り分け立派と言えずとも
ようやっと何かをやりはじめた姿は
祖母にどう映っているのだろうか?
「…あはは、大したこたぁないんですけどね」
ギリギリと締め付けられた胸と腹から出た愛想笑いだった。
こんな事があっても
映画やドラマみたいに分かりやすく奮起出来ない事に、
心の中でもう一人の自分がすすり泣く声が聞こえた気がした。
「ホントに来てくれてありがとうねぇ」
仕事に戻るべくお暇しようとすると祖母が玄関ホールまで見送りに来てくれた。
90手前だというのに杖も手押し車も無しに僕の隣を歩いてくれる。
「あら、あなた身長伸びた?」
「背が伸びる様な歳じゃないよ、もう30だよ?」
「ううん、絶対おっきくなってる」
「ちょっと姿勢が良くなっただけとかじゃないかな」
「そうかしらねぇ」
玄関で手を振るちんまりとした祖母にスタッフの方が寄り添う。
何者にもなれなくたって、祖母はいつだって僕を気遣い、愛情を向けてくれた。
でも、僕が言葉で説明出来る何かになった分、彼女はちょっと嬉しそうだった。
何者にもならなくたって人は人だ。
生きてて良いのだ、花丸なのだ。
だけど、胸を張って自分の顔を持つ事が、
誰かを助ける事もあるのかもしれない。
そう思った午後だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
