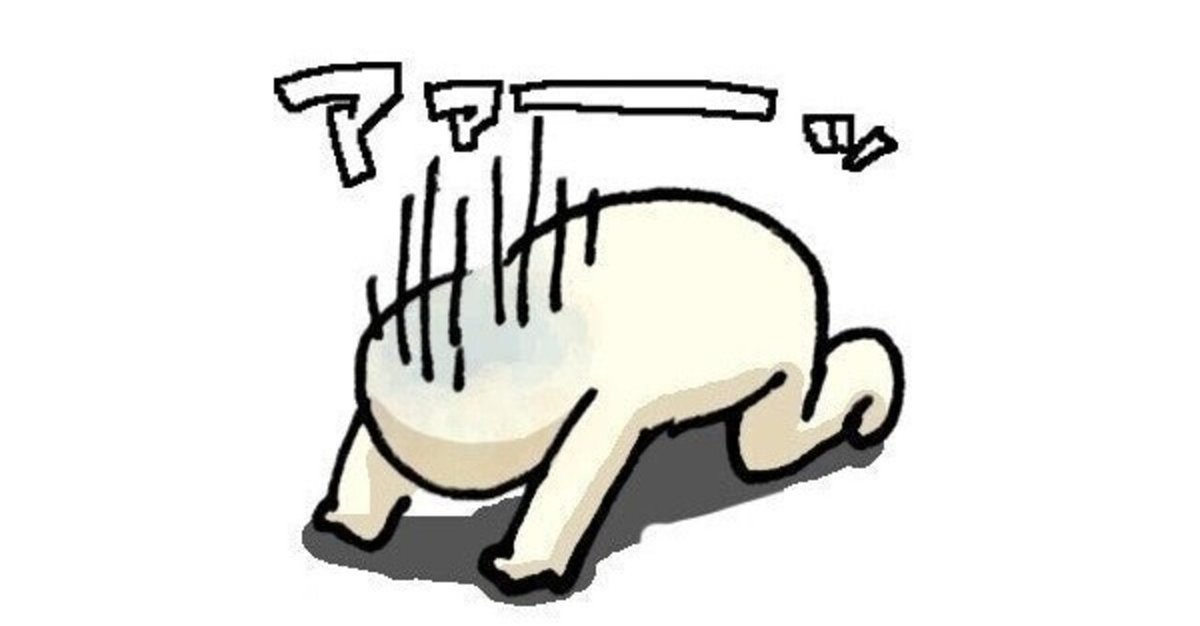
挑戦できていなかった話
何かを始めるときに、どのように判断していますでしょうか?
私は最近、会社でですが、できるかできないかで判断していることが多かったです。
なぜかというと、他人の評価を気にしていたからです。
伊藤洋一さんのvoicyを聴いて、気づけました。
【自分を信じてやり抜く方法】できるかできないかではなく、やるかやらないか。
— おやき|おやき屋開業のためにSNS収益化 (@oyaki_labo_ueda) May 27, 2021
できるorできないで考えるとできることしかできなくなってしまう。
制限の枠を外して、挑戦するためにやると決める!
できるかできないかではなく、やるかやらないか - 伊藤羊一 @youichi_itou https://t.co/YHSZoIB6kl
気にしていないはずの会社での評価からの気づき
会社からの評価を気にしていないと思っていましたが、気にしていた事が分かりました。
会社では、何かしらできていないと評価されません。
そのため、ゴールとして、できることを頭に思い浮かべて、そこに向かって取り組んでしまっていました。
そうするとどうなるかというと、飛び抜けたことはできずに、結局は評価には結びつきません。
会社での評価目線で自分がどのように判断しているかを確認するのは、良いと気づけました。
『できるorできない』で判断しているのか、それとも『やるorやらない』で判断しているのか、どちらでしょうか?
『やるorやらない』で判断するメリット
『できるorできない』、『やるorやらない』でどちらの判断方法が良いかというと、『やるorやらない』の方が良いです。
なぜかというと、無駄に頭の判断エネルギーを使わないからです。
『できるorできない』を考えると、様々な外部要因を考えて総合的に『できるorできない』を判断します。
例えば、読書について考えますと、下記のようなことを判断します。
・本を読む時間が確保できるか
・読む本をどうするか
・読み終える事ができるか
これを『できるorできない』でなく、『やるorやらない』で考えると、
『やるorやらない』の判断でしかないです。
しかも、自分の能力に関わらず、自分の考えで決められます。
色々と考える必要はなく、2択です。
そして、挑戦することにより、大幅な自己成長が出来ます。
まとめ
『やるorやらない』で決めるメリット3つ
1.脳の判断エネルギーを使わないで済む
2.制限を外せるために、可能性が広げる
3.大幅な自己成長ができる
この記事が参加している募集
サポート歓迎しています。サポート頂いたお金は大事にしっかり使います。 お金は学びをメインに使います ・Voicyプレミアムリスナー ・聴く読書(Audible、audiobook) ・オンラインサロン ・メルマガ購読
