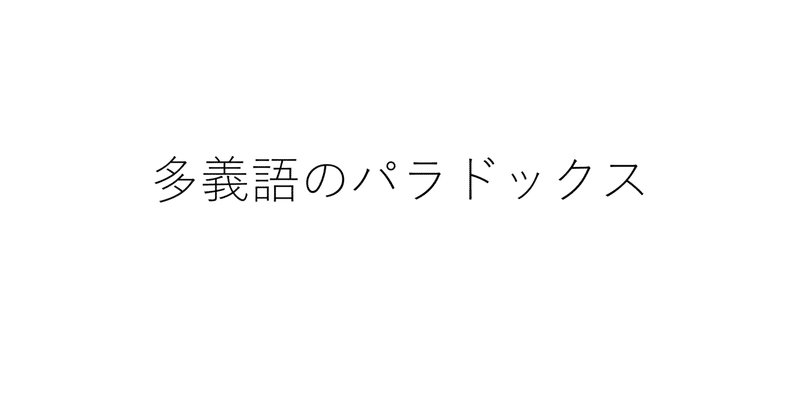
【多義語研究】多義語のパラドックスについて解説をします!
こんにちは。ひさのりです。多義語の研究を始めて、かれこれ4年が経ちました。おかげさまで、ネットでも、私の論文がかなり読まれているのかな?なんと「多義語 論文」とググってみると、僕の論文が出てきます。下の写真は「多義語 論文」と検索した1ページ目です。この写真の一番下にある論文「多義語のパラドックスについて〜」というのがボクの論文です。

これは、慶應湘南藤沢学会(慶應湘南藤沢キャンパスには学内の学会があります)で発表したものです。確か、論文集に寄稿したんですよね。その時には。それがネット公開されているんですね。
さて、今日はそんな「多義語のパラドックスは何か」ということについて解説をしていきます。多義語のパラドックスについてブログ媒体で述べるのはなかったので、この記事が多くの人に広がっていけばいいなと思いつつ。
1:多義語の言語学的な定義について
いきなりですが、多義語のパラドックスについて説明する前に、多義語の言語学的な定義の話からしたいと思います。皆さんは、多義語の定義というとおそらく「2つ以上の意味のある言葉」と思いつくのではないでしょうか。
しかし、多義語には言語学的な定義があるのをご存知でしょうか。正確には上に書いた「2つ以上の意味のある言葉」よりも正確な定義があります。今からその定義を紹介しますね。下の太線で示された文が多義語の定義です。
1つの言語形式の中に複数の関連した意味の持った言葉
これが多義語の言語学的な定義です。でも、これ、よくみてみると、いくらか「?」となってしまう箇所があります。これについて、ニュージーランドのオークランド大学の言語学者「John.R.Taylor」は、これを「多義語のパラドックス」と命名して、以下の問題点を挙げています。
2:多義語のパラドックスとは何のこと?
さて、先ほどの言語学者の方は、多義語の定義について、以下の3点の問題があり、それが議論されることなく、あたかも認知言語学の研究の前提のようにして扱われてきた、と主張しています。では、3点ある多義語の定義の問題とは何でしょうか。以下、列挙しました。
①1つの言語形式?
これは英単語を指すのか、イディオムまで含むのか?
②複数の?
辞書の意味の数でさえ、辞書ごとに異なるのに意味の数はどのように決定?
③関連した?
関連してしているの具体的な判断基準は?
つまり、これら3点の問題(1つの言語形式・複数の意味・関連したニュアンス)について、一定の結論を得られていない。しかし、認知言語学において、これが「前提」ではなく「合意」のもとにすすめられたら、多義語の研究のパラダイムが変わるのではないか、と認知言語学における多義語の研究の未来について示唆しています。
以上の「多義語の定義に関する一連の問題」が「多義語のパラドックス」と呼ばれています。多義語のパラドックスに関する記事が、海外を中心に最近では増えてきました。以下、多義語の研究がどのように行われてきたのかということを書きながら、解決への示唆へと議論を進めていくことにします。
3:大前提:多義語か否か、決めるのは学習者だ
上では、多義語のパラドックスとは何か、ということについて解説をしてきました。では、多義語のパラドックスの解決を示唆するにあたり、ここである前提を話していかないといけません。それは「多義語かそうでないかを決めるのは学習者である」ということです。
ここで、多義語と、よく、同じようにして?扱われることの多い「同音異義語」という言葉について扱います。同音異義語というのは「同じ意味を持った全く意味の違う言葉」ですね(文字通りに解釈すると)。実は、同音異義語にも言語学的な定義はあります。ここで、多義語の定義と比較する形で同音異義語の言語学的な定義を紹介します。
多義語→
1つの言語形式の中に複数の関連した意味のある言葉
同音異義語→
1つの言語形式の中に複数の関連しない意味のある言葉
さて、ここで、多義語と同音異義語の定義の違いがわかりましたか。そうです、多義語には、意味の上で「関連性がある」。しかし、同音異義語は意味の上で「関連性がない」のです。これが、多義語か同音異義語か、分類するラインになります。
でも、その関連性って、言語学者が決めることはないような気がします。というのも、僕らは「関連性理論」という「自分の持っている知識と関連づける」ことができる仕組みを脳内に備えているからです。つまり、意味同士の関連性を結びつけるかどうかは、学習者次第であって、これはいくら言語学者が意味の結びつきがあるないを言っても、学習者が結びつけたらそうなってしまうのです。
その意味で、多義語か同音異義語かを決定するのは、学習者であって、辞書を作っている人や、言語学者ではないのです。その意味では、辞書の定義には意味がないと言えるでしょう。なぜなら、多義語か否か、決めるのは学習者だから、です。
4:多義語のパラドックス関する研究について
多義語のパラドックスに関する研究について、これまで先行研究があるのかというと、ちょっとはある、感じです。ここでは、いくらかの先行研究を紹介します。3件あります。
Taylor(2003c)「Polysemy's Paradox」
この論文と、前年に出版されている彼の文献において、多義語のパラドックスについてはじめて取り上げられました。多義語の 論文についてそれまでの文献を俯瞰するという形で行っていますが、結論として「多義語の定義が変わればこれまでの多義語の研究の大きなパラダイム が異なるものになるであろう」としており、多義語の定義に関する問題はこの論文で解決されている とは言い難いものがあります。
Falkum(2011)「The semantics and pragmatics of polysemy』
この論文は、多義語のパラドックスを正面から扱った、数少ない論文になります(しかも、大学院の博士論文という位置づけです)。おおまかな内容としては、語彙意味論と語用論の立場から、文の用例採集を中心に行い「多義語というのは会話などから意味が蓄積されるものである」としています。
この研究は確かに語用論的発達としての多義語の発達ということをテーマに取り上げています。つまり、しかし、この研究は多義語を覚えなければいけない場面において、応用可能かというとそうではない。すなわち外国語としての英語、学ぶ上でどのように応用されるのかという点で示唆が欠けておりどちらかというと、英語の母語話者向けの研究であると考えられます。教育への示唆として、やはりなんらかの方法で多義語に対しての意味づけを明示的に教えな ければいけないのではないかと考えています。
ちなみにですが、上のFalkumは、現在、オスロ大学で多義語について研究をしており、認知言語学における素晴らしい若手研究者です。Falkumの論文はいつも新しい示唆に富んでいて、面白いです。FalkumのGoogle Scholarのページを貼りますね。特に2015年の論文は現在の多義語研究の流れについてよくまとまっています。
ここまでで、勘の良い読者なら気づいたと思いますが、そうです、この他疑義のパラドックスの研究はまだまだ進んでいかなければいけないのですね。
例えば、多義語の新しい理論を生み出したとして、それが多くの多義語に汎用可能なのか、汎用可能ではないとしたらそれはどのような多義語で、どういう経緯で起きたものなのか、多義語に関する新しい理論は既存の理論とどう違うのか、などなど、考えなければいけないことはたくさんあるのです。
5:多義語という現象はどうして起こったのか?
ちなみに、ここでちょっと話を原点に戻してみましょう。そもそも多義語という概念はいつ起こったのかということです。「1つの言葉に複数の意味がある」というのは、古代、アリストテレスの時代から言われていました。
1897年に、フランスの言語学者が初めて「多義語」の英訳になる「Polysemy」という言葉をつけます。
Poly→多くの semy→意味、という意味です。
その後、ノーム・チョムスキーが「生成文法理論」を創始しました。生成文法理論というのは「人間は生まれながらにして母語を獲得する脳を備えている」という理論です。彼は言語について、言語単体で扱ったので、多義語の研究までそこまで触れませんでした。その時、チョムスキーのもとで指導を受けていた人たちがそのアンチテーゼとして作ったのが認知言語学で、そこで大きく多義語が取り上げられることになります。それについては、下記の記事で紹介をしています。よろしければご一読を。
6:まとめ
さて、今回は多義語のパラドックスについて解説をしてきました。多義語の定義が言語学的に決まってしまったものとして、それを「解決」するということが何を意味しているのか、僕にはよくわかりません。
しかし、多義性とは何か?という、今までは考えられてこなかった多義語の問題に正面から問うことになります。どうして多義性は生まれてきたのかということ、はたまた、教育へ応用するにはどうしたらいいのか?ということなど、考えることはたくさんあります。
次回は多義語を包括する理論の流れということで、先人たちのまとめた多義語の理論をまとめていきます。では、次の記事でお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
