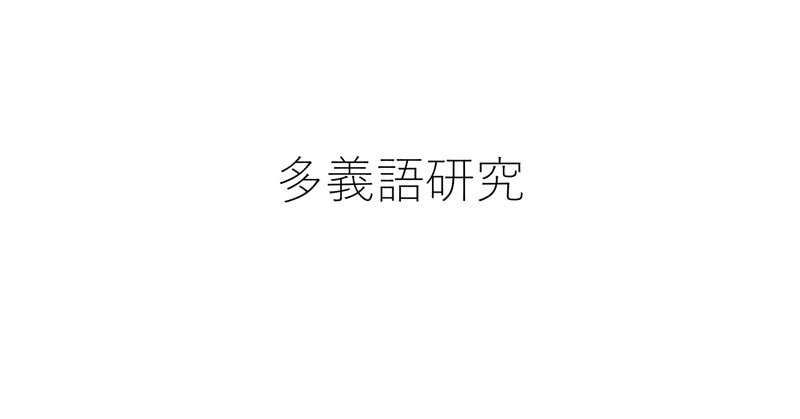
【多義語研究】多義語の研究について最近考えていること
<はじめに>
多義語の研究を始めて、5年以上の歳月になる。今回は、多義語の研究を振り返ってみて、思うところがあるので、その「思うところ」について書いてみます。
①多義語の研究を始めたとき(学部3年〜学部卒業)
多義語の理論的な研究を始めたのが、今から5年前。ちょうど、今の認知言語学研究室に入ったときに遡ります。
幸い、僕の通っている大学のキャンパスは、学部1年生の頃から研究室に所属できるので(しかも卒業単位になります)いろんな研究室に所属したものでした。脳科学・心理学などなど。
その時に思ったのは「言語の世界は奥深い」ということ。ありきたりになってしまうけれど、本当に調べれば調べるほど、いろんなことを学べました。
中でも面白かったのが、ジョン・テイラーという研究者が2012年に出版した「メンタル・コーパス」という本です。「メンタル・コーパス」の第10章には「多義性」と題して「多義語の言語学的な定義から人間の多義への考え方を探る」という内容で書かれています。
その本を知ってから、多義語の定義的な問題の研究を始めます。まさに、あの本は言語学について考えさせてくれる本の1つになりました。さて、その多義語の言語学的な定義については以下の記事で取り上げています。
とにかく、学部の頃は読む論文が新鮮な感じがしていました。研究が面白いと思って、もうすこし続けてみたいと思ったので修士課程へ。
いよいよ、大学院生としてのスタートです。
②多義語の研究に飽きたとき(修士課程時代)
そんな僕も、やはり多義語の研究に飽きるときはきます。正確には、多義的な性質を他のものに応用したいと思うようになりました。もっと具体的にいうと、多義語の研究を「教育への応用」を視野に入れて研究していきたいと思うようになりました。今にして思えば、とても大事な視点です。
とはいえ、修士課程の研究は一気に基準が上がって、とても難しかったように思います。修士課程の研究は非常に高度です。もちろん、そこを簡単に颯爽と駆け抜けていく人はいました。しかし、僕にはそんな高尚な才能がありません涙。ですので、せめて「続けよう」と思いました。
さて、今、僕の中の一つの価値観を書きました。「続ける」ということについてです。続けることはとても大事です。少なくとも、僕は続けるということにおいては誰にも負けたことがありません。好きなら続けていればいい。
結果的に修士論文はうまくいかなかったので、もう少し研究を続けたいと思った僕は博士課程へ。こうなると、さすがにいつ前続くのだろうと思いますけど笑。ちなみに、修士論文は英語で書きましたが、本当に進めるのに苦労しました。辛かった…。
③多義語の研究に戻ってきました(〜現在まで)
というわけで、続けてきました。今は、教育への応用とか考える間も無くてただ論文を生産する日々です。認知言語学の教育への応用を考えるときはとてもかけがえのない時間です。1つの論文をじっくり精読する時間が懐かしいです(そういう時間が戻ってきてほしいと切に願います)。
辞書を見れば、大半の言葉が多義語です。多義語は文字通りに解釈すると「複数の意味がある言葉」となります。しかし、事実と認知は違います。
いくら「事実」として「多義語」でも、個人が「同音異義語」と思っているならば、それは「同音異義語」です。あくまでも、多義語か否かを決めるのは個人であり、辞書ではありません。
この先の研究テーマは一応のところ決まりました。それに向けて頑張っていくのみです。しっかり、論文になってくれるといいけど…。
④最後に
こうして書いていると、常に多義語の研究をしてきたことがわかります。というわけで、これまでの回想でした。無事、博士課程を修了できればいいけれど。まあ、これからですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
