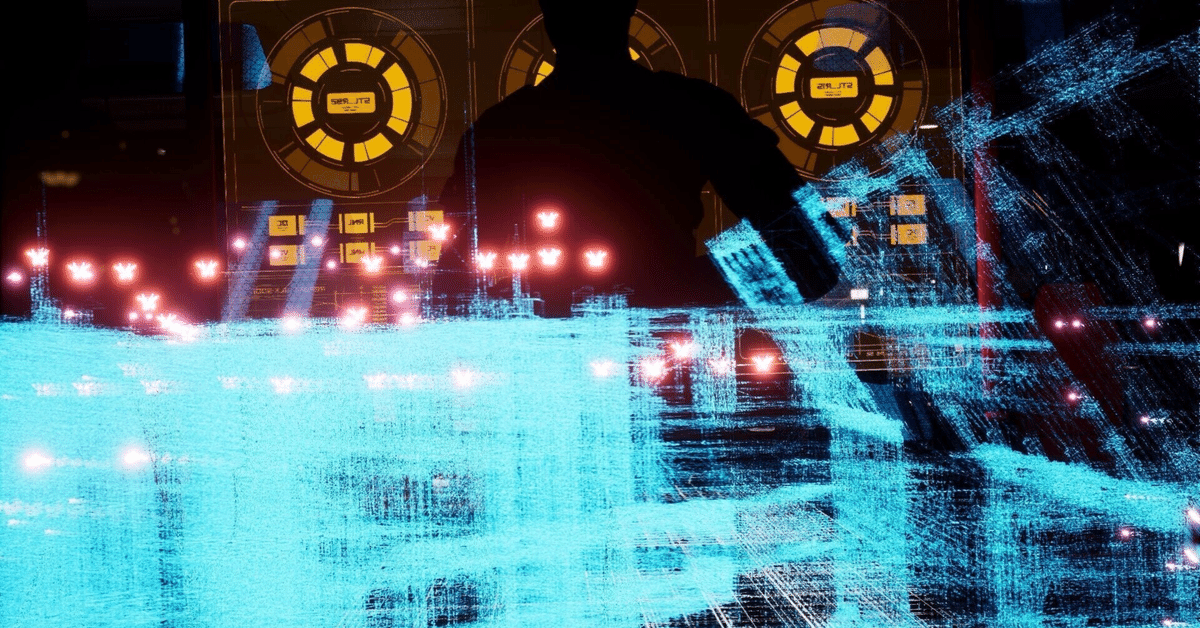
HDDやSSDの限界を超える次世代ストレージ「HDS」
HDDでもSSDでもない「HDS(「ホログラフィックデータストレージ:Holographic Data Storage)」とは、光の屈折率を使用して立体的にデータを記録する技術である。
読み取りの並列実行が可能なので、データ読み取りと書き込みの速度も向上する。また、データの破損や劣化にも強くなり、高耐久・高信頼性のデータ保存が可能となるのだ。
ただし、このホログラム方式は、光の性質を計算して作らなければならないため、製造コストがとても高くつく。
よって、まだ一般的には普及していない。
そして、そのホログラム方式よりもさらに高価なのが、量子ビット方式のメモリだ。
量子ビット方式は、一秒間に百兆回の演算が可能であり、理論上はどんな小さな情報でも記憶できると言われている。
ただ、現在の技術では、このサイズのチップを製造することは難しく、かなり高価になってしまうのだ。
ちなみに、現在市販されている半導体メモリの中で、最も小さいものは、一辺十ミリ程度の立方体のサイズしかない。
つまり、一般的なスマホに搭載されているCPUの四分の三ほどの大きさしかないわけだ。そんな超小型の半導体メモリの中に、一体どれだけの情報が入るのか……想像しただけで恐ろしいものがあります。
あと、この半導体メモリの製造には特殊な設備が必要であり、研究段階から商用化に至るまでにはまだ長い道のりがありそうだ。
もっとも、このホログラム方式にしても、量産化の目処はまだ立っていないのだが……。
しかし、現時点ですでに実用化されている技術をいくつか組み合わせれば、このサイズが実現できたりする。
例えば、シリコンベースの半導体メモリなら、今ある技術だけでも作ることができるだろう。
だが、ナノテクノロジーを利用した半導体メモリを作るためには、特殊なナノ結晶が必要になるはずだ。
それが簡単に手に入るとは思えないし、そもそもナノレベルまで微細加工出来る工場なんて無いと思う。
そう考えると、やはり、今のところ、現実的な選択肢としては、ホログラム方式か量子ビット方式くらいしかなさそうである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
