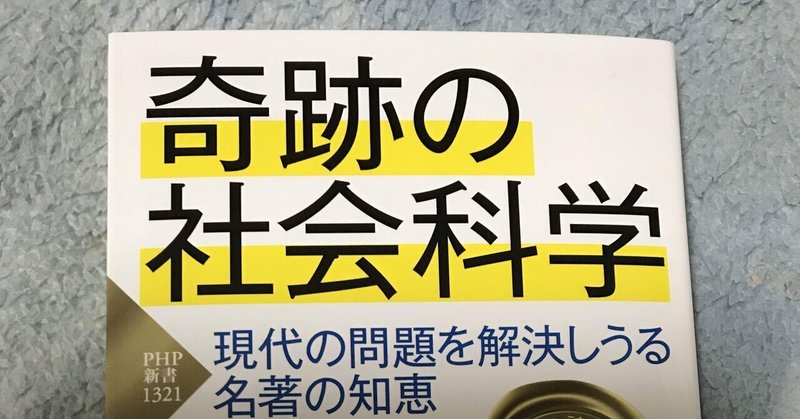
「奇跡の社会科学」(中野剛志著、PHP新書)ウェーバー②
リンゴが美味すぎて止まらんです🍎
あ、ぽんニャンです🐱
マックス・ウェーバー②です。
この項目では、「グローバル化」についても言及されています。
よくよく読んでいくと、「チェーン店」もグローバルだよなと思えてきます。
また、介護事業で言うと、先進的で脱官僚的な介護事業所も、それを真似したりチェーン店化すると、とたんに官僚的になるなぁと思いました。
それでは、どぞー😊
ウェーバーが官僚制の分析をして以来、インスピレーションを得て、現代社会を分析する研究が数多く現れた。
代表例として、社会学者のジョージ・リッツァが1993年に発表した「マクドナルド化する社会」を取り上げる。
リッツァは「マクドナルド化」を「ファストフード・レストランの諸原理がアメリカ社会のみならず世界の国々の、ますます多くの部門で優勢になる過程」とていぎしている。
マクドナルドのシステムは、効率性と合理性とを徹底しており、リッツァはそこにウェーバーが観察した官僚制の極致を見ている。
リッツァは、マクドナルドのシステムに、以下の4つの性格を見出した。
①効率性
従業員は会社の規則に従い、効率的に作業する。
従業員は店長のすぐ側で作業し、店長は従業員を監視する。
お客も効率的。ドライブスルーが典型。
②計算可能性
マクドナルドでは、販売商品の分量、費用、提供時間の迅速さという「量」を重要視する。
従業員は低賃金で、作業を素早くこなす事を要求される。
お客は食事の時間を短縮する事を要求される。
商品は「Lサイズ」「ビッグマック」など、量を強調される。
③予測可能性
マクドナルドの商品は、世界各国で買える。商品もほぼ同じで意外性がない。
従業員もマニュアル化しているため、反応が予測可能。
④制御
お客は、行列のライン、決められたメニュー、座り心地の悪い椅子などによって、店側から制御されている。
従業員は監視のもと、規律に従い、作業ラインに従って機械的に作業している。
マクドナルドは、人間によるミスがないように、あらゆる工程を機械化している。
つまり、マクドナルドは、極めて官僚制的である。
「トヨタ生産方式」
工場の生産ラインは官僚制的。
古くはフォードの「フォーディズム」。ベルトコンベアによる作業。
そこから「トヨタ生産方式」へと進化している。
「ディズニーランド」
ディズニーランドは、世界各国でほぼ同じエンタテイメントを提供している。
マクドナルド化などの典型であり、官僚制的でもある。
「教育」
決まった教科書、知識の詰め込み、スピーディーな解答。
結果がすぐ出るので「効率的」
数値で評価されるため「計算可能的」
ウェーバーは官僚制の問題点として、非人間的であることを挙げている。
リッツァも、マクドナルド化は反人間的または脱人間的システムになることを挙げている。
商品は健康に悪い影響をおよぼす懸念がある。
従業員は単純作業を反復し、創造性を要求されない。
お客も、食べ物を詰め込む感覚にさせられるし、どこに行っても変わらないメニューで楽しくはない。
従業員と客の関係も希薄で、昨今デリバリーが流行って加速している。
ロバート・マートンが指摘した「逆機能」もマクドナルド化では起きている。
健康に悪い食べ物を盗り続けると、健康維持にコストがかかり、安上がりではなくなる。
従業員も、低賃金で単純労働のため、不満がたまり、離職率や欠勤率が高まる。結果、人材育成に時間とお金がかかり、人件費の高騰につながる。
「マクドナルド化」=「グローバル化」=「官僚制化」
みんなに受ける物を提供。
従業員は誰でもできる仕事を与えられる。
どこの国にも出店できる。
「マクドナルド化」は脱人間性を伴う。ということは、「グローバル化」も脱人間性を伴うということ。
「グローバル化は不可避だ」と言われると、そうかと思う。しかし、「官僚制化は不可避だ」と言われると嫌悪感が湧くのではないか?
ウェーバーも「ひとたび完全に実施されると、官僚制は、もっとも破壊されにくい社会組織のひとつになる」と述べている。
なぜ行き過ぎたグローバル化を警戒するかと言えば、グローバル化=官僚制化であり、官僚制化は「非人間性」であるから。
つまり、グローバル化が進むと人間性が失われていくからである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
