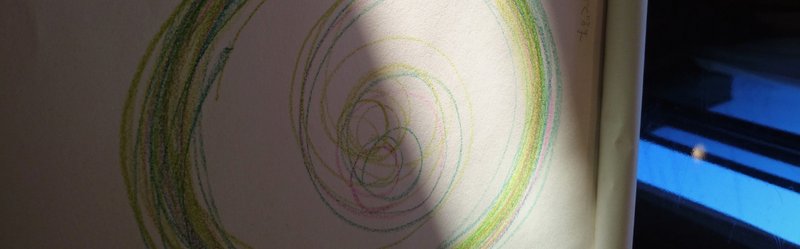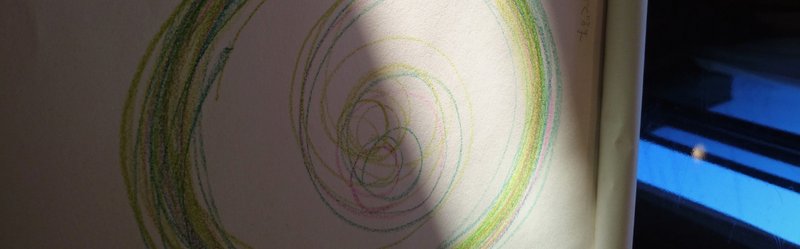音楽プロセス体験研究室の地味なZoom
ただただ、黙々と自習するために、集うZoomというのを見かけたことがある。
自習する内容はなんでもよくて、でもそこに集うためには課金が必要で。
それはきっと一人でするより、きっとうんと集中すると思うし、まして課金しているのなら、なおさら。
わかるわかる。
不思議なもんで、そのPCやスマホの向こうで他の人も黙々とやっていると思うと、一人でするのとはきっと全然違うんだろう、やってみたいなあと思っていた。
音楽プロセス体験の昨夜のズームは、二人きり。
私は取り組みの途中だったメロ