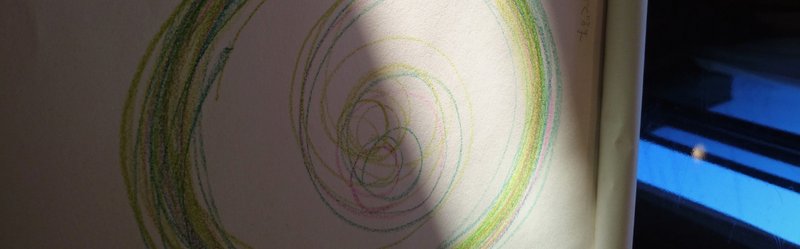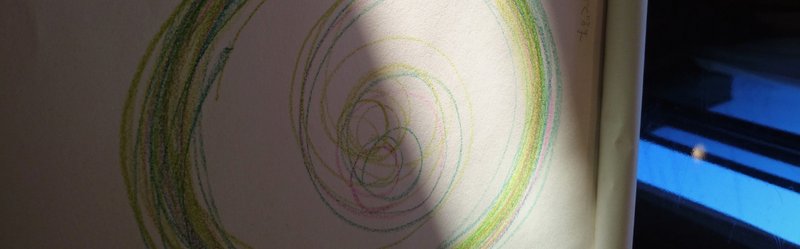子どもたちのピアノコンサートを終えて
いいコンサートができたんじゃないかなとおもう。
誰も取り残さないコンサートにしたいとおもってて・・
ちゃんと、その生徒が追っている音楽の筋がみえる、
無理のない、それでいて、「発表会」ではない「コンサート」と言えるクオリティの。
そこには芸術的価値観、というものが反映してくると思う。
というか、
ピアノ教室の発表会の根底に「芸術的価値観」をもってくるっていう
そういう発想を私はあまりみたことがないが、
私はずっとそれは思っていて、
だから、発表会とは呼ばず、リトルコンサー