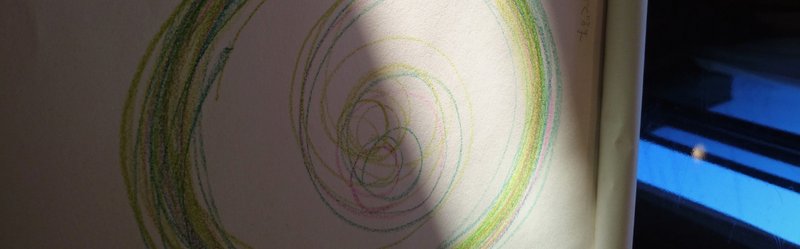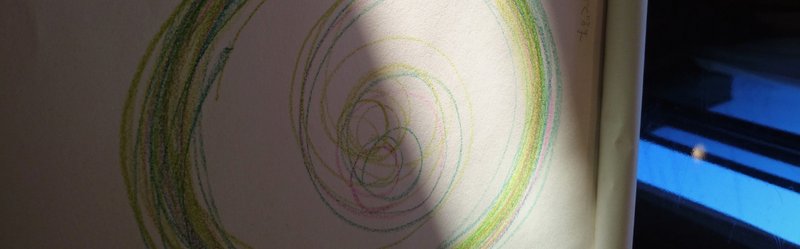問いを深めることがレッスンの意味
初めの問いはその人にも分からない、がデフォルト教室のドアを開ける人はさまざまで、音楽に対して持つイメージや思いは、みんな違っています。そして、その憧れや、問いへの対象はまだ曖昧です。はっきりとこうしたい、と言っている人でも、私なりに解釈し、それをどのように実現していくか筋道をたて具体的に関わろうとしてみると、その「こうしたい」はその対象を掴み得ず、結局理想というのは、曖昧なもんです。それは、当然だし、仕方ないことです。だって、まだ未知なもの学びに来てるんだから、全部わかってた